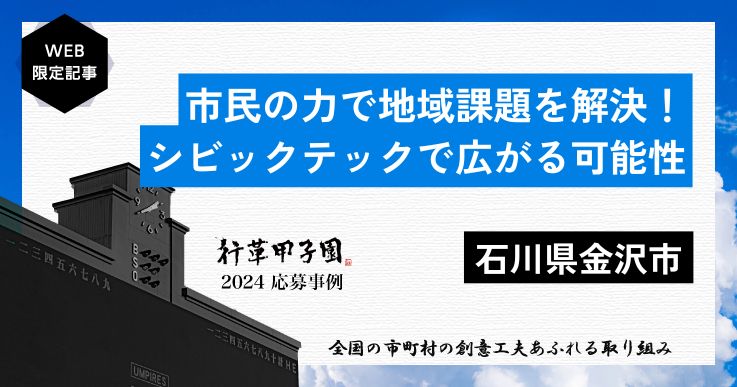
全国の市区町村の創意工夫あふれる取り組みを表彰する、愛媛県主催の「行革甲子園」。7回目の開催となった令和6年の「行革甲子園2024」には、35都道府県の78市区町村から97事例もの応募があったという。
今回はその中から、石川県金沢市の「シビックテックによる市民協働のまちづくり」を紹介する。
※本記事は愛媛県主催の「行革甲子園2024」の応募事例から作成しており、内容はすべて「行革甲子園」応募時のもので、現在とは異なる場合があります。
取り組み概要
金沢市では、令和2年度より市民自らが地域課題を解決できる社会の実現のため、シビックテック※マインドを浸透させるためのイベントや、市民同士が協働できるプラットフォームの提供を開始した。
1. 「シビックテックスクール」開催により地域課題を自ら解決できる人材を育成
2. 「市民のためのデータ活用講座」開催によりオープンデータの活用方法を解説
3. 「シビックテックミーティング」開催によるシビックテックに取り組む人と地域課題をもつ人が顔を合わせて交流できる場を提供
4. プラットフォーム「マッチ箱」提供によりWEB上でいつでも課題をもつ人と解決できる人をマッチング
※「シビックテック(Civic Tech)」:Civic(市民)とTech(テクノロジー)をかけ合わせた造語で、市民がテクノロジーを活用して、地域が抱える課題を解決しようとする取り組みや考え方を指す。国内や国外では、シビックテック活動が各地で広がっており、市民やNPO法人、民間企業等が主体となって、地域課題の解決につながるような様々なアプリやサービスが制作されている。
背景・目的
シビックテックの推進を図ることで、同市において、市民や行政のニーズに即した地域課題の解決につながるアプリケーションやサービスが提供されるようになることを目指している。日本初のシビックテック団体として「Code for Kanazawa(コード・フォー・カナザワ)」が平成25年に設立。ごみ分別アプリ「5374.jp」の開発をきっかけに金沢市との協働が始まり、令和2年に「金沢シビックテック推進協議会」(事務局:金沢市市民協働推進課)が発足した。
取り組みの具体的内容特徴(独自性・新規性・工夫した点)
1. 地域課題を自ら解決できる人材を育成「シビックテックスクール」
ICTを活用した地域課題解決に興味をもつ人を対象に、ノーコードツールを活用したアプリ等開発講座や、Google アプリケーションの活用に関する講座などを開催することで、地域課題を自ら解決できる人材を育成する。
2. オープンデータの活用方法を解説「市民のためのデータ活用講座」
行政が公開するオープンデータなどのデータの活用メリットや手法について解説し、体験してもらうことで地域課題解決に役立ててもらう。
3. シビックテックに取り組む人と地域課題を持つ人をつなぐ「シビックテックミーティング」
地域住民や団体などを主な対象とし、シビックテックに取り組む人々や興味がある人々、地域課題を持つ人々とが実際に顔を合わせ、協働につなげるためのイベント(講演、セミナー、ワークショップなど)を開催する。
4. 地域課題解決マッチングボックス「マッチ箱」
市民が自由に地域課題を投稿し、どのようにすれば解決できるかをWEB上で議論できる場を提供する。協働が可能な場合は希望者によりプロジェクトチームを結成し、解決に向け取り組む。
※一般社団法人コード・フォー・カナザワとの共同運用
特徴(独自性・新規性・工夫した点)
将来さらに多様化していく市民ニーズへは従来の画一的な行政サービスだけで対応することは難しい。シビックテックマインドをより多くの市民へ少しずつ浸透させ、市民や民間団体自らによる地域課題解決を後押しすることにより、より住みやすい地域社会の実現に向けた種を蒔く。全国で先駆けて設立したシビックテック団体「Code for Kanazawa」や、市内のIT企業とも協力し、地域課題の解決を進める。
取り組みの効果・費用
【効果】
・シビックテックスクールやデータ活用講座で習得したノウハウが地域課題解決のために利用されている。
・地域課題解決マッチングボックス「マッチ箱」では、134名のメンバーが参加し、26の課題が投稿されて、解決に向けた議論・協働が行われている。(令和6年5月27日現在)
【費用】
・シビックテック推進協議会費 年2,500千円
・シビックテックミーティング開催費 年 900千円
・マッチ箱運営費 年 330千円
取り組みを進めていく中での課題・問題点(苦労した点)
市民を主体とした課題解決プロセスを定着させていくことが目的であるため、行政はあくまで後押しする(講座やプラットフォームなどを提供する)という立場から、どのようにすれば市民などにシビックテックに対して興味をもってもらえるか、自主的にプレイヤーとして参加してもらえるかというアプローチが難しい。
今後の予定・構想
1. シビックテックマインドのさらなる浸透
ICTに関心がある人々への浸透は進んできたが、市民団体などへのシビックテックの認知度はまだまだ低い。実際に課題を多く持っているのは市民団体などの人々であり、それらの人々への浸透を目指す。
2. シビックテックプレイヤーの拡大
金沢市内には多くの学生やエンジニアなどがおり、近年CSR(企業の社会的責任)が求められている。シビックテック活動で得られるものは多いことを強調し、さらなるシビックテックプレイヤーの拡大を目指す。
3. 課題をもつ人自らによるICT活用による解決
スマートフォンなどの機器の普及、ノーコードツールやクラウドサービスの進歩が著しいことから、技術者に頼りすぎることなく“課題をもつ人自らがICTを活用して解決できる”環境づくりを進める。
他団体へのアドバイス
地元企業や地域団体の中には地域への貢献の機会を探している人が必ずいるはず。そうした人と地域課題を人をつなぐ場を提供することが、行政によるシビックテック推進の第一歩だと思う。
【金沢シビックテック推進協議会ホームページ】
https://kanazawa-civic-tech.jp/
【シビックテックミーティングカナザワホームページ】
https://civictechsummit.jp/

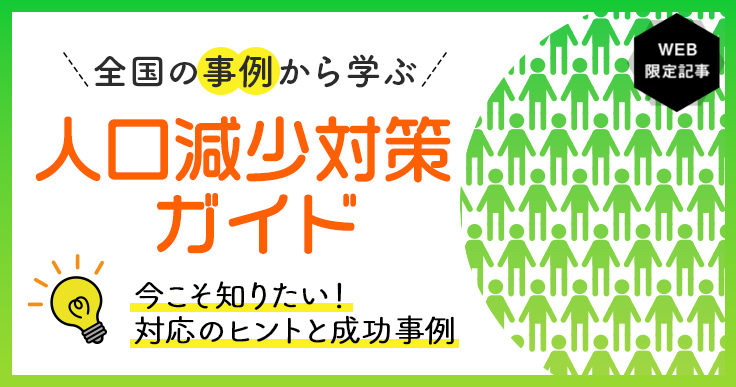
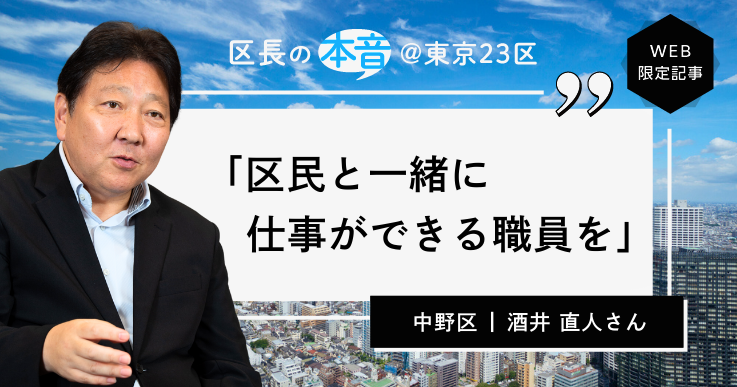
.png)











.jpg)
】バナー広告_株式会社ICHICO_PR.jpg)
.png)







