公開日:
公務員の休みはホントに多い?年間休日・有給・特別休暇から週休3日制まで徹底解説!

公務員は「民間よりも休みが多い」「休暇が取りやすい」と言われることがある。土日祝日と年末年始の休みに加え、有給休暇や特別休暇などの制度も整い、年間休日総数は確かに民間を上まわっている。ただ実際にどの程度休めるかは、部署や職種によっても異なるようだ。一方で近年は、週休3日制など柔軟な休み方を探る自治体も増えている。この記事では、地方公務員の休暇制度と取得の実態から、各自治体の先進的な事例までまとめて紹介。有利で効果的な休暇の活用に役立ててもらいたい。
【目次】
• 公務員の年間休日数はどれだけあるの?
• 年次休暇の取得の実態は?
• 特別休暇の種類と使い方は?
• ワークライフバランスと休暇制度の進化。週休3日制も!
• 先進自治体の取り組みは?
• 充実した休暇制度を活用して自分らしく働こう!
※掲載情報は公開日時点のものです。
公務員の年間休日数はどれだけあるの?

はじめに、公務員の休み方について紹介する。年間休日数および民間との違いを理解しておこう。
土日祝+年末年始休暇が基本
地方公務員の勤務条件については、地方公務員法 第24条にて「条例で定める」とされているが、基本的には、休日は週休2日(土日)・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)の場合が多い。
また、年間休日数は土日104日程度、土日と重複しない祝日16日程度、年末年始休暇6日程度で合計125日前後となる。
民間企業と比べると?
厚生労働省の「令和6年就労条件総合調査の概況」によると、民間企業の令和5年1年間の年間休日総数の平均は「112.1日」という調査結果が出ている。この日数は昭和60年以降で最も多い日数である。
補足だが、年間休日総数の平均を企業規模別に見ると以下の通りとなっている。
・1,000人以上:117.1日
・300~999人:115.9日
・100~299人:113.6日
・30~99人:110.0日
民間企業の年間休日総数は年々増加しており、公務員との差は縮小傾向にある。しかし公務員の場合、約6日間の年末年始休暇があるため、民間企業よりも日数が多くなる傾向がある。
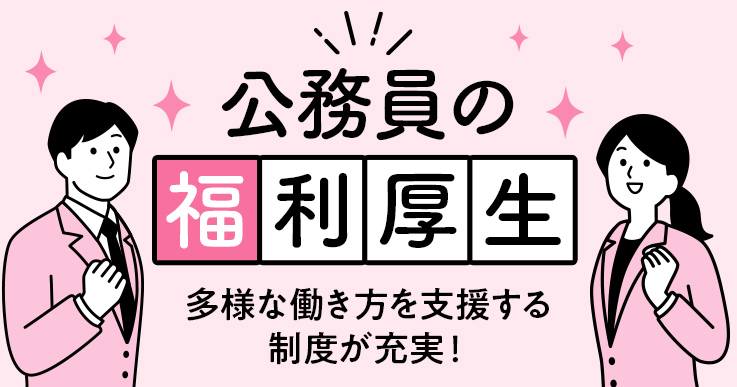 関連記事はコチラ
関連記事はコチラ
▶ 公務員の福利厚生について知ろう!手当・休暇・保険など、多様な働き方を支援する制度が充実
年次休暇の取得の実態は?
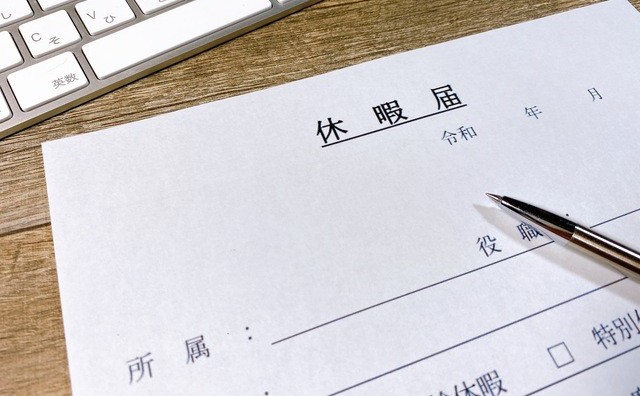
地方公務員の年次休暇と取得率について紹介する。民間企業や国家公務員との違いも確認しておこう。
年間最大20日。繰り越しも可能
地方公務員法 第24条で、「職員の勤務時間その他職員の給与以外の勤務条件を定めるに当つては、国及び他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない」と定められているため、年次休暇の日数や休みの取り方についても「年間20日」「1時間単位からの取得可能」と全国の自治体が横並びとなっている。
なお、公務員には労働基準法が適用されないため、どの自治体でも入職時から年次休暇が付与されている。これに対し民間企業は、労働基準法 第39条で「雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない」と定められており、入社後最低でも6カ月経過しないと年次休暇が付与されない。公務員と民間との大きな違いだ。
取得率は民間を上まわる
総務省「地方公務員における働き方改革に係る状況」によると、地方公務員の年次休暇平均取得日数(令和5年)は14.0日で取得率は70%という結果であった。
この数字は、民間企業の65.3%(平均付与日数16.9日・平均取得日数11.0日)よりは高いものの、国家公務員の80.1%(平均付与日数20.0日・平均取得日数16.2日)と比較すると低い。
※出典:総務省「地方公務員における働き方改革に係る状況」、厚生労働省「令和6年就労条件総合調査の概況 」、人事院「国家公務員の年次休暇の使用実態」
特別休暇の種類と使い方は?

地方公務員には、夏季休暇や育児休暇などの特別休暇も用意されている。種類や取得状況について詳細を解説する。
夏季、育児、介護、ボランティアなど充実
地方公務員の特別休暇には、3~6日の夏季休暇以外に、介護休暇、忌引休暇、結婚休暇、ボランティア休暇などがある。自治体にもよるが、特別休暇については条例や規則で明文化されていることが多く、時期にもよるが、希望すれば取得しやすいのが特徴だ。
一方、民間企業の場合、特別休暇制度自体が任意となっており、厚生労働省の「令和6年就労条件総合調査の概況 」によると、特別休暇制度を設けている企業の割合は59.9%となっている。さらに「夏季休暇はあるが、ボランティア休暇はない」など、制度の内容も企業ごとに異なっている。
男性の育休取得も増加中
地方自治体では男性の育休取得も増加傾向にある。総務省の「地方公務員における働き方改革に係る状況」によると令和5年度の男性地方公務員の育休取得率は前年比15.8%増の47.6%であった。ちなみに、同年度の民間企業で働く男性の育休取得率は13.0%増の約30%である。
民間企業と比較すると、男性の育休が取得しやすい環境ではある。しかし、男性地方公務員の育休期間は「2週間以上1カ月以下」が最も多く、女性地方公務員が取得した育休期間で最も多い「12カ月超24カ月以下」よりもかなり短いという特徴もある。
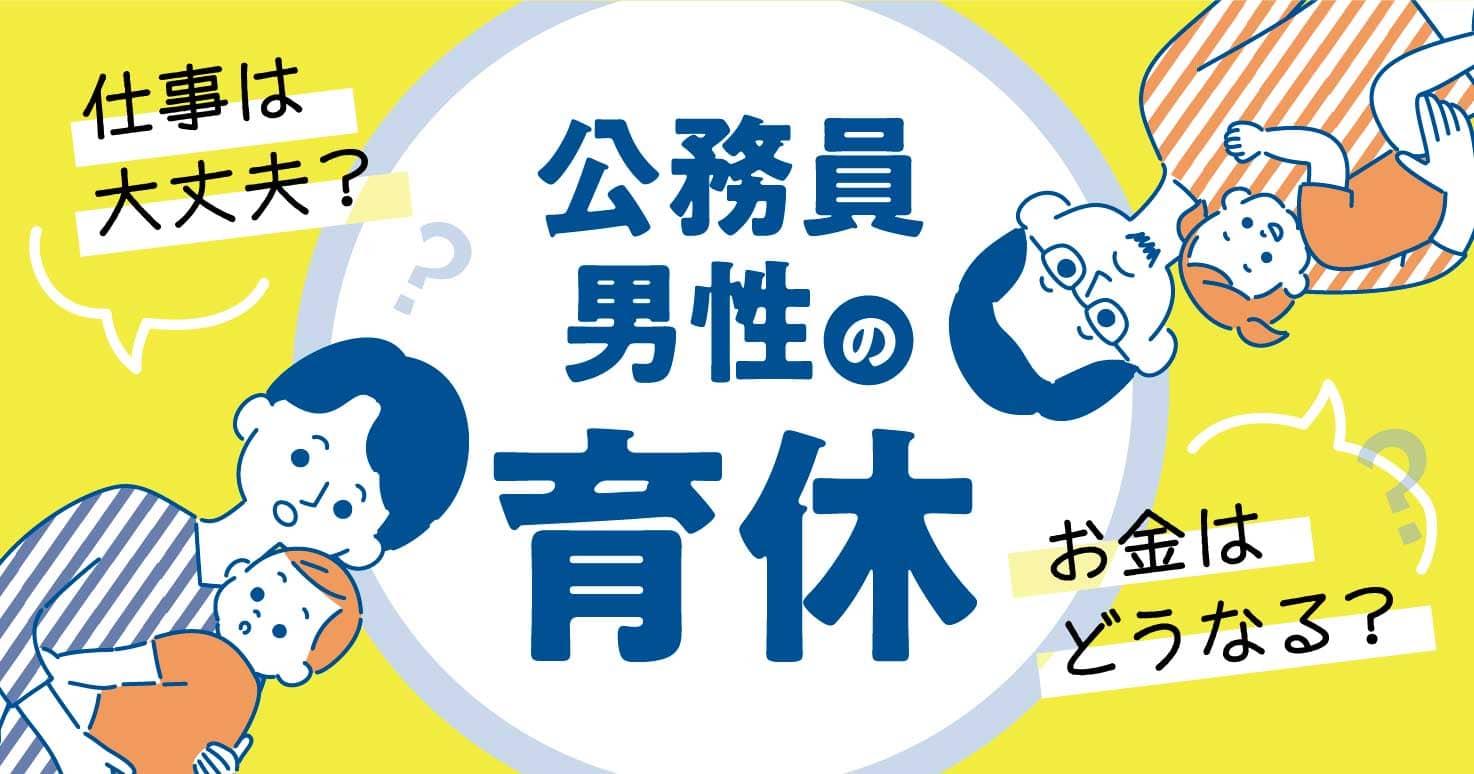 関連記事はコチラ
関連記事はコチラ
▶ 公務員男性の育休完全ガイド!手当・取得のポイントから成功のコツまで
ワークライフバランスと休暇制度の進化。週休3日制も!
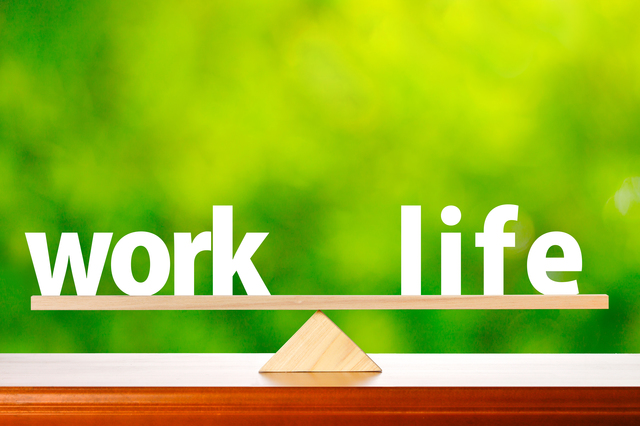
仕事と生活のバランスを取り、両方を充実させる「ワークライフバランス」が叫ばれるようになって久しい。地方自治体でも広がりつつある柔軟な働き方について整理しよう。
地方公務員にも「働き方改革」の波
デジタル社会の到来、感染症や大規模災害のリスク増大など様々な社会変化を経て、国全体で働き方が大きく見直されつつある。総務省も「働き手のライフプランや価値観の多様化への対応」を推進しており、労働基準法の適用を除外されている地方公務員の働き方についても、改革の流れが広がっている。
具体的な取り組みには「ノー残業デーの推進」「年休の計画取得」「子育て・介護への柔軟な対応」などがある。今後も「フレックスタイム制度導入」などが多くの自治体で進められるだろう。
「選択的週休3日制度」が公務員にも広がる
令和7年4月、総労働時間を変えずに土日にプラスしてもう1日休みが取れる「選択的週休3日制度」が官公庁で本格導入された。この流れに乗り、地方自治体でも導入を検討するところが増えている。
選択的週休3日制度は、人材確保や定着率向上の面から大きなメリットがあると考えられる。また、育児や介護と両立しながら働く人の助けにもなるはずだ。
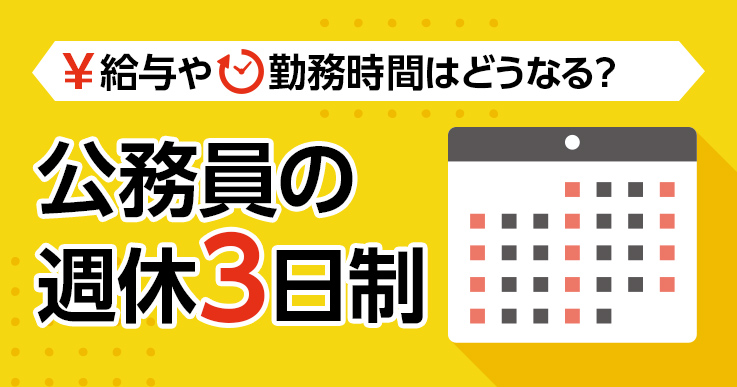 関連記事はコチラ
関連記事はコチラ
▶ 広がる公務員の選択的週休3日制度!給与や勤務時間はどう変わる?
先進自治体の取り組みは?

すでに、柔軟な働き方や休暇制定に取り組んでいる「栃木県宇都宮市」「千葉県」「佐賀県」「鳥取県」の例を紹介する。ぜひ参考にしてほしい。
栃木県宇都宮市
栃木県宇都宮市では、公務能率向上や職員のワークライフバランスを目的とし、フレックスタイム制度や選択的週休3日制度を一部で試行していたが、令和7年4月より、全ての部署に本格導入した。
同市のフレックスタイム制度・選択的週休3日制度では、4週間を1単位とし、総労働時間155時間が変わらないよう1日の勤務時間を設定できる。なお、必ず勤務しなければならないコアタイムは10時~16時となっている。
この制度を活用すると、「1日の最短労働時間:5時間」「1日の最大労働時間:10時間」「1週間当たりに追加可能な週休日数:1日」という働き方も可能となる。
出典:宇都宮市「働く環境」
千葉県
千葉県では、職員の柔軟な働き方を強化するため、全職員(交代制勤務職員・短時間勤務職員などは除く)を対象に令和6年6月からフレックスタイム制度を導入した。さらに週休を3日取得することも可能となっている。
同市のフレックスタイム制度のコアタイムは10時~15時。フレキシブルタイムの7時~22時の間に始業時間および終業時間を設定する。また、1週間につき1日に限り、週休日の設定も可能だ。
なお、4週間の単位期間内で155時間の勤務が必要だが、育児や介護などの事情がある場合、単位期間は1~4週間の間で選択もできる。
佐賀県
佐賀県では、夫婦一緒の子育て応援を目的として「ハッピー・ツー・ウィークス」という取り組みを令和3年度から実施。男性職員の2週間以上の育休取得率100%を目指している。具体的な取り組み内容は以下の通りだ。
・育休を取得しないことを例外にする目的で、14日間以上取得しない職員に「不取得理由書」の提出を求める
・「妻の出産前後に育休を連続取得」「妻の出産後、育休を取得」など、育休取得のパターンを職員に提示
これらの取り組みもあって、令和6年度12月時点で男性職員の育休取得率は86.3%となった。
出典:佐賀県「『ハッピー・ツー・ウィークス』を始めました!」
鳥取県
鳥取県では令和5年9月、職員の自治会やPTAなどの地域活動、およびボランティア活動への参加促進を目的として「ふるさと応援休暇」を制定した。
また、同年10月には、更年期世代の職員が引き続き能力を発揮するための支援として「更年期障がい休暇」が、令和6年には、職員自身や家族が犯罪被害にあった時に取得できる「犯罪被害職員等支援休暇」が新設されている。
※出典:鳥取県「特別休暇(ふるさと応援休暇、更年期障がい休暇)の新設について」、「犯罪被害職員等支援休暇の承認の請求及び取得状況の管理について(通知)」
充実した休暇制度を活用して自分らしく働こう!

地方公務員の休暇制度は、法律や条例によって整備されているため、民間企業と比較すると、休みを取得しやすいという特徴がある。年間約125日の休日や特別休暇に加え、フレックスタイム制度や選択的週休3日制度の導入も進みつつあり、非常に恵まれた環境にあるといえるだろう。
今後は、より一層の多様化が期待できる。自身の自治体で導入されている制度を十分に理解し、自分らしい充実した働き方を実現してほしい。

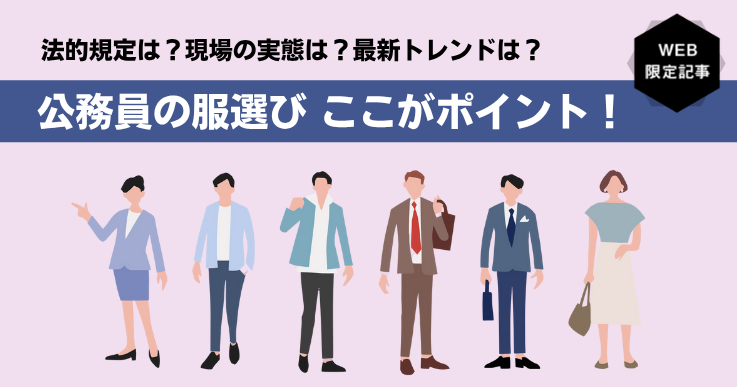


.jpg&w=3840&q=85)








