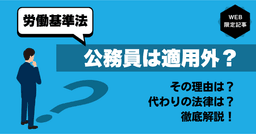この記事で分かること
■日本の水産業が直面する深刻な課題
■国や自治体、地域で進められている解決への取り組み
■技術革新と消費者の役割の重要性
日本の水産業が抱える主な課題

日本の食卓に豊かな海の幸を届けてきた水産業は、今、多くの厳しい課題に直面している。これらの課題は、漁業関係者だけでなく、私たちの食生活や海洋環境にも深く関わっている。ここでは、日本の水産業が抱える主な課題について具体的に見ていこう。
深刻化する漁獲量の減少とその要因
日本の漁業・養殖業の生産量は長期的に減少傾向にある。水産庁の統計によれば、昭和59年のピーク時には1,282万トンだった漁業・養殖業の生産量は、令和2年には423万トンまで減少している。 この背景には、地球温暖化に伴う海水温の上昇や海流の変化、一部魚種における乱獲、さらには外国漁船による違法・無報告・無規制(IUU)漁業などが複合的に影響していると考えられている。特定の魚種、例えばサンマやスルメイカなどは、近年特に深刻な不漁が続いており、食卓への影響も出ている。
出典:水産庁「漁業・養殖業の国内生産の動向」
担い手不足と高齢化の現状
漁業就業者数は年々減少し、同時に高齢化が進行している。農林水産省の「漁業センサス」によると、海面漁業者に関して、平成15年に約23.8万人だったが、令和5年に約12.1万人と、半分以下にまで落ち込んでいる。
さらに、漁業就業者の高齢化も深刻で、平均年齢は60歳を超える状況が続いており、65歳以上の就業者が全体の4割近くを占めるというデータもある。若者の漁業離れや後継者不足は、伝統的な漁業技術の継承を困難にし、地域社会の活力低下にもつながっているのだ。
出典:政府統計の総合窓口「漁業センサス」
魚食文化の変化と国内消費の低迷
日本人の魚介類消費量は、食生活の多様化やライフスタイルの変化などを背景に、長期的に減少傾向にある。水産庁の「食料需給表」によると、1人1年当たりの食用魚介類消費量は、平成13年度の40.2kgをピークに減少し、令和4年度には22.0kgとなっている。
特に若年層を中心に魚離れが進んでいるとの指摘もあり、魚調理の煩わしさや、肉類と比べた価格の高さなどが要因として考えられる。国内消費の低迷は、水産物の価格形成にも影響を与え、漁業経営を圧迫する一因となっている。
出典:政府統計の総合窓口「食料需給表」
燃料価格高騰と漁業経営への影響
漁船の燃料として使用されるA重油や軽油の価格は、国際的な原油価格の変動や為替レートの影響を大きく受ける。近年、燃料価格は高値水準で不安定な動きを見せており、漁業経営における大きな負担となっている。
漁業支出に占める燃料費の割合は、漁業種類によって異なるが、15%以上を占めることもあり、特に燃料消費量の多いイカ釣り漁業や底引網漁業などでは、経営への影響が深刻だ。国や県は、燃料価格高騰に対するセーフティーネット事業などを実施しているが、根本的な解決には至っておらず、多くの漁業者が厳しい経営状況に置かれている。
出典:H27学術講演会論文集60「イカ釣り漁業のエネルギー収支」
海洋環境の変化と環境問題
地球温暖化に伴う海水温の上昇や海洋酸性化、海洋プラスチックごみ問題など、海洋環境の変化は水産業に多大な影響を及ぼしている。海水温の上昇は、魚種の分布域の変化や回遊ルートの変動を引き起こし、これまで獲れていた魚が獲れなくなったり、逆にこれまで見られなかった魚種が漁獲されたりする現象が各地で報告されている。
また、海洋プラスチックごみによる海洋汚染は、生態系への悪影響だけでなく、水産物の安全性への懸念も引き起こしている。磯焼けによる藻場の減少も、多くの水産生物の生育環境を脅かす問題となっている。
水産業の課題解決に向けた国の取り組み

日本の水産業が抱える数々の課題に対し、国は持続可能な発展を目指して様々な取り組みを進めている。資源管理の強化から、漁業の成長産業化、スマート水産業の推進に至るまで、多角的なアプローチが展開されている。
水産資源管理の強化と推進
水産庁は、科学的根拠にもとづく資源評価を拡充し、漁獲可能量(TAC)制度による管理対象魚種を拡大するなど、資源管理の強化に取り組んでいる。改正漁業法にもとづき、MSY(最大持続生産量)ベースでの資源評価を進め、令和12年度までに漁獲量を444万トンまで回復させることを目標としている。
また、漁業者による自主的な資源管理計画(資源管理協定)の策定と実施を促し、地域の実情に応じたきめ細やかな管理体制の構築を支援している。国際的な資源管理にも積極的に参画し、地域漁業管理機関(RFMOs)を通じた国際協力を推進している。
出典:水産庁「新たな水産基本計画」
漁場環境の保全と改善活動
国は、水産動植物の生育環境である藻場・干潟の造成や保全、海底耕うん、漂着物・堆積物の除去といった漁場環境改善の取り組みを支援している。特に、栄養塩類の供給を通じた漁場生産力の回復や、赤潮・貧酸素水塊の被害防止対策技術の開発、海洋プラスチックごみの削減に向けた活動も推進している。
出典:水産庁「水産多面的機能発揮対策事業」
水産業の成長産業化と輸出促進
水産庁は「養殖業成長産業化総合戦略」を策定し、マーケットイン型の養殖業への転換を目指している。この戦略では、ブリやマダイといった魚類に加え、ホタテや真珠などの貝類・藻類も対象とし、生産から販売・輸出まで一貫した取り組みを推進している。 具体的には、優良種苗の開発・供給、養殖技術の高度化、HACCP対応型施設の整備支援などを通じて国際競争力の強化を図っている。
出典:水産庁「養殖業成長産業化総合戦略」
スマート水産業の導入支援
担い手不足や高齢化が進む中、ICTやAI、IoTといった先端技術を活用した「スマート水産業」の導入が期待されている。水産庁は、漁船のブロードバンド化や漁獲情報などの電子化、AIを活用した資源評価や漁場予測システムの開発・実証を支援している。
具体例としては、ICTブイによる海洋観測データのリアルタイム収集、AIによる給餌の最適化、ドローンを活用した漁場探索や養殖場の管理などが挙げられる。これらの技術導入により、操業の効率化、省力化、安全性の向上、そして若者の就業促進を目指している。
出典:水産庁「スマート水産業」
持続可能な水産業を実現する各地の取り組み事例

日本各地で、水産業の持続可能性を高めるための多様な取り組みが展開されている。資源管理の先進事例から、最新技術の導入、担い手育成まで、地域の実情に合わせた創意工夫が見られる。
北海道における資源管理型漁業の推進事例
広大な海域を有する北海道では、古くから漁業種類や魚種ごとに資源管理型漁業が推進されてきた。例えば、ホタテガイ漁業では、稚貝の放流や桁網の網目制限、休漁期間の設定などを通じて資源の維持・増大を図っている。
道庁は「北海道水産業・漁村振興推進計画」を策定し、水産資源の適切な管理と秩序ある利用を基本方針の一つとして掲げている。漁業者は「資源管理協定」を締結し、自主的な資源管理に取り組んでいる。
出典:北海道政府「北海道水産業・漁村振興推進計画(第5期)」
三重県におけるICT活用による養殖業効率化事例
三重県では、ICTやAIを活用したスマート養殖の取り組みが進んでいる。特にクロノリ養殖において、三重県水産研究所や鳥羽商船高等専門学校、地元企業が共同で、漁場環境をリアルタイムで監視できるIoT海洋観測モニタリングシステム「うみログ」を開発した。
このシステムは、養殖漁場に設置した観測機器から水温、潮位、クロロフィル濃度などの情報を収集し、スマートフォンアプリで漁業者が確認できるようにするものである。これにより、養殖開始日の決定、異常潮位時の網の高さ調整、ノリの色落ち予測などに活用され、生産効率の向上や品質管理に貢献している。
出典:三重県「水産業スマート化推進事業」
出典:株式会社アイエスイー「海洋モニタリングシステム「うみログ」新登場 」
長崎県における若手漁業者育成の取り組み事例
漁業就業者の高齢化と後継者不足が深刻な問題となる中、長崎県では若手漁業者の育成と確保に力を入れている。県は「ながさき漁業伝習所」を設置し、漁業未経験者やU・Iターン希望者に対して、漁業技術の研修から就業相談、独立自営に向けた支援まで、段階に応じたサポートを提供している。
また、「新たにチャレンジ水産経営応援事業」などを通じて、若手漁業者が行う新たな漁法の導入や海業・6次産業化への挑戦を支援している。県内各地の漁業者がUターンやIターンで就業し、活躍している事例も多く紹介されている。
出典:長崎県庁「ながさき漁業伝習所」
出典:長崎県庁「新たにチャレンジ水産経営応援事業」
企業や研究機関による技術開発とイノベーション

水産業の持続可能性と成長産業化を目指し、企業や研究機関では、AI、IoT、ロボティクスといった先端技術を活用した様々な技術開発やイノベーションが進められている。これらの技術は、漁業の効率化、省力化、そして環境負荷の低減に貢献することが期待される。
AI・IoTを活用した漁撈技術の高度化
AI(人工知能)やIoT(モノのインターネット)技術は、漁撈活動の様々な場面で活用され始めている。例えば、衛星情報や気象・海象データ、過去の漁獲実績などをAIが解析し、精度の高い漁場予測を行うシステムが開発されている。
これにより、漁船は効率的に漁場へ向かうことができ、燃料費の削減や操業時間の短縮につながる。また、IoTセンサーを搭載したブイや漁具からリアルタイムで水温、塩分濃度、魚群情報などを収集し、操業判断を支援するシステムも登場している。
環境負荷の少ない陸上養殖システムの開発
海洋環境への負荷を低減し、持続可能な養殖業を実現するため、閉鎖循環式陸上養殖システムの開発が進んでいる。このシステムは、飼育水を浄化して再利用するため、排水による海洋汚染のリスクを大幅に低減できる。
また、外部環境から隔離されているため、病気の発生リスクを抑えやすく、薬剤の使用量を減らすことにもつながる。さらに、立地を選ばないため、消費地に近い場所での生産も可能となり、輸送コストの削減や鮮度の高い水産物の供給が期待できる。
未利用魚や低利用魚の価値化と商品開発
漁獲されてもサイズが小さい、知名度が低いなどの理由で市場にあまり出回らない「未利用魚」や「低利用魚」を有効活用する取り組みが広がっている。これまで十分に利用されてこなかったこれらの魚種に新たな価値を見出し、加工品や新メニューとして商品開発することで、フードロス削減と漁業者の収入向上を目指すのである。
これらの取り組みは、消費者に新たな味覚を提供するとともに、水産資源の持続的な利用にも貢献するのである。
代替たんぱく質としての水産物の可能性
世界の人口増加に伴う食料需要の増大や、環境負荷への意識の高まりから、代替たんぱく質の開発が注目されている。水産物においても、培養技術を用いたシーフードの開発や、藻類などからたんぱく質を抽出する研究が進められている。
これらの技術は、天然資源への依存を減らし、持続可能な食料供給システムを構築する上で重要な役割を果たす可能性がある。まだ開発途上の段階ではあるが、将来的には水産業の新たな選択肢として期待されている。
私たち消費者にできること

水産業の持続可能性は、生産者側の努力だけでなく、私たち消費者の意識と行動によっても大きく左右される。日々の食卓で魚を選ぶ際に、少し意識を変えるだけで、豊かな海を守り、未来へつなぐことに貢献できる。
責任ある水産物(サステナブル・シーフード)の選択
持続可能な漁業で獲られた、あるいは環境や社会に配慮した養殖場で育てられた水産物、いわゆる「サステナブル・シーフード」を選ぶことは、私たち消費者ができる最も直接的な貢献の一つである。
MSC(海洋管理協議会)認証やASC(水産養殖管理協議会)認証といった国際的な認証ラベルが付いた商品を選ぶことで、資源管理や環境保全に積極的に取り組む漁業者や養殖業者を応援することができる。日本でも、MSC「海のエコラベル」の認知度は向上しており、消費者の3人に1人がサステナブル・シーフードを選びたいと考えているという調査結果もある。
地産地消による地域漁業の応援
地元で獲れた魚を積極的に消費することも、地域の漁業を支える大切な行動である。輸送距離が短い地元の魚は鮮度が高く、輸送に伴う環境負荷も低減できる。また、地域の魚食文化に触れるよい機会にもなる。
直売所や地元の鮮魚店を利用したり、地域の漁業者が開催するイベントに参加したりすることで、生産者の顔が見える関係を築き、地域経済の活性化にもつながる。
海洋ごみ問題への意識と行動
プラスチックごみをはじめとする海洋ごみは、海の生態系に深刻な影響を与え、水産資源を脅かしている。私たち一人ひとりが日常生活でプラスチックごみの削減を心がけること、例えばマイボトルの利用、レジ袋の削減、適切なごみの分別とリサイクルなどが重要である。また、海岸清掃活動に参加するなど、積極的に海の環境保全に関わることも、豊かな海を守る行動の一つである。
まとめ
日本の水産業は、漁獲量の減少、担い手不足、海洋環境の変化といった多くの課題に直面しているが、これらの課題解決に向け、国、自治体、企業、研究機関、そして私たち消費者が一体となった取り組みが進められている。
資源管理の強化、スマート技術の導入、持続可能な漁業認証の普及などを通じて、水産業の未来をより明るいものにしていくことが求められている。これらの努力が実を結び、豊かな海の幸が将来の世代にもたらされることを期待する。



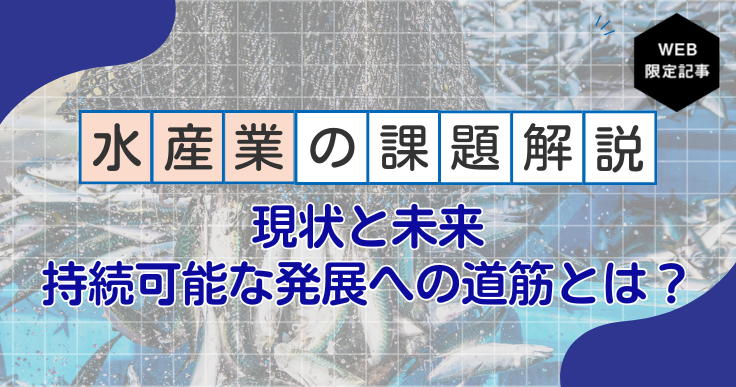 【あわせて読みたい】
【あわせて読みたい】

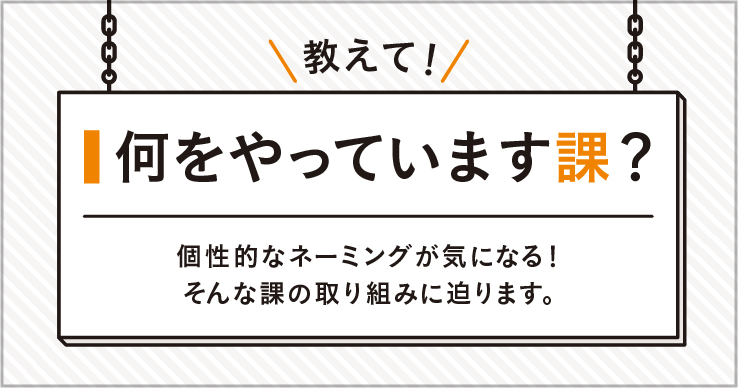 【あわせて読みたい】富山県入善町「キラキラ商工観光課」の取り組み
【あわせて読みたい】富山県入善町「キラキラ商工観光課」の取り組み

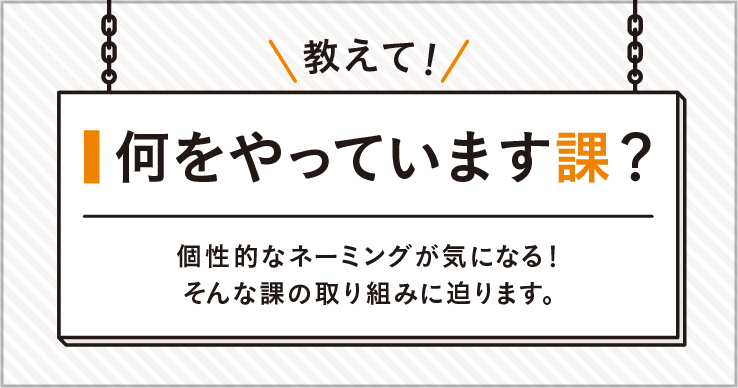 【あわせて読みたい】三重県「フードイノベーション課」の取り組み
【あわせて読みたい】三重県「フードイノベーション課」の取り組み