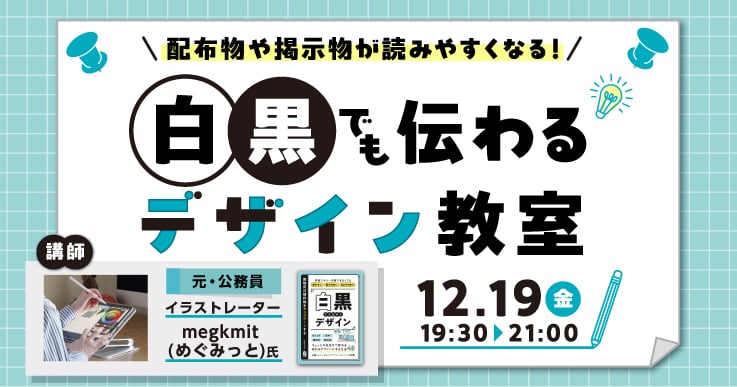公開日:
前例踏襲からの脱却方法|改革を進める具体的な3ステップや成功事例を紹介
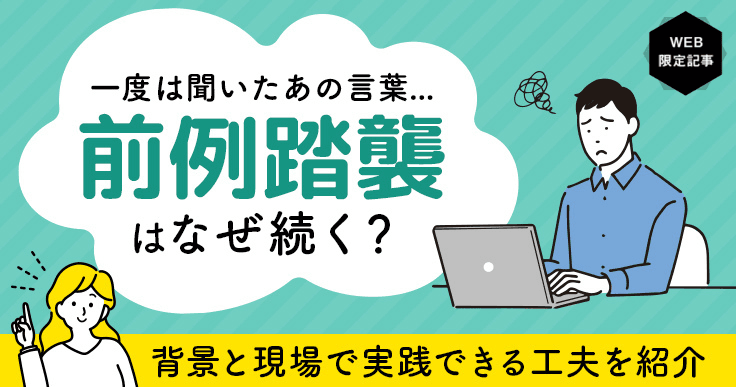
前例踏襲(ぜんれいとうしゅう)とは、過去のやり方をそのまま引き継ぐことである。公務員組織ではリスク回避や失敗防止の観点から当然視されてきた。しかし人口減少やDX推進など変化の時代には、前例に頼らない柔軟な対応が欠かせない。本記事ではその背景とメリット・デメリットを整理し、公務員が改革を進める脱却方法3ステップと自治体の成功事例を紹介する。
※掲載情報は公開日時点のものです。
■前例踏襲のメリットとデメリットが業務や住民サービスに及ぼす具体的な影響
■脱却の3ステップと自治体に学ぶ実践的な成功事例
前例踏襲とは?公務員組織に根強い理由と課題
前例踏襲(ぜんれいとうしゅう)とは、これまでに行われたやり方をそのまま引き継ぎ、同じように仕事を進める考え方である。公務員組織といえば「前例踏襲」というイメージがある人も多いだろう。なぜ、このような文化が根付いたのかを探ってみる。
公務員組織に根づくリスク回避の風土
公務員には、法令順守や公平な判断が求められ、失敗が許されにくい環境にある。このため、批判や混乱を避けるリスク回避の姿勢が、日々の業務に根づいてきた。
また、公務員組織は、安定した雇用や昇進制度が整い、着実な仕事ぶりが評価されやすい。その結果、過去のやり方を踏まえて進める「前例踏襲」の文化が形成されやすくなった。前例に従う判断は、安全で確実な対応として受け入れられることが多く、それが積み重なって、前例踏襲が自然な選択肢として根づいたといえる。
失敗できない文化と責任の所在
公務員の業務では、ちょっとしたミスが住民からのクレームや法令違反につながるおそれがある。また、誤りが発生した場合でも、訂正には多くの確認や手続きが必要になることもあり、簡単には修正できないケースも少なくない。こうした背景から、公務員組織では「失敗は許されない」という意識が強まりやすい。
さらに、国家賠償法では、公務員の行為によって損害が生じた場合、原則として国や自治体が賠償責任を負うが、重大な過失があれば、公務員個人に対して求償される可能性もある。このような制度上のリスクも、慎重な判断やリスク回避の姿勢につながっている。
若手職員の提案が通りにくい構造
公務員組織では、「縦割り」や「年功序列」といった意識が根強く残っており、若手職員の提案が通りにくい構造がある。現場で出される改善案や新しい取り組みも、「前例がない」「過去に例がない」として退けられることがあり、結果として前例踏襲の文化が維持される要因となっている。
前例踏襲のメリットとデメリット
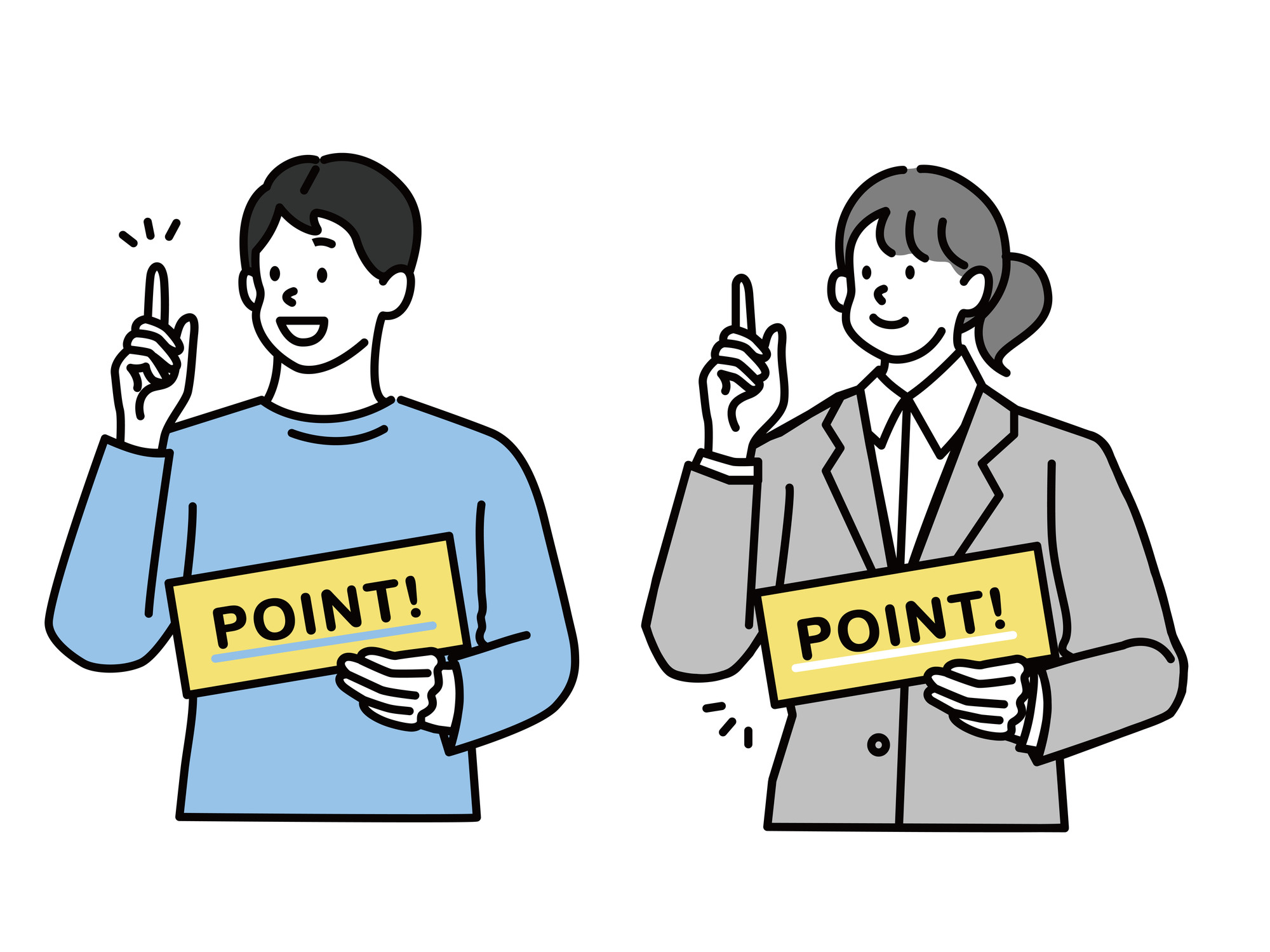
前例踏襲は、しばしば「変化を拒む姿勢」として否定的に語られることもあるが、必ずしも悪いこととは言い切れない。特に行政の現場では、過去の事例に基づいた判断や運用が、業務の安定性や公平性の確保につながる場面も多い。
一方で、状況の変化に対応できないまま前例に固執してしまうと、非効率や形骸化を招くおそれもある。ここでは、前例踏襲のメリットとデメリットを整理し、その意味や役割を改めて考えてみたい。
メリット
1. 考える時間や労力を省ける
書類の様式や作業手順など、あらかじめ決まった前例があれば、新たな方法を検討する必要がない。そのため、打ち合わせや判断の時間を短縮し、効率よく業務を進めることができる。特に限られた時間内で確実に対応する必要がある場面では、前例踏襲は大きなメリットとなる。
2. 公平なサービス提供につながる
住民サービスにおいては、対応の一貫性と公平性が求められる。全ての職員が前例に従って対応することで、担当者ごとの判断による差異が生じにくくなり、行政としての信頼性の向上にもつながる。
3. 業務の引き継ぎが容易になる
業務のやり方が前例として明文化・共有されていれば、異動時の引き継ぎもスムーズになる。過去の対応や手順を参考にすれば、疑問が生じたときにも周囲や記録から答えを得やすく、職員間の知見が循環しやすくなる。
デメリット
1. 業務改善の機会を逃しやすい
前例をそのまま踏襲していると、押印の見直しやデジタル化など、本来であれば効率化につながる施策の導入が後回しになってしまうことがある。改善の必要性に気づいても、「これまで通り」で済ませてしまうことで、組織全体の業務改革が進みにくくなる。
2. 住民ニーズの変化に対応しづらい
前例が作られた当時と比べて、住民の要望や利用環境は大きく変化している。「オンライン申請をしたい」「高齢者にもわかりやすくしてほしい」といった声に応えるには、柔軟な見直しが欠かせない。過去の基準をそのまま使い続けることで、住民満足度を下げる可能性もある。
3. 思考停止につながりやすい
「過去にこうやってきたから」と思考を止めてしまうと、課題の本質を捉えられず、改善の芽を摘むことになる。前例に依存し続けることで職員の成長機会も失われる。
4. 時代遅れや業務負担の偏りを生む
状況の変化に合わせた見直しを怠ると、制度や手順が現実にそぐわなくなり、時代に取り残される。古い仕組みを維持することでムダや非効率が積み重なり、結果として特定の職員に過度な負担が偏るなど、新しい不合理を生む要因となる。
前例踏襲には一定の利点がある一方で、変化する住民ニーズや業務の効率化に対応するには、柔軟な見直しも欠かせない。
これまでのやり方を見直すことで、改善のチャンスが生まれ、職員にとっても働きやすい環境づくりにつながる。前例にとらわれず、一歩踏み出すことが、よりよい行政サービスへの第一歩となるだろう。
公務員ができる前例踏襲からの脱却方法3ステップ

前例踏襲には一定の役割もあるが、変化の大きい時代には見直しが不可欠である。では、公務員が現場で実践できる脱却の方法とは何か。ここでは、無理なく始められる3つのステップを紹介する。
1. 「目的」と「根拠」を仕分けする
前例踏襲から脱却するためには、まず業務の「目的」と「根拠」を明確に仕分けすることが不可欠である。自治体職員の業務では、法令や条例によって義務付けられている業務と、慣習的に続けてきた業務が混在している。この二つを区別できなければ、改善可能な業務と不可欠な業務の線引きができず、非効率な慣習が温存されてしまう。
仕分けの際には、次の3つの観点が有効である。
◆法令・条例に明記されているか(変更できない前例)
例:住民票の発行や選挙事務は法律で定められた手順であり、住民サービスの公平性を守るため、見直しはできない。
◆住民の安全や公平性に直結する業務(慎重に扱うべき前例)
例:災害時の避難所運営や福祉サービスの申請受付は、住民の命や権利を守るために必要である。
◆慣習で続く業務(見直し可能な前例)
例:担当者がExcelで手入力・集計を続けているが、スプレッドシートにすれば共有や自動集計がしやすくなる業務。
このように、目的と根拠を切り分けることで「本当に守るべき前例」と「見直すべき前例」が明確になる。小さな慣習的業務であっても改善を積み重ねることで、住民サービスの質を高めながら、自治体における前例踏襲からの脱却を実現できる。
2. “小さな実験”として提案する
前例踏襲から脱却する際に有効なのは、業務改善をいきなり全面導入するのではなく、“小さな実験”として実施することである。自治体職員の業務は住民サービスに直結するため、大規模な変更は抵抗感を生みやすい。まずは一部の業務や限定的な範囲で試し、効果を検証することが望ましい。
小さな実験を設計する際は、次の3つの視点を意識するとよい。
◆対象範囲を限定する
例:一課内、特定の地区、あるいは一つの業務に絞って試行する。
◆撤退条件を明示する
例:利用率が一定基準を下回った場合やトラブルが想定以上に発生した場合は中止するなど、数値や期間を含めた条件を設ける。
◆目的を住民サービスに結びつける
例:「効率化」よりも「住民の利便性向上」「公平性の担保」といった言葉で説明すると理解を得やすい。
例えば、従来は紙で行っていた申請受付を、一部のみオンラインで試行する方法がある。栃木県大田原市や静岡県沼津市では、マイナポータルの「ぴったりサービス」を活用して市民講座やイベント申込をオンライン化し、住民は24時間いつでも申し込めるようになった。あわせて職員による入力や集計作業も削減され、業務効率化にもつながっている。
このように「住民の利便性向上」と「職員の業務効率化」の双方を示せば、関係者からの賛同を得やすい。小さな実験として成果を出すことが、前例踏襲を乗り越える大きな一歩になる。
出典:デジタル庁「イベント等申込のオンライン化に関するぴったりサービスの活用事例」
3. 成果を“新しい前例”にする
小さな実験を行った後は、その成果を明確に記録し、庁内で共有することが不可欠である。前例踏襲から脱却するには、従来のやり方よりも「効果がある」と客観的に示さなければならない。そのためには、成果を数値や住民の声で可視化することが重要である。
・例:処理日数が30%短縮した
・例:窓口での待ち時間が10分減少した
・例:住民からの苦情件数がゼロになった
こうした成果を庁内資料やマニュアルに反映すれば、改善は「一時的な試み」ではなく、新しい前例として定着する。また、「1年後に再検証する」といった見直し時期を設定すれば、硬直した“新しい前例踏襲”を防ぎ、改善が継続的に循環する仕組みを構築できる。
この3ステップを踏むことで、「従来のやり方をただ否定する」のではなく、データに基づいて前例を見直し、改善を積み重ねることが可能になる。次章では、このアプローチを実践し、業務効率化や住民サービス向上につなげた自治体の成功事例を紹介する。
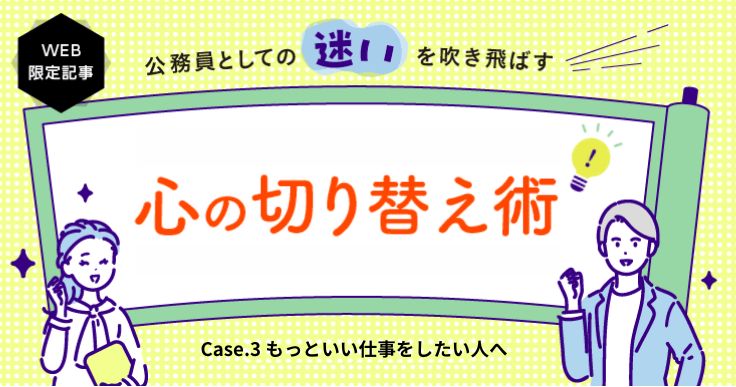 【あわせて読みたい】心の切り替え術!
【あわせて読みたい】心の切り替え術!
▶もっといい仕事をしたいと思っている人にぜひ読んでほしいこと。
前例踏襲を見直した自治体の成功事例

前例踏襲からの脱却は重要だが、全てを一から作り直す必要はない。既存の制度や手続きを活かしながら改善する方が効率的で現実的である。その際には、他自治体の取り組みを参考にするのも有効だ。
庁内で横展開しやすい成功事例を取り入れれば、失敗のリスクを抑えつつ改善を進められる。ここからは、前例を活かしつつ不足を補った自治体の成功事例を紹介する。
静岡県浜松市|庁内データ可視化で業務改善の基盤を構築
浜松市は庁内データ分析基盤を用いて、業務の実態や課題を可視化し、部局横断的にエビデンスを共有。これにより、効率化や政策立案の質向上を支える仕組みが構築されている。
-取り組み内容:庁内データ分析基盤を導入し、部局横断で業務データを可視化。
-ポイント:既存制度(業務フローや決裁ルール)は残しつつ、「データに基づいた施策の立案、評価、課題改善」をした。
このように同市では、従来の前例を全て否定するのではなく、既存制度を活かしながら新しい仕組みを柔軟に取り入れている。「前例を踏襲する」か「ゼロから作り直す」かの二択ではなく、現状を維持しつつ必要な部分だけを見直すことで、業務改善の成果を上げた好例といえる。
福岡県古賀市|LINE活用による行政手続きの利便化と時間削減
古賀市はデジタル実装の前例がない中で、公式LINEアカウントを活用し、住民向けの事業予約や災害情報の配信を行ってきた。さらに、LINEによる予約導入により、窓口への来庁が減少し、窓口受付時間を最大90分短縮する成果を上げている。利便性向上だけでなく、職員の負担軽減にも寄与した事例である。
-従来の前例:窓口や電話による予約受付が慣例だった。
-取り組み内容:公式LINEを活用して住民がオンラインで予約できる仕組みを導入。
-ポイント:住民サービスの手段を拡張しただけで、既存の窓口受付フロー自体は廃止していない。
同市は、既存の窓口予約の仕組みを残しつつ、オンラインでのLINE予約という新たな選択肢を追加した。従来の前例を壊すのではなく「補完する」形で住民サービスを向上させた好例であり、デジタル化の第一歩として参考になる事例である。
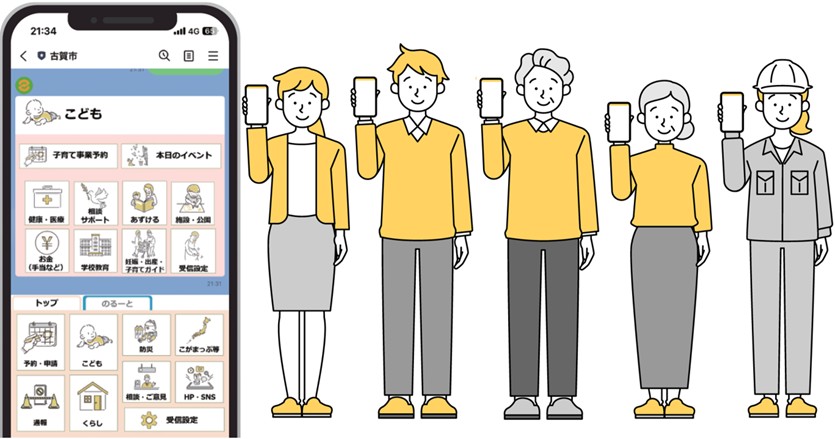 【あわせて読みたい】福岡県古賀市の取り組み事例
【あわせて読みたい】福岡県古賀市の取り組み事例
▶デジタル活用で来庁者が減少し、窓口受付時間を90分短縮へ。
【FAQ】前例踏襲に関するよくある質問
Q. 「前例踏襲」は悪い意味?
A. 前例踏襲は必ずしも悪い意味ではない。業務の安定性や公平性を保つ利点がある一方、変化に対応できず非効率や住民ニーズの遅れを招く場合もある。重要なのは「悪」と決めつけることではなく、状況に応じて活用と見直しを使い分けることだ。
Q. 前例踏襲のメリットとデメリットは?
A. メリットは判断の迅速化・公平性の確保・引き継ぎの容易さ。デメリットは業務改善の遅れ・住民ニーズへの不対応・法改正との齟齬である。
Q. 公務員が前例踏襲から脱却する方法は?
A. 目的と根拠を仕分け、小さな範囲で試行し、成果を数値で示すことが有効。段階的に改善を広げれば抵抗感を抑えつつ「新しい前例」を作れる。
前例踏襲を見直し、新たな前例をつくる
前例踏襲には、「考える手間を省ける」「公平な住民サービスを提供しやすい」「業務の引き継ぎがしやすい」といったメリットがある一方で、「業務改善のタイミングを逃す」「住民ニーズの変化に対応できない」「業務の問題点を振り返りづらい」といったデメリットもある。現状に合った住民サービスの提供や役所内の業務効率化を進めたいのであれば、前例踏襲を見直すことが重要である。
ただし、全ての前例を否定する必要はない。まずは、自分や身の回りの小さな業務から見直しを始め、部署内で共有しながら少しずつ改善していくとよい。既存の制度や手順の中で有効なものは残しつつ、不要なものや現状に合わないものだけを見直すことで、住民サービスの質を保ちながら、より柔軟で効率的な業務運営が可能になる。
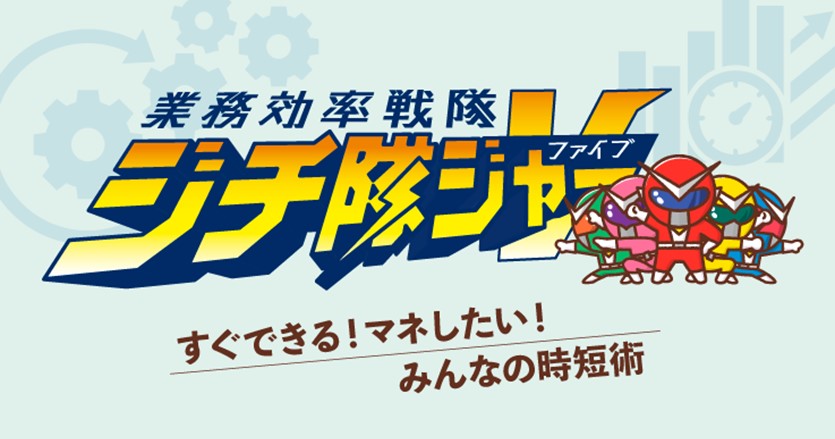 【あわせて読みたい】時短効率戦隊-ジチ隊ジャーV-
【あわせて読みたい】時短効率戦隊-ジチ隊ジャーV-
▶すぐできる!マネしたい!みんなの時短術


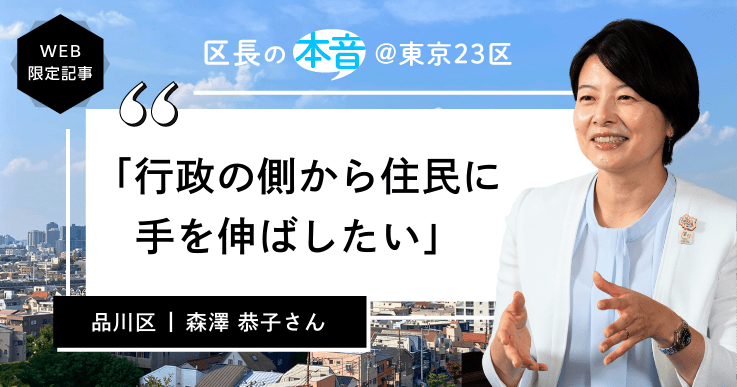
.png&w=3840&q=85)