公開日:
空き家活用の成功事例15選!テーマ別自治体の取り組みや使える支援制度も紹介

全国の空き家活用成功事例15選と、自治体が活用できる支援制度・補助金のポイントを紹介する。空き家の増加が続く中、賃貸住宅や民泊、古民家カフェなど多様なアイデアで地域活性化や移住促進に成功した自治体が増えている。本記事では、成果を上げた自治体の取り組みと支援制度を整理し、今後の施策立案に役立つ実践的なヒントをまとめた。
※掲載情報は公開日時点のものです
空き家問題の現状と社会的影響

空き家問題は、身近な社会課題となっている。総務省が令和6年に公表した「住宅・土地統計調査」によると、令和5年の空き家数は約900万戸に達し、平成30年から51万戸増加した。 使用目的のない空き家はこの20年間で約2倍に増加しており、総住宅数に占める割合も13.8%と過去最高を更新している。
老朽化や景観の悪化、防災・治安への影響など、地域への影響は大きく、自治体にとっても早期の対応が求められている。
空き家増加の背景と放置の要因
空き家が増える背景には、実家の相続や親の施設入居など、身近な事情がある。 一度空き家になると、「解体費用をかけたくない」「家財を片付けられない」「将来使うかもしれない」といった理由から判断が遅れ、放置されるケースが多い。
国土交通省の調査では、空き家所有者の約4分の1が1時間以上離れた地域に居住しており、こうした遠隔地所有や管理負担が放置を助長している。
国の政策動向と自治体支援制度
令和5年の「空家等対策特別措置法」改正では、倒壊のおそれがある「特定空家」に加え、管理不全空家も指導対象に追加された。また、「空き家バンク」による 移住・定住の促進や補助制度の拡充など、国は自治体支援を強化している。
こうした制度面での後押しを背景に、「空き家を地域資源として活かす」動きが全国で広がっている。
空き家活用の成功事例15選【自治体の実践例まとめ】

全国の自治体では、空き家を地域資源として再生し、移住促進や観光振興、地域経済の活性化につなげる動きが広がっている。ここでは、空き家を活かした取り組みを賃貸住宅化、民泊・宿泊施設、サテライトオフィス、地域拠点、古民家カフェ・商業施設などのテーマごとに紹介する。
賃貸住宅化による移住・二地域居住の推進
空き家を賃貸住宅として再活用し、移住希望者や二地域居住者とのマッチングを図る自治体が増えている。地域内の住宅不足を補うだけでなく、移住支援や子育て支援と連動させることで、定住促進や地域コミュニティの再生にもつながっている。
1. 栃木県栃木市|空き家バンク成約200件超で移住促進
栃木市は市独自の「あったか住まいるバンク」を運営し、空き家バンクを中心に移住促進と地域活性化を図っている。リフォーム工事には最大50万円の補助金、家財処分には最大10万円を交付。さらに、空き家の所有者に対しても解体費用を最大50万円助成する制度を設けた。
「農地付き空き家」の取り扱いを開始するなど施策を拡充した結果、平成25年度から令和3年度までの実績では、登録物件683件のうち476件(成約率約69.6%)が成約しており、高いマッチング成果を上げている。
2. 岐阜県飛騨市|官民連携の空き家バンク「住むとこネット」
飛騨市は、人口減少と空き家対策の一環として、宅地建物取引業者との官民連携により「飛騨市住むとこネット」を開設した。空き家所有者が物件を賃貸住宅として登録した場合は、改修工事費として最大250万円を補助。
さらに、空き家を店舗へリノベーションする場合は最大100万円、家財道具の処分には最大10万円を助成するなど、活用目的に応じた支援策を設けている。令和7年10月末時点では、299件が成約しており、地域移住の推進に大きく寄与している。
3. 沖縄県国頭村|条例で整備した空き家活用住宅を貸与
国頭村では、空き家を改修して移住者向けの賃貸住宅として活用。「定住促進空家活用住宅条例」を制定し、村が改修工事を実施した上で、地域の担い手となる移住者に向けて、空き家を月額33,000円(令和7年3月入居例)という低廉な家賃で貸し出している。
入居条件には「地域活性化の担い手となること」を掲げ、地域行事への参加を促すなど、移住者と地域がともに暮らす仕組みを整えた。
出典:国頭村役場「国頭村定住促進空家活用住宅入居者募集要項」
4. 沖縄県うるま市|「お試し移住住宅」で離島定住を促進
うるま市では、離島地域の人口減少と少子高齢化対策として、空き家の再生を活用した定住支援を進めている。平成28年から令和3年にかけて、島しょ部の古民家を改修し、「お試し移住住宅」として運用。6年間で11組・25人の移住につながった。
また、令和2年度には地域おこし協力隊を派遣し、空き家調査や活用推進に着手。その成果として、宮城島では空き家を再生した古民家食堂もオープンし、地域の雇用と交流の拠点となっている。
出典:うるま市「島しょ地域への移住定住促進について【過年度】」
民泊・宿泊施設リノベーションによる観光・インバウンド活用
空き家を観光やインバウンド対応の拠点として再生する自治体が増えている。 古民家の趣や地域文化を活かした宿泊施設は、地域の魅力を発信し、交流人口や観光客の増加につながる好事例として注目されている。
5. 和歌山県湯浅町|古民家宿泊施設「千山庵」で観光資源化
醤油醸造のまちとして知られる県湯浅町では、平成28年度に内閣府の地方創生加速化交付金を活用した「ゆあさ地方創生観光まちづくり推進事業」の一環として、重要伝統的建造物群保存地区内の空き家を活用する方針を決定した。
築130~150年の古民家を改修し、昔ながらの暮らしを体験できる貸し切り宿「千山庵」として再生。土間や吹き抜け、天窓など伝統建築の趣を活かした空間が観光客に好評で、地域の新たな観光資源としてまちの活性化に寄与している。
出典:湯浅町役場「平成28年第一回定例会回定例会町長所信表明」
6. 長野県松本市 | 歴史的建造物を再生した宿泊施設に活用
松本市では、約10年間空き家となっていた江戸期の本陣跡・旧小澤家住宅を、民間企業と連携して宿泊施設「Satoyama Villa 本陣」として再生した。 現存する建物は大正2年に再建されたもので、令和3年には国の登録有形文化財に指定されている。
地域の自然・文化・経済の調和を図る持続可能な観光モデルが高く評価され、令和6年には観光庁長官賞(第8回ジャパン・ツーリズム・アワード)を受賞した。
出典:扉ホールディングス株式会社「Satoyama villa HONJIN」
サテライトオフィス・テレワーク拠点化による地方創生
空き家をサテライトオフィスやコワーキングスペースとして再生し、企業や人材を呼び込む動きが全国で進んでいる。 テレワークの普及を背景に、地域に働く場を生み出す空き家活用モデルとして、関係人口の創出や地域経済の活性化に寄与している。
7. 徳島県神山町|空き家改修でサテライトオフィス誘致
神山町は、地方創生の先進地として全国的に注目されている。 空き家を改修して企業や人材を呼び込む「神山プロジェクト」を推進し、平成17年に整備した光ファイバー網を活かして、古民家をサテライトオフィスや移住者向け住居として再生している。
Sansan株式会社の「神山ラボ」やプラットイーズ社の「アーカイブ棟」など、IT企業の拠点が次々に誕生。 令和7年6月時点で16社が進出し、平成24年には社会動態人口が初のプラス(+12人)を記録するなど、過疎地における地方創生モデルとして高く評価されている。
出典:総務省「働き方の変化(テレワーク)を活用した地方創生」
8. 山梨県富士吉田市 |「まるサテ」構想で分散型オフィス整備
富士吉田市は、空き家や空き店舗を活用して、市内全体をワークスペース化する「まるごとサテライトオフィス構想(まるサテ)」を推進している。机と椅子、無料貸与のBeacon端末を設置するだけで登録可能な仕組みを整え、カフェや宿泊施設、歴史的建造物など約40拠点が提携施設として稼働中である。
また、交流拠点「ドットワークPlus」を中心に、空き店舗オーナーと新規出店希望者が出会う機会を創出。実際に無人古着店など新たな店舗開設も生まれている。空きスペースの活用と関係人口の拡大を両立させるモデルとして注目されている。
出典:富士吉田市 地域振興・移住定住課「富士吉田市まるごとサテライトオフィス構想」
9. 滋賀県米原市|駅前空き家を改修したシェアオフィス
米原市では、令和5年に駅前の空き家を改修したシェアオフィス「MAIBARA EAST01」が開設された。 東京に本社を置く建築・リフォーム企業が、地域の空き家バンク制度や市の協力を得て整備したもので、市のサテライトオフィス誘致施策と連携している。
現在は企業の拠点利用に加え、地元事業者やフリーランスにも開放され、交流やビジネス創出の場として活用されている。行政支援を活かし、民間主導で空き家の再生と地域経済の活性化を両立させた好例といえる。
出典:長浜経済新聞「米原駅前にシェアオフィス「MAIBARA EAST01」 徒歩3分の空き家を再生」
地域コミュニティ拠点としての空き家再生
空き家を地域交流や子育て支援の拠点として再生する自治体が増えている。 地域住民や移住者が集い、支え合う場として活用することで、子育て支援・高齢者福祉・地域活性化を一体的に進める好事例が生まれている。
10. 宮城県名取市| 子育て世代を支援する複合施設に再生
名取市では、空き家を改修して子育て世代や女性を支援する複合施設「子育てシェアスペース Omusubi(おむすび)」を整備した。施設は、一時預かり専門託児所・託児付きコワーキングスペース・女性専用シェアハウスの3機能を併設。
生後2カ月から小学生までの子どもを理由を問わず預かるほか、移住や就職、進学を希望する女性に向けて安心して暮らせる住居環境を提供している。空き家を単なる住宅ではなく、地域課題の解決拠点として再生した好例である。
11. 沖縄県久米島町 |古民家「仲原家」を移住・交流拠点に活用
久米島町では、琉球古民家を改修したコワーキングスペース「仲原家」を運営している。移住相談のワンストップ窓口やテレワーク拠点として活用されるほか、学習支援や地域イベントにも利用されている。仕事・暮らし・交流を一体的に支援する「多目的な地域拠点モデル」として注目されている。
12. 福岡県北九州市 |空き家×地域共生モデルで住宅支援
北九州市では、空き家を地域のセーフティネット住宅として活用する取り組みを展開している。産学官が連携する「北九州未来づくりラボ」が中心となり、空き地・空き家の相談窓口を設置。
ここでは、低所得者・高齢者・子育て世帯・移住希望者など、住まいや居場所に困っている人を支援。空き家所有者と生活困窮者をつなぐマッチング支援事業を通じて、地域共生型の住宅政策モデルを構築している。
古民家カフェ・商業施設としての地域活性化
空き家を古民家カフェや商業施設として再生し、地域のにぎわいと雇用を生み出す取り組みが全国で進んでいる。歴史ある建物の趣を活かしたリノベーションは、観光振興や移住・定住促進にもつながる地域資源化の好例となっている。
13. 岡山県瀬戸内市 |古民家カフェや工房で地域にぎわい創出
瀬戸内市では、移住交流促進協議会「とくらす」が中心となり、空き家を活用した地域づくりを進めている。地域住民が移住希望者の住まいや仕事探しを支援するIJUコンシェルジュ制度や空き家バンク、地域おこし協力隊などを連携させ、移住者の受け入れと空き家の再生を一体的に推進。
これまでに築100年を超える古民家を改修し、カフェやデザイン工房、美容院、交流拠点として再生。空き家活用が移住・定住の後押しとなり、地域のにぎわいづくりにもつながっている。
14. 沖縄県名護市|築120年古民家を地域交流拠点に活用
名護市では、築120年の古民家を改装したカフェ兼居酒屋「かめたろうやー」が、地域交流の拠点として注目を集めている。店舗運営は地域住民が主体となって行っているが、市の空き家活用支援事業や観光振興策の後押しを受けて再生が実現した。
令和7年には一棟貸しの民泊施設として業態転換し、国内外から観光客が訪れる人気の宿泊拠点へと発展。敷地内には飲食用の共有キッチンも整備され、地域住民と来訪者が交流する場としての機能も担っている。自治体の支援を活かした民間主導型の空き家再生モデルである。
出典:やんばる経済新聞「名護・羽地に民泊施設「古民家かめたろうやー」 居酒屋から業態転換」
15. 広島県尾道市 |官民連携の「空き家再生プロジェクト」
尾道市では、官民が連携して空き家の利活用を進める「尾道空き家再生プロジェクト」を展開している。昔ながらの街並みが残る山手地区では、建て替えが難しい物件が多く、空き家の増加が課題となっていた。
同プロジェクトでは、文化財を含む20件以上の空き家を改修し、ゲストハウスやカフェ、コミュニティスペースとして再生。さらに、市と連携して「空き家バンク」を運営し、移住希望者とのマッチングも推進している。これまでに100件以上の空き家再生を実現しており、観光振興と移住促進を両立する持続可能な官民連携モデルとして注目されている。
空き家活用の成功を支える支援制度・補助金

空き家活用の取り組みを進める上では、事例の共有だけでなく、制度を活用した仕組みづくりも欠かせない。ここからは、自治体が実際に活用できる国の支援制度や補助金を紹介する。
空き家対策総合支援事業(国土交通省)
空き家の除却や活用、実態調査などを総合的に支援する国の代表的な制度。「空家等対策計画」を策定し、協議会を設置している自治体が対象となる。 危険空き家の除却や所有者特定、利活用の促進、地域の民間団体との連携費などが補助対象。 社会資本整備総合交付金とは別枠で補助が可能なため、独自事業を進めたい自治体にも使いやすい。
- 主な対象:空き家対策計画を策定し、協議会を設置した自治体
- 補助内容:調査・除却・利活用・民間連携にかかる経費
- 活用のポイント:小規模自治体でも制度設計から一括支援を受けられる
全国版空き家・空き地バンクと情報提供ガイドライン
「全国版空き家・空き地バンク」は、自治体の空き家情報を一元化し、全国規模で検索できるマッチングシステムである。令和5年10月末時点で1,000を超える自治体が参画。自治体独自の空き家バンクがなくても掲載でき、情報発信の効率化に寄与している。
また、「空き家所有者情報の外部提供ガイドライン」改正により、所有者の同意があれば民間事業者への情報提供が可能となった。自治体と民間の連携を促進し、マッチングの精度とスピード向上を図っている。
- 主な対象:空き家バンク未設置自治体を含む全ての地方公共団体
- 改正ポイント:個人情報法の整理により、民間連携が容易に
- 活用のポイント:職員負担を減らしながら情報発信を強化できる
住宅セーフティネット制度・フラット35地域連携型支援
空き家を子育て世帯や高齢者、低所得者などの住宅確保要配慮者の住まいとして再活用する仕組み。 空き家の改修費や家賃補助が受けられるほか、 住宅金融支援機構と連携した「フラット35地域連携型」では自治体と協定を締結することで金利を5年間0.25%引き下げ、「地方移住支援型」では10年間0.3%引き下げが適用される。移住・定住支援にも有効だ。
- 主な対象:住宅確保要配慮者への賃貸供給を行う自治体・事業者
- 補助内容:改修費・家賃補助・金利優遇
- 活用のポイント:移住促進・子育て支援と組み合わせて施策効果を拡大
法改正・税制優遇による空き家再生支援
令和元年施行の建築基準法改正により、空き家を福祉施設や店舗に転用する際の手続きが緩和され、再生のハードルが下がった。
さらに、平成28年度税制改正で創設された「相続空き家の3,000万円特別控除」は令和9年12月末まで延長されており、相続を契機とした空き家流通の促進につながっている。
- 主な対象:相続空き家・既存建物の用途変更案件
- 改正内容:用途変更の要件緩和、譲渡所得控除の延長
- 活用のポイント:民間主導の空き家再生事業を後押し
制度を効果的に活用するポイント
空き家対策を効果的に進めるには、「除却」→「利活用」→「居住支援」 の3段階を意識した制度設計が重要である。初動では「空き家対策総合支援事業」で基盤整備を行い、流通促進には「全国版空き家・空き地バンク」で民間連携を図る。
その上で、「住宅セーフティネット制度」や「フラット35地域連携型」によって居住支援までをつなげることで、除却から再生、定住までを一貫して推進できる。
こうした制度を戦略的に組み合わせることで、空き家活用を通じた移住・定住促進、地域経済の循環、コミュニティ再生といった多面的な効果を生み出せる。行政・民間・住民が連携し、継続的なマッチング体制を整えることが、成功のカギとなる。
自治体が取り組むべき空き家活用の次のステップ
全国で増え続ける空き家は、地域の安全や景観、財政に影響する大きな課題となっている。 一方で、空き家を再生し、移住者や観光客、地域住民が集う場として活用することで、まちに新たな価値を生み出す自治体も増えている。
空き家を住まいや拠点として再利用すれば、移住・定住の促進や地域経済の循環、コミュニティの再生にもつながる。 その実現には、自治体が「空き家」と「使う人」をつなぐ役割を担い、国の支援制度や民間との連携を進めることが欠かせない。
制度を上手に活用し、地域に合った対策を積み重ねることが、持続可能なまちづくりへの第一歩となる。

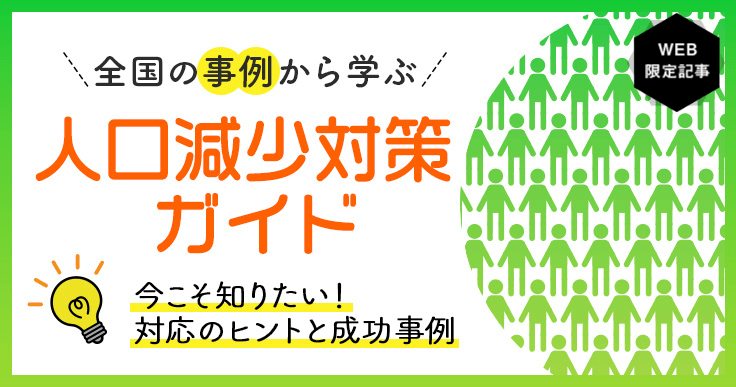
.jpg&w=1920&q=85)











