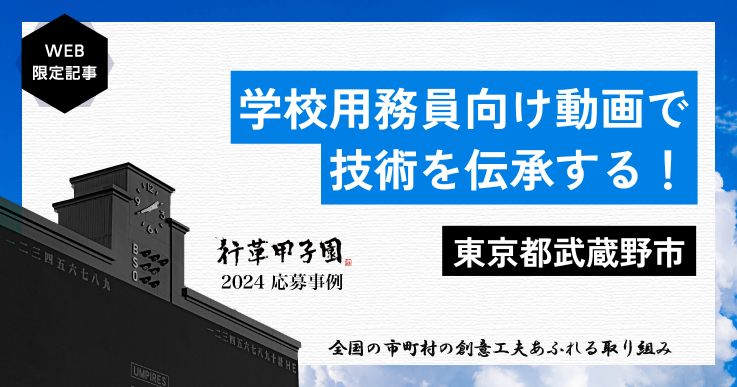
全国の市区町村の創意工夫あふれる取り組みを表彰する、愛媛県主催の「行革甲子園」。7回目の開催となった令和6年の「行革甲子園2024」には、35都道府県の78市区町村から97事例もの応募があったという。
今回はその中から、東京都武蔵野市の「学校用務員向けのスキルアップ動画」を紹介する。
※本記事は愛媛県主催の「行革甲子園2024」の応募事例から作成しており、内容はすべて「行革甲子園」応募時のもので、現在とは異なる場合があります。
取り組み概要
武蔵野市では、学校用務員向けに作業手順や道具の使い方をレクチャーする動画を、市のYouTubeチャンネルで公開している。
動画に出演しているのは、実際の学校現場で仕事をしている市の職員や学校用務員で、撮影、編集、アップロードも職員や用務員が行っている。
背景・目的
学校施設に詳しく、学校用務員にマンツーマンの実技研修なども行っていた市のベテラン職員の退職に際し、修繕の方法などの引き継ぎ資料が必要に。紙のマニュアルでは作業の工程が分かりにくいため、研修の内容を中心に動画を作成し、YouTubeにアップロードした。
取り組みの具体的内容
学校用務員に学校施設の修繕や、設備の使用方法を周知する目的で、令和5年2月からYouTube上で動画を公開している。動画内では、ドアノブ、窓サッシの鍵の交換や、学校樹木の剪定などの基本的な作業から、プール滅菌機やスプリンクラーなど学校特有の設備について紹介している。
令和6年5月現在、20本近くの動画が公開されており、総再生回数は約3万回。中でも再生回数が多いのは、トイレの部品交換についてレクチャーした「大便器フラッシュバルブ修理」の動画で、1万回以上再生されている。

はじめは、用務員を対象として研修等を行っていた市の職員が出演し、実際の学校で解説しながら作業する様子を撮影した。その後、用務員の中から、他校の用務員のスキルを教わりたいという意見が出たため、床のワックスがけの講習会を行い、その様子を撮影して公開するなど、用務員同士でスキルを共有するツールにもなっている。また、撮影や編集を用務員が行うなど、取り組みの形を広げている。
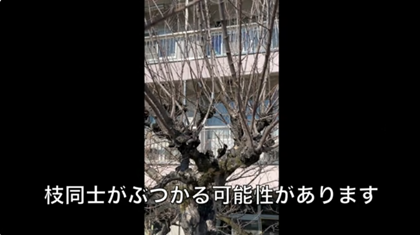
特徴(独自性・新規性・工夫した点)
1. YouTubeに公開したことで、いつでもどこでも何度でも視聴できる。
2. 学校の用務員と市の職員が職場や職種の違いを超えて連携したことで、用務員が知りたい内容を、YouTube動画という方法で発信できた。
3. プールやスプリンクラーなど、学校に特有の設備についても紹介している点がYouTube上のほかの動画と比べて珍しい特徴となっている。
取り組みの効果・費用
1. 動画の撮影は、学校で行い、道具等も普段から使用しているものを使って撮影するため、費用はほとんどかかっていない。
2. 合計再生回数は3万回以上で、多くの用務員に視聴されている。
3. 用務員の日常業務の引継ぎは各校、各個人に委ねがちであったが、必須となるスキルを動画形式でいつでもどこでも何度でも気軽に学べるようになった。
4. 市役所職員だけでなく、学校用務員がレクチャーする動画も作成された。清掃業者で勤務経験のある用務員が床のワックスがけについてレクチャーするなど、様々なバックグラウンドを持つ用務員同士が、それぞれの分野で培った熟練の技や知識を他校の用務員にも広める好循環が生まれている。個々の用務員のモチベーションが高まるとともに、学校の枠を越えた用務員同士のコミュニケーションも活性化した。
取り組みを進めていく中での課題・問題点(苦労した点)
市職員は動画撮影や動画編集の経験がなかったが、一発撮りで撮影して編集不要な動画にしたため、ハードルを感じずに始めることができた。後に、動画編集を得意とする用務員に編集を依頼し、字幕やナレーションがついた完成度の高い動画も作成された。
また、動画内でレクチャーする用務員と、動画のアップロードなどの事務作業をする市役所職員の連携が不可欠だったが、用務員同士の交流会に事務職員が出席したり、用務員のメール利用を後押したりしたことにより密に連携をとった。
今後の予定・構想
市職員や用務員が知恵を出し合い、ニーズの高い内容の動画の種類を増やすことにより、同市だけでなく、日本全国の用務員のスキルアップやモチベーションアップを促す。
他団体へのアドバイス
動画投稿というと、特別な操作や知識が必要なのではと考えがちだが、シンプルなものから挑戦することで取り組みやすくなると思う。用務員のスキルアップに加えて、モチベーションアップにもつながるだろう。
【武蔵野市 第8回 小・中学校用務員スキルアップ動画作成の取り組み】
https://www.city.musashino.lg.jp/shussan_kodomo_kyoiku/sho_chugakko/musashino/1047380.html













.jpg)
】バナー広告_株式会社ICHICO_PR.jpg)







