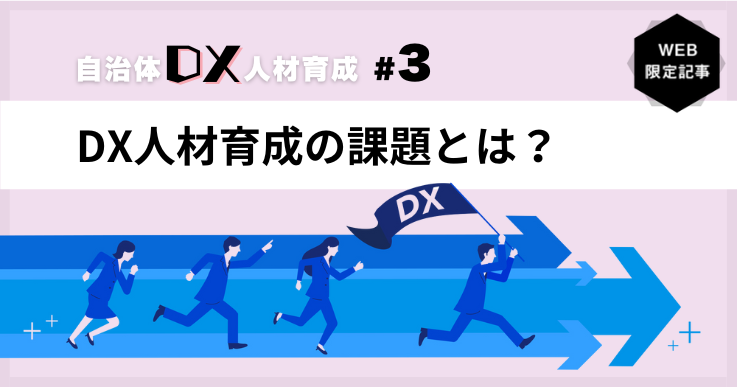
前回は、自治体DX推進にむけたデジタル人材育成において伝えるべきポイントを解説しました。しかし、3つのポイントを伝えれば全職員一丸となって自治体DXを進められるというわけではありません。実際には、人材育成の様々な課題が潜んでいます。そこで、人材育成を失敗に終わらせないためのポイントについて解説していきます。
■このシリーズの記事
1. 自治体DXは誰が担当するの
2. 人材育成で伝えるべきことは?
3. DX人材育成の課題とは? ←今回はココ
4. やらされ感から自分ゴトへ
5. 地域DXはどうやって進めるの?
※掲載情報は公開日時点のものです
[PR]株式会社ディジタルグロースアカデミア

解説するのはこの方
高橋 範光 (たかはし のりみつ) さん
デジタル人材育成専門家
株式会社ディジタルグロースアカデミア代表取締役会長。株式会社チェンジホールディングス執行役員。2005年に株式会社チェンジ(現チェンジホールディングス)に参画し、人材育成事業を管掌。2013年よりデジタル人材育成事業を開始し、2021年にKDDIとチェンジホールディングスの合弁会社である株式会社ディジタルグロースアカデミアを立ち上げ、現職に至る。
『道具としてのビッグデータ』(日本実業出版)、『最短突破 データサイエンティスト検定(リテラシーレベル)公式リファレンスブック』(共著、技術評論社)。オープンガバメント・コンソーシアム理事。情報処理推進機構(IPA)専門委員。経済産業省 デジタルスキル標準検討会 DXリテラシー標準WG主査。
DX推進リーダーの孤立を防ごう。
1. できる限り短期間に全職員育成を進める
先述したとおり、自治体DX推進は全職員一丸となって推進する取り組みです。よって、 これまでのような情報システム担当の教育だけでなく、全職員を対象としたデジタル人材育成施策が求められます。そこで気をつけるべき点は、各業務担当課から1名選抜されDX推進リーダーとして育成プログラムを受講するような育成プログラムです。これだけでは、効果は限定的といえるでしょう。
というのも、研修をうけたリーダーが現場に戻って展開しようとしても、新しい取り組みに抵抗する組織の力が勝ると、研修による育成効果は無に帰すためです。自治体職員の多くは、これまでの慣れた手順ややり方に安心感を持っています。そのため、内容を理解したDX推進リーダーがこれまでの業務の現場で「業務の変革」を提案しても、現場の理解が得られず孤立してしまいます。
では、全職員を対象に育成に取り組めば解決するでしょうか。実際には、予算や業務の都合などの理由から、全職員が研修を受講し終える頃には数年を要することになりかねません。
これでは、一部のリーダーだけが学習したのと同じように、現場での変化に対する抵抗にあい、これまでのやり方に戻されることになるでしょう。よって、全職員が「一丸となって推進できる環境」を用意するためにも、全職員ができる限り短期間に学習することが求められるということです。
自治体DXをDX推進リーダーの孤軍奮闘に頼らず、全員参加型の取り組みとして進めるためにも、できる限り短期間で全員が学習するところから始めましょう。

デジタル用語を日常に定着させる。
2. 共通言語化が推進のカギ
全員が短期間で研修することが決まった後に直面する課題が、「デジタルの用語や活用が難しい」という壁です。特に、デジタル用語や技術理解が浸透していない職場では、理解のための時間を要し、スムーズなコミュニケーションが妨げられてしまいます。
例えば、自治体DX推進において頻出する「クラウド」「AI」「RPA」などの用語が理解・浸透していない状況では、職員間での会話や協議が進まないどころか、停滞することさえあります。このような状況を避けるためにも、デジタル用語の共通言語化が不可欠といえます。
具体的には、以下の取り組みが有効です。
• 基礎知識の習得:デジタル用語を短時間かつ簡潔に理解できるコンテンツを用意し、いつでも見返せるようにする
• 日常業務への活用:学んだ用語を日常の会話や業務で積極的に使用する習慣を各担当組織の中でつくる
このようにして共通言語化することができれば、ムダな説明の時間が減り、意思決定や業務変革が格段にスムーズに進むようになります。特に、幹部層の意思決定や異なる部署間での連携が求められる自治体DXにおいては、共通言語化がDX成功のカギとなることを覚えておきましょう。
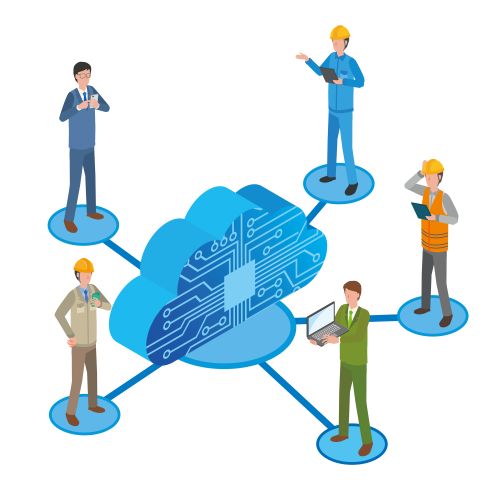
研修の継続と支援が不可欠。
3. 一過性の研修で終わらせない
「全職員で一度に取り組み」、「共通言語化を進める」。これでDXが進むかと思いきや、次の壁が現れます。「一度の研修では変革が定着しない」という課題です。
上述した通り、これまでの業務や慣習が長年にわたってしみついている職場では、一度の研修による意識変革やスキル習得だけで完全に定着するところまでいくことは困難です。しばらくすると、職員は元のやり方に戻ってしまい、「研修はやったけど何も変わらない」という状況に陥りがちです。
そこで、DX推進には継続的な研修による定着化と支援体制の構築が不可欠といえます。具体的には以下の取り組みを検討してください。
• 段階的な研修計画:複数回受講いただけるよう、基礎・活用・実践と進む研修カリキュラムを設定し、職員の定着化を促す
• 実務に直結した支援:研修だけでなく、現場でのツール活用などの実践を支援するフォローアップ体制やフォローアップ研修をDX推進リーダー中心に実施する
• 成功事例の共有:自治体内や組織内での実際の成功事例をアピールできる機会を増やすことで、モチベーション向上につなげる
最終的に、DXに取り組むことが「特別なこと」ではなく「当たり前」になる職場文化をつくることが求められます。これを実現するには、成果が見えるまで何度も粘り強く取り組む姿勢が欠かせません。

現場の課題に対策を
自治体DXを推進するために重要なことは、職員全員が一丸となり、継続的に取り組むことです。今回は、以下の3つのポイントを整理しました。
1. できる限り短期間に全職員育成を進める
2. 共通言語化が推進のカギ
3. 一過性の研修で終わらせない
これらを意識して取り組みを進め、各職場での実践・定着化を通して、自治体DXを成功に導きましょう。
次回は「やらされ感から自分ゴトへ」です!


.png)
.png)










.jpg)
】バナー広告_株式会社ICHICO_PR.jpg)
.png)







