公開日:
【自治体DXの人材育成 #4】やらされ感から自分ゴトへ-小さな成果から実感を

前回は、自治体DX推進にむけたDX人材育成の課題について整理しましたが、課題の解決とともに、取り組む一人ひとりが自分ゴト化してやる気にならなければ、自治体DX推進は成功しません。そこで今回は、職員一人ひとりが自治体DX推進をやらされ感ではなく自分ゴト化するためのポイントを解説します。
■このシリーズの記事
1. 自治体DXは誰が担当するの
2. 人材育成で伝えるべきことは?
3. DX人材育成の課題とは?
4. やらされ感から自分ゴトへ ←今回はココ
5. 地域DXはどうやって進めるの?
※掲載情報は公開日時点のものです
[PR]株式会社ディジタルグロースアカデミア

解説するのはこの方
高橋 範光 (たかはし のりみつ) さん
デジタル人材育成専門家
株式会社ディジタルグロースアカデミア代表取締役会長。株式会社チェンジホールディングス執行役員。2005年に株式会社チェンジ(現チェンジホールディングス)に参画し、人材育成事業を管掌。2013年よりデジタル人材育成事業を開始し、2021年にKDDIとチェンジホールディングスの合弁会社である株式会社ディジタルグロースアカデミアを立ち上げ、現職に至る。
『道具としてのビッグデータ』(日本実業出版)、『最短突破 データサイエンティスト検定(リテラシーレベル)公式リファレンスブック』(共著、技術評論社)。オープンガバメント・コンソーシアム理事。情報処理推進機構(IPA)専門委員。経済産業省 デジタルスキル標準検討会 DXリテラシー標準WG主査。
デジタルは願いをかなえるための手段。
1. やりたいことを見つける
自治体DXに向けて各自がデジタル化に取り組む際の第一歩は、自分がやりたいと感じることを見つけることです。普段の様々な業務や突発的な業務がふってくると仕事が山積する中、「時間があればやりたいけど諦めていること」は少なくないはずです。ここでいう、「やりたいこと/諦めていること」というのは、必ずしもデジタル活用に限った話ではありません。やりたいことを広くイメージしてみてください。
例えば、次のようなことを考えてみてください。
• 来庁が困難な住民へのサービス提供(オンラインやリモートでの訪問)
• まちおこしや地域活性化
• まちの将来を担う子育て世代の支援 など
このように、職員一人ひとりがまちのためにやりたいことをまず挙げます。次に、それらを諦めずに実現するためにはどうすればいいかを考えてみましょう。そうすると、まず時間を捻出する必要があり、そのためにデジタル活用が有効な手段であるということが分かるでしょう。また、やりたいことを実現する手段の1つとしてもデジタルツールが活用できるかもしれません。このように、デジタル化は単なる効率化ではなく、「やりたかったことを実現する」ための手段であると考えて取り組むことができれば、自ずとやらされ感は払拭されるでしょう。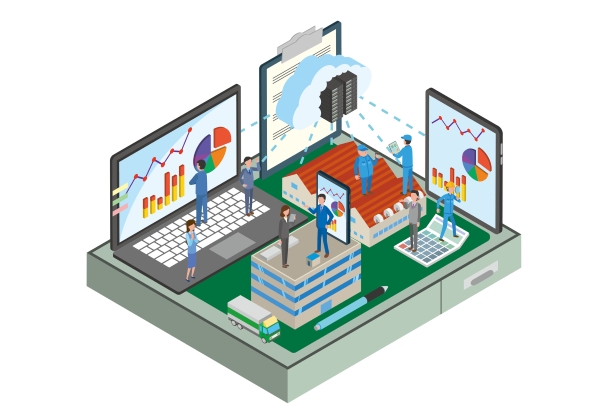
まず無理のない範囲で便利さを体験する。
2. 小さな成果を生むところから始める
デジタルツールの活用において、大がかりな取り組みから始めると、当然成果創出にも時間がかかってしまいます。その間にほかの課題や取り組みをやめざるを得ない事情もでてくるかもしれません。そこで小さな一歩から始め、成果を生むことが成功への近道です。
例えば、次のようなことに挑戦してみてはいかがでしょうか?
• 導入済のツールを使ってみる:もし、生成AIが導入されており、利用できるのであれば、メールの文案作成や報告書のドラフト作成を試してみましょう。成果を実感できるはずです。
• 日頃よく使うソフトウェアの様々な機能に触れてみる:資料作成や表計算などの日頃よく使うツールであっても、実は使ったことがない様々な機能が搭載されています。中には、知らなかったことで、これまでの作業時間を大幅に損していたと気づくような機能もあります。まずは、使っていない機能がないかを調べてみるとよいでしょう。
• 真似ることから始める:同僚やほかの自治体職員が使っている便利な機能ややり方を聞いてみて、取り入れてみるのも効果的です。
ポイントは、「自分にとって無理のない範囲」で始めることです。一度でもデジタルツールの便利さを体験できれば、自然と次のステップに進みたくなるものです。

自分の業務で実践。“簡単”を実感する。
3. 面倒だと感じる自分の問題をデジタルで解決してみる
デジタル化を進める際に最も効果的な練習台は、自分自身の業務です。日々の業務で「面倒だ」と感じる部分を、デジタルツールで解決してみることが、最も効果を実感しやすい方法だといえるでしょう。
例えば、次のような問題を解決してみましょう。
• 時間がかかる手作業の効率化:例えば、毎月行う報告書作成やデータの集計作業にRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を導入できれば、時間を大幅に短縮できます。
• 重複・反復作業の効率化:複数のフォーマットで同じ情報を記入する必要がある場合、自動化ツールを活用して一括処理を行えないか検討してみてください。
• 情報集約の効率化:複数の方から情報を集約し取りまとめる作業は、全員で入力できるようなツールが用意できれば、取りまとめ作業そのものが大幅に削減できます。
自分の業務で実践することで、「こんなに簡単になるんだ!」という実感を得られます。そして、自分で実践できれば、万一のトラブルが発生したときでも、自分で直すことができ、待ち時間もストレスも軽減することができるでしょう。
重要なのは、「誰かに頼る」のではなく、自分自身で実践し解決できる力を養うことです。これがデジタル人材としての成長につながります。

業務効率化から自治体全体のサービス向上へ。
自治体DX推進を加速させるには、取り組む本人がやらされ感ではなく、自分ゴト化して取り組むことが不可欠です。今回は、やらされ感を払拭し、デジタル活用の第一歩を踏み出すための3つのポイントをご紹介しました。
1. やりたいことを見つける
2. 小さな成果を生むところから始める
3. 面倒だと感じる自分の問題をデジタルで解決してみる
これらを実践することで、単に自身の業務効率化だけでなく、自治体全体のサービス向上につながります。まずは、今日からできることを一つ始めてみてください。
次回は「地域DXはどうやって進めるの?」です!
お問い合わせ
サービス提供元株式会社ディジタルグロースアカデミア
〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-1-4 東都ビル5階


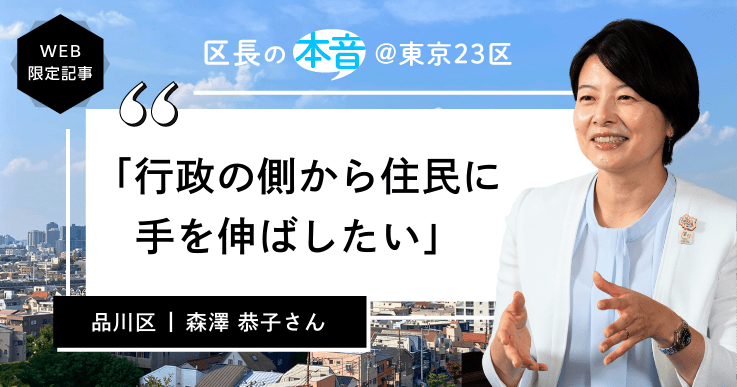
.png&w=3840&q=85)







