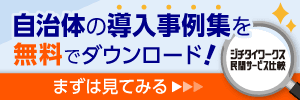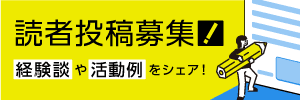公開日:

災害時、自治体では様々な情報の収集と、その分析・処理が必要になる。中でも被災者に関する情報は重要だが、非常時の限られたリソースでデータを収集するのは簡単ではなく、機微なものもあるので取り扱いも難しい。石川県では、能登半島地震においてデジタル庁などと連携し、交通系ICカード(以下、ICカード)の「Suica」を活用。被災者の情報把握をはじめ、被災地域での支援サービスにも役立てているという。取り組みの経緯を追った。
※所属およびインタビュー内容は、取材当時のものです。
Interviewee
石川県 総務部デジタル推進監室
中央:県庁デジタル推進課 課長 福居 久志(ふくい ひさし)さん
右:地域デジタル推進課 地域DX企画グループリーダー 竹本 太郎(たけもと たろう)さん
左:地域デジタル推進課 地域DX推進グループ 城ノ戸 浩司(きのと こうじ)さん
能登半島地震では、発災直後の避難者数が4万人を超えた。避難形態も、指定避難所だけでなく、自宅の納屋やビニールハウス、車中泊などと分散化したが、こうした中で被災者の状況把握に関する課題が浮き彫りになった。3人は口を揃え、当時の状況をこう語る。
「物資などの支援を少しでも早く届けたいという行政の思いとは裏腹に、避難者がどこにいるのか把握することが非常に困難な状態になりました。災害関連死を防ぐためにも何とかしなければと、焦りを感じていました」。
そんな中、デジタル庁と防災DX官民共創協議会(以下、BDX)とともに「マイナンバーカードを避難所・避難者情報の把握に活用できないか」と検討した。3者で協議し、市町にもヒアリングしたが、この案については見送ったという。
「避難者には、マイナンバーカードはおろか財布すら持っていない人も多かった。同時に、カードリーダーを全避難所に配置するのも難しいと判断したのです」。
ほかの方法はないか模索しているなか、BDXおよびデジタル庁から「ICカードのSuicaを活用してはどうか」という提案があり、JR東日本の協力を得て実現することになった。Suicaを避難者に配布し、“誰が・いつ・どこにいるのか”を把握できるようにする、というアイデアだった。
ICカード活用の仕組み
■避難者にICカードを配布。カード受取時、登録用紙に住所、氏名、生年月日などを記入してもらう
■記入された個人情報は自治体のサーバで管理、配付したICカードと紐づけて登録・データ化する
■カードをリーダーにかざすと、時間、場所(タッチした端末の設置場所)などのデータがサーバに送信される
■自治体は、サーバから抽出した時間、場所などのデータと個人情報から“誰が・いつ・どこにいるのか”を確認できる

▲避難者に配られた交通系ICカード(左)とカードリーダー。設置作業は県とデジ庁、BDXの職員が担当した。
「この方法であれば避難者の所在がある程度把握できる上、ICカードの所持で避難所の利用者であることが分かるので、防犯上の効果も期待できると考えました。仮にカードを紛失したとしても、カード自体に個人情報は入っていないから安心です」と福居さん。
同県は試してみる価値があると判断し、令和6年1月下旬に被災した市町へ声をかけ、志賀町から導入の同意を得た。こうして、同町でのICカードによる避難者情報把握に向けた動きが始まった。
この取り組みを進めるにあたって、石川県と志賀町で手順を協議。まずは避難者が多かった「志賀町文化ホール」と「富来活性化センター」の2カ所から運用を始め、その後に町内の全指定避難所へ広げていくことになった。ただしこの仕組みを稼働させるには、避難所でのICカード配布と、登録用紙の記入・回収、カードリーダーの設置といった工程が必要になる。こうした作業は、同県とデジ庁、BDXの職員が担当したという。
「被災地にできるだけ負担をかけたくないという考えから、わたしたちも現地に入って動くことに決めました。各避難所を訪問し、避難者に直接声かけをして理解をいただいた上でICカードを配布し、その間に機器を設置するといった流れです」。
これらの準備が完了し、避難所でのICカード運用がスタート。運用方法は各現場に任せることとした。「例えば、朝起きたとき、食事に来られたときなど、ICカードを読み込ませるタイミングは避難所それぞれです。いずれにしても、最初に登録用紙に記入すればあとはカードリーダーにタッチするだけなので、デジタル感がさほど強くなく、高齢者でも気軽に使える点がいいと感じました」。
しかし、ICカードを活用した取り組みは、県の想定通りにはいかなかった。避難者データの活用が広がらなかったのだ。大きな理由は、「運用開始が発災からすでに1カ月を経過していたこと」だと竹本さんは分析する。
「避難所の運営はある程度でき上がっており、避難者と運営側も“顔の見える関係”が築けている状況。その上で避難者の状況確認をするとなると、“見守られている”と感じる人もいれば、“なぜ”と抵抗感を示す人もいます。また、運営側の職員から『負担が増す』という声が出ることもありました」。
さらに、石川県ではSuicaよりも「ICOCA」の方が住民にとってなじみが深く、その点も浸透のしづらさの一因になっていたようだ。こうした様々な反応を踏まえ、「被災者にメリットを訴求し、被災地の負担にならないよう配慮しつつ、集めたデータを活用する。これらを両立することの難しさを改めて感じました」と振り返る。
同県は避難所でのICカード運用を続けつつ、ほかの活用方法を検討した。そうした中で浮上したのが、入浴支援での利用だった。
同県の入浴支援は、健康福祉部の薬事衛生課が実施していた。被災によって自宅で入浴できなくなった住民が地域の入浴施設を無料で利用できるサービスであるが、ここでICカードが活用できると思いついたのだ。城ノ戸さんは以下のように説明する。
「最初に登録用紙に記入してもらえば、あとはタッチするだけで済むので利用者にはとても便利です。施設側の準備も、電源さえ確保できればすぐにカードリーダーが設置できます。もちろん、ICカードを使わずに利用の都度、受付票に記入する方法も用意しました」。

▲入浴支援でICカードをリーダーにかざす被災者。“お風呂のカード”として高齢者に定着した。
ICカードを活用した入浴支援は、能登町の「ホテルのときんぷら(能登勤労者プラザ)」を皮切りに運用をスタート。避難所での学びも活かされた。「ルールを後付けすると、住民からは『なぜ』と疑問の声があがる。そうではなく、最初からICカードありきで進めることが大切だと考えました」。
そこで、入浴支援サービスの開始時から、「このカードを使えば毎回受付票を記入する手間がなくなる」という案内をしていったのだ。こうした工夫により、ICカードの登録者は日々増加していったという。「ネックストラップを配布したのも功を奏しました。デジタル一辺倒ではなく、アナログ的なしかけも盛り込むことで、自然に受け入れられたのだと思います。地元の高齢者には“お風呂のカード”として認識されているようです」。
ICカード導入は、被災者の利便性向上だけでなく、施設側の負担も大きく軽減している。利用ごとに書類記入をしてもらう手間がなくなり、データも自動で転送されるので報告の負担もない。また、県にとっても利用状況はすでにデータ化されているので、国への報告も大幅に効率化されているという。
「入浴支援を提供する59施設のうち15施設(令和6年7月5日時点)でICカードが運用されています。石川県の公衆浴場に来ると、首からSuicaを下げた人たちをよく見かけるのはそのためです」。
被災者支援という目的を果たしつつ、利用者、施設、自治体それぞれにメリットがある“三方よし”を実現したこの取り組み。福居さんは「本来は避難所運営でも有用な仕組みです」と付け加える。
「入浴支援は開始当初からICカードを導入し、メリットも明確だったので広まりました。避難所での活用でも、開設当初から利用を促し、“お弁当受け取りカード”などと利用メリットを打ち出していけば、より大きな効果が出せたのではと思います」。
ちなみに同県では、被災後に独自の「広域被災者データベース・システム」を構築。区域外に出た避難者を追跡して、市町にも情報提供している。義援金申請の際に住民が記入したものが主な情報源だが、ICカードで把握した情報もインプットされているという。
このシステムはデジタル田園都市国家構想交付金の対象事業に採択され、今後、国や他自治体、団体や有識者が参画するワーキンググループを立ち上げ、全国展開を前提とした動きを進めていくそうだ。
試行錯誤を経つつ、同県の挑戦はこうした形で結実した。福居さんは約半年間の道のりを振り返って、こう総括してくれた。
「平時からデジタル活用を進めておくことで、発災後の初動対応は速やかになるだろうということを、様々な場面で感じました。今回はSuicaを活用しましたが、マイナンバーカードも免許証くらいの位置付けになれば活用の可能性も広がるはず。いずれにしても災害はいつくるか分からないので、平時からフェーズフリーを意識していかなければならないと思います」。