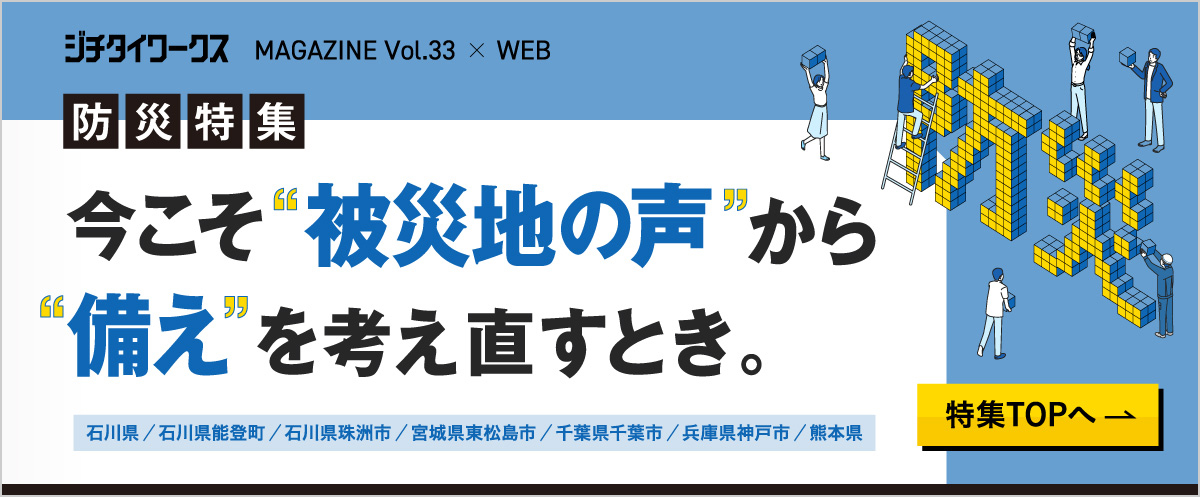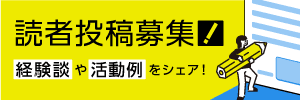公開日:
感染症、透析患者への対応…職員が直面した避難所の実態。【防災特集】

能登半島地震では、1次避難者の数が4万人を超え、各避難所は憔悴した住民であふれた。震度6強を観測した能登町でも状況は同じで、運営側は避難者の生命・健康を守るための様々な対応に追われた。
現地職員に聞く【避難所運営】では、能登半島地震で被災した自治体の職員や応援職員などにインタビューし、大規模災害における被災地の現実を伝えた。
ここでは、同町・小木中学校避難所の運営に携わった職員へのインタビューから、医療・衛生面での取り組みをピックアップ。避難所運営の記事と合わせ、自治体における今後の災害対策のヒントとして紹介する。
※所属およびインタビュー内容は、取材当時のものです。
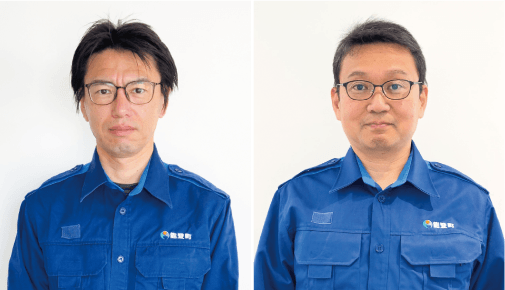
Interviewee
左から
石川県能登町
総務課 危機管理室
室長 道下 政利(みちした まさとし)さん
復興推進課
主幹 灰谷 貴光(はいや たかみつ)さん
避難所を窮地に追い込む感染症の流行と、職員たちの奮闘。
災害時、避難所における懸念事項の1つが“感染症の流行”だ。不特定多数の人が集まり、衛生状態も悪化する避難所では、集団感染が発生するリスクも非常に高くなる。事実、東日本大震災においても、インフルエンザの流行やノロウイルスなどによる感染性胃腸炎の集団感染が各地で発生。熊本地震でも同じような状況が見られた。
能登半島地震でも、避難所は同様のリスクにさらされていたが、今回は新型コロナウイルス感染症の懸念が加わっていた。灰谷さんが運営に携わっていた小木中学校避難所でも、開設から間もなく感染拡大の兆候があらわれはじめたという。
「避難所開設の3日後に最初の感染者が見つかりました。水、食料、トイレと様々な問題がまだ解決されていない中でのことです。しかも、当時は小木中避難所だけで約700人の避難者を抱えていました」。
こうした状況の中、被災者支援と並行して新型コロナとの戦いが始まった。

▲ 灰谷さんが運営に携わっていた小木中学校避難所(画像提供:石川県)
灰谷さんたちはまず、保健所や医師会などにアドバイスを求め、患者の隔離を実施。
小木中学校の一部教室を隔離専用の部屋として、そこに医療環境を整備し感染拡大に備えた。
「避難者の生活スペースでは感染拡大防止に向けた対策を実施したのですが、患者は次第に増えていきました。しかも、小人数ではありましたが、同時期にインフルエンザの感染者まで見つかったのです」。
そこで、応援に来ていた救命士が災害派遣医療チーム(DMAT)と連携しつつ感染管理認定看護師に支援を要請。その看護師が避難者に向けて感染対策の徹底を促していった。
「ピーク時には、1日で30人ほどを隔離した時期もありましたが、応援の皆さんの協力が得られたことで何とか乗り切れました」。
このように、苦境が続いた小木中学校避難所だったが、灰谷さんは「ほかの避難所と比べると、リソースの面では恵まれた方だったといえます」と付け加える。
DMATと連携し、要配慮者への対応を進める。
前述の通り、避難所における医療・衛生面については専門家との連携が欠かせない。
これは福祉の面も同様で、中でも注意が必要なのが要配慮者への対応だ。
高齢化率が5割を超える同町では、災害時に5カ所の福祉避難所を設置して要介護者を受け入れる計画を立てていた。しかし今回の地震では施設も職員も被災し、福祉避難所としての開設や、新規入所者の受け入れができない状態になった。
「この状況に対し、1月9日から長野県の災害派遣福祉チーム(DWAT)に来てもらい、当町とともに対策を検討。既存施設を活用して福祉避難所を設置し、社協や保健師が入って対応することにしました」。
さらに別の問題も発生した。避難者の中には、人工透析のために通院を要する人たちが多くいたのだ。
「命に関わることなので、緊急を要しました」と道下さんは振り返る。
「町内の病院に通院している方ならどうにか把握できるのですが、町外の病院に通っている場合はそれも困難です。そうした中で“明日が透析の予定だ”といった人も出てくる。とにかく迅速な対応が求められました」。
このケースでは、最終的にDMATが調整に入り、ヘリや臨時の車を手配して金沢市に搬送するといった方法で対処。妊婦や乳幼児に関しても緊急時には同様の処置がとられたという。
避難所の環境改善に向け、他自治体と連携して段ボールベッドを導入。
避難所の運営においては、公衆衛生の視点にもとづいた活動も行わなくてはならない。
特に小木中学校避難所のように感染症の拡大リスクが高まっている場合、トイレや食事の環境に配慮するのはもちろん、避難者が生活する空間の改善も重要になる。
そこで有効な策が、土足禁止の徹底と、段ボールベッドの活用だ。
「靴底の付着物を入れないために施設内を土足禁止にして、同時に段ボールベッドを設置する。床面から40センチほど上がるのでほこりなどの吸い込みも減り、寒さも緩和されます」と灰谷さんは説明する。
同避難所は当初土足OKで開所したが、感染症が拡大しはじめたため、まん延を防ぐために土足禁止への変更を検討した。関係者による議論の結果、段ボールベッドが届いたら全面土足禁止にするという計画で進めることになったという。
「1月17日の導入を目指して計画を練りました。この計画の策定をはじめ、避難者への説明や実際の設置など、現場のオペレーションに関しては対口支援に入っていた宮城県と滋賀県の職員が色々と協力してくれました」。

▲ 段ボールベッドを設置した避難所(画像提供:能登町)
もちろん、土足禁止にするためには床面をいったん清潔な状態にしなくてはならない。そこで、体育館だけでなく学校の校舎も全てクリーンにしようということになり、アルコール洗浄を実施した。
「手指消毒をするアルコールが大量にあったので、それを使って消毒を行うことにしました。職員だけでなく、小木中学校の教員や生徒、地域住民の力も借り、モップがけをした後にアルコールで消毒をするという段階的な方法で実施。その後、無事に段ボールベッドが搬入され、避難者の生活環境も従来より改善されました」。
支援活動を継続するために欠かせない“職員の心身ケア”について。
発災後、目まぐるしく変わる状況に対応し、各団体や支援者とも連携しつつ避難所の医療・衛生に関する環境改善を進めた同町。
道下さんは「避難所においては、災害関連死や二次被害を減らすことが最優先」だとしつつ、職員の健康管理やメンタルヘルスの問題も無視できないと強調する。被災者を支援する立場の職員がダウンしてしまったら、支援活動の継続に支障をきたすからだ。しかし、現場の状況はなかなかそれを許さなかったという。
被災自治体では、「自分だけ休むわけにはいかない」という意識が強く働き、職員はオーバーワークになりがちだ。しかし復旧作業や被災者支援活動に出口は見えず、職員はメンタル面で追い込まれてしまう。
「避難所でも庁舎でも、睡眠不足とストレスで職員は限界に達していました。普段は温厚な人が突然怒りはじめるようなことが起きるのです。時間外勤務が400時間を超える職員も少なくない状況では、無理もないといわざるを得ません」。
そんな状況を見かねて、町長から“できるだけ休ませるように”という指示が出た。どこまでできるかは部署により異なるが、“休むことも仕事”「対口支援はわれわれを休ませるために来てくれている」といった意識を持つように伝えていったそうだ。
そうした中、日本赤十字社から「こころのケア要員」が到着。会議室などを利用してリラクゼーションや足湯を提供しつつ、職員の話に耳を傾けてくれた。
また、職員向けのアンケートも実施し、疲労度や精神的な状況を確認して、必要に応じてカウンセリングの場を設けるなど、様々な側面から職員の心身を支える取り組みを行っていったという。

▲ 日本赤十字社からの「こころのケア要員」(画像提供:金沢赤十字病院)
この能登町を含め、能登半島地震で被災した地域はまだ復興の途中にある。ここまでの道のりを振り返って道下さんは、次のように締めくくってくれた。
「当町でも地域防災計画を立てていましたが、1つの避難所に1,000人が避難するということは想定していなかった。もちろん最悪の想定で計画を立てると財源がいくらあっても足りなくなるので、ある程度のレベルで被害を想定するのですが、それを超えた場合に備えることも必要。近隣自治体や事業者などと協定を結ぶといった準備の大切さを痛感しています。そうした仕組みをつくりつつ、人を育てていくことが今後の課題だと考えています」。