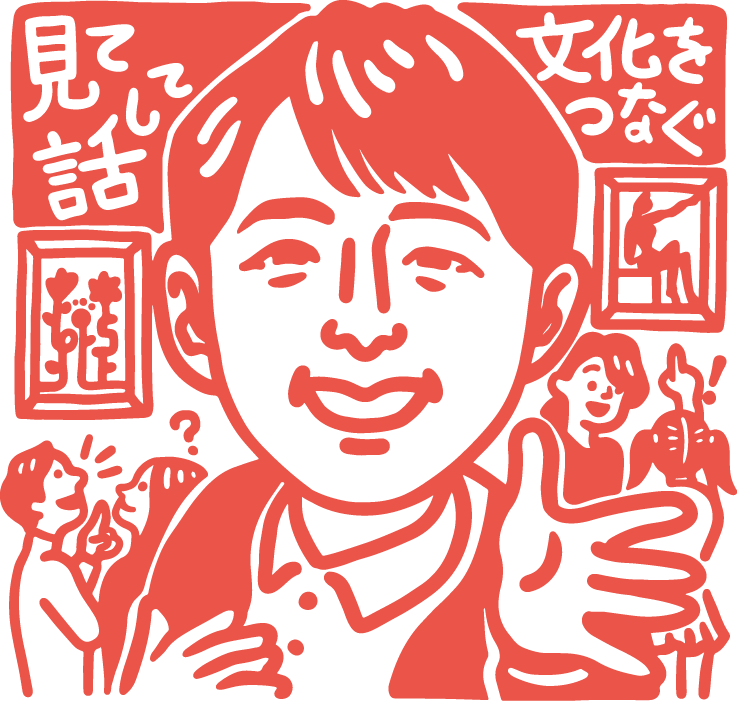
北海道夕張市
教育委員会事務局 教育課
社会教育主事 兼 学芸員
山口 一樹(やまぐち かずき)さん(入庁6年目)
「ミュージアムは遠い存在だと思っている子どもでも“みんなで話しながら作品を見るよ”というと、気軽に参加してくれるのがうれしいです」と山口さん。一緒に対話をした人が知り合いになる面白さもあるそうだ。
みんなで見て気軽に話す。
大学生のときにバックパッカーとして国内外を巡っている最中、初めて夕張市を訪問。炭鉱のまちという背景と地域の人たちに魅力を感じ、地域おこし協力隊を経て、市の職員になりました。その後、勤務の傍ら大学院に通い、文化財や博物館のあり方を学び、学芸員になったのです。学芸員を志したのは、炭鉱の記憶をもとに市民が描いた絵を見たのがきっかけ。地域の記憶や歴史を掘り起こし、作品などの文化遺産を、次の世代につなぎたいという思いが芽生えました。
現在、旧・市美術館の収蔵作品をイベントなどで展示して、対話による鑑賞を進めています。この鑑賞方法は、まず参加者と一緒に作品を見る。そして“何が描かれていますか”“ここも気になりますね。皆さんはどう思いますか”など対話を繰り広げ、多様な視点を共有します。考えを伝え合うことで、作品への理解や思いが深まるのです。作品に向き合う時間は、参加者の感受性を育みます。
1つの作品をじっくり見るため、動きまわる必要がなく、車いすを利用している人なども気軽に参加してくれています。多様な人が分け隔てなく参加しやすい点も魅力です。
また、小学校に出張し、授業として実施することもあります。授業中、子どもたちは思い思いの感想を交わし合っている印象です。自分の考えを話すことで、子どもたちの主体性も高まるのかもしれません。
この事業はすぐに成果が見える取り組みではないものの、お金をかけずに実施できるので、予算措置も不要で簡単に始められます。取り組みの意義を知ってもらうため、同僚にも参加してもらい、評価を受けています。
文化遺産への愛着を育む。
過去から託された文化遺産を保存して後世に伝えていくためには、それらを大切に思い、自分が感じたことを言葉にできる人を増やす必要があると思います。こうして引き継がれることで、価値が増すのではないでしょうか。地域にあるものを見に行き、触って、思いを巡らせ、話す機会をつくることが、その後押しになると信じています。対話による鑑賞もその一つで、参加者からは、“忘れられない経験になった”“風土に目を向けるきっかけになった”“地域の歴史の深さを知った”という声が届けられています。
最近は休日に各地のミュージアムに出かけています。どのような展示や運営が会話を生み出すのかを学び、今後の取り組みに活かしていきたいです。仕事としては、福祉施設に入居していて公共施設に足を運べない人の所へ、作品とともに出張し、作品を見てもらいながら、対話による鑑賞を行いたいですね。これからも、地域の宝物を多様な人たちへ共有する機会をつくっていきたいと思っています。
 ▲対話による鑑賞の様子。
▲対話による鑑賞の様子。
★あなたのまちのG-people、教えてください。
info@jichitai.works 件名「G-people 情報提供」