
地球温暖化が環境に及ぼす影響は年々深刻さを増している。地球の環境を守るため、世界各国が一丸となって対策に取り組む必要がある。
脱炭素社会の実現に向けて、2050年までの温室効果ガス排出量削減に取り組む地方公共団体が増えており、「カーボンニュートラル」という言葉を耳にする機会も増えているのではないだろうか。
本記事では、カーボンニュートラルの基本的な考え方や目指すべき方向性を解説するとともに、先進的な自治体の取り組み事例を紹介する。各自治体の事例を参考に、地域の特性を活かしたカーボンニュートラルを目指した取り組みに向けて参考にしてほしい。
【目次】
• カーボンニュートラルとは?
• カーボンニュートラルの国を挙げた取り組みとは
• 地方自治体によるカーボンニュートラル宣言
• カーボンニュートラルの実現に向けた各自治体の取り組みをご紹介!
• カーボンニュートラルの始め方とヒント
• カーボンニュートラルは地球のために全人類で実現すべき目標
※掲載情報は公開日時点のものです。
カーボンニュートラルとは?
.png)
カーボンニュートラル(Carbon Neutral)とは、温室効果ガスの排出を削減する努力を行いながら、削減できなかった温室効果ガスを森林の植林や保全などの様々な方法で吸収・除去することで実質ゼロとなるよう目指すことをいう。
温室効果ガスの大部分を占める二酸化炭素を削減し、脱炭素社会を実現することで、気候変動の緩和や持続可能な開発目標の達成に貢献することが期待されている。
気候変動問題は世界各国が一体となって取り組むべき課題であり、パリ協定(※1)では世界共通の長期目標として「世界的な平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をする」と定められた。
日本政府は2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにする目標を掲げており、カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みを加速させている。
カーボンニュートラルとはそもそも何か
カーボンニュートラルは「炭素中立」とも呼ばれ、以下の2つの方法で達成を目指す。
- 温室効果ガス排出量をできるだけ削減する
- 削減できなかった温室効果ガスを吸収または除去することで実質ゼロにする
社会経済活動に伴う温室効果ガスの排出を最小限に抑えつつ、森林などによる吸収や革新的な技術による除去により、大気中への排出量を実質ゼロにするものである。
カーボンニュートラルに取り組むメリットや効果
カーボンニュートラルへの取り組みは、地球温暖化対策としてだけではなく、経済成長への取り組みでもあると考える動きが広がっている。
世界では、120以上の国と地域が2050年のカーボンニュートラルを目指し、ESG投資が拡大している。ESG投資とはEnvironment(環境)・Social(社会)・Governance(ガバナンス)に配慮した企業に対して投資を行うもので、国際社会における企業の存在感を高める上でも重要なものとなる。
脱炭素社会への移行は、新たなビジネスチャンスや成長につながるとの期待があり、積極的な取り組みが求められているのである。
カーボンニュートラルの国を挙げた取り組みとは
.jpg)
カーボンニュートラルの実現に向けて、日本政府は国を挙げて様々な取り組みを推進している。取り組みの一部を紹介する。
- 脱炭素事業への新たな出資制度
- 2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略(成長が期待される14分野の産業において高い目標を設定)
- 「ゼロカーボンシティ」の表明から実現へ
- 脱炭素ライフスタイルへの転換
- ゼロカーボン・ドライブ(走行時のCO2排出量がゼロの運転のこと)
カーボンニュートラルへの挑戦のためには、日本全体で取り組みを進める必要がある。
政府は企業へ向けた出資制度や成長戦略、自治体に向けた「ゼロカーボンシティ」の表明促進、国民のライフスタイル転換などを促している。
特に注目したいのが「ゼロカーボンシティ」への取り組みだ。環境省は「2050年までに二酸化炭素を実質ゼロにする」と宣言した自治体を「ゼロカーボンシティ」と定義し、脱炭素に取り組む地方公共団体を支援している。
地方自治体によるカーボンニュートラル宣言
東京都・京都市・横浜市を始めとする多くの自治体が、2050年までに二酸化炭素排出実質ゼロを目指す「ゼロカーボンシティ宣言」を行っている。
2024年3月29日時点で1,078の自治体が宣言に参加(※2)しており、地方自治体の脱炭素化に向けた意識の高さがうかがえる。
ゼロカーボンシティとして定義されるためには、首長が記者会見、議会、プレスリリース、ホームページ等で「2050年CO2(二酸化炭素)実質排出ゼロ」を目指すことを宣言する必要がある。
自治体は、カーボンニュートラルへの取り組みをまちづくりの機会ととらえ、地方自治体の魅力向上、利便性向上、地域産業の活性化など、地域課題の解決につなげることが期待されている。
※2出典 環境省「地方公共団体における2050年二酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」
カーボンニュートラルの実現に向けた各自治体の取り組みをご紹介!
地方自治体では、カーボンニュートラルの実現に向けて、地域の特性を活かした様々な取り組みが進められている。ここでは、先進的な事例をいくつか紹介しよう。
1.【埼玉県さいたま市】スマートシティの実装化+シェア型マルチモビリティの導入
さいたま市では、市民のウェルビーイングな暮らしを実現する「スマートシティさいたま」の構築に向けた取り組みとして、スマートシティの実装化とシェア型マルチモビリティの導入に力を入れている。
駅を核とした「スマート・ターミナル・シティ」を形成することで、慢性的な渋滞の解消を解消し、脱クルマ依存型生活行動を支えるねらいがある。
シェア型マルチモビリティは、在住者・在勤者の移動の利便性を向上させるためのシェアリングサービスだ。電動アシスト付自転車・スクーター・超小型EVをスマートフォンで予約し、利用することができる。返却は、借りた場所でなくても、指定ステーションであればどこでも返却できる。
これらのシェア型モビリティを市内に高密度で配置することで、市民が気軽に利用できる環境を整備し、将来的に自家用車の利用を減らすことを目指している。
2.【北海道札幌市】「札幌版次世代住宅基準」を策定し補助金を提供
厳しい気候条件のため冬季の暖房使用によるエネルギー消費が大きい札幌市では、年平均気温が100年あたり約2.5度の割合で上昇しているという(※3)。そこで温室効果ガスを削減していくための取り組みとして「札幌版次世代住宅基準」を定めている。住宅やビルの断熱性能を向上させ、暖房使用を抑えることでゼロカーボンシティを実現するねらいだ。

断熱性能によってプラチナ・ゴールド・シルバーの等級にランク付けされ、札幌版次世代住宅基準に適合していると認定されると、新築の建築費用として最大220万円の補助金を受けられる(※4)。この補助制度により、高性能な住宅の普及を後押ししている。
※3・4出典 札幌市ホームページ「札幌版次世代住宅基準」
3.【兵庫県姫路市】観光まちづくり+ゼロカーボンキャッスル

兵庫県姫路市は、脱炭素化と観光振興を両立させる取り組みとして「観光まちづくり+ゼロカーボンキャッスル」を推進している。
姫路市は、重化学工業を中心とするものづくりがさかんな地域だ。姫路市は播磨臨海工業地帯の中心地域であるため、産業部門からの温室効果ガス排出割合が全国平均の約2倍と高くなっている。そのため同市では、温室効果ガス排出量削減を喫緊の課題として対策に取り組んでいる。
姫路市は、多くの観光客が訪れる観光都市でもある。平成5年(1993年)に姫路城が法隆寺とともに日本で初めて世界文化遺産に登録されたものの、コロナ禍において観光客需要は下降していた。
そこで、令和4年度から令和5年度にかけて姫路城におけるライトアップ設備のLED化を進め、リニューアルしたライトアップにより観光客を呼び込みつつ、姫路城のCO2排出量を抑制する取り組みを行った。
観光資源である姫路城を活用しつつ、脱炭素化を進める先進的な事例といえる。
▶ 「カーボンニュートラル」に関する、民間サービスを確認する。
「ジチタイワークス民間サービス比較」では、サービス資料の確認とダウンロードが可能です。
カーボンニュートラルの始め方とヒント
カーボンニュートラルの実現に向けて、自治体が取り組みを始めるにあたってのヒントをいくつか紹介しよう。
環境省は、自治体によるカーボンニュートラルの取り組みを支援するため、様々な施策を用意している。
例えば「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(※5)」や「地域脱炭素ロードマップ(※6)」などだ。まずはこれらの制度を活用することで、自治体は効果的に取り組みを進めることができる。
新しいテクノロジーに関する情報を随時収集し、いち早く手を打つことも大切である。脱炭素化に向けては、再生可能エネルギーや省エネ技術、電気自動車など、様々な分野での技術革新が進んでいる。これらの最新動向を把握し、自治体の実情に合った技術を選択・導入することが求められる。先進的な取り組みを行う自治体の事例なども参考になるだろう。
また、企業や住民にカーボンニュートラルを周知させるための広報活動も欠かせない。脱炭素社会の実現には、社会全体の行動変容が必要だ。自治体は、カーボンニュートラルの意義や具体的な取り組み方を分かりやすく伝えることで、企業や住民の理解と協力を得ることができる。広報誌やウェブサイト、イベントなど、多様な媒体を活用して情報発信を行うことが重要だ。
※5出典 脱炭素地域づくり支援サイト「地域脱炭素推進交付金」
※6出典 国・地方脱炭素実現会議 「地域脱炭素ロードマップ」
【石川県加賀市】再エネ電力で充電するEVを公用車として導入!レンタルサービスも
.jpg)
石川県加賀市では、EV(電気自動車)を公用車として導入している。90台以上ある公用車をEVに置き換えることで、温室効果ガスの削減を目指す。
さらにEVシェアリング事業として、市民向けのレンタルサービスにも活用している。平日の夜・土日・祝日に公用EVをスマホでレンタルできるサービスで、15分220円から利用可能だ。
レンタルサービスの導入において、稼働状況や管理コストなどを分析する提案は民間企業からの提案を受けた。市内企業と連携しながら、ガソリン車を毎年5台ずつ減らしていく計画を立てている。
加賀市の事例は、自治体がEV化に取り組む際の「スモールスタート」の重要性を示唆している。大規模な投資や施策の実施が難しい自治体でも、まずは身近なところから取り組みを始めることができる。公用車のEV化やレンタルサービスの導入は、その第一歩となるだろう。
関連記事|【石川県加賀市】公用車をEVに切り替え、地域の脱炭素化の先駆けに。
【徳島県上勝町】日本の自治体として初めて「ゼロ・ウェイスト宣言」!ゴミのリサイクル率80%を達成
▲はてなマークの形をしているゴミステーション「ゼロ・ウェイストセンター」。「なぜ買うのか?」「なぜ捨てるのか?」がテーマ
画像提供 上勝町「ゼロ・ウェイストタウン上勝」
徳島県上勝町は、日本の自治体として初めて「ゼロ・ウェイスト宣言」を行った先駆的な地域だ。
ゼロ・ウェイストとは、ゴミを出さない、ゴミをつくらないライフスタイルを目指す考え方である。
上勝町では、ごみ収集車によるごみ回収を行っていない。町民は自らゴミステーションにごみを持ち込み、分別する。町内で唯一のゴミステーションである「ゼロ・ウェイストセンター」で、町民はごみを13種類43分別に分けて廃棄する。
この分別の徹底により、ゴミの大部分がリサイクルされ、リサイクル率80%以上を達成したという。
さらに上勝町では、ゼロ・ウェイストの取り組みを通じて、環境教育にも力を入れている。ワークショップや分別体験、ゼロ・ウェイストセンター内にある宿泊体験など、様々な体験プログラムを通して、町外の人にも環境について学ぶ機会を提供している。
カーボンニュートラルは地球のために全人類で実現すべき目標
カーボンニュートラルの実現は、地球温暖化という人類が直面する最大の脅威に立ち向かうための、私たち全員の責務だ。
CO2をはじめとする温室効果ガスの排出を実質ゼロにすることは、持続可能な社会を実現するための不可欠の条件である。
しかしカーボンニュートラルの実現のためには、化石燃料に依存した社会システムを根元から変革していかなければならない。エネルギー、産業、交通、建築、ライフスタイルなど、あらゆる分野で抜本的な転換が求められる。
この挑戦において、地方自治体の果たす役割は極めて大きい。国の施策と連動しつつ、地域の特性に合った戦略を立案し、実行していくことが求められている。自治体にはまず「地球温暖化対策の推進に関する法律」にもとづき、「地方公共団体実行計画」を策定することが求められる。住民や企業、団体などの理解と協力を得ることも大切だ。
カーボンニュートラルの意義を分かりやすく伝え、一人ひとりが主体的に行動するためのヒントとして、本記事で紹介した先進的な自治体の取り組みをぜひ参考にしてほしい。



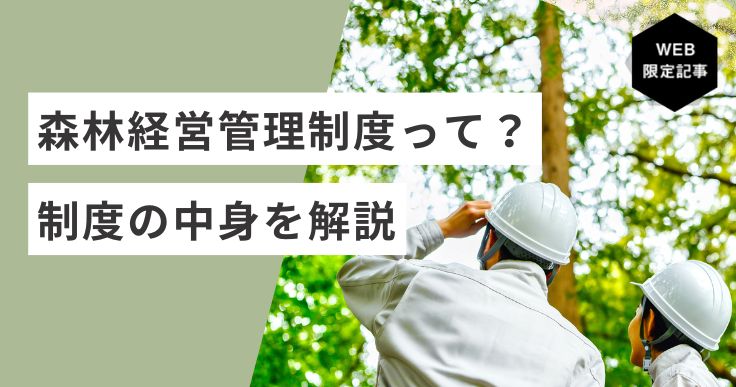
.png)











.jpg)
】バナー広告_株式会社ICHICO_PR.jpg)
.png)







