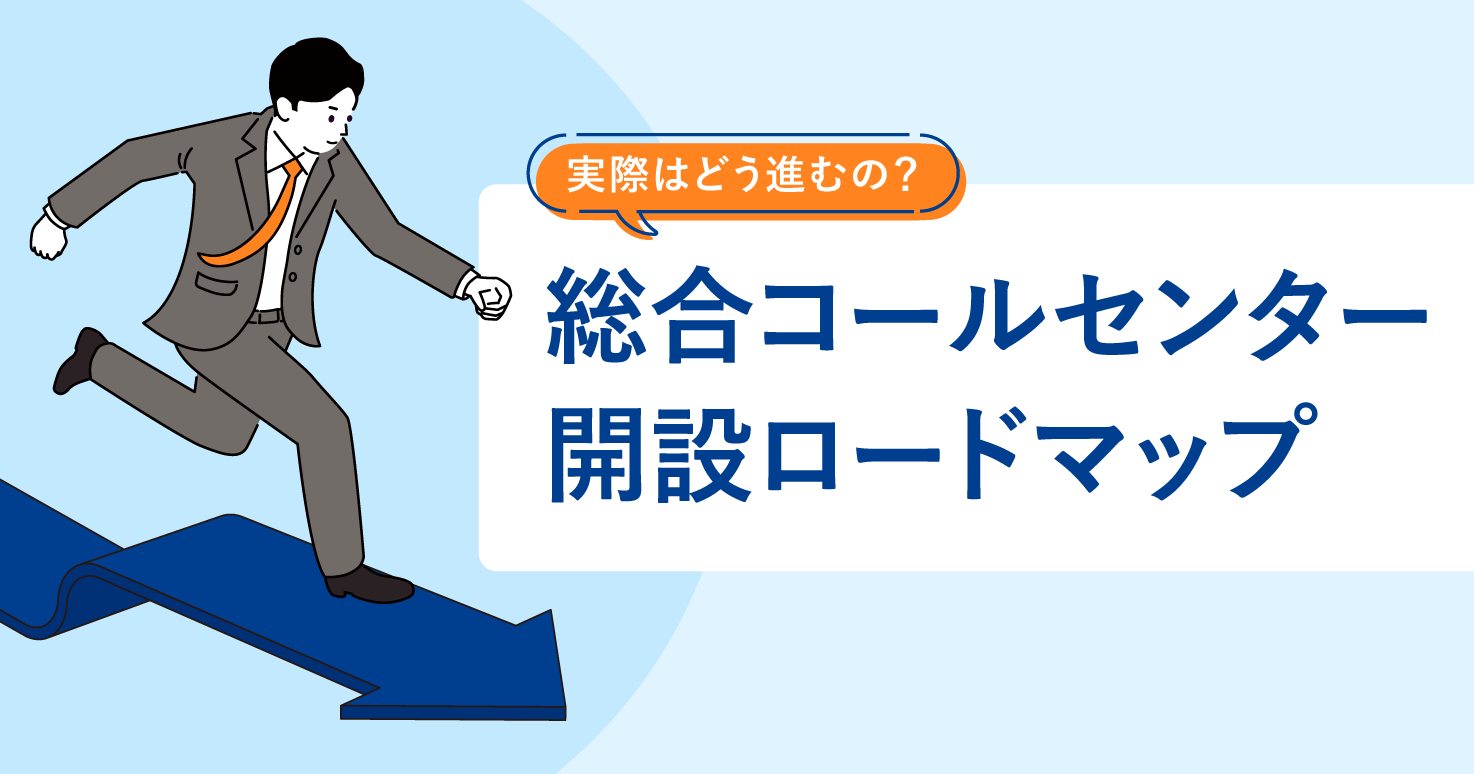
※下記はジチタイワークス特別号(2025年3月発行)から抜粋し、記事は取材時(2023年9月)のものです。
[提供]NTTマーケティングアクトProCX

【#01 検討期】 総合コールセンター開設への道
1. 現状把握:まずは内部を知ることから
入電数などの具体的なデータ収集や庁内ヒアリングを行い、問い合わせ対応にかかっている職員の工数を可視化する。
2. リサーチ・照会:まわりを見渡して情報を集めよう
すでに導入している先行自治体の視察や、仕様書を入手して分析する。事業者へのヒアリングや見積もりも実施する。
3. 予算獲得:議会のハードルをクリアする!
費用対効果に関する説明資料は必須。先行自治体の試算を参考に導入効果を数値化して準備する。
4. 事業者選定:プロポーザルは準備をしっかりと
規模や予算感、委託範囲など、実現したい姿によって提案も変わる。要望の伝わる仕様書を作成する。
【♯02 準備期】 総合コールセンター開設への道
5. システム要件定義:現場で使う立場になって想像する
FAQ、応対履歴などに必要な要件を決める。職員・オペレーター双方の立場で設計することが大切。
6. ネットワーク整備:見えないけれども運用の要となる
委託内容や範囲に合わせて、最適な体制を整える。基本的には事業者から提示されるスケジュールに沿って進める。
7. 庁内向け説明会:協力がなければ始まらない
準備や運用には全課の理解と協力が必要となる。“全庁一丸”という雰囲気づくりには工夫も必要。
8. FAQデータ作成:作業は大変だけど超重要!
FAQ(よくある質問集)の完成度が導入効果を左右する。各課の作業を取りまとめ、進行を管理する。
【♯03 直前期】 総合コールセンター開設への道
9. 運用体制整備:チームとしての一体感を醸成
庁内で改めて全体説明会を実施。同時にオペレーターとも相互理解を深める機会をつくる。
10. 住民向け広報:じわじわスタートでもOK
事前に告知するか、開始と同時に周知していくかを検討しておく。
【♯04 運用期】 総合コールセンター開設への道
11. 運用開始:定点観測で効果を上げていく
ここからが本当の始まり。日々の入電数や応答率、応対履歴などを確認しながら、FAQを更新しつづけることが重要。
教えて!アクトさん Q&A
自治体の規模や方針によって、総合コールセンターのあり方は異なる。ここでは自治体からよくある質問を紹介しよう。
Q. 総合コールセンターはどこまで対応してくれますか。
A. 住民からの問い合わせに対し“FAQを用いて回答できるもの”が対応範囲です。
例えば、地域ごとのごみ収集日など、すでに決まっていて同じ回答ができるものであれば対応可能。個人情報を踏まえた回答が必要なものは転送になります。西宮市のFAQサイトが参考になると思いますので、ご覧ください。
Q. 入電は全てコールセンターに集約されるのですか。
A. 自治体の方針により異なります。
全て集約する場合、職員の受電業務は減りますが委託コストが大きくなり、担当課に直接電話をしたい場合でもオペレーターを介する必要があります。逆に直通電話を残すと、委託コストは抑えられますが、職員の受電業務は大幅には減りません。
Q. 災害や緊急時は総合コールセンターも停止しますか。
A. 別の拠点や持ち出し用機器で可能な限り対応を続けます。
その場所での継続は難しくなりますが、緊急時のBCP対策として、仮設テントや別の施設などに持ち出して使える機器のセットも用意しています。
Q. 地域雇用のため、地元に設置したいのですが。
A. 全国に40以上ある当社コールセンター拠点内での設置をご提案しています。
数百名ものオペレーターを常時抱えていますので、例えば急な欠員や災害リスクにも備えることができます。
Q. 小規模自治体でも導入した方がいいのでしょうか。
A. 将来を考えると、必要性は高いと思います。
費用対効果の面で議論されがちですが、住民の声が集まる応対履歴の活用や災害時の対策なども踏まえると、メリットは大きいです。予算がハードルになる場合は、近隣自治体との共同調達も検討可能ですので、ご相談ください。
Q. できるだけスムーズに導入するコツはありますか。
A. 途中で頓挫させないための“舵取り役”が重要です。
担当課によるボトムアップでの導入よりも、トップダウンで企画系の部署が主導する方がスムーズに進むケースが多く見られます。進行管理については当社がサポートしますのでご安心ください。
お問い合わせ
サービス提供元企業:株式会社NTTマーケティングアクトProCX
CXソリューション部
Email:cc_info@nttactprocx.com
大阪市都島区東野田町4-15-82
会社概要・ソリューション詳細はこちらから
.png)
.png)
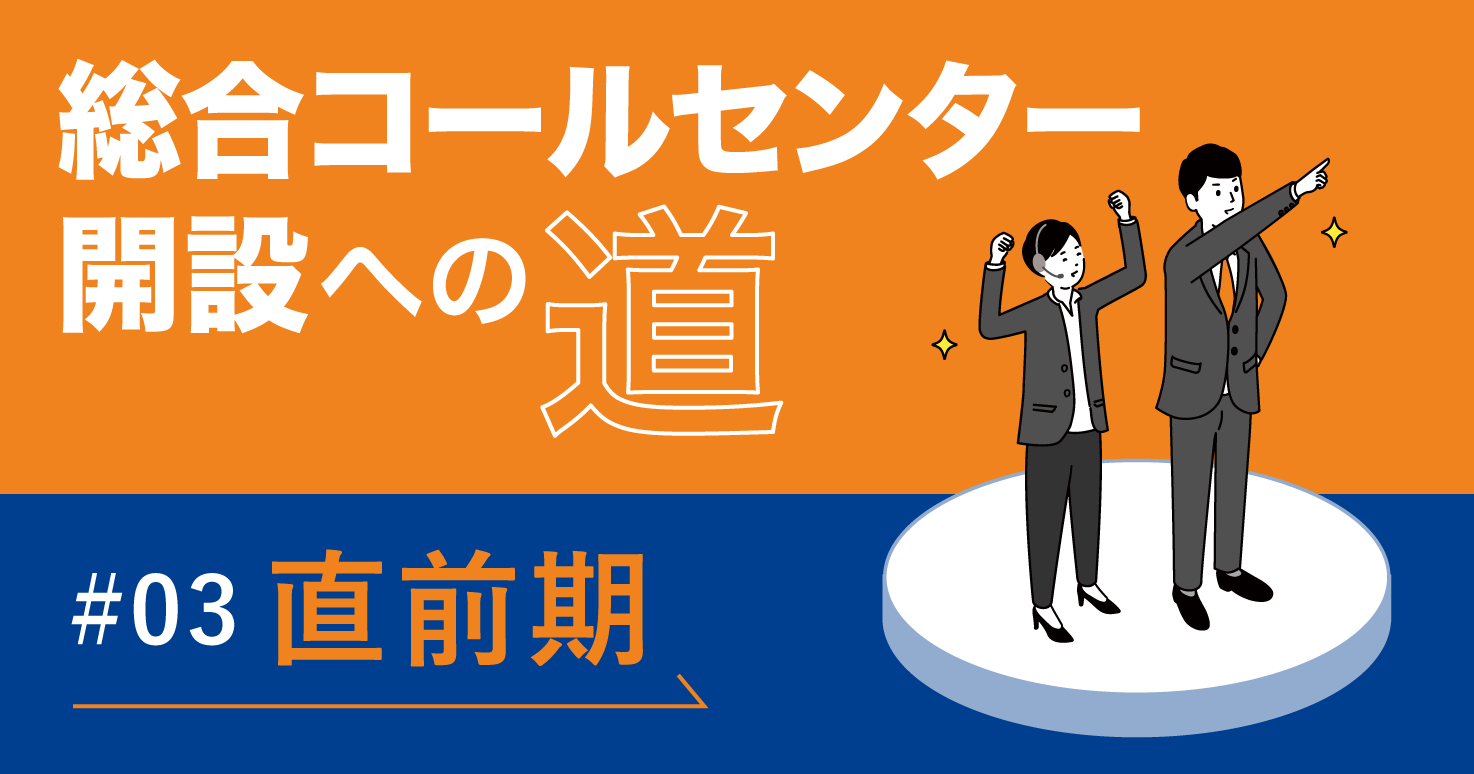
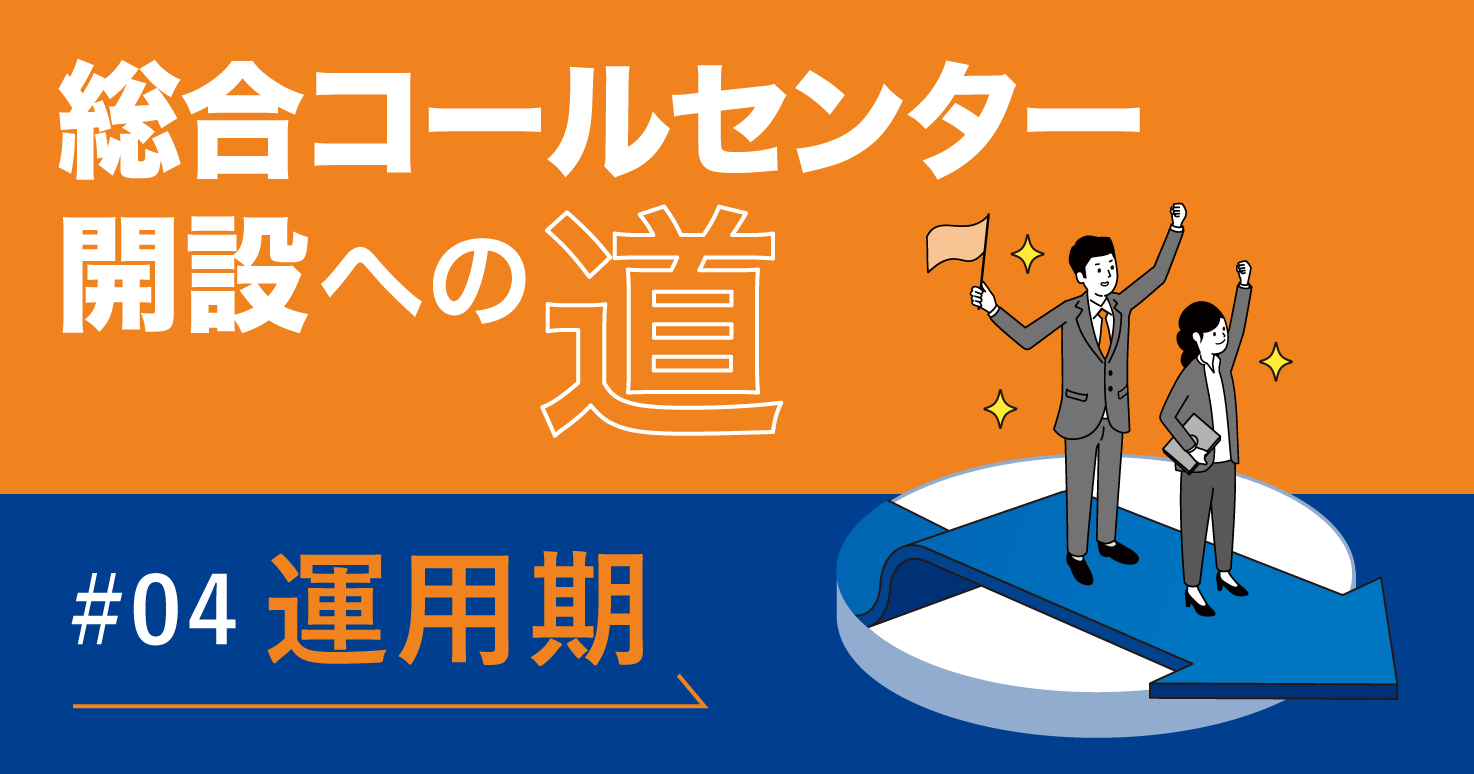
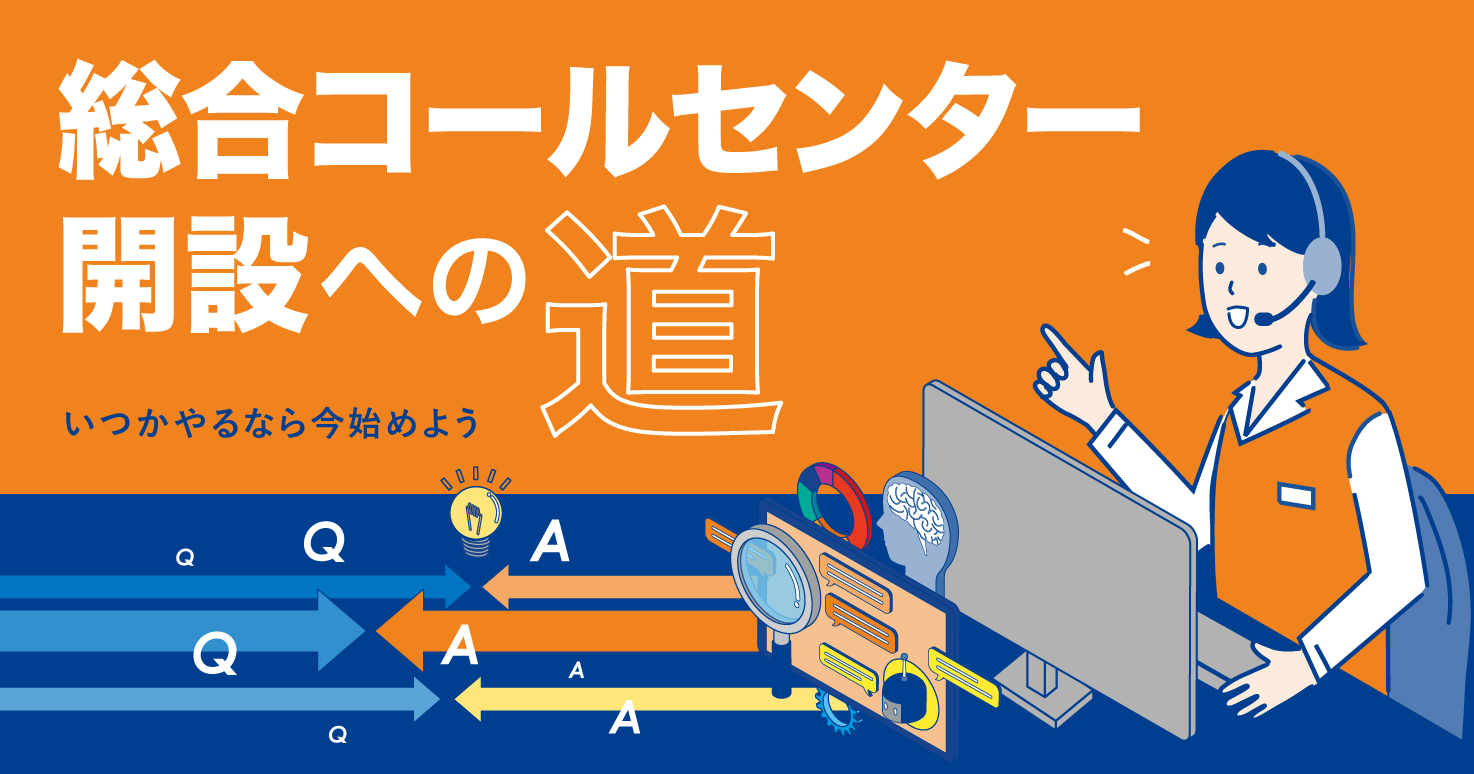

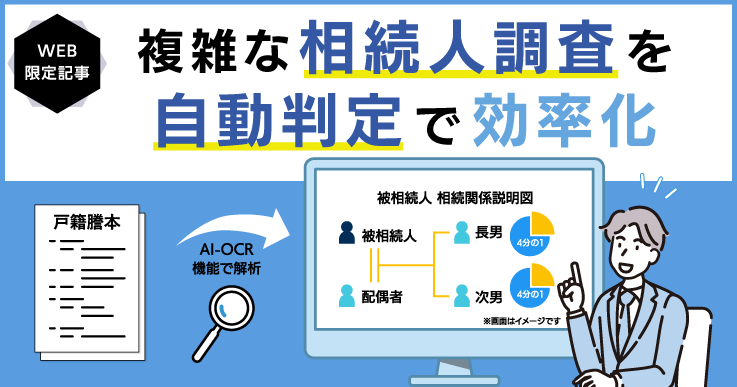
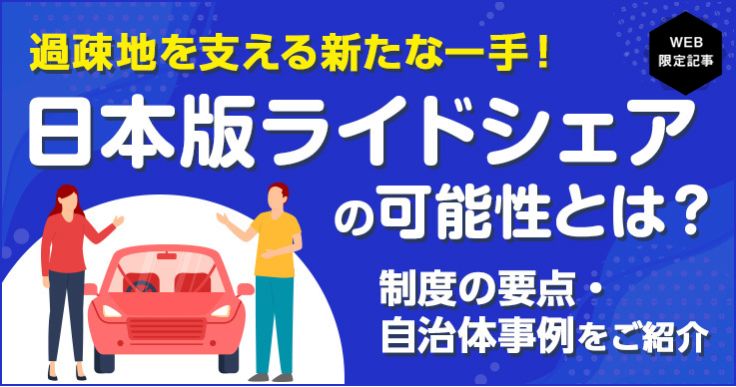
.png)











.jpg)
】バナー広告_株式会社ICHICO_PR.jpg)
.png)







