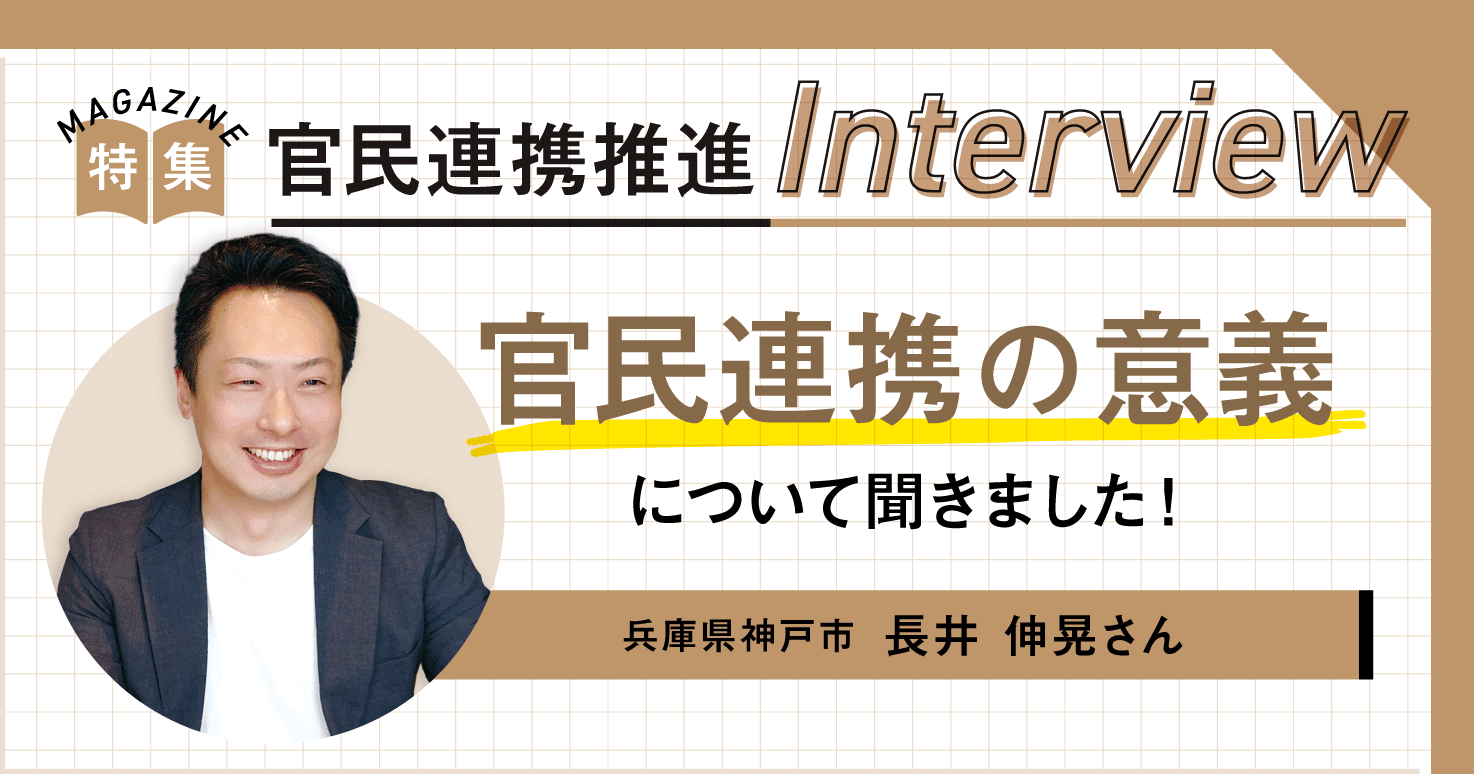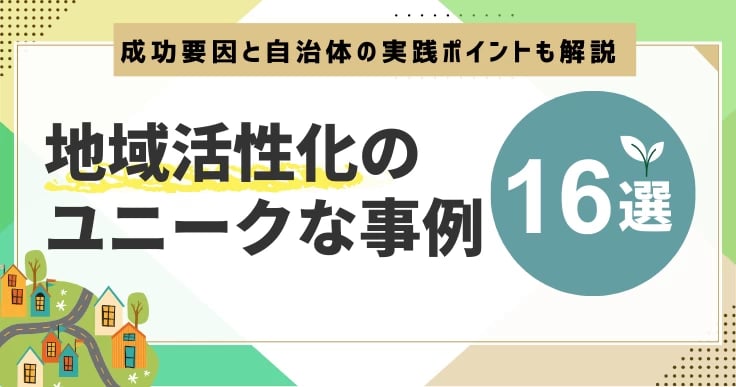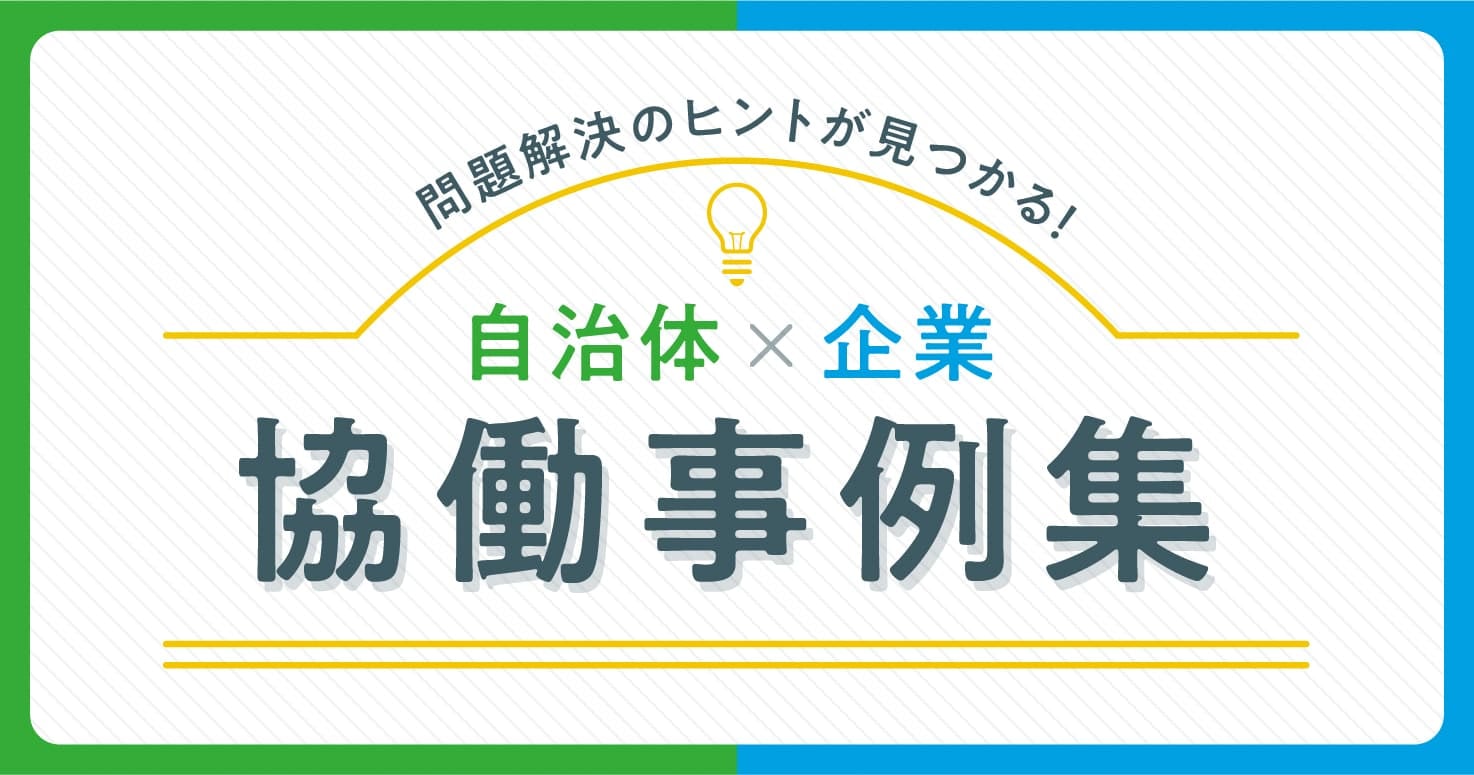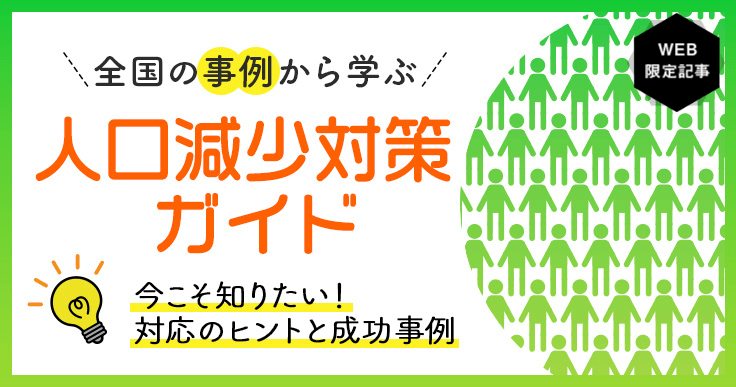公開日:
地域活性化の課題と成功のポイント|自治体の事例と最新トレンドも解説

人口減少に直面する今、“地域の元気をどう取り戻すか”は、全ての自治体に共通する課題だ。地域活性化は、人口減少や高齢化、地域経済の停滞といった課題を抱える自治体にとって、持続可能な地域づくりの要となる施策である。本記事では自治体が成果を上げるための成功ポイントと、失敗から学ぶ実践的なヒントを解説する。
※掲載情報は公開日時点のものです。

【監修者】早川 裕章さん
フリージャーナリスト(福岡在住)
1987年 KBC九州朝日放送入社、2019年~報道局解説委員兼福岡県政キャップとして福岡・佐賀県内の地域の課題や選挙などを取材しテレビ・ラジオ・ネットのニュースで発信。2024年に定年退職後フリーに。2025年3月まで「アサデス。ラジオ」コメンテーター。現在は福岡市を拠点にnoteで地方移住をテーマに官民の動きを取材し地方目線で毎週発信中。ネット上でとびかうデマにどう向き合っていけばよいか自治体職員や企業などを対象にした「SNS時代のメディアリテラシー」についての講演活動も行う。
地域活性化とは?

地域活性化とは、地域の課題を解決し、住民が安心して暮らせる持続可能な地域社会をつくるための包括的な取り組みである。少子高齢化や人口減少が進行するなか、地域の活力維持と経済再生を実現するため、自治体の最重要テーマの一つとして位置づけられている。
令和7年版の国土交通白書では、地域活性化を「地域経済の振興」「都市・生活機能の再編」「多様な交流の促進」によって実現を図る取り組みと定義している。自治体や地域住民、民間事業者などが協働し、持続可能な地域社会の形成を目的として進められるものだ。また、「地方創生2.0」として、デジタル実装や官民連携、関係人口の拡大など、地域の実情に応じた動きが全国で加速している。
地方創生と地域活性化の関係
地方創生は、これまで政府主導で進められてきた地域活性化政策の一つである。戦後の地域活性化(地域おこし)は、昭和47年に当時の田中 角栄首相が提唱した「日本列島改造論」に端を発するという見方が一般的だ。東京に集中し過ぎた人やモノを地方に分散させようと、工業の地方分散や、高速道路や新幹線などを全国に張り巡らせることなどを唱えた。
その後、昭和から平成にかけて竹下内閣が実施した「ふるさと創生1億円事業(正式名称:自ら考え自ら行う地域づくり事業)」も、その名の通り地域活性化を目的とした政策である。
人口減少時代における地域活性化の政策展開
現在進められている地方創生は、平成26年に第二次安倍内閣が制定した基本法(「まち・ひと・しごと創生法」)にもとづく人口減時代の地域活性化政策である。
東京一極集中によって生じた人口減少を背景に、「地域が存続の危機に陥っている」という指摘を受けて始めた取り組みであり、地方創生担当大臣が新設された。国が示す基本方針のもと、都道府県や市町村が地域の実情に応じた戦略を策定し、推進する仕組みとなっている。
初代の地方創生担当大臣は石破 茂氏であり、石破氏は令和6年秋の総理就任後も「地方創生2.0」を掲げ、地方創生を強力に推進した。今後は、2025年10月にスタートした高市内閣がこの流れをどのように継承していくかが注目だ。
出典: 国土交通省『平成30年版 国土交通白書 第II部 第4章「地域活性化の推進」』
自治体が抱える地域活性化の課題
少子高齢化や人口流出により、地域の働き手と税収が減少し、経済の停滞や公共サービスの維持が難しくなっている。こうした構造的課題が、地域活性化の必要性を一層高めている。国は「地域経済の再生」と「生活基盤の維持強化」を柱とする地方創生を進めており、自治体には地域の将来像を描き、持続可能な地域運営を実現することが求められている。
一方で、現場の自治体は計画策定や官民連携など多くの課題に直面しているのが現状である。以下では、その主な課題を整理する。
計画策定とインフラ維持の限界
地域の将来像を見据えた都市・地域計画の策定や、老朽化したインフラの維持・再編が課題となっている。職員数や専門人材の不足により、実効性のある計画づくりが難しいのが現状だ。「コンパクト・プラス・ネットワーク」を実現するには、医療・福祉・住宅・防災などの分野を横断した調整と、広域的なマネジメント力の強化、災害対応とまちづくりを一体で進める体制整備も急務である。
官民連携(PPP/PFI)に関するノウハウ不足
施設運営や地域資源の活用を効率化する手段として、PPP/PFIへの関心が高まっている。廃校や公共施設を活用する「スモールコンセッション」は注目されているが、事業化の進め方や民間との連携体制づくりに課題を抱える自治体は多い。導入が進む自治体は一部にとどまり、専門的な知見や支援体制の不足が課題である。官民の強みを活かすには、契約・財務・リスク管理に精通した人材の育成と、中間組織との連携が欠かせない。
交通・除雪など生活基盤の持続可能性
地域交通や除雪など、住民生活に直結する分野では、担い手不足や財政負担の増大が深刻である。特に「交通空白」地域では公共交通の維持が難しく、国が推進する日本版ライドシェアや交通DXの導入が期待されている。寒冷地や中山間地域では、除雪費の高騰や委託先の確保が課題となっており、自治体には安全確保と持続可能な運営体制の構築が求められている。
地域活性化の最新トレンド

社会や経済の変化、技術革新の進展により、地域活性化の手法は多様化している。ここでは、令和7年版の国土交通白書をもとに、自治体が今後の施策に取り入れやすい最新トレンドを紹介する。
出典: 国土交通省『令和7年版 国土交通白書 第II部 第3章「地域活性化の推進」』
DX・新技術の導入による効率化と付加価値創出
デジタル技術の導入は、地域課題の解決と新たな価値創出の原動力となっている。自動運転やドローン、ICTを活用した実証事業、バスや鉄道のキャッシュレス化など、交通・生活分野のDXが進む。さらに電子クーポンや地域通貨、SNS発信、オープンデータ活用など自治体独自の取り組みも広がり、効率化にとどまらず「地方から未来社会を構築する」挑戦へと発展している。
多様な移動手段の確保と日本版ライドシェアの拡大
地域交通の担い手不足に対応するため、日本版ライドシェアの導入が全国に広がっている。住民の自家用車を活用する仕組みで、地域のニーズに応じて運行時間や車両数を柔軟に設定できるのが特徴だ。全国47都道府県に拡大しており、移動手段の確保だけでなく、地域コミュニティの維持にも貢献している。
居住形態の多様化と関係人口の拡大
人口減少に対応し、二地域居住や関係人口の拡大が進んでいる。市区町村では「特定居住促進計画」の策定が進み、都市と地域を往来するライフスタイルを支える仕組みが広がる。また、地域住民や企業が連携し、空き家活用やコミュニティ再生を進める動きも加速中だ。こうした取り組みは、外部人材や民間の力を取り込みながら“地域をともに育てる関係”を築き、地域活性化の持続的な推進力となっている。
観光地の高付加価値化と地域拠点の形成
観光分野では、地域資源を磨き上げて高付加価値化する動きが進む。なかでも「道の駅」は、休憩・情報発信・地域連携の機能に加え、防災拠点や子育て支援施設としての役割を担い始めている。「かわまちづくり」や「みなとオアシス」「海の駅」など、地域の特性を活かした拠点形成も進み、観光・交流・防災の多機能な地域ハブとして注目を集めている。
地域活性化に必要なものとは?成功に導く3つのポイント
地域活性化を持続的に進めるには、国の支援を活かしつつ、地域が主体となって創意工夫を発揮することが重要である。ここでは、令和7年版の国土交通白書をもとに、自治体が地域の強みを活かして実効性ある活性化を実現するための3つの成功ポイントを整理する。
地域の創意工夫と自主性を活かした取り組み
地域の強みや文化を活かした自発的なまちづくりが、地域活性化のカギとなっている。地域の景観や歴史、観光資源などを守りながら、新たな交流や経済活動を生み出す動きが全国で広がっている。例えば、河川空間や港湾を地域資源として活用し、まちと一体的に整備する取り組みなど、地域発の発想と連携が持続的な成果を生み出している。
官民連携(PPP/PFI)によるノウハウ・資金の活用
民間の発想や資金を取り入れる官民連携は、地域課題を解決する実践的な手法である。廃校や公共施設を活用した「スモールコンセッション」など、地域資産を再生する動きが広がっている。また、道路や公園などの公共空間を官民で活用し、「居心地が良く歩きたくなるまちなか」を目指す動きも拡大中だ。こうした柔軟な連携は、限られた財政や人員の中でも成果を上げやすい実践的なアプローチとなっている。
広域連携と戦略的なインフラ投資
地域の持続的発展には、広域的な連携と戦略的な交通インフラ整備が欠かせない。国は、高規格道路やリニア、整備新幹線の整備を進めるとともに、半導体など成長産業の拠点づくりを支援している。こうしたネットワーク強化は、産業・物流・観光を結びつけ、地方全体の競争力を高める役割を果たしている。
地域活性化を実現した自治体の成功事例

地域活性化の取り組みには、地域の特性を見極めながら課題を解決し、持続的な仕組みを築く工夫が求められる。成功している自治体に共通するのは、地域資源の再定義、官民の連携、住民を巻き込んだ継続的なまちづくりである。
ここでは、全国の中でも注目を集める3つの自治体を取り上げ、その背景と成果、そして他自治体が学べる実践のヒントを紹介する。
北海道下川町|森林資源を活用した循環型まちづくり
北海道下川町は、林業を基幹産業とする自治体で、平成26年に「循環型森林経営」を確立した。町有林約3,000ヘクタールのうち毎年50ヘクタールを伐採し、同面積を植栽するサイクルを60年かけて繰り返す仕組みを構築。伐採後の木材は加工・販売まで地域内で完結させ、雇用と産業創出を両立させている。平成30年には町民と策定した「下川版SDGs」を掲げ、環境・経済・社会を循環させる地域モデルを確立した。
出典: 下川町「第2期SDGs未来都市計画 ~人と自然を未来へ繋ぐ“しもかわチャレンジ”(2021~2023)~」
長野県塩尻市|官民連携によるワイン産業のブランド化
長野県塩尻市は、桔梗ヶ原ワインバレー特区を中心に、官民連携で地域特産のワイン産業を振興している。明治期からの醸造文化を継承しつつ、平成20年にブランド推進室を設置。県の「信州ワインバレー構想2.0」と連携し、地域ブランドと観光振興を一体で推進している。県全体のワイナリー数は平成25年時点で約25場から令和5年時点で71場に拡大し、ぶどう栽培面積も191.7haから343.2haに増加している。
福岡県糸島市|「食」と自然を軸にしたブランド戦略と移住促進
福岡県糸島市は、農林水産業を軸とした地域ブランド戦略を推進し、「食」と自然の魅力を一体的に発信している。行政内に「ブランド政策課」を設置し、農産物や海産物の販路拡大を支援。観光や移住促進とも連動させ、地域経済の好循環を生み出している。
出典: 糸島市「第2期まち・ひと・しごと創生 総合戦略(2020-2024/改訂版)」
失敗から学ぶ持続可能な地域活性化のヒント
地域活性化の取り組みは、成功の裏に多くの試行錯誤がある。過去の事例を振り返ると、構想段階での見通しや運営体制の課題が明らかになっており、「何を避けるべきか」「どこに落とし穴があるか」を知ることも成功への第一歩である。
ここでは、現場の教訓として押さえておきたい4つのポイントを整理する。
これらの事例に共通するのは、限られた人員や予算の中で成果を急ぐあまり、実現性や住民との連携が後回しになることがある。重要なのは短期的な成果よりも、地域の特性や声を活かした持続可能な仕組みづくりを意識すること。
失敗を恐れず、課題を共有しながら改善を重ねていくことが、自治体にとって本当の意味での“成功”につながる。
まとめ
地域活性化は、人口減少や産業の衰退といった課題を克服するだけでなく、地域の個性を再発見し、日本全体の力を底上げする取り組みでもある。小さな成功や試行錯誤の積み重ねが、次の挑戦へのヒントとなり、全国へ波及していく。住民・行政・企業がそれぞれの立場で力を出し合い、“地域の未来を自分たちでつくる”という意識を持ち続けることが大切だ。その一歩が、地域の元気を、そして日本全体の活力へとつながっていく。