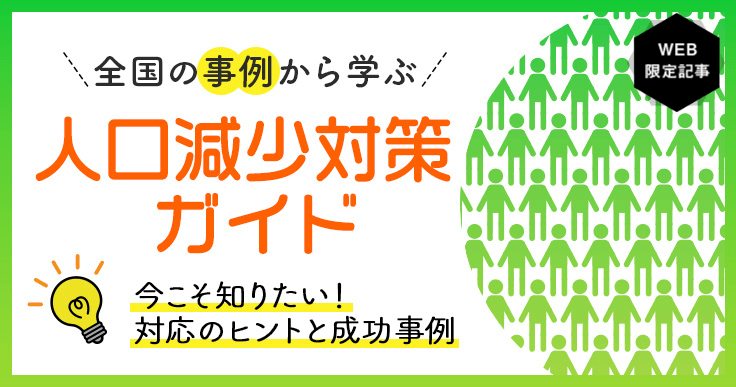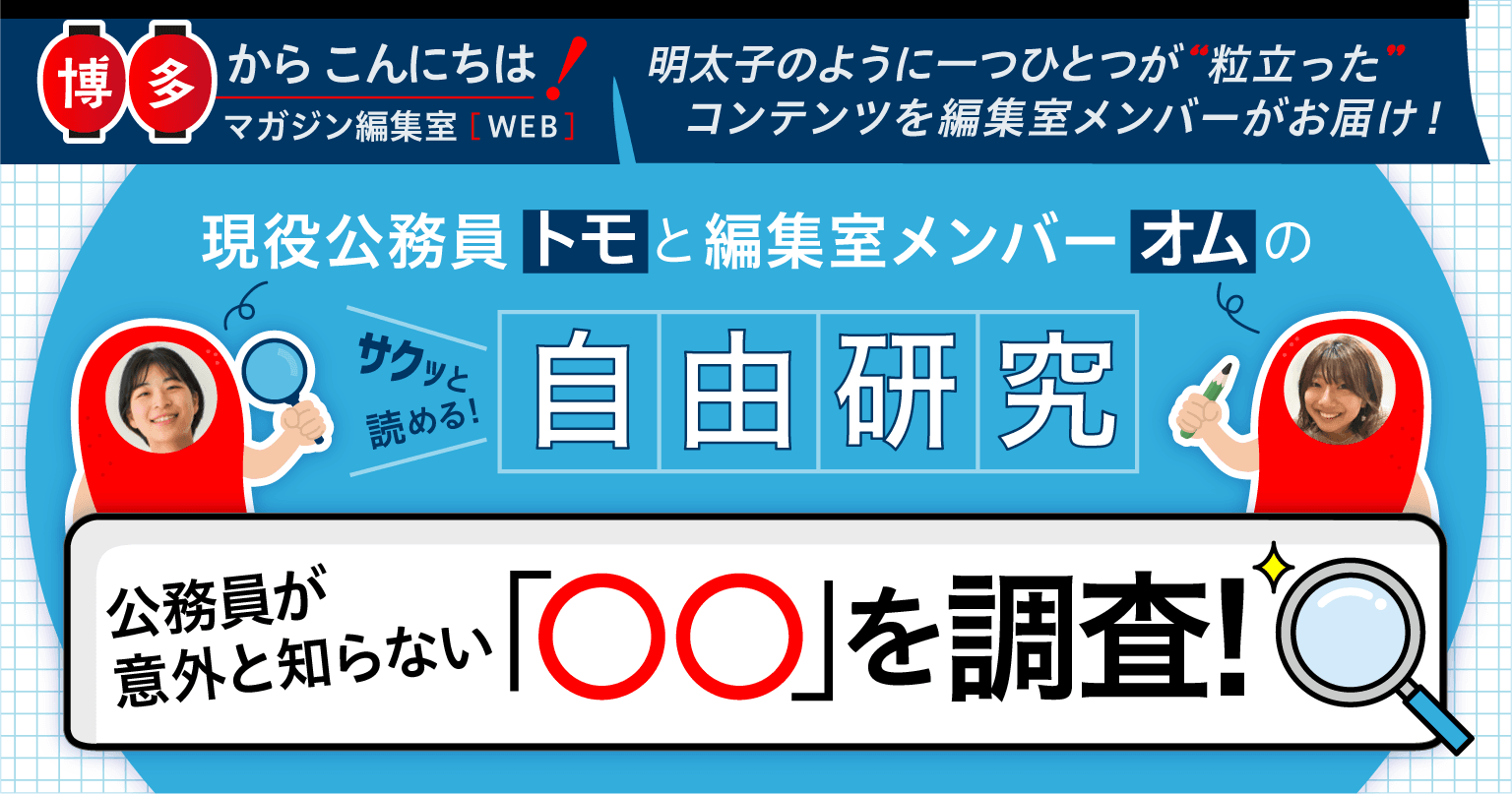地方創生交付金とは?
地方創生交付金は、地方公共団体が地域の特性を活かし、持続的な発展を進めるために国が支援する制度である。従来の「デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生タイプ)」を引き継ぎ、令和6年度補正予算からは「新しい地方経済・生活環境創生交付金」として刷新された。
この「新しい地方経済・生活環境創生交付金」は、総称して「第2世代交付金」とも呼ばれ、自治体の自主性や創意工夫を尊重しながら、デジタル活用と多様な主体の連携による課題解決を後押しする仕組みである。
交付金全体の目的
新しい地方経済・生活環境創生交付金は、政府が掲げる「地方創生2.0」の理念に沿って制度設計されており、次のような方向性が示されている。
- 地域の可能性を引き出し、持続可能で魅力ある地域づくりを推進すること。
- 地域の将来像の実現に向け、分野横断的な連携とソフト・ハード両面の施策を一体的に進めること。
- 地方公共団体が、多様な主体と協働しながら、共創による地方創生の取り組みを展開できるよう支援すること。
地方創生交付金は、「地域課題の解決」と「持続可能なまちづくり」を推進するための基盤的な財源といえる。自治体は事業計画を策定し、国の認定を受けることで、地域の実情に応じて柔軟に活用できる。
【令和7年度版】地方創生交付金の種類一覧

出典: 内閣官房 地方創生推進室「新しい地方経済・生活環境創生交付金について(令和7年9月)」
令和6年度補正予算では、旧制度である「デジタル田園都市国家構想交付金」が制度の名称と内容を拡充し、「新しい地方経済・生活環境創生交付金」として創設された。 従来のデジタル基盤整備にとどまらず、地域経済の活性化や生活環境の改善、地域再生などを包括的に支援する仕組みへと進化している。ここでは、その主な種類と特徴を整理する。
第2世代交付金
第2世代の地方創生交付金は、地方がそれぞれの特性に応じた発展を遂げることができるよう、日本経済成長の起爆剤としての地方創生策を推進する制度である。地方公共団体の自主性と創意工夫に基づき、地域の多様な主体が参画する取り組みを、計画から実施まで一体的に支援する点が特徴だ。
【主な特徴と要件】
- 最先端技術教育の拠点整備・実施など、ソフト・ハードを一体的に支援
- 地域の多様な主体が参画する仕組みを構築し、分野横断的な取り組みを推進
- 国による伴走支援を強化し、計画策定から実施まで一体的に後押し
- 農産物直売所や多世代交流施設など、地域の実情に応じた整備を支援
出典: 内閣官房 地方創生推進室「新しい地方経済・生活環境創生交付金について(令和7年9月)」
デジタル実装型
デジタル実装型は、自治体がデジタル技術を活用して地域課題を解決し、地域の魅力を高める取り組みを支援する制度である。意欲ある地域の挑戦を交付金で後押しし、TYPE別の事業立ち上げに必要な経費を単年度で支援する。
支援対象となるのは、デジタルを効果的に活用した事業であり、コンソーシアムを形成して地域内外の関係者と連携し、継続的に推進できる体制を備えることが共通要件とされている。
【TYPE別の内容】
- TYPE1:既存の優良モデルを活用し、課題解決策を迅速に展開
- TYPEV:AIやブロックチェーンなど新技術を用いた先進的な取り組みを高補助率で支援
- TYPES:「デジタル行財政改革」に沿って、公共財の開発を通じた構造改革を推進
あわせて、「デジタル実装伴走支援事業」では、デジタル実装に取り組む地域が計画を策定できるよう、国が必要な支援を行っている。
出典: 内閣官房 地方創生推進室「新しい地方経済・生活環境創生交付金について(令和7年9月)」
地域防災緊急整備型
地域防災緊急整備型は、安心・安全で持続可能な地域づくりを進める地方公共団体の取り組みを支援する制度である。災害時にも安心して暮らせる地域社会の実現を目指し、避難所の生活環境改善や防災設備整備を交付金で後押しする。
具体的には、トイレ・キッチン・ベッド・風呂など、避難所での生活機能を迅速に提供できる環境を整備するとともに、 地方公共団体が地域経済の活性化や住民の防災意識向上を見据え、平時から利活用できる仕組みづくりを支援する。
【支援対象となる取り組み例】
- トイレカーや簡易トイレなど快適なトイレ環境の整備
- キッチンカーや炊き出し資機材による温かい食事提供体制の確保
- 簡易ベッドやパーテーションによるプライバシー確保
- 入浴環境の充実
このほか、令和6年能登半島地震を踏まえた新技術カタログで紹介された、避難生活の質を高める技術の活用も対象となる。
出典: 内閣官房 地方創生推進室「新しい地方経済・生活環境創生交付金について(令和7年9月)」
地域産業構造転換インフラ整備推進型
地域産業構造転換インフラ整備推進型は、半導体などの戦略分野で進む産業拠点の整備を支えるインフラ整備を支援する制度である。国内投資を促進し、国際競争力の強化や雇用創出につなげることを目的としている。
交付対象は、選定された民間プロジェクトに関連する工業用水、下水道、道路などのインフラ整備で、都道府県の実施計画に位置づけられたものとされる。
【プロジェクト選定の主な視点】
- 国策的意義:国として支援すべき大規模な産業拠点整備であること
- 緊急性・合理性:関連インフラの優先整備が合理的であること
- 地域貢献性:雇用創出や地域経済の活性化など地方創生に寄与すること
出典: 内閣官房 地方創生推進室「新しい地方経済・生活環境創生交付金について(令和7年9月)」
【令和7年度版】地方創生交付金申請における最新の変更点と注意点
令和7年度の地方創生交付金(新しい地方経済・生活環境創生交付金)では、制度運用が大きく変わっている。KPI設定と成果公表の義務化、デジタル実装型の重視、政策効果の「見える化」と説明責任の強化など、自治体にとって実務上の対応が欠かせない。
さらに、臨時交付金はコロナ対応から物価高騰対策へと用途が移り、使い方にも注意が必要だ。ここでは、最新の変更点と申請時の留意点を整理する。
KPI・成果公表の推進
第2世代交付金では、KPI設定や成果の検証・公表が制度要綱上で重視されている。令和7年度は報告様式が見直され、「地域の多様な主体の参画」や「成果・改善方策」に関する記載項目が追加された。また、産官学金労言など多様な主体が参画し、進捗測定や改善方策に関与する体制づくりが推奨されている。
KPIは、事業と直接関連する定量的な指標を設定することが求められ、効果検証の結果や改善方策を公表する仕組みが制度上明記されている。これにより、国民や地域住民に対する説明責任の履行が求められるようになった。
出典: 内閣官房「新しい地方経済・生活環境創生交付金制度要綱 」
出典: 内閣官房新しい地方経済・生活環境創生本部事務局「新しい地方経済・生活環境創生交付金の採択結果について」
出典: 内閣府 地方創生推進室「新しい地方経済・生活環境創生交付金(デジタル実装型)Q&A集」
デジタル実装型の重視(RAIDA活用など )
第2世代交付金では、「デジタル実装型(TYPE1)」が明確に位置づけられ、自治体によるデジタル技術活用が重点化されている。窓口DX、オンライン申請、地域アプリ導入など、住民サービスの利便性向上や行政効率化に直結する事業が対象となる。
また、国が運営する「RAIDA(地方創生データ分析評価プラットフォーム)」では、採択事例やKPI情報が閲覧可能となり、他自治体の成功事例を計画づくりに活用できるようになった。
出典: 内閣府 地方創生推進室「新しい地方経済・生活環境創生交付金デジタル実装型 TYPES制度概要」
出典: 内閣府・内閣官房総合サイト「デジタル実装型」
出典: 内閣官房「RAIDA(地方創生データ分析評価プラットフォーム)」
政策効果の見える化・住民への説明責任の強化
第2世代交付金では、政策効果の「見える化」と説明責任の強化が制度上明確化された。自治体は、事業実施後の効果検証や改善方策の公表を行うことが求められ、報告書には運用課題や横展開に向けた知見の記載も推奨されている。
多様な主体の参画を通じ、評価や改善に反映させる体制を整備することが重要であり、自治体職員にとっては「成果をどう測定し、どう公表するか」を計画段階から設計することが求められる。
- 効果検証と公表:KPI達成度や改善方策の検証結果を公開することが要綱で明記された。
- 報告内容の充実:実施報告書には、運用課題や横展開に向けた知見など、より具体的な情報を盛り込むことが求められる。
- 多様な主体の参画:産官学金労言などの関係者を交え、評価や改善に反映させる体制を構築することが必須とされている。
自治体職員にとっては、計画段階から「成果をどう測定し、どう公表するか」を設計し、住民と国への説明責任を果たせる体制整備が実務上の重要ポイントである。
出典: 内閣官房「新しい地方経済・生活環境創生交付金制度要綱 」
出典: 内閣官房新しい地方経済・生活環境創生本部事務局「新しい地方経済・生活環境創生交付金の採択結果について」
臨時交付金の用途シフト(コロナ対応 → 物価高騰対策)
「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」は、従来の地方創生臨時交付金の枠組みを引き継ぎながら、コロナ禍での緊急対応から、物価高騰・エネルギー価格上昇への対応へと重点を移した制度である。令和6年度以降は、次のような生活支援策を中心に活用が進んでいる。
- 非課税世帯や低所得子育て世帯への生活支援
- 令和6年1月以降の家計急変世帯に対する支援・地域での物価高騰対応(光熱費・燃料費負担の軽減など)
臨時交付金の「時限性」と「用途の変化」を正確に把握し、迅速に制度設計と住民周知を行うことが実務上の重要ポイントである。
出典: 地方創生「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金制度要綱」
自治体による地方創生交付金の活用事例
地方創生交付金は、観光振興やDX推進、子育て支援など幅広い分野で活用されている。ここでは、全国の自治体による最新の活用事例を紹介し、交付金を実際にどう成果につなげているのかを解説する。
地方創生推進交付金|岡山県矢掛町「道の駅周辺に観光・物流拠点整備」
岡山県矢掛町では、令和6年度まで実施された「地方創生推進交付金」を活用し、道の駅周辺の道路整備や観光・物流拠点の機能強化を進めた。中心市街地の古民家再生による観光拠点づくりを進めた結果、観光客数が大幅に増加していたが、施設間を結ぶ道路が狭く複雑で、回遊性の低さが課題となっていた。
この課題解決のため、矢掛町の町道と隣接する井原市の広域農道を結ぶ道路整備を実施。アクセス時間の短縮や物流機能の向上を図り、道の駅の集客力向上や地元農産物の販売拡大につなげている。
出典: 地方創生「地域再生計画」
地方創生臨時交付金(物価高騰対応)|福井県鯖江市の生活者・事業者支援状況
福井県鯖江市には、令和6年度の物価高騰対応地方創生臨時交付金として約9億9,961万円が交付された。市はこの財源を活用し、以下のような生活者・事業者支援を実施している。
- 住民税非課税世帯への給付金支給
- 子育て世帯へのデジタル商品券の配布
- 高齢者・障害者福祉施設の電気料負担軽減
これらの支援策により、物価高騰の影響を受けやすい世帯や施設の負担軽減が図られている。具体的な使途や金額の詳細は、鯖江市の公式ウェブサイトで公開され、住民への透明性確保と説明責任を果たしている。
出典: 鯖江市市役所「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の活用状況について」
拠点整備交付金|長崎県新上五島町「廃校を活用した子育て世代向け交流拠点」
長崎県新上五島町では、令和6年度まで実施された「デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生拠点整備タイプ)」を活用し、廃校となった小学校の校舎や体育館を再生。屋内型の遊び場を備えた子育て世代向け交流拠点として整備した。
この拠点は、子育て世代が安心して集える場を提供することで、住民の満足度向上と転出防止、さらには移住・定住の促進を図る取り組みである。廃校施設の有効活用と少子化対策を同時に進める点で、他自治体にとっても参考となる事例だ。
出典: 地方創生総合サイト「デジタル田園都市国家構想交付金地方創生拠点整備タイプ 採択事例集」
デジタル田園都市構想交付金|香川県高松市「地理空間データ基盤『スマートマップ』構築」
香川県高松市は、令和6年度まで実施された「デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生タイプ)」を活用し、地理空間データ基盤として『高松市スマートマップ』を構築した。このアプリには、防災拠点や避難所などの防災情報、道路や上下水道といったインフラ情報が登録されているほか、道路渋滞状況や駐車場の満空情報もリアルタイムで確認できる。
市民にとって利便性が高いだけでなく、行政側にとってもデータの一元管理や災害時の迅速な対応に役立つ仕組みであり、DX推進と住民サービス向上を両立させる事例として注目されている。
出典: 内閣府「スマートシティインタビュー Vo;3-1 令和7年3月21日」
地方大学・地域産業創生交付金|福島県「水素社会を見据えたバイオマス技術開発と人材育成」
福島県では、地方大学・地域産業創生交付金を活用し、福島大学・県内企業・自治体が協働して、小規模地産地消型のバイオマス由来水素と炭化物の製造システムの研究開発と人材育成に取り組む計画が認定されている。
この計画では、バイオマス(剪定枝や稲わら等)を原料とし、生成した水素および炭化物を地域内で利活用するモデルを追求。大学の研究力強化や人材育成を通じ、地元企業の技術力向上と産業創出を両立させる狙いがある。若者の県外流出対策として、研究と雇用を地域に根づかせることを目指し、地方創生につなげる先進的な取り組みとして注目されている。
出典: 福島県庁「地域における大学振興・若者雇用創出事業に関する計画 」
地方創生交付金の使い道と活用ポイント
地方創生交付金を申請する際、「どのように使えば効果的なのか」と悩む自治体も少なくない。ここでは、各自治体が取り組みやすく、成果につながりやすい活用方法の例を整理する。
■DX・デジタル基盤整備
住民向けの防災情報や生活情報を一元化するアプリの開発は、交付金活用の代表例である。また、観光地や特産品の紹介・販売プラットフォームを構築すれば、観光客や地域ファンを増やし、地域経済の活性化にもつながる。
■子育て・教育・福祉拠点
交付金を活用して子育て・教育・福祉の複合拠点を整備すれば、子どもの遊び場、地域住民の情報交換の場、健康づくりの拠点として機能する。地域コミュニティの活性化や定住促進に寄与する点が大きなポイントだ。
■産業振興・人材育成
民間企業の研究開発費支援や、地元の小・中学校・高校・大学への教育支援に充てることで、新産業の創出や技術革新を後押しできる。特に、若者の人材流出防止と地元定着につながる取り組みは、多くの自治体が重点化している分野である。
■住民生活支援(臨時交付金)
物価高騰や収入減で影響を受ける非課税世帯・子育て世帯・高齢者世帯への給付金、あるいは地域企業への物価高騰対策支援も臨時交付金の有効な使い道である。短期的な支援であっても、住民の安心や地域経済の持続性を支える重要な施策となる。
地方創生交付金は、観光振興からデジタル基盤整備、福祉拠点、産業振興、生活支援まで幅広く活用できる。自団体の地域課題に直結する施策を見極め、複数の政策目的と組み合わせることで、交付金活用の効果を最大化できる。
関連する臨時制度・補助金の活用策
地方創生の推進には、交付金だけでなく、目的別に設けられた臨時制度や補助金の活用も重要である。令和7年度時点では、物価高騰対策や地域産業振興、大学との連携強化など、各分野を支援する制度が並行して実施されている。
ここでは、地方創生交付金とあわせて理解しておきたい主要な制度を整理する。
物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金
物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金は、これまでの「地方創生臨時交付金」の仕組みを引き継ぎ、物価高騰対策を重点的に支援するために新たに設けられた制度である。物価高騰の影響を受けやすい層への生活支援と、地域経済の下支えを目的として、次の枠組みが設けられている。
- 低所得世帯支援枠:住民税非課税世帯など、物価高騰の影響を受けやすい世帯への給付支援。
- 給付金・定額減税一体支援枠:定額減税を補完し、給付金を組み合わせて支援。
- 給付支援サービス・事務支援枠:給付金の支給や手続きにデジタルサービスを活用する取り組みを支援。
これにより、自治体は地域の実情に応じた迅速かつ効果的な支援を実施できる。
出典: 地方創生総合サイト「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」
地方大学・地域産業創生交付金
地方大学・地域産業創生交付金は、地方大学の機能強化と地域産業の振興を一体的に進めるための交付金である。人口減少や若者流出といった地域課題に対応し、人材定着と産業の自立を促すことを目的としている。
【主な支援対象事業】
- 若者にとって魅力ある雇用機会や産業を創出するための事業
- 全国や海外から学生が集まる魅力ある大学づくりのための事業
地方大学と地域産業を連携させ、地域の持続可能な成長を支える基盤として活用が進められている。
出典: 地方創生総合サイト「地方大学・地域産業創生交付金事業」
【そのほか】地方創生に役立つ関連補助金
地方創生を進める上では、交付金だけでなく国や自治体が設ける各種補助金も重要な財源となる。これらの補助金は、地域課題の解決や住民の定住促進、地域産業の活性化を後押しするために活用できる。
代表的な補助金の例は次のとおりである。
- 起業支援金:地域での起業や新規事業立ち上げを支援
- 移住支援金:都市部から地方への移住者に対する生活・就業支援
- ものづくり補助金:中小企業による新製品開発や生産性向上の取り組みを支援
これらの補助金を組み合わせて活用することで、自治体の地方創生施策をより効果的に推進することが可能となる。
まとめ
地方創生交付金は、自治体の活性化や持続可能な地域づくりを進めるために不可欠な財源である。しかし第2世代交付金からは、KPIの設定や成果の公表、政策効果の「見える化」が義務化され、透明性と説明責任がより一層重視されるようになった。
これからは、交付金を獲得すること自体を目的とするのではなく、「交付金を活用して何を実現し、どのように成果を示すか」までを計画に組み込むことが重要だ。成果の測定・改善を通じて住民に還元できる仕組みを構築することが、自治体に求められている。