
少子高齢化や人口減少が加速するなか、「地方移住」は「地方創生」における地域の活性化や持続可能なまちづくりに向けた重要な施策のひとつとして注目を集めている。とはいえ、実際に自治体職員として業務に携わる際には、制度や事例、現場の課題など幅広い知識と理解が求められ、どこから学び始めればよいのか迷う方も多いのではないだろうか。
そこで本企画では、報道の最前線で地域課題や行政の取り組みを長年取材し、現在は「地方移住」をテーマに全国の動きを地方目線で発信しているフリージャーナリストの早川 裕章さんに、自治体職員が押さえておきたい基礎知識や最新動向を分かりやすく解説していただく。
※掲載情報は公開日時点のものです。
 解説するのはこの方
解説するのはこの方
早川 裕章(はやかわ ひろあき)さん
フリージャーナリスト・ライター(福岡在住)
1987年 KBC九州朝日放送入社、2015年 東京支社から報道部に異動。2019年~報道局解説委員として福岡県・佐賀県内の地域の課題や選挙などを取材しテレビ・ラジオ・ネットのニュースで発信。2024年に定年退職後フリーに。2025年3月までKBC「アサデス。ラジオ」レギュラーコメンテーター。現在はnoteでテーマを「地方移住」に限って福岡市を拠点に官民の動きを取材し「地方目線」で発信中。ネット上でとびかうデマにどう向き合っていけばよいのか自治体職員や企業などを対象とした「SNS時代のメディアリテラシー」についての講演活動も行う。
「地方移住」の今を地方目線で発信
読者の皆さんはじめまして。福岡在住のフリージャーナリスト早川裕章です。筆者は令和6年まで福岡市に本社を置くKBC九州朝日放送の報道部門で記者を務め、10年前から福岡県庁の記者クラブをベースに福岡県や佐賀・大分・山口といった福岡近隣の県や市町村の人口減少や地域活性化を取材しニュースやニュース解説で伝えてきました。その中でこのままでは自分のふるさとが消えてしまいかねないという危機感を抱き、令和6年の定年退職後、フリーランスとして地方移住を後押しする発信を続けています。
学生時代と会社員時代に計11年間首都圏で生活し、東京暮らしの魅力も短所も知っています。その経験をもとに地方移住のトレンドと移住先として人気がある福岡県の魅力などを伝えてきました。
「衰退する地方」側からの発信でありながら、なるべく東京をディスることなく、地方のよさを発信して、地方移住が頭をよぎった皆さんの背中をおし、移住定住促進に取り組む自治体職員や議員の皆さんの支援に取り組んでいます。
今回は、これまでの官民連携による地方移住の歩みを整理するとともに、今後の移住政策に大きな影響を与えるであろう新組織の誕生について解説します。自治体職員の皆さんには、地域の移住定住施策を企画・推進するうえでのヒントとして、ぜひ参考にしていただければと思います。

「地方移住」これまでの官民の取り組み
現在の加速度的な人口減少は「静かなる有事」といわれますが、ここで石破内閣の看板政策の1つである「地方創生2.0」のうち「地方移住推進」についてこれまでの官民の取り組みを振り返ってみたいと思います。
人口減は「自然減」と「社会減」があり、地方移住は「社会減=転出入の転出超過」を転入超過に変え「社会増」を実現する手段です。筆者は「自然減を解消させる少子化対策を強く推し進めながら、並行して地方移住を推し進めるべき」という考えに立って日々の取材と発信を行っています。
戦後の政府の人口減対策は、第二次安倍内閣の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」(平成26年12月閣議決定)いわゆる「地方創生」が初めての取り組みととらえている方も多いと思いますが、筆者は麻生太郎内閣が平成21年に打ち出した故・鳩山邦夫総務大臣による「地域力創造プラン(鳩山プラン)」が始まりととらえています。平成18年に総務省に設置されていた「人口減少自治体の活性化に関する研究会」をふまえ、現在は全国で7,910人(令和7年4月4日・総務省発表)が活動している「地域おこし協力隊」は、改善すべき課題はありますが、麻生内閣が平成21年に始めています。「地方創生元年」とされる平成27年の6年前です。
では民間側がどうかというとさらに早く、「ふるさと回帰支援センター」が設立されたのは平成14年で、総務省の「人口減少自治体の活性化に関する研究会」設置より4年早いです。設立には、労働組合の連合が深くかかわっていますが、これは連合が「団塊の世代の組合員」が大量に定年に到達する平成19年を前に「定年退職後にどこで暮らすのか」「ふるさと回帰も選択肢なのではないか」と考えたことがきっかけです。連合はセンターの相談窓口で回帰後の受け入れ先となる農協や漁協などとともに平成17年には本格的な移住相談を開始し、令和6年は28,800人が来場した「ふるさと回帰フェア」も同年に始めています。
都市から地方への移住、都市と農山漁村地域との交流を推進しようと「旧JOIN 移住交流推進機構」が任意団体として発足したのは平成19年。両団体ともリーマン・ショック以前に「地方移住」への取り組みを始めていることには注目しておきたいところです。
地方移住を推進する新組織が誕生
 先月(令和7年7月1日)、国内で「地方移住=都市から地方への移住」に取り組んできた民間の2団体、認定NPO法人「ふるさと回帰支援センター」と一般社団法人「ふるさと回帰・移住交流推進機構(旧JOIN)」が、両組織の統合と新組織の発足を発表する記者会見を開きました。(記者会見の様子写真提供:早川裕章氏)
先月(令和7年7月1日)、国内で「地方移住=都市から地方への移住」に取り組んできた民間の2団体、認定NPO法人「ふるさと回帰支援センター」と一般社団法人「ふるさと回帰・移住交流推進機構(旧JOIN)」が、両組織の統合と新組織の発足を発表する記者会見を開きました。(記者会見の様子写真提供:早川裕章氏)
新組織の名称は、公益社団法人ふるさと回帰・移住交流推進機構(JOIN-FURUSATO)。47の全都道府県と全国の市区町村の86.4%にあたる1,486の市区町村が自治体会員になっていて、法人55社なども会員となっています(令和7年6月26日現在、記者会見配布資料より)。
前身2団体の業務は新組織で継続
今回の統合で前身団体の1つとなる「ふるさと回帰支援センター」は、6月30日をもって解散しました。これまで取り組んできた年間6万件を超え、増え続ける地方移住希望者への相談や、今年は9月20日(土)・21日(日)の2日間、東京国際フォーラム(東京)で予定されている「ふるさと回帰フェア2025」、「都市と農山漁村の交流・移住実務者研修セミナー」などの事業は新組織の中で継続します。
もう1つの前身団体「移住・交流推進機構」がこれまで取り組んできた、「地域おこし協力隊」の事業支援、「JOIN 移住・交流&地域おこしフェア」(今年は11月22日・23日に東京ビッグサイトで開催予定)といった移住・交流希望者への情報発信などの事業も、全て新組織の中で継続されます。
「ふるさと回帰フェア」や「JOIN 移住・交流&地域おこしフェア」は、首都圏の移住検討者と全国で移住定住に取り組む団体が集結するイベントで、近年参加者が増えています。筆者のブログでもレポートしていますが、地方移住を取り巻く現在の空気をリアルに感じることができるので、「地方移住」に取り組んでいる、あるいは取り組みを検討している自治体の首長や職員、議員の皆さんは日帰りOK。出張でも私的旅行でもよいのでぜひ一度会場を訪れることをお勧めします。
新組織「ふるさと回帰・移住交流推進機構(JOIN-FURUSATO)」の会長には、岩手県知事や総務大臣を務めた増田寛也氏(野村総合研究所顧問)が就任しました。常勤の理事長には「旧ふるさと回帰支援センター」の高橋公理事長、非常勤の副理事長には、旧JOIN(移住・交流推進機構)のトップを務めていた百木田康二氏(東武トップツアーズ社長)、業務執行理事には旧JOINでも業務執行理事を務めていた林崎理(地域活性化センター理事長)が就きました。
統合の転機は昨年(令和6年)夏の政府報告書
「地方創生は期待したほどの成果を出すことができなかった」
これまでも「地方移住」で一定の連携をしてきた両団体が統合に向けて大きくかじをきったきっかけは、昨年(令和6年)6月に岸田内閣の「デジタル田園都市国家構想実現会議(現・内閣官房新しい地方経済・生活環境創生本部)」が発表した「地方創生は期待したほどの成果を出すことができなかった」という報告書(※)です。
※出典:地方創生サイト「地方創生10年の取組と今後の推進方向 」
旧ふるさと回帰支援センターで理事長を務め、新組織の理事長も務める高橋公氏はこの報告書に「強い危機感」を抱き、「地方移住のスケールアップには同じ志をもつ『旧JOIN』との統合が不可欠」という思いから、『旧JOIN』の林崎執行理事に打診し意気投合した、と公表しています(「統合への思い」より)。
両団体がそれぞれ会員自治体に「組織統合に関する決断」を文書で伝えたのは昨年(令和6年)9月24日。地方創生を「日本経済の起爆剤」と位置づけ、大規模な対策を講じる方針を打ち出した石破茂現総理が、自民党総裁選を戦っている最中でした。
増田会長「もう一度地方に輝きを作り出していきたい」
記者会見の冒頭で増田寛也会長(野村総合研究所顧問)は、その石破内閣が今年6月13日に「地方創生2.0基本構想」を閣議決定したことにふれ、「いわゆる地方創生、地域を住みやすい地域にしていくということに大いに関心をもっているので、そういう役割を担っていきたいと(会長を)お引き受けをしました。何よりも戦後日本の高度成長の中では、『東京に人を集める』というのは有力な手段だったと思いますが、その時代を過ぎた上で、今は逆に地方が日常生活に非常に不便を感じるほど衰退してきているという状況なので、ここは大きく国全体としてそういう力が必要だろうと新組織の中で様々な活動を展開し、もう一度地方に輝きを作り出していきたいと思います」と述べました。
統合が自治体に与える影響
それでは民間側で「地方移住」に取り組んできた2つの組織が統合したことは「移住定住行政」に携わる自治体の皆さんの仕事にどんな影響を与えるのでしょうか?
窓口が一本化され、両団体の主な事業が少なくとも今年度は前年度通りに維持されるので、自治体側の仕事には大きな変化はなく、プラス面が多いとみています。記者会見では「今後西日本の活動を強化する」という方針が示されたので、九州などの自治体の皆さんは、今年度の業務をこなしながら来年度以降にアクセルを踏む備えをしておくこともできそうです。
旧ふるさと回帰支援センターの解散に伴って、ここの会員だった市町村が、新組織で議決権を有しなくなったマイナス面がありますが、高橋公理事長はこれについて「移住希望者の受け皿となる全国の自治体の皆様とは従来以上に緊密に地方創生・地方移住に取り組む姿勢は変わらない」(「100万人のふるさと2025年初夏号」)と記し「代替となる新たな意見交換の場の設置を検討している」としています。こういう場を利用して「地方創生の中の地方移住」に理解を深めていくこともできそうです。
参院選の結果、衆参ともに与党が過半数割れし、石破政権の行く末は不透明感が漂いますが、民間側は「ふるさと回帰・移住交流推進機構(JOIN-FURUSATO)」が、「地方創生・地方移住の総合的な対応を行う「日本のセンター」を目指し、公益法人として新たに船出をしました。平成26年に「このままでは896の地方自治体が「消滅」する可能性がある」と提言した日本創成会議で座長を務めた増田寛也氏を会長に迎え自治体側への発信力は高まるはずです。
新組織の今後に注目したいと思います。

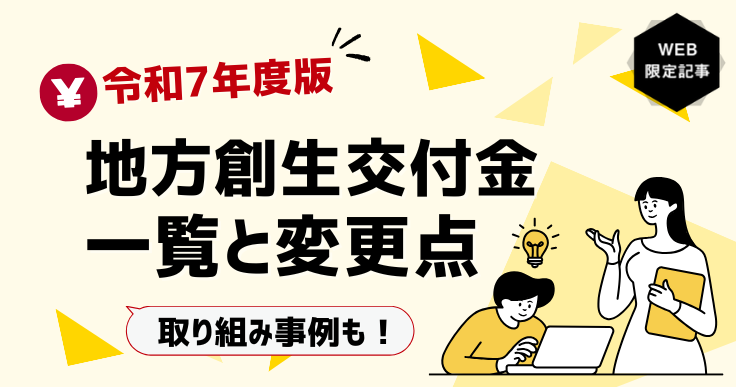

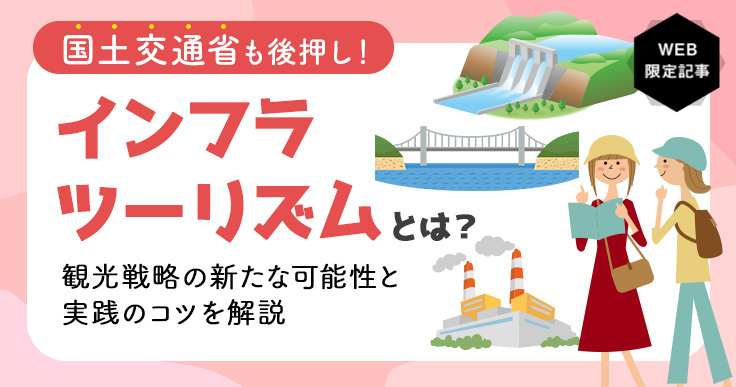
.png)











.jpg)
】バナー広告_株式会社ICHICO_PR.jpg)
.png)







