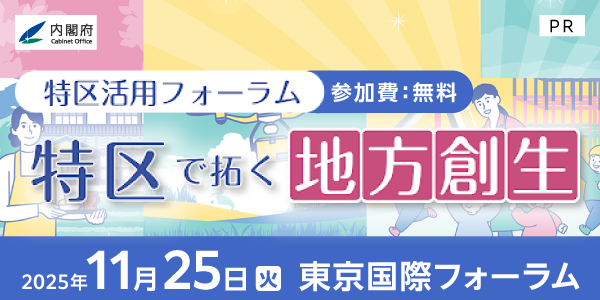インフラツーリズムとは?令和7年モデル地区や成功事例・国交省推進の理由を解説
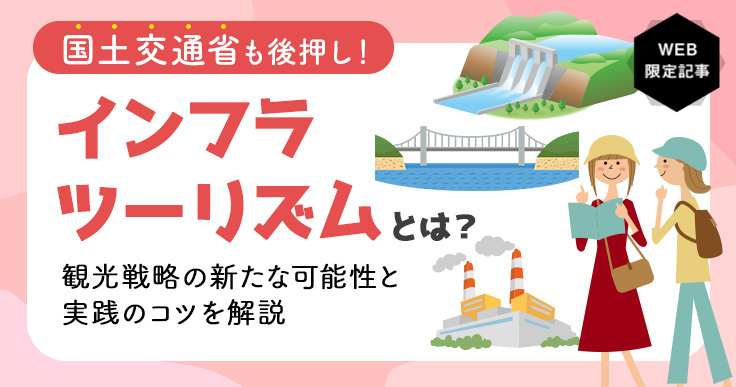
新たな地域振興の手段として、ダムや橋、港湾、発電所などの社会基盤を観光資源として活用する「インフラツーリズム」が全国で注目を集めている。本記事では、自治体がインフラツーリズムを導入する際に期待できる効果や住民・観光客への波及効果、先進自治体の成功事例、導入に向けた具体的なステップを体系的に解説する。
【目次】
• インフラツーリズムとは?国土交通省が推進する理由とその魅力
• 自治体におけるインフラツーリズムのメリットや期待できる効果
• 【令和7年最新版】インフラツーリズムのモデル地区一覧
• 自治体で進むインフラツーリズムの成功事例
• インフラツーリズムの実践で見えてきた課題と導入の流れ
• インフラツーリズムを自治体施策の切り札に!地域の魅力を再発見する一歩を
※掲載情報は公開日時点のものです。
■自治体が成果を上げた多様な成功事例と導入の工夫
■人員・予算・住民理解などの課題を乗り越える実践ステップ
インフラツーリズムとは?国土交通省が推進する理由とその魅力

インフラツーリズムとは、ダムや橋、港湾、発電所、鉄道施設など、産業や生活を支える社会基盤(インフラ)を観光資源として活用する取り組みである。従来の施設見学や広報活動とは異なり、地域ならではの資源として企画化し、観光や教育、防災啓発と結びつける点が特徴だ。
自治体にとっては、既存の社会基盤を新しい観光資源へと転換できるため、追加投資を抑えながら地域ブランド化を進めやすい利点がある。
インフラツーリズムの目的
インフラツーリズムの目的は大きく二つある。一つは、観光や体験を通して、住民や来訪者にインフラの役割や重要性を分かりやすく伝えること。防災教育や社会教育の機会としても有効であり、住民理解を深める効果が期待できる。もう一つは、インフラを観光資源として活かし、交流人口や関係人口を拡大して地域経済を活性化することである。
観光客が魅力を感じるのは「普段立ち入れない構造物を見学できる非日常体験」と「歴史や役割を学べる知的な楽しさ」の融合にある。自治体にとっては、こうした魅力を整理して発信することが、観光戦略や移住促進の基盤にもなる。
国土交通省が推進する背景
国土交通省がインフラツーリズムを推進するのは、社会資本の重要性を広く伝えるとともに、地域振興施策の一環として観光の多様化を支援するためである。近年は自然災害の増加により防災インフラへの関心が高まり、「学び」と「体験」を組み合わせた観光が求められていることも背景にある。
国は平成30年11月以降、ダムや港湾などを対象とした「インフラツーリズム魅力倍増プロジェクト」事業を進め、自治体や観光協会との連携を促してきた。自治体にとっては、国の方針と連動した観光施策を展開することで、補助制度の活用や広域連携の機会を得られるという実務的なメリットもある。
出典:国土交通省「インフラツーリズム魅力倍増プロジェクト始動!~社会実験モデル地区を選定~」
自治体におけるインフラツーリズムのメリットや期待できる効果

インフラツーリズムは観光客を呼び込むだけでなく、自治体にとっても財政健全化、地域経済活性化、住民サービス向上、広報・ブランド戦略といった多方面で効果が期待できる。地域資源の活用と政策的な効果を同時に実現できる点が大きな特徴である。
インフラ施設の有効活用と維持管理コストの最適化
高度経済成長期に整備された多くのインフラは老朽化が進んでおり、2033年(令和15年)には建設から50年以上経過する道路橋が全体の約63%に達すると予測されている。修繕・更新にかかる費用の増加は自治体財政にとって大きな課題だ。
インフラツーリズムは、住民が施設の重要性や維持管理の現状を理解する機会となり、関連予算の確保や合意形成を進めやすくする効果がある。また、有料ツアーや関連グッズ販売による収益を維持管理費に充てられる点も魅力であり、官民連携で魅力的な商品化に成功している事例もある。こうした「施設活用+財源確保」の両立は、自治体にとって重要な成果といえる。
地域経済と官民連携(PPP)の活性化
インフラツーリズムは、観光客が施設を訪れることで宿泊・飲食・買い物に波及効果をもたらし、地域経済の循環を促す。さらに、官民連携(PPP)を通じて観光事業の持続可能性を高めることができる。
施設管理を担う自治体や国が安全管理・場所の提供を行い、旅行会社や地元企業が企画・販売を担う協力体制は理想的である。民間ならではの柔軟な発想が新しい体験型観光を生み出し、インフラに新しい価値を付与することで、地域のビジネスチャンスの拡大にもつながる。
住民サービスと教育機会の向上
インフラツーリズムは外部からの観光効果に加え、住民サービスや教育の面でも効果を発揮する。地域にある施設が観光資源として注目されることは、住民の地域への誇りや愛着を高める。
また、小・中学校の社会科見学や防災教育の教材としても活用され、子どもたちが産業や歴史を学ぶ場となる。特にダムや放水路など治水施設の見学は、防災意識を高める教育効果が大きく、地域全体の防災力向上に寄与する。自治体にとっては、観光と教育、防災施策を一体的に推進できる点が強みである。
自治体の広報・ブランディングの強化
インフラ施設は自治体の象徴となり得る。例えば埼玉県春日部市の首都圏外郭放水路は「地下神殿」という愛称で呼ばれ、国内外のメディアやSNSで拡散され、地域の知名度向上に大きく貢献した。
温泉や城下町といった汎用的な観光資源とは異なり、巨大な社会基盤を活用するインフラツーリズムは独自性が高く、差別化戦略として有効である。SNS時代に適したビジュアル訴求力を持ち、自治体の広報・ブランド形成に直結する資産となる。
 【あわせて読みたい】グリーンインフラとは?
【あわせて読みたい】グリーンインフラとは?
▶防災力と地域力を高める効果や自治体事例を紹介
【令和7年最新版】インフラツーリズムのモデル地区一覧

国土交通省は、ダムや橋、交通拠点などのインフラ施設を観光資源として活用する取り組みを全国に広げるため、平成30年11月に「インフラツーリズム魅力倍増プロジェクト」を立ち上げた。その一環として、地域と連携しながら社会実験を行う「インフラツーリズム モデル地区」を指定し、先進的な事例づくりを進めている。
モデル地区は、観光振興、防災教育、地域ブランディングなど多様な効果を上げており、令和7年現在は全国で10カ所が選定されている。
・八ツ場ダム(群馬県長野原町)
・天ヶ瀬ダム(京都府宇治市)
・来島海峡大橋(愛媛県今治市)
・鶴田ダム(鹿児島県さつま町)
・白鳥大橋(北海道室蘭市)
・日下川新規放水路(高知県南国市)
・首都圏外郭放水路(埼玉県春日部市)
・バスタ新宿(東京都渋谷区)
・温井ダム(広島県安芸太田町)
とりわけ令和6年に新たに追加された「首都圏外郭放水路」「バスタ新宿」「温井ダム」の3カ所は、最新の社会実験が展開されており、今後のインフラツーリズムの方向性を示す重要な事例といえる。次に、それぞれの特徴と自治体にとっての意義を詳しく紹介する。
埼玉県春日部市|首都圏外郭放水路「地下神殿」の観光ブランド化
首都圏外郭放水路は、洪水被害を防ぐ世界最大級の地下放水路で、その巨大な調圧水槽は「地下神殿」と呼ばれ観光資源化が進んでいる。平成30年8月からは東武トップツアーズ株式会社と連携してインフラツーリズムを展開し、令和4年度には54,624人が見学に訪れ過去最高を記録した。
現在は「防災学習コース」や地下河川を歩く「アドベンチャー体験コース」など5つの見学コースを運営しており、年間10万人規模の集客を目標にしている。春日部市にとっては、防災教育と地域振興を両立させる戦略的な取り組みであり、自治体広報や地域経済の活性化にも直結するモデル事例といえる。
出典:関東地方整備局「インフラツーリズム年間見学者5万人超! ~首都圏外郭放水路の実力と今後について~」
東京都渋谷区|バスタ新宿を活用した都市型インフラツーリズム
バスタ新宿は、1日平均約2.8万人が利用する日本最大規模の高速バスターミナルで、首都圏と地方を結ぶ交通の要所である。令和6年に国土交通省の「インフラツーリズム モデル地区」に追加され、都市型インフラを観光資源として活用する先進事例となっている。現在は、施設の構造や運営の裏側を紹介する見学ツアーを展開し、都市交通の仕組みを学べるインフラツーリズムの新たな観光コンテンツを提供。バス会社や観光協会と連携し、ツアー参加者を地方観光へ送客する取り組みも進められている。
自治体目線で見ると、バスタ新宿の事例は「都市型インフラを観光資源化する」という新しい挑戦であり、交通結節点を起点に交流人口を拡大するモデルケースである。都市観光やMICE誘致の可能性を広げるだけでなく、地方との広域連携を促進し、観光振興を首都圏と地方の双方に波及させる効果が期待できる。
出典:国土交通省関東地方整備局「バスタ新宿インフラツーリズム始動 ~バスタ新宿インフラツーリズムの実施に向けて公募を開始~ 」
広島県安芸太田町|温井ダムと地域観光を組み合わせたインフラツーリズム
中国地方最大級のアーチ式ダムである温井ダムは、年間約3万人が訪れる人気観光地で、毎年4月から6月初旬にかけて行われる放流イベントは全国から注目を集めている。令和6年に国土交通省の「インフラツーリズム モデル地区」に新たに指定され、ダム内部の見学ツアーや、通常は立ち入れない湖面でのアクティビティをはじめ、町内の観光資源と連携したプログラムが計画されている。
安芸太田町にとって温井ダムの活用は、自然資源と防災教育を一体的に発信し、観光・教育・防災を融合させることで交流人口の拡大や雇用創出、地域ブランド化につなげる有力な施策である。地域経済と住民サービスの両面で効果を発揮する事例といえる。
出典:安芸太田町役場「『インフラツーリズム魅力倍増プロジェクト』のモデル地区に温井ダムが選定されました」
自治体で進むインフラツーリズムの成功事例

全国の自治体では、インフラ施設を観光資源として活用し、交流人口拡大や地域ブランディングにつなげる取り組みが広がっている。ここでは、自治体が主体的に実施したインフラツーリズムの成功事例を紹介する。
東京都|地下調節池を“光の回廊”に。非日常体験で話題化
東京都は神田川の環状七号線地下調節池を活用し、通常は入れない地下40mの巨大トンネルをLEDでライトアップした見学ツアーを実施した。幻想的な「光の回廊」を進みながら防災施設の役割を学べる内容で、民間事業者と連携し都内観光と組み合わせた8種類のコースを展開している。インフラを単なる見学にとどめず、観光コンテンツと組み合わせて新しい付加価値を生み出している。
自治体目線で見ると、この事例は「防災施設を地域の魅力資源に転換」した好例であり、住民理解を深めながら観光需要を取り込むモデルといえる。インフラツーリズムを企画する自治体にとって、官民連携による発信力強化や、都市観光との相乗効果を示す実践的な成功事例となっている。
大阪府|土木構造物の現場見学と体験型ツアーの両立
大阪府と奈良県の境にある亀の瀬地区は、昭和7年の大規模地すべりで鉄道トンネルが崩壊した歴史をもつ。現在は、その対策として整備された排水トンネルや、平成20年に発見された「旧大阪鉄道・亀の瀬トンネル遺構」を見学できるインフラツーリズムを展開している。
防災施設と歴史遺構を同時に体験できるストーリー性が評価され、令和5年には来訪者数が2万人を突破。自治体にとっては、災害の負の遺産を「防災学習」と「観光資源」の両面で活用した成功事例といえる。
福島県|ダム・橋・電車体験を組み合わせた複合ツーリズム
福島県は、ダム・橋・鉄道施設など複数のインフラを既存観光地と組み合わせ、広域を巡るインフラツーリズムを展開している。県主導の推進協議会には市町村や観光協会、交通事業者が参加し、令和7年8月時点で58のインフラ施設を案内対象としている。モデルコースでは、ダム内部への潜入体験に加え、果物狩りや温泉など地域資源も盛り込み、2泊3日で福島の魅力を満喫できるよう設計されている。
特に桜水車両基地での鉄道体験は人気が高く、普段は非公開の車両内部の見学や線路走行の運転体験が可能で、鉄道ファンや家族連れから高い評価を得ている。自治体目線で見ると、複数のインフラと観光資源を一体化させることで滞在型観光を実現し、「ここで泊まって体験したい」と思わせる地域振興につながる好事例である。
愛媛県西条市|ダム見学を核に地域経済と防災意識を育てる
愛媛県西条市では、石鎚山系の黒瀬ダムをはじめとする水関連インフラを観光資源化し、インフラツーリズムを推進している。特に「ダムカード」は、現地に行かなければ入手できない限定性が人気を集め、ダム巡りの動機づけとなってリピーターを生んでいる。
市観光協会や民間企業も積極的に関わり、「うちぬき」と呼ばれる湧水群を巡るガイドツアーや、ダム・下水処理場を組み込んだ団体ツアーを企画。行政・観光協会・民間の三者連携によって地域経済への波及効果を高めると同時に、住民の防災意識向上にもつなげている。自治体にとっては、自然資源と水インフラを組み合わせた観光振興の好例である。
北海道美瑛町|観光庁補助を活用し、採石場跡や堰堤をジオ・インフラツーリズムに転換
北海道美瑛町は、日本で初めて「インフラ」と「ジオ(大地)」を組み合わせたインフラ・ジオツーリズムを打ち出した。代表的なプログラムは、有名観光地「白金青い池」を題材に「青く見える池の水は本当に青いのか?」をテーマにしたツアーで、水の成分や堰堤の仕組みを専門ガイドが解説しながら巡る。
この取り組みは、観光庁の地域観光魅力向上事業の補助金を活用し、国・美瑛町・周辺自治体・ジオパーク協議会・観光協会が一体で企画した「共創」モデルが特徴だ。採石場跡や堰堤を舞台に、半日1人1万円という高価格の体験型ツアーを開発し、観光地としてのブランド強化と地域経済効果を同時に実現している。自治体にとっては、補助制度を活かしながら新しい観光形態を生み出すモデル事例といえる。
.jpg) 【あわせて読みたい】エコツーリズムとは?
【あわせて読みたい】エコツーリズムとは?
▶エコツーリズムは自然環境と人間活動を両立する新しい観光の形!
インフラツーリズムの実践で見えてきた課題と導入の流れ

インフラツーリズムは全国で広がりを見せているものの、まだ認知度は十分ではなく、来訪者が一部の有名施設に集中する傾向がある。全国の自治体が効果的に推進していくためには、現場で直面する課題を整理し、解決策を共有することが欠かせない。
自治体が直面しやすい課題
インフラツーリズムを推進する際、多くの自治体が以下の課題に直面する。
・人員や体制:新たな業務が増え、職員の負担が大きい
・安全管理:インフラ施設特有のリスク対策が必要
・地域連携:施設見学だけでは経済効果が限定的になりやすい
・持続性:単発イベントに終わる可能性がある
・住民との関係:観光客増加による生活環境への影響
これらを克服するには、官民連携による役割分担、地域一体での周遊ルート開発、有料化による自立採算モデルの構築、住民理解を得るための対話など、多角的な対策が求められる。自治体にとっては、観光・防災・教育を横断する総合的なまちづくりの一環として位置づけることが重要である。
インフラツーリズムの導入ステップと活用できる補助金の例
インフラツーリズムを成功させるには、段階的に進める計画性が欠かせない。
1. 資源の発掘:地域にあるダム・橋・港湾などを観光資源として洗い出す
2. 連携体制の構築:自治体・観光協会・民間事業者が協働できる仕組みを整える
3. ツアー企画と受け入れ環境整備:見学内容の設計、駐車場・トイレ・案内表示の整備
4. 情報発信:SNSや自治体サイトで魅力を発信し、誘客につなげる
5. 改善の継続:運営開始後はPDCAサイクルで改善を重ねる
6. 住民との関係:観光客増加による生活環境への影響
これらの取り組みを支援するため、観光庁や内閣府は地域創生に関する補助金・交付金を用意している。
例えば、地方創生推進交付金(現:新しい地方経済・生活環境創生交付金/第2世代交付金)は、インフラ整備と地域独自の観光・交流施策を一体で進める事業に活用可能である。補助制度を上手に組み合わせることで、財源確保と持続的な事業展開の両立が期待できる。
出典:地方創生 内閣府 地方創生推進事務局「第2世代交付金の概要」
インフラツーリズムを自治体施策の切り札に!地域の魅力を再発見する一歩を
インフラツーリズムは、自治体が持つインフラ資産を見つめ直し、新たな価値を創出する地域振興策のひとつである。成功のポイントは、他地域の事例をそのまま模倣するのではなく、その土地ならではの施設や歴史を活かし、官民が連携して持続可能な仕組みを築くことにある。
地域に眠るインフラの魅力を観光や教育、防災と結びつけて発信することは、交流人口の拡大や地域経済の活性化、住民の誇りの醸成にも直結する。今こそ、自治体が主体となって足元の資源を再発見し、インフラツーリズムをまちづくりの切り札として活用することが求められている。
.jpg) 【あわせて読みたい】ナイトタイムエコノミーとは?
【あわせて読みたい】ナイトタイムエコノミーとは?
▶夜の時間帯も楽しめるまちをつくろう!実際の事例も詳しく解説






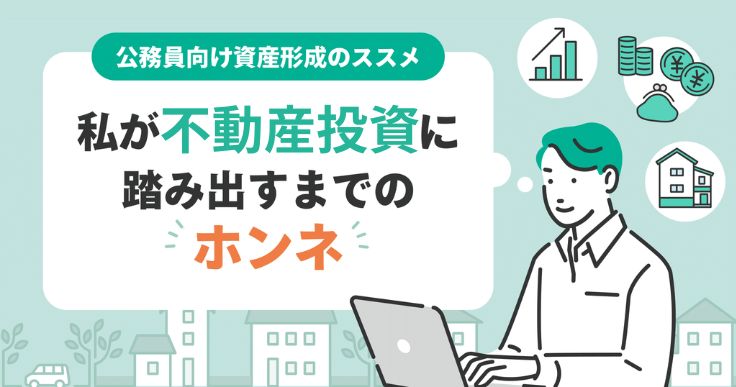
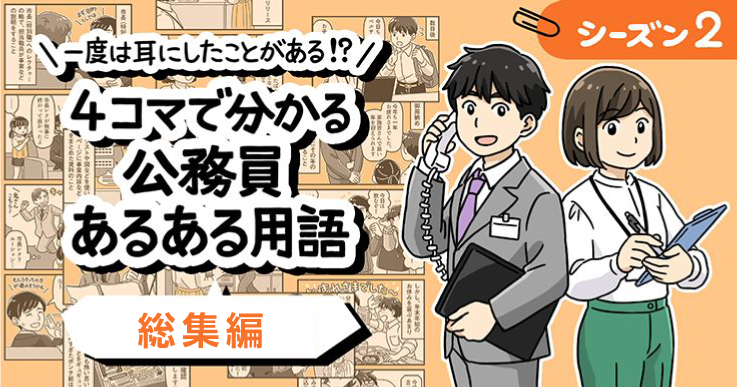







】バナー広告_株式会社ICHICO_PR.jpg)