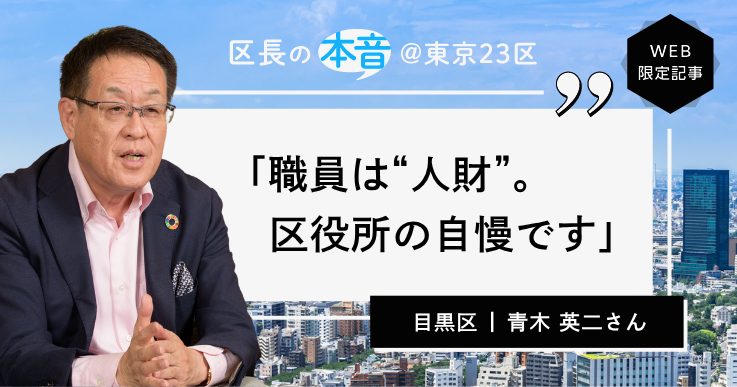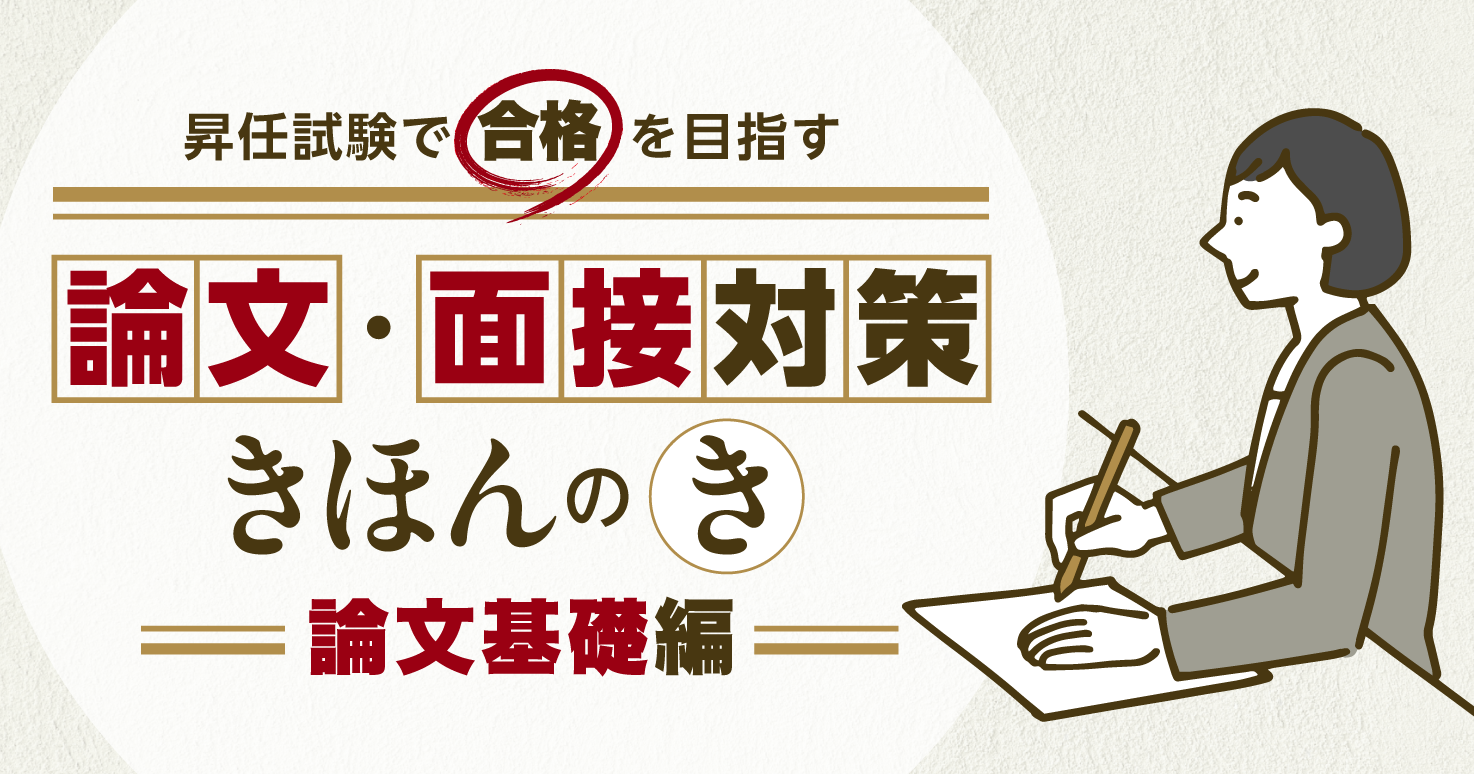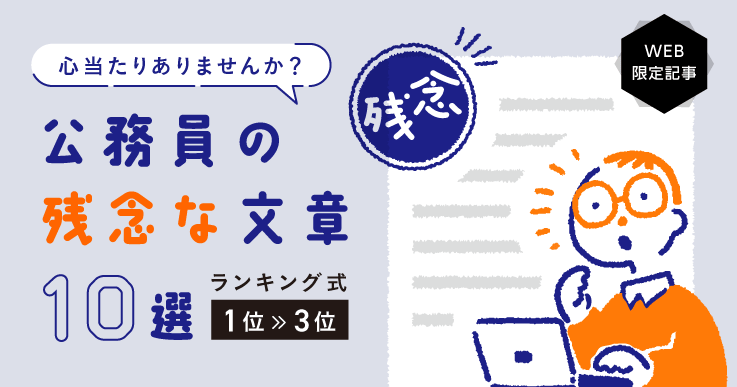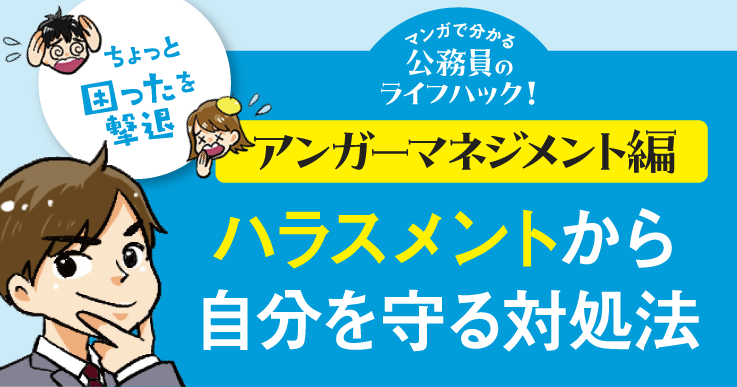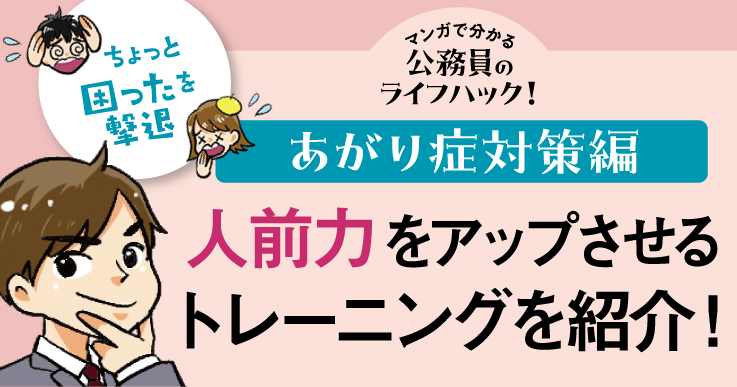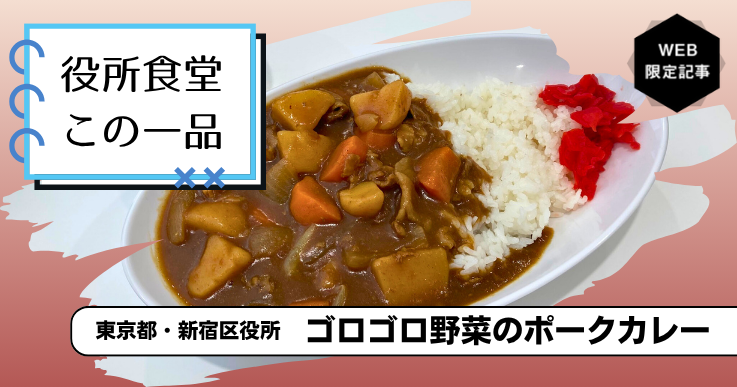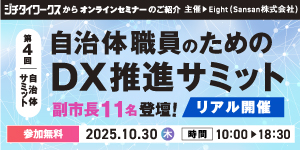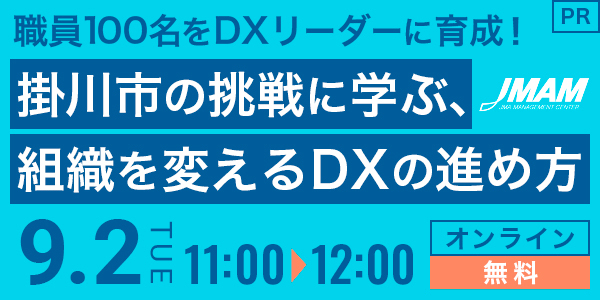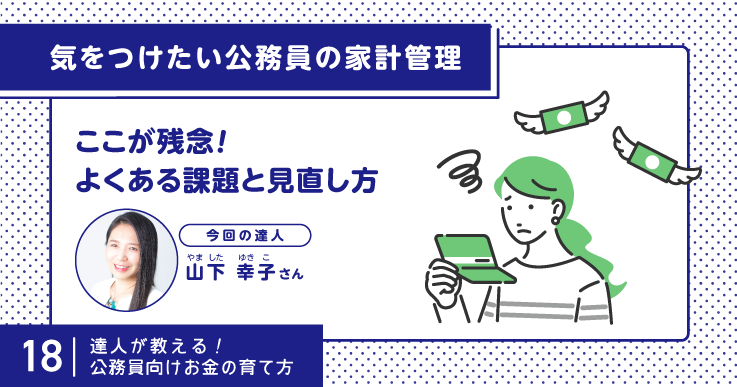
安定した収入と手厚い福利厚生が魅力といわれる公務員だが、その安定性ゆえに家計管理が後手にまわり、いざという時に備えが足りなくなるケースも少なくないという。物価高やインフレ時代に対応するために必要な家計の見直し術を、ファイナンシャルプランナーの山下 幸子さんが事例を通じて詳しく解説する。
※本記事は、資産形成に対する理解を深めるための情報提供を目的としており、いかなる投資の推奨・勧誘を行うものではありません。
 解説するのはこの方
解説するのはこの方
山下 幸子(やました ゆきこ)さん
山下FP企画 代表
ファイナンシャルプランナー CFP®
約20年間にわたり、2,000世帯以上のお金の相談に向き合い、お客さまのライフプランをもとに、マネープランのアドバイスと実行支援(家計・保険・投資・不動産・相続)をワンストップでトータルサポートしている。

ピンチに陥りやすい家計の共通点とは?
1. ボーナス頼みの家計運営
これまでに私が実際に受けた相談では、 公務員家庭において、物価高やインフレの影響で毎月の家計が赤字になっても、「不足分はボーナスで補えばいい」という考えが根強い印象がありました。そのため、月々の収入だけでやりくりしようという危機感が薄い傾向が見られます。
民間企業では業績次第でボーナスがカットされることも珍しくありませんが、公務員はその影響を受けにくいのが現状です。その結果、「毎月の赤字を決まって支給されるボーナスで補てんする」という生活習慣が定着しやすくなり、黒字家計を実現し、貯蓄や投資にまわせる余裕を生むのが難しくなります。
生活費はなんとかまわっているものの、実際には年齢に見合った資産が十分に蓄えられていないケースが多く見られます。そして、子どもの進学や退職といったライフイベントが訪れる頃、「お金が足りない!」と慌てることになるのです。
2. 保険の過剰加入
公務員が加入する共済組合では、多種多様な保険が用意され、保障が充実しています。
ケガや病気に対応するものだけでなく、三大疾病、介護、障害、死亡時の保障、さらに将来への備えとしての年金保険などがあり、自分だけでなく家族も加入できる場合があります。
これらの保険は毎年更新型で、一つひとつの保険料は割安です。しかし、“あれもこれも”と複数の保険に加入すると、月々の保険料がかなりの負担となるケースもあります。
特に、リスク回避を意識するあまり、本当に必要な保障以上に保険を契約してしまうことが少なくありません。
公務員は福利厚生も充実しており、例えば現職中に重い病気にかかり、月額100万円の高額療養費が必要になったとしても、自己負担額は2万5,000円(上位所得者※でも5万円)程度で済みます。 この差額は共済組合が負担します。
また、この保障は家族にも適用されるため、現職中であれば自由診療以外のケースでは、手厚い医療保険に加入する必要性はありません。
※標準報酬月額53万円以上の組合員のこと
3. 家計管理が「守り一辺倒」
公務員の家計管理は、リスクを避けることを重視するあまり、貯金一辺倒になりがちな印象です。財形貯蓄や銀行預金よりも利率が高い共済預金に、上限いっぱいまで預けている人も少なくないようです。
「ムダ遣いをせずコツコツ貯金を増やしている」「積立共済だけでなく個人年金も活用している」「小銭を貯金箱にチリツモ貯金をしている」「外食を控え、弁当持参でお小遣いは月1万円」「ポイ活で貯めたポイントでお菓子を購入している」といったように、ぜいたくを控え堅実に預金を増やす努力をされています。
しかし、厚生労働省が令和6年に公表した「財政検証結果」によると、現役世代の手取り収入に対する年金の給付水準(所得代替率)は、中長期的に実質経済成長率がほぼ横ばいの場合、33年後には、約2割減少すると見込まれています。
さらに、インフレや円安の影響で生活費が増加し、円預金の実質的な価値が目減りするリスクも懸念されています。
一見手堅いこの「守り」の家計管理ですが、貯金残高に満足するあまり、資産運用の機会を逃してしまうことがあります。その結果、インフレや円安といった経済変動に対応できず、資産が減少していく可能性があります。
老後に向けて堅実に貯蓄に励んできたにもかかわらず、物価高やインフレの影響を受け、将来的に厳しい家計状況に直面するリスクを抱えることになりかねません。

ライフプラン別 家計の見直し
ここからは、ケース別に具体的な改善策をご紹介します。
- 独身男性Aさんの場合 -
 家族構成と現状:
家族構成と現状:
公務員のAさん(32歳・一人暮らし)は1年後に結婚する予定で、結婚式や新居について具体的な相談を進めていました。しかし、Aさんの貯金額が100万円しかないことに気づいた婚約者は激怒。このままでは結婚式や新婚旅行、夢のマイホームが遠のいてしまいます。一見、真面目に働き、派手な生活とは縁遠いAさんですが、その家計を詳しく調べてみると驚きの事実が浮かび上がりました。
Aさんの月々の収支は以下の通りです。
収入:手取り25万円/月 (ボーナス含む)
支出:25万円/月
 [内訳]
[内訳]
家賃:4.5万円 ※住宅手当を除く
食費:4万円
水・光熱費・通信費:3万円
車関連費(ガソリン・保険・駐車場代):2万円
課金ゲーム・フィギュア購入など:平均5万円
その他生活費:4万円
奨学金返済:2.5万円
収支:0 貯金総額:100万円
残念家計の原因
課金ゲームとフィギュア収集
派手な暮らしをしていなくても、一つの趣味に没頭し過ぎると、支出額を自覚しにくいことがあります。Aさんの婚約者は彼のことを「倹約タイプ」だと思い込んでいましたが、実際には趣味の「ゲーム」に課金し、レアなフィギュアを見つけるとつい購入してしまう状況でした。その結果、赤字の月はボーナスで補てんしていたものの、趣味にかかる費用が月に5万円にも達していることが判明しました。
▼
▼
▼
具体的な改善策
・趣味にも予算を設定
・所有しているフィギュアを売却して現金化
課金ゲームについては、月の課金額を5,000円以内に抑えるようにし、家計の浪費の穴をふさぎます。フィギュアの購入もやめたので年間で約50万円貯蓄可能に。
また、所有しているフィギュアを売却して現金化し、結婚準備資金に充当。
一人暮らしが長くなると、自覚症状なく趣味や好きなことにお金をかけすぎてしまい、貯蓄が不足しがちな「残念家計」に陥ることがあります。
公務員の安定収入を活かし、長期的なマネープランを構築することで、夢のマイホームや安定した家庭生活が実現可能なのですから、今後は、二人で話し合いながらお金の優先順位を決め支出のコントロールをしていくといいでしょう。
家計簿を付けるとなると一気にハードルが上がります。Aさんの場合はほかの支出は問題ありませんので、課金ゲーム代のみ管理すれば大丈夫です。
- 公務員共働き夫婦Bさんの場合 -
 家族構成と現状:
家族構成と現状:
Bさんご夫婦は公務員で、夫36歳、妻31歳、子ども2人(3歳・1歳)の4人家族です。現在上のお子さんが小学校に入学するまでにマイホーム購入を目指していますが、思うように自己資金が貯まらないことに焦りを感じています。
Bさんの月々の収支は以下の通りです:
収入: 手取り55万円/月(ボーナス含む)
支出: 45万円/月
 [内訳]
[内訳]
・家賃:8万円 ※住宅手当を除く
・食費:8万円
・水道光熱費・通信費:3万円
・車関連費(ガソリン・保険・駐車場代):3万円
・保育関連費:4万円
・その他生活費:3万円
・共済保険:4万円
・学資保険:6万円
・NISA(つみたて投資枠):4万円
・iDeCo:2万円
収支:10万円 貯金総額:700万円(独身時代の貯蓄も含む)
残念家計の原因
家計を診断した結果、Bさん家計の課題は、保険と投資の配分が過剰であるため、流動性資金(現金)が不足し、マイホーム購入資金の準備が進みにくい状況になっています。特に、学資保険は子どもが大学進学のために心配になって加入したものですが、元本割れでした。
▼
▼
▼
具体的な改善策
1.保険の見直し
共済保険を月4万円→月1.2万円に。
ご夫婦が共働きであるため、どちらかが万が一の場合でも収入源が完全に途絶えることはありません。そのため、遺族年金で補えない不足分のみ死亡保障を確保します。
また、医療保障の過剰なオプションを外し、合理的な内容にすることで、月額2.8万円程度の削減が可能になります。
さらに、学資保険を月6万円を解約。
毎月6万円の学資保険は家計を圧迫しています。学資保険には子どもの死亡保障や医療保障が含まれ、元本割れのリスクがある上、インフレ対策も不十分のため解約します。
その分を住宅購入資金に振り替えます。子どもの教育費は、既存のNISAと預金の2本立てで準備します。
2.投資の配分調整
NISAは継続しますが、家計からの拠出額を月4万円から2万円に減額し、不足分の2万円は児童手当を活用して補います。iDeCo(月2万円)は節税効果が比較的高く、将来の年金補完に有効であるため、現状通り継続します。
3.マイホーム購入計画の見直し
目標:4年以内に1,000万円の頭金を準備 。
毎月の収支で余剰の10万円が発生していますが、保険料や学資保険にまわっているため現金貯蓄が進んでいません。 以下の改善を実施することで、年間約260万円の貯蓄が可能となります。
▪保険見直しと学資保険解約で月8.8万円の余裕資金を確保
▪NISA毎月4万円を積み立てのうち2万円は児童手当から充当
▪家計生活費のうち1万円を節約
これにより、上のお子さんが小学校に上がるまでに約1,000万円の自己資金を用意でき、マイホームの夢がかなえられそうです。
漠然とした将来不安やお子さまの教育費の準備を焦るあまり頑張ってお金を貯めているつもりでも、貯める道具があっていないと残念家計に陥ります。特に円資産に長期にわたり積み立てしていく場合はインフレで目減りしていないか?注意しないといけません。
次回は、ずぼらでも続けられる!簡単家計簿の付け方についてお話しします。