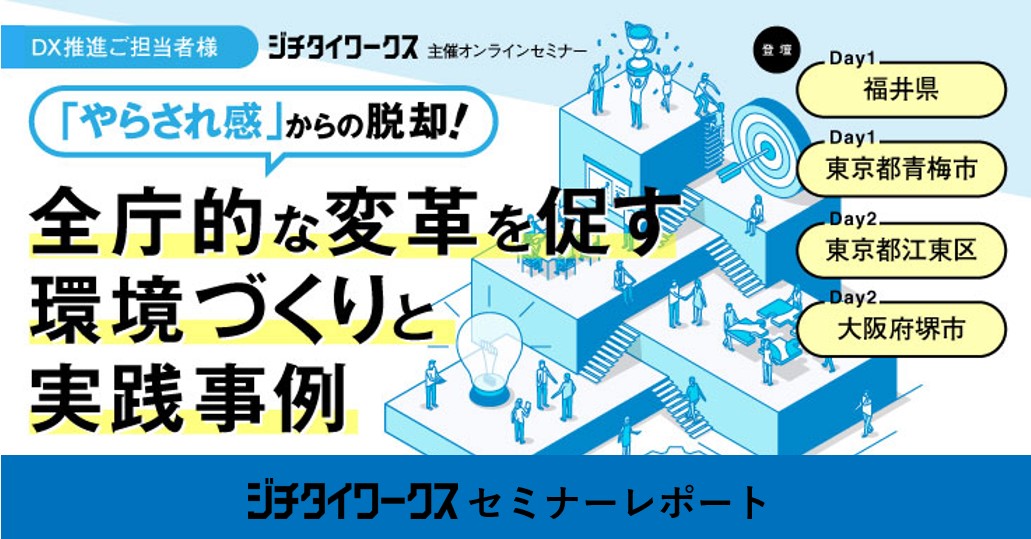
自治体DXという言葉が叫ばれる昨今。順調に取り組みを進めている自治体と、「なかなか庁内に浸透しない」と悩む自治体との差が顕在化しはじています。推進の妨げとなる理由には様々なものがありますが、その1つが職員の自発的な行動です。
本セミナーでは、職員がDXを自分事として捉えられるよう工夫を凝らし、挑戦を続けている自治体の事例を紹介。それを支えるソリューションを提供する事業者の情報共有もまじえ、自治体DXを支える人材育成と環境づくりの実践事例をお伝えしました。
概要
■タイトル:「やらされ感」からの脱却! 全庁的な変革を促す環境づくりと実践事例【DAY1】
■実施日:2025年5月29日(木)
■参加対象:自治体職員
■開催形式:オンライン(Zoom)
■申込者数:219人
■プログラム:
第1部:【福井県】自律的なDX推進へ向けて~意識改革に向けた福井県の取り組み紹介~
第2部:自治体DX推進に伴う人材育成のススメ方~マニュアルで教育・育成の仕組みを構築~
第3部:【青梅市】「変える職員を創る!」青梅市の人材育成とBPR
第4部:なぜ、その教育DXは失敗するのか?教育の負担・属人化を断ち切る、人財育成改革の進め方
第5部:ノーコードで自分で作れる地図システム「カンタンマップ」
自律的なDX推進へ向けて~意識改革に向けた福井県の取り組み紹介~
福井県では、DXの成功に向けて「ビジョンの徹底」と「成功体験の積み重ね」を実践。職員の意識統一を図りつつ庁内一丸となった動きを進めている。第1部では同県の現場を先導するDX推進監が、具体的な取り組み内容について共有した。
[講師]
写真.jpg) 前側 文仁 氏
前側 文仁 氏
福井県 未来創造部 DX推進監
マインドシフトに向けて実践した2つの施策。
福井県におけるDXの特徴は、全職員が自律的に業務変革を推進する、ということに尽きます。知事自らが積極的にデジタルを活用するトップダウンの取り組み、各所属のDXリーダーによる業務改革支援、気運醸成に向けたセミナーなどで、行動できる環境づくりに取り組んでいるのです。こうした当県のDXについてお伝えしました。
-1_P13.jpg)
IPAが公表している、DX推進人材の育成に関する課題に関するデータがありますが、1位は「スキル向上・獲得へのマインドシフト」。つまり自律的に行動するように意識変革させることです。意識改革の必要性は認識されている。ただ、何から始めたらいいのか分からないと感じている、ということだと思います。そうした中、当県では何をやったのかというと、「ビジョンの徹底」と「成功体験の積み重ね」です。
-1_P14.jpg)
まず、ビジョンの徹底について。こちらは大別すると「ビジョン・戦略の徹底」、「組織・体制整備」、「人材育成体系の整備」、「気運醸成の制度設計」の4つとなります。この内容に沿って、特徴的な取り組みをいくつか紹介します。
約5年前、デジタルツールを活用した服務規律、「Life Style Shift 共通ルール」を整備しました。若手職員による有志チームがまとめたもので、会議資料をTeamsで事前共有する、出先機関とのミーティングは原則オンライン会議など、今では当たり前のことを根付かせていこう、ライフスタイルをシフトしていこうというものです。このような活動で変革のビジョンが周知徹底されていきました。
-1_P17.jpg)
次に、組織・体制の整備。DX推進監に外部人材を登用し、DX推進本部も設立しました。DX推進本部は知事をトップとし、各部局長などで構成されています。この本部がトップダウンで推進すると同時に、ボトムアップで進めるDXリーダー制度も整備しています。各現場で業務を熟知したDXリーダーが自律的、かつ積極的に取り組むことが重要なので、そのための目標設定や伴走支援などを積極的に実施しています。
また、人材育成については、デジタル人材育成方針を人事課と共に策定し、職位に応じた役割と要件を定義。スキルマップと研修を紐付けました。
ちなみに、研修コンテンツはDX推進監などによる内製です。当県に合った分かりやすい内容で作成しています。さらに、実業務を題材としたノーコードなどのツール研修もハンズオン研修として体系化しています。
-1_P20.jpg)
そして、気運醸成に向けた制度としては、勤務時間の20%を自分の担当業務外に充てられる“ふくい式20%ルール”、若手職員がテーマを設定し、知事へのプレゼンを経て優れた政策は事業化する“チャレンジ政策提案”、年度途中でも部局長判断により事業検証が可能な“政策トライアル枠予算”、優れた行動を表彰しモチベーションを高める“クレドアワード”などを実施し、職員の自主的な行動を促しています。
成功体験をもとに3万時間の削減効果を創出。
次に、成功体験の積み重ねを作り出す取り組みを紹介します。
M365などのデジタルツールが日常的になってくると、使いこなせる職員と、そうでない職員の二極化が発生します。これを回避するため、気軽に相談できるコミュニティをTeams上に設置しました。
当初はDX担当が回答していたのですが、現在は気づいた職員が回答したり、複数の職員で議論しながら解決策を模索したりと、自律的なものになってきています。同時に、職員が作成したツールやプログラムを公開する場もあり、横展開しやすい状況です。
-1_P25.jpg)
また、悩んだ際の支援を行う外部専門人材をDX推進アドバイザーとして配置しています。現在はデータサイエンス、業務改善、意識改革などの専門知識を有するアドバイザーが7名体制でサポートしており、職員は自信を持ってDXを推進できる環境です。
研修についても様々なものを実施していますが、中でも特徴的なものが“ブートキャンプ”です。RPAやノーコードツールを用い、参加者が業務課題を持ち込んで、解決するツールが完成するまで帰れないという内容。これによりデジタルの便利さを知り、難しくないと感じてもらえるよう取り組んでいます。こうした研修を多数開催することで、100を超えるアプリが内製化され、年間3万時間以上の削減効果を創出。さらに業務改善による結果を可視化することで、職員のモチベーションアップにもつなげています。
-1_P29.jpg)
DXを自律的に進めていくためには、内部的な動機づけが重要です。そのために、特にマネジメント側の職員は“監督”のようにふるまうのではなく、皆と一緒に取り組む現場の“キャプテン”のような存在になることが大切だと思います。
DXを自治体の文化にしていくには、まだまだ時間がかかるでしょう。しかし大事なことは、立ち止まらずに、ワクワクしながら全庁一丸となって、小さなことからでもいいので取り組みを進めることだと思います。当県の挑戦が少しでも参考になれば幸いです。
自治体DX推進に伴う人材育成のススメ方~マニュアルで教育・育成の仕組みを構築~
第2部は、人材育成がテーマ。DX推進を阻む人材不足の課題に対し、マニュアル活用という切り口で自治体をサポートする企業の担当者が、人材育成を成功させるためのステップと、ソリューション活用術について解説しました。
[講師]
株式会社スタディスト
事業本部 アライアンス営業部 パートナー推進グループ
DX推進では“何を実現したいか”がカギになる。
当社は、BtoBのクラウドサービスであるマニュアル作成共有システム「Teachme Biz」の開発・提供をはじめ、各種コンサルティングサービスを展開している企業です。ここでは「マニュアルを活用した人材育成」についてお伝えします。
昨今DXの気運が高まっていますが、その大きな理由の一つが人材不足という課題。自治体においても、既存人員の効果を最大化させることが求められています。
-2_P05.jpg)
しかし、多くの組織でDXが思うように進んでいないのが現状です。よく聞く悩みは、「何をすればいいのか」「既存システムの動きが把握できていない」「ツールを入れたが全く使われない」といったものです。そこで、限られたリソースの中でより効果的なDX推進、人材育成を進める方法について紹介します。-2_P07.jpg)
まず、DX推進の重要なポイントについて。皆さんが実現したいことをシンプルにまとめると、“業務改善とIT化”だと思います。従って、DXの推進も一般的な業務改善と同じように進めるのが効果的です。
最初に、各部門における業務課題などを洗い出し、アナログになっていないか、非効率な部分はないか、といった観点で現状整理と把握を行います。整理と把握ができたら、課題の優先度を検討し、「何を実現したいのか」という目的を定めます。
次は課題を解決する手段の検討です。現状の業務フロー改善でいいのか、ツールを導入した方が効果的なのか、と目的に合わせて考えるのですが、注意点があります。この段階で安易にツール導入を決定することは避けた方がいい、ということです。ツール導入が本当に適切なのか見極める必要があります。
-2_P14.jpg)
課題解決の手段が固まったら、新しい業務フローや手順を標準化して、庁内に浸透させていきます。継続して改善できる体制を整えておくことも重要。導入したツールをしっかり活用して、生産性の高い仕組みを作っていきます。
また、ツールの導入時は現場に負担が発生します。それが原因で活用が進まないとか、業務効率が逆に悪化することも考えられます。このような状態にしないためにもマニュアルの整備が効果的です。手順を正しく伝え、正しく実行できる情報伝達を行うことで導入効果を生み、浸透・定着の促進につながっていくのです。
充実したマニュアルの作成は、引き継ぎや人材育成にも貢献する。
次は、マニュアルを活用した人材育成の進め方について。
作成したマニュアルを効果的に活用するために、下記ステップで人材育成の仕組みを構築していきます。
-2_P22.jpg)
最初に、現状把握を行い、可視化していきます。ポイントは、業務ごとにマニュアルを作成すること。作業工程をそのまま記載してもOKです。
続いて、マニュアル作成文化を醸成するために、マニュアル作成会を各課・各係で実施します。若手が作成することによって、人材育成にもつながるでしょう。
そして、作成したマニュアルの活用をスタート。現場からのフィードバックをもとにマニュアルをブラッシュアップし、業務標準化を図っていきます。この標準化されたマニュアルを活用していくことで、異動に伴う引き継ぎや、技術の伝承にもつながっていきます。
-2_P28.jpg)
上図は、ある製造業者の事例です。新人研修の一環として、学んだ内容をマニュアルにアウトプットすることで、社内コミュニケーションが活性化。さらに次年度以降は、新人向けにそのマニュアルを活用できる。こうした取り組みがありました。これは自治体においても同様の効果が期待できると思います。
とはいえ、マニュアル化について悩みを持っている方は非常に多いのが現状です。「作ったものの使われない」「読んでも意味が分からない」「そもそもマニュアルがどこにあるのか分からないので人に聞く」といったものです。これだと、作っても意味がありません。マニュアル活用には、作成、浸透、改善という3つの壁があるのです。
この「作成・浸透・改善」という3つの壁を乗り越える上で有効なのが、誰にでも分かりやすい標準作業手順書です。その作成と共有を支援するのが、当社が提供しているマニュアル作成共有システム「Teachme for Public」です。ビジュアルで分かりやすく表現でき、更新も共有も簡単で、パソコンはもちろんタブレットやスマホからも利用可能なマルチデバイス対応となっています。LGWANにも対応しており、普段使っている業務端末から利用可能です。
-2_P33.jpg)
特徴は作成の手軽さで、画像や説明文を入れて、その画像に矢印やテキストなどを付けたら完成します。さらに、作ったマニュアルを活用するための機能も豊富で、作成マニュアルをタスク配信することで閲覧実施の確認ができ、二次元コードを使うことでマニュアルをダイレクトに見ることが可能。操作ログを使った分析もできます。
現在、導入自治体として公開しているのが石狩市、東京都港区、奈良市、三原市などで、三原市についてはデジ田交付金を活用して導入されています。こうしたサービスを展開しつつ、当社は自治体DXに貢献します。詳細についてはお問い合わせください。
「変える職員を創る!」青梅市の人材育成とBPR
DXの推進方針を定め、取り組みを始めたものの、スタート時はうまくいかなかったという青梅市。突破口となったのはBPRや民間との連携など、様々な角度からのアプローチだった。同市の担当職員がこれまでの歩みを振り返りつつ、直面した課題と克服の工夫を語った。
[講師]
 大塚 瑞樹 氏
大塚 瑞樹 氏
青梅市 企画部 DX推進課
職員をスタートラインに立たせるための意識改革。
このパートでは、当市が進めてきたDX人材の育成とBPRの取り組み、また民間企業と連携した人材育成について説明します。まずは、DX人材の育成に関する取り組みです。
国が令和2年12月に自治体デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進計画を策定したことを受け、当市では令和4年度からDXの取り組みに本格着手しました。大まかな流れは下図の通りです。
-3_P03.jpg)
令和4年度に、DXの推進方針である「スマートローカル青梅」を策定したものの、庁内におけるDXのイメージは芳しくありませんでした。それまでDXについて学ぶ機会がなかったので仕方ないのですが、当初は意識の低さに愕然としました。
この状態では進まないという危機感のもと、まずは全職員の意識を変えることが必須だと結論し、準備に着手しました。
-3_P05.jpg)
マインドセット研修の実施を決め、最初のターゲットは取り組みに影響力を持つ幹部職員に決定。市長、副市長、教育長も参加いただくこととしました。研修は外部委託しましたが、講師の力もあり、幹部職員の意識が変わり始めたのです。
次にターゲットにしたのが、各現場を動かす係長職です。しかし研修を進めるうちに、中堅職員にも同じマインドが必要だと気づき、主任職を対象とした研修も追加実施。ワークショップ形式で、意見交換もしながら進めています。初年度に実施した研修は、以下の通りです。
-3_P08.jpg)
こうした取り組みと同時に設けた制度が“DX推進員制度”です。DX推進を図るため、部局横断で中心的役割を担うDX推進員を各課に1名ずつ配置。もちろん推進員を任命しても、知識がなければどうにもなりません。そこで、様々な研修を矢継ぎ早に実施しました。ほぼ毎月のペースだったので推進員にも各職場にも負担をかけましたが、推進員のリテラシーは短期間で大きく向上しました。
また、推進員の活動には、上司のリーダーシップと同僚の協力が不可欠です。そこで、係長職とDX推進員の双方を一体的に活用しようと考えました。係長職には追加で各種研修を集中的に受講してもらい、短期間でDXの中心的役割を担う人材として育成しました。
-3_P12.jpg)
こうした協力体制のもと、他の職員を巻きこみながら職場全体でDXを推進することが可能に。推進員を設置して3年、以前よりも自発的にDXに取り組む課が増えました。同時に、業務に課題意識を持ち、自ら考え変革していこうと考える職員が明らかに増えてきていることを実感しています。
全庁に展開したBPRからアワード受賞の取り組みもあらわれる。
次に、当市のBPRの取り組みについて説明します。
近い将来、必ず訪れる2040年問題。当市にも危機感はありましたが、何から手を付けたら良いのか分からない状態でした。まずは現状を知るため、全課を対象に業務量調査を実施。その結果、正規職員がノンコア業務に51%もの時間を費やしていることが判明したのです。
-3_P16.jpg)
そこで、業務量調査の結果を市長以下幹部職員に共有した上で、全課に対し、半強制的にBPRを推進しようと指示しました。はじめに取り組んだのが「1課1業務改善運動」です。1つの課で、1業務だけでいいので改善しようというものでしたが、現場は大いに混乱しました。それでもなんとか進めていった結果、2カ月という短期間で3,500時間余の作業時間を削減できたのです。
しかし喜んでいる場合ではありません。この成功体験をステップに、次の策として「全庁BPR推進キャンペーン」を実施。下記の通りの好結果が出ました。
-3_P18.jpg)
これらの取り組みを通じ、少しずつBPRに対する意識が変わってきました。中にはすごい取り組みも出てきます。窓口職場で導入した「書かない窓口」の取り組みは、早い時期に導入したことから注目を集め、東京都で実施している「Tokyo区市町村DXaward」では「DXスプリント賞」を受賞。関係職員一同大いに喜びました。
このアワードを徹底的にパクり(TTP)、「シン・オウメDX(業務改善)award」と題した庁内イベントを令和6年4月に開催。大いに盛り上がりました。今後も、受賞を目標に業務改善の勢いが増すことを願いつつ、続けたいと考えています。
-3_P20.jpg)
当市では他にも、民間企業と連携した人材育成も実施しています。DX推進員に対する研修はNTT東日本 東京西支店に委託。同社はDXに対する知見が深いので、その最先端DXを職員に体感してもらおうと「DX体験会」を開催。また、NTT東日本が取り組むDX事業を体感できる施設「e-CityLabo」の見学など、職員のDXに関する知識のアップデートに協力いただいています。同社とは令和6年10月に連携協定も締結しました。
以上、当市が行ってきた取り組みを説明しましたが、まだ道は半ばです。アナログからデジタルへの転換は重要ですが、それ以上に大切なのは、変革マインドの醸成です。今後も我々はDX人材の育成を通じて、変革を恐れず様々なものを変えることのできる職員を増やし、明るい未来を築いていきたいと考えています。
なぜ、その教育DXは失敗するのか?教育の負担・属人化を断ち切る、人財育成改革の進め方
第4部は、教育DXサービスを提供する事業者が登壇。職員教育の落とし穴と、それを避けるための方法について、自治体における事例や最新ソリューションの紹介もまじえながら分かりやすく解説する。
[講師]
 藤原 覚也 氏
藤原 覚也 氏
株式会社FCE
執行役員 トレーニング・カンパニー事業本部長
自治体の教育DXで陥りがちな3つの落とし穴。
本パートのテーマには“人財”という言葉が使われています。当社はこの文字にこだわっているのですが、ではなぜ人財育成をするのか。皆さんも庁内の職員に色々な育成をしているかと思いますが、まとめるとこういうことではないでしょうか。
-4_P04.jpg)
“成果”というのは、住民満足度の向上などを意味します。この成果、もしくは生産量を向上させるために人財育成を進めているのではと思われます。
しかし、日本の人口は次第に減っていくので、おのずと生産量も減少します。質についても、日本の生産性は国際比較でさほど高くない。採用も厳しくなっていく。そうすると、自治体においても人財の育成力が重要になってくるのです。
当社では、自治体も含め1,200ほどの団体に人財育成支援をしていますが、その中でも、育成する職員と若手とのギャップを感じる時がある。特に今は“タイパ”が重視される時代です。こうした事実を踏まえて、職員教育DXを進めていく必要があります。
この職員教育DXには、eラーニングはもちろん、ラーニングマネジメントシステム(LMS)、オンライン研修などが活用できますが、こうしたDXツールだけではなく、対面研修やOJTなど色々な要素を入れていき、効果的に設計すること、つまりブレンデッドラーニングが重要です。
-4_P11.jpg)
また、自治体の方々と話をしていると、「eラーニングを入れたが効果が出ない」、「職員が学んでくれない」といった声が耳に入ります。この教育DXの落とし穴は何なのか、という点について把握しておくことも大切です。
この“職員教育DXの落とし穴”は、大きく3つあります。1つ目が「学ぶ理由」です。そして、2つ目は「知っている」と「できている」の違い、3つ目が「タイムパフォーマンス」です。
まず、学ぶ理由とは何か。現状があって、目指す姿がある。このギャップが課題になり、「こうなりたい」というかたちで学ぶ理由が出てくる訳ですが、この目指す姿が見つからないという状況がある。であれば、こちらから“求める人財像”を用意しましょう。
例えば、主任や係長にはこういう人、局長にはこういう人、という自治体が求める姿を明確にして提示する。ここで自分とのギャップが明確になるので、学ぶ理由を持つきっかけが生まれます。
-4_P17.jpg)
ただし、自発的な学びは継続するのに対し、きっかけが受動的なものになると続かないというケースもあります。これが、「知っている」と「できている」の違いなのです。「できている」という状態にするためには、インプットとアウトプットを繰り返すことが求められます。それに加え、途中で「いいね」、「できているね」とフィードバックを入れることも重要です。
職員教員のパフォーマンスを上げるプラットフォームについて。
次に意識するのは“タイパ”です。職員が学びたい時に学べる、そして分からないことだけ学べるようにする。そのためにLMSやeラーニングを活用すればタイパが上がります。
ここで1つポイントなのですが、世の中の多くの人は、探し物やルールなど、調べものに費やす時間が年間550時間あり、労働時間の28%を占めているという調査結果があります。この部分をITツールなどで効率化することも必要。AIチャットボットやAIアシスタントが、そうしたサポート役となってくれるでしょう。
-4_P22.jpg)
最後に、本日の内容に関わる当社のサービスラインナップを紹介します。
「Smart Boarding」は、職員教育DXのプラットフォーム。ここで話した内容を全て網羅したサービスです。さらに、パーソナルRPAの「RPA Robo-Pat」や、生成AI活用をサポートする「FCEプロンプトゲート」も提供しています。
Smart Boardingの導入事例としては、岐阜県瑞穂市や、滋賀県草津市、新潟県三条市、青森市のシルバー人材センターなどがあります。
-4_P30.jpg)
瑞穂市役所では、新入職員に継続的かつアウトプット可能な学びの機会を提供したいということで導入。職員のスキマ時間での動画視聴、レポート提出、人事からのフィードバックなどで学びを加速化し、非常に良いサイクルになっています。こうした事例が数多くあるので、興味がある方はお問い合わせください。
-4_P28LAST.jpg)
上記は、当社が色々な自治体や企業と情報交換をしていく中で分かったことです。実際に、職員の皆さんが驚くべき才能を開花させるシーンをたくさん見てきました。重要なのは教育を諦めないこと、そして職員の可能性を信じることです。今回の話が、庁内における職員教育のヒントになれば幸いです。
ノーコードで自分で作れる地図システム「カンタンマップ」
DAY1の最後は、“地図”がテーマ。ノーコードツール+地図という視点で、住民サービスの向上と職員負担の軽減を両立した実績を踏まえ、専門事業者が新しい地図活用のあり方と今後の可能性について伝えてくれた。
[講師]
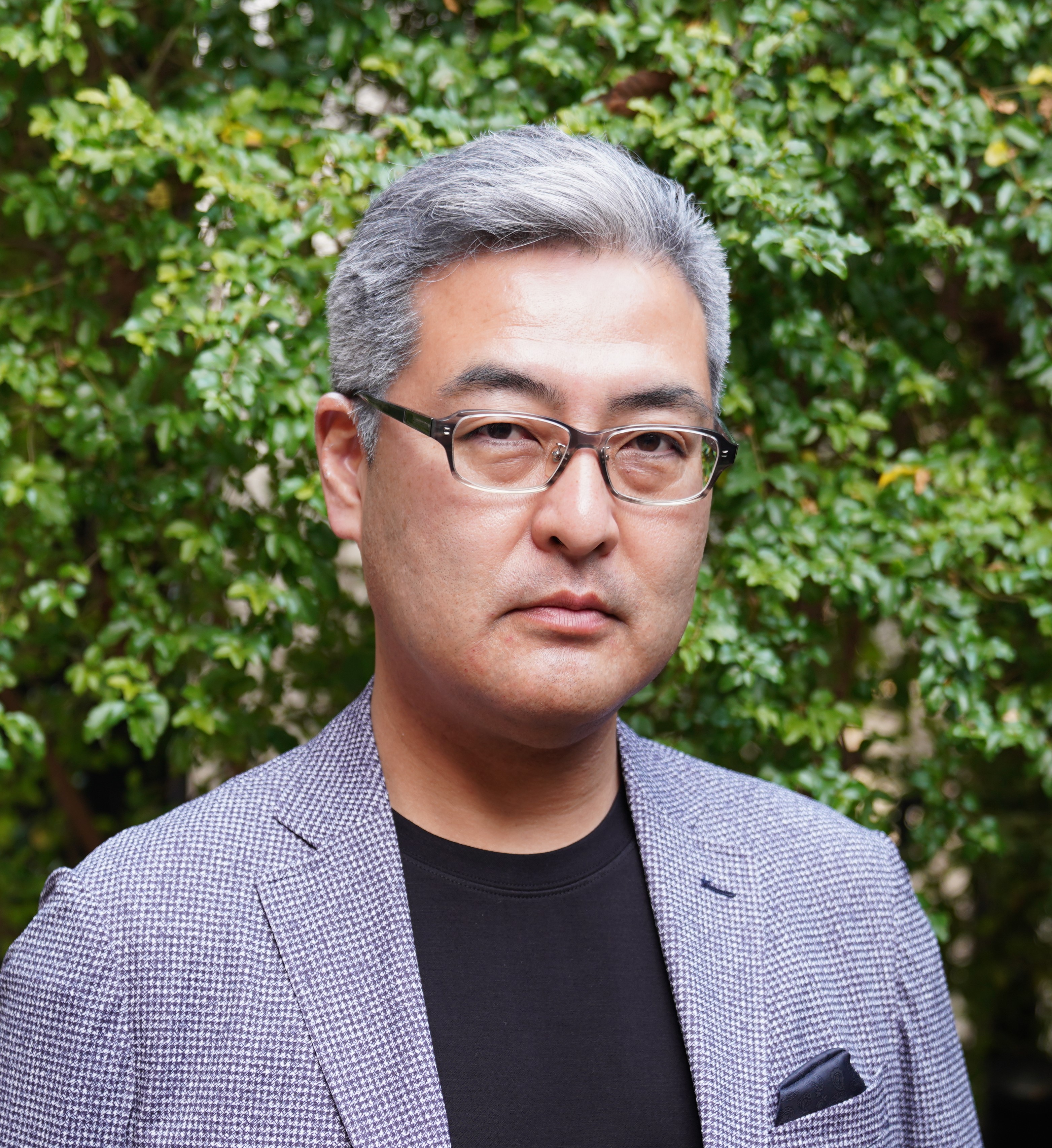 黒木 紀男 氏
黒木 紀男 氏
あっとクリエーション株式会社
代表取締役
自治体における地図活用の課題から生まれたソリューション。
私は以前、建設コンサル会社で勤務した経験があり、自治体のGISの仕事をやっていました。その経験の中で、果たしてGISは自治体DXに役立っているのだろうか、という疑問を抱え続けていました。
それから時代も進み、もっと簡単な地図を作りたいと考えて「カンタンマップ」というサービスを作りました。kintoneを活用し、ノーコードで地図システムが作れるというコンセプトで開発しています。
-5_P04.jpg)
GISのように多機能で専門的なものではなく、誰もが直感的に扱えるシンプルな地図システムを目指して開発したのがカンタンマップです。
システムのベースになるkintoneは、自治体でかなり広がっています。当社にも、kintoneを導入している、もしくはしようとしている自治体から、「地図を連携して使えないか」という問い合わせが増え、現場の声を聞こうと100以上の自治体を訪問しました。
-5_P06.jpg)
ご存知の通り、自治体ではあらゆる原課が地図を必要としていて、そうした地図を使う業務を改善したいという要望が、全国の自治体で起きているということです。そうした訪問、対話の中で分かったことが以下の3つです。
-5_P10.jpg)
相談は、現在使っている地理情報システムを、kintoneとカンタンマップに置き換えることで「業務効率化ができないか」、あるいは「市民からの通報と地図をリンクさせたい」、そして「地図情報を持っているが、市民に公開できないから問い合わせが減らない」、という内容です。
これらの悩みに対応したのですが、今回はこの中から、「市民からの通報」に関する事例を紹介します。
豊橋市の事例と、システム活用拡大の可能性について。
愛知県豊橋市では、「いぬねこ回収パッケージ」というシステムで、カンタンマップを活用していただいています。動物の死骸回収業務を、kintoneとカンタンマップで効率化した事例です。
このシステムは、豊橋市のホームページで公開されており、市民は画面から「動物の死骸がここにある」と通報ができる仕組みで、簡単に言うとkintone上で動く地図のサービスです。
-5_P11.jpg)
パッケージには、「職員の現地調査があるのでモバイルでも動かしたい」、「市民が現地から通報できるように」、「集まった情報を市民に公開できるように」といった自治体の要望が個別に実装され、必要なものだけを追加できるようになっています。機能がフル装備されていて高価、というものではなく、必要なものだけを選べるのです。
そもそもkintoneは、ノーコードでシステムを作れることが強みです。この画面の入力項目も、全て職員が作っています。我々は隣でアドバイスした程度でした。
-5_P12.jpg)
同市では従来、市民から通報があると、作業指示書を作成し、回収場所を紙の住宅地図などで探してコピーを貼り、それを印刷して委託業者にFAXを送信したり、電話をしたりしていた、ということでした。
そこで、このフローも自動化しようということになり、業者にもkintoneのユーザーIDを持ってもらった上でシステムを構築したのです。今では、「処理を依頼」というボタンを押したら業者に通知が飛び、業者への連絡が完了します。業者は画面を見て現地に行き、回収をして写真を撮り、完了報告のボタンを押すだけです。
こうした作業はデータとして蓄積されるので、議会などで報告をする際に備えてグラフや表で集計できるようにもなっています。業務に関する全ての対応がシステムの中で完結できるようになりました。
-5_P13.jpg)
もちろんこの仕組みは動物の死骸回収にしか使えない訳ではなく、道路の破損や放置自転車の通報、災害時の被害、粗大ごみの回収依頼など、様々なシーンで活用できます。こうしたものを作った結果、現在各自治体からは地図情報に関連する業務の効率化や、コスト削減に関する問い合わせを多く受けるようになっています。当社からも様々な提案が可能なので、気になる方はぜひご連絡ください。
お問い合わせ
ジチタイワークス セミナー運営事務局
TEL:092-716-1480
E-mail:seminar@jichitai.works


.png)
.png)











.jpg)
】バナー広告_株式会社ICHICO_PR.jpg)
.png)







