公開日:

読者投稿ページは、自治体職員が日々の業務や活動している内容を発表・共有できる場です。読者自ら執筆した原稿の中から、編集室が選出した記事を、ジチタイワークスWEBで公開させていただきます。
ぜひ、皆さんの自治体職員としての経験や取り組みを、編集室にお届けください。
※掲載情報は公開日時点のものです
● 投稿者(自治体職員)プロフィール
テーマジャンル : 災害対応
投稿者名 : 荒牧 正暢さん(30代)
所属 : 福岡県
2025年は、阪神・淡路大震災から30年という節目の年であることから、避難所の生活環境改善や災害関連死の予防などが注目されています。
この投稿では、一般社団法人日本災害医学会が運営する「地域保健・福祉の災害対応標準化トレーニングコース(Basic Health Emergency Life Support for the Public:通称BHELP)」について紹介します。
BHELPは、発災直後から避難所での活動を効果的・効率的に実践するために、災害対応における知識、共通の言語と原則を理解し、被災者の生命と健康の維持、災害発生直後からの被災地内での災害対応能力向上に資することを目的としています。
全国各地で対面またはオンライン開催にて研修を実施しており、保健・医療・福祉に関する専門職や、防災業務などに従事する行政職員が受講対象です。
私は行政事務職ですが、学会認定のインストラクターの一員として、主に九州開催の研修に参画しています。今年参加した3つのコースを通じて、BHELPについて紹介します。
私が参加したコースでは、行政職員として、県や市の保健医療部局・防災部局職員(事務)、行政医師、保健師、警察官、小学校の教員などに参加いただきました。また、専門職として、医師、歯科医師、薬剤師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、ケアマネジャー、救急救命士、病院職員、日本赤十字社の職員などに参加いただきました。
各コースでは共通の内容として、「災害対応に関する共通言語と共通原則」について学習するほか、「住民の健康維持に配慮した避難所の設営・運営」に向けて、グループワークを重ねます。
所属・職種や日頃の業務の垣根を越えて、活発な意見交換が行われ、異なる職種の役割や専門性に触れることで、多職種連携の必要性についても実感いただくことできたのではないかと感じています。
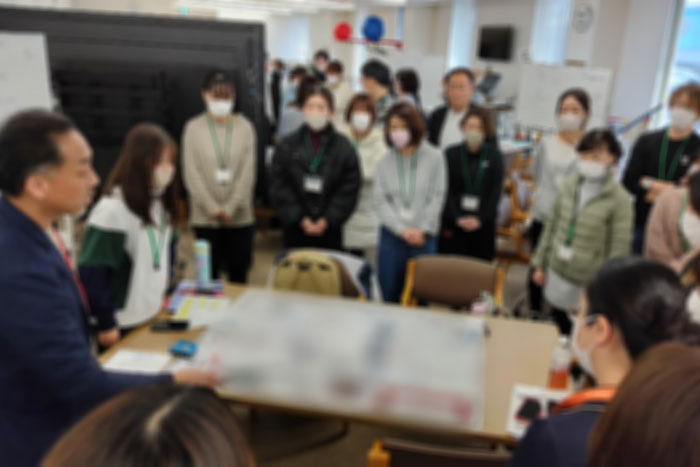
・第2回佐賀BHELP標準コース
令和7年1月18日(土)開催
主催:特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン
会場:医療法人ロコメディカル 江口病院(佐賀県小城市)

・第4回長崎BHELP標準コース
令和7年1月26日(日)開催
主催:一般社団法人長崎市医師会
会場:長崎市医師会館(長崎県長崎市)

・第1回大分BHELP標準コース
令和7年2月8日(土)開催
主催:大分大学医学部附属病院
会場:大分大学医学部附属病院(大分県由布市)
受講者アンケートでは、“色々な意見や考え方があり、勉強になった”とか、“ほかの受講者の意見を聞くことで、考え方などを確認することができた”など様々な意見が寄せられ、私自身も毎回、受講者から多くの学びを得ています。
多くの自治体職員の皆さんにBHELPの取り組みを知っていただき、受講を検討してもらえるとうれしいです。
今後の研修開催予定については、災害医療イベントポータルサイト「D-PORT」にて、随時更新しています。
・災害医療イベントポータルサイト「D-PORT」
https://mcls.jp/dport/?evType=BHELP
・一般社団法人日本災害医学会
地域保健・福祉の災害対応標準化トレーニングコース
https://jadm.or.jp/contents/BHELP/










