.jpg)
ナイトタイムエコノミーとは夜間の経済活動のこと。日没から日の出まで、18時から翌朝6時頃までの時間帯に観光や飲食などの経済活動の場を増やし、経済活性化の後押しをしようという取り組みだ。
日本では24時以降の飲食を伴うダンスやエンターテインメント営業が禁止されてきたが、平成28年の風営法改正により営業許可が新設され適法化。これがきっかけとなりナイトタイムエコノミーが政策化された。
本記事ではナイトタイムエコノミーを巡る社会の動きや課題のほか、全国の自治体での事例について詳しく解説する。ナイトタイムエコノミーに取り組む実際の事例から、夜間の経済活動推進策のヒントを得よう。
【目次】
• ナイトタイムエコノミーとは夜間の経済活動を推進する動き
• ナイトタイムエコノミーの課題とは
• 夜景に力を入れる自治体も
• 実際のナイトタイムエコノミーの事例をご紹介
• 観光客や住民が夜の時間帯を楽しめるまちづくりを
※掲載情報は公開日時点のものです。
ナイトタイムエコノミーとは夜間の経済活動を推進する動き
.jpg)
ナイトタイムエコノミーとは夜間の経済活動のこと。一般的には18時から朝6時頃までの時間帯に動く全ての事業を総称するもので、飲食などの「夜遊び」だけではなく公共交通機関や医療、福祉など夜間帯の社会を支える事業も含まれている。
ナイトタイムエコノミーは夜の時間帯における観光や飲食などの活動の場を増やし消費拡大を図ることで、経済を活性化させようという考え方で推進されている。
インバウンド消費増加のカギとして注目されている
ナイトタイムエコノミーの推進はインバウンド消費増加のカギとして注目されている。観光庁によると令和6年の訪日外国人旅行者数は3,687万人(※1)で、ナイトタイムエコノミーが消費単価の高い滞在型観光につながるため、消費拡大策として夜間の観光客向けのコンテンツを充実させようという動きがある。
観光庁が発表した「令和6年版観光白書」によると、コロナ禍により落ち込んでいた外国人旅行者数も回復傾向にあり、令和5年の訪日外国人旅行者数は約2,507万人と、コロナ禍より前と比べて79%回復した(※2)。その一方で、令和4年の「外国人旅行者受入数ランキング」で日本は世界42位、アジアでは5位と世界的な潮流からの遅れも見られる。 日本を訪れる旅行者の一人当たりの消費額を増やすため、夜の時間帯を活用しようというのがナイトタイムエコノミーの考え方だ。
先進地はイギリス

イギリスはナイトタイムエコノミー先進地といわれており、ナイトタイムエコノミーの経済規模は日本円で約7兆円超。
パブでお酒を飲みながらスポーツ観戦するといったイメージも強いが、若者の価値観の変化を受けてイギリスの夜の過ごし方も多様化している。ビデオゲームをプレイしながらお酒を楽しめる「ゲームバー」や、お酒を飲まない人をターゲットにノンアルコール飲料を提供する「夜のカフェ」など、様々なニーズに対応した事業が登場している。
イギリスでは平成24年から夜間でも安全に外出できるまちを認定する「パープルフラッグ制度」も設けている。この制度には犯罪対策、アルコール提供のガイドライン、泥酔対策、交通整備、 地域で提供されるサービスや利用者の多様性といった様々な基準が設けられ、一定の水準に達した地域が認証を得られる仕組みになっている。
平成28年6月に改正風営法が施行

日本でナイトタイムエコノミーの議論が活発になった背景には、平成28年6月に風営法が改正されたこともある。
音楽に合わせてダンスを楽しむクラブの営業時間は、原則24時までとされていたが、改正風営法では照明の明るさなど一定の条件を満たせば、特定遊興飲食店として24時から翌朝6時まで営業できるようになった。こうした規制緩和により、それまで風営法の規制を受けていた店舗も夜間営業が可能になり、ナイトタイムエコノミーのあり方もよりよいものにしようという動きが生まれた。
ナイトタイムエコノミーの課題とは
ナイトタイムエコノミーを推進する上で課題となっていることもある。以下で詳しく解説していく。
夜間の交通手段の確保

夜間の交通手段の確保が課題として挙げられる。日本では終電が早いという訪日外国人の声もあり、都市部から離れた郊外に行けばなおさら終電の時間も早くなる。
週末のみ電車を走らせる時間を延長する、人気路線のみ24時間営業にするといったアイディアは出ているものの、民間事業者だけで採算を取ることは難しいため実現には至っていない。イギリスでもロンドンオリンピックに向けてナイトタイムエコノミーが振興され、オリンピックの予算で環状線の24時間営業が整備された。こうした交通施策はアフターオリンピックを見据えたもので、行政が介入して夜間の交通の利便性が向上した事例として注目されている。
文化が体験できる場所の夜間営業
文化が体験できる場所の夜間営業も課題の1つ。日本では夜間営業を行う娯楽施設や芸術・文化施設が少なく、施設の営業終了時間が早いため、日本文化を体験したい観光客のニーズにどのように応えていくかが課題となっている。
治安や衛生など安心・安全対策
夜遅い時間の治安や衛生など、安心・安全対策も大きな課題。ニューヨークやアムステルダムなどでは、「ナイトメイヤー(夜の市長)」と呼ばれる役職が設けられ、行政や住民、事業者などのステークホルダーとの間に立って政策立案などの取りまとめを行っている。
アルコールに関するトラブルや騒音対策、嘔吐物やごみの問題など夜間帯に多いトラブルに対処しながらナイトタイムエコノミーを活性化させることがナイトメイヤーという役職を設ける目的だ。日本でも平成28年に東京都渋谷区でヒップホップ・アクティビストのZeebra氏が夜の観光大使「ナイトアンバサダー」に就任。渋谷のナイトタイムエコノミーを推進するための情報発信を行っている。
夜景に力を入れる自治体も
.jpg)
夜間しか楽しめない観光コンテンツとして夜景に力を入れる自治体も多い。一般的に日本三大夜景として知られているのは「函館、神戸、長崎」だが、明確な選定基準や認定団体などはなく、いつ広まったかも定かになっていない。全国には多くの夜景スポットがあり、近年は様々な団体が独自の三大夜景を発表して観光PRが行われている。ここからは、それぞれの三大夜景について見ていこう。
日本新三大夜景
「日本新三大夜景」は「一般社団法人 夜景観光コンベンション・ビューロー」が選定する三大夜景。平成24年に設立された非営利団体で、日本夜景遺産の認定や夜景観光士の検定事業、夜景に関するイベントの開催などを手がける。夜景を観光資源として地域活性化に役立ててもらおうと、3年ごとに「日本新三大夜景」を発表。令和6年に選ばれたのは「北九州市、横浜市、長崎市」で、そのうち北九州市は前回のランキングでも1位を獲得している。
新日本三大夜景
「新日本三大夜景」は「新日本三大夜景・夜景100選事務局」が選ぶ三大夜景。夜景愛好家の団体「夜景倶楽部」が平成14年に事務局を立ち上げ、平成14年に「新日本三大夜景」を発表した。選ばれたのは「笛吹川フルーツ公園(山梨県山梨市)」「若草山(奈良県奈良市)」「皿倉山(福岡県北九州市八幡東区)」で、一部の愛好家だけではなく一般の人も気軽に訪れることができる夜景スポットであることが選定基準になっている。
長崎市は世界新三大夜景にも認定!
日本国内の夜景スポットだけではなく、世界を対象にした「世界新三大夜景」もある。令和3年に選ばれたのは「長崎市、モナコ、上海」の3都市。一般社団法人夜景観光コンベンション・ビューローが主催した「世界夜景サミット」の投票で選出されたもので、長崎市は平成24年に続き2回目の認定。
「世界新三大夜景」は平成24年に創設され、10年を目途に再度選ぶことにされていた。長崎市では初めて「世界三大夜景」に認定されてから、稲佐山中腹と山頂を結ぶスロープカーの運行を開始したほか、ハートや星座の形が浮かび上がる夜景の演出照明などに取り組んでいる。
実際のナイトタイムエコノミーの事例をご紹介
ここでは実際のナイトタイムエコノミーの事例を紹介する。
訪日外国人からの人気トップクラス!【東京都渋谷区】
.jpg)
東京都渋谷区の渋谷区観光協会は、平成28年から「渋谷区観光大使ナイトアンバサダー」をスタート。ヒップホップ・アクティビストのZeebra氏、FIG&VIPERディレクターでDJの植野有砂氏、TRANSIT GENERAL OFFICE代表の中村貞裕氏がアンバサダーに就任し、渋谷の夜の魅力を発信している。
渋谷横丁と強炭酸水「VOX」がコラボレーションし、Zeebra氏のコラボメニューを開発して渋谷横丁の飲食店で提供するなど、多彩な活動を行っている。訪日外国人にも支持されており、ナイトアンバサダーの3人がオススメするナイトコースが掲載された渋谷区観光協会のナイトマップは、各所から問い合わせが来るほどの人気。このナイトマップにはカードやWi-Fiの使用可否や店舗のメニューの英語対応の状況なども記載され、希望者に無料で配布されている。
民間事業者から事業提案を募集【千葉県千葉市】
千葉県千葉市では令和元年に「千葉市ナイトタイムエコノミー推進支援制度」を創設。地域経済の活性化および夜間におけるにぎわい創出のため、民間事業者から事業提案を募集して採択した事業を展開している。
令和6年度は全部で6つの事業を採択し、年間を通してビアフェスやインドの料理と音楽、ダンスなどをテーマにした「インドナイトちば」といったイベントを開催するほか、ホテルの宿泊者を対象にした飲食店の予約とタクシーの送迎をセットにしたワンストップのツアーパッケージも提供。それに加えて、千葉市内で見ることができる工場夜景やイルミネーションの情報をホームページに掲載するなど、夜間帯に観光客が楽しめるコンテンツを積極的にアピールしている。
観光客や住民が夜の時間帯を楽しめるまちづくりを
.jpg)
ナイトタイムエコノミーは夜の時間帯を楽しく健全に遊べるコンテンツの充実を図り、住民や観光客の消費拡大を目指す取り組みだ。コロナ禍で、回復してきたインバウンド客に向けた取り組みを行う事例もあり、一人当たりの消費単価の増加にもつながることから注目されている。
ナイトタイムエコノミーの考え方や、全国の自治体が取り組む先進事例を参考に、それぞれの地域の夜の時間帯にも注目して経済振興策を考えてみよう。

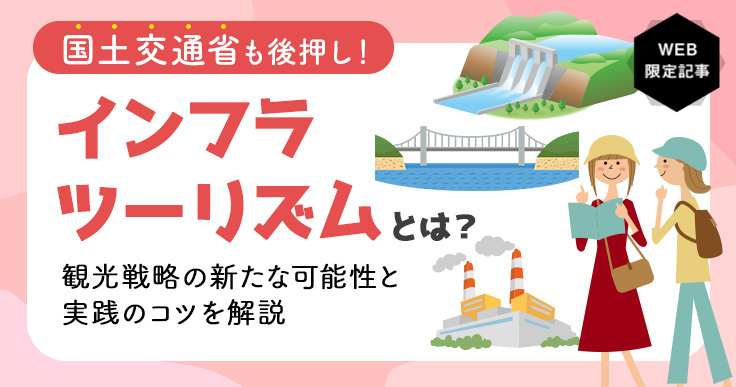
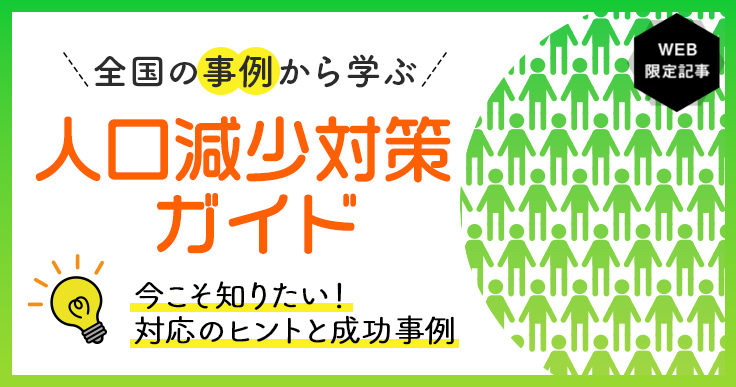
.png)











.jpg)
.jpg)
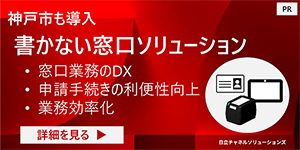
.png)







