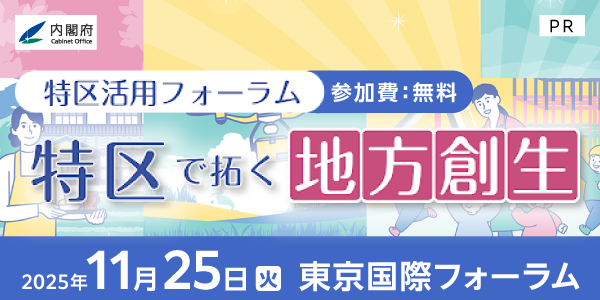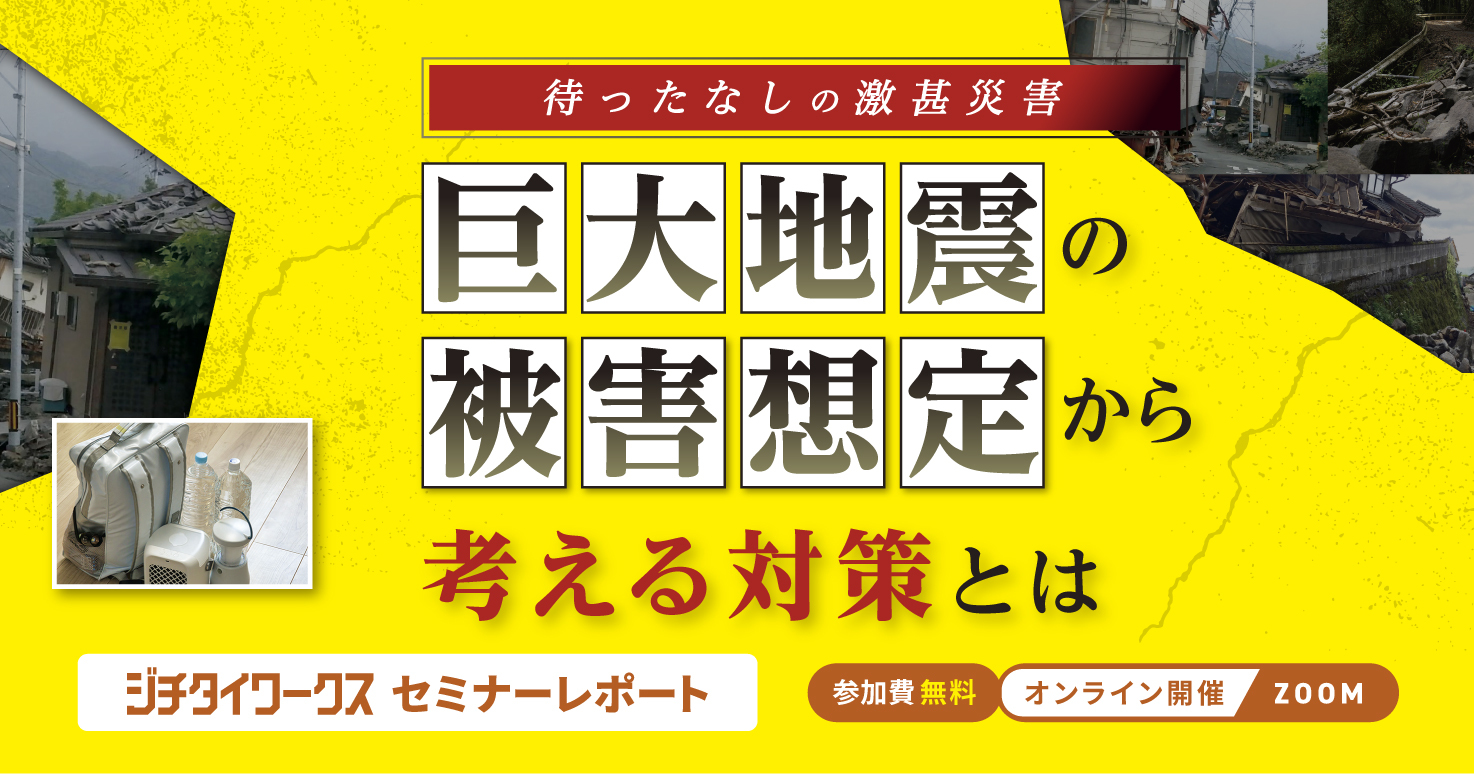
“大規模災害への備え”をテーマに、2DAYSにわたってお送りしたセミナー。2日目は、自治体の防災部門や、民間の災害支援団体、防災DXに知見を持つ事業者から5名の登壇者が集結しました。
いつ来るか分からない巨大地震への対策に、自治体は何をすればいいのか、職員はどのような心構えで臨むべきなのか、様々なヒントが交換されました。当日の様子をダイジェストでお届けします。
概要
■タイトル:待ったなしの激甚災害 巨大地震の被害想定から考える対策とは【DAY2】
■実施日:2025年5月23日(金)
■参加対象:自治体職員
■開催形式:オンライン(Zoom)
■申込者数:165人
■プログラム:
第1部:避難所環境づくり
第2部:避難所の災害に強い環境整備(電気・ガス・水のライフライン防災)
第3部:温かいご飯が「命」を救い、「未来」を築く!
第4部:導入自治体300以上。避難所運営だけでなく、避難所外の被災者の把握を行う防災DX最新事例
第5部:“個人情報をあえて取得しない”避難所管理システム
避難所環境づくり
セミナー1番手は、DAY1でも登壇してくれた、いなべ市防災課の大月さん。今回のDAY2では避難所に焦点を当て、過去の災害における避難所の課題、今後求められる姿などについて、自身の経験も含めて語っていただいた。
【講師】 大月 浩靖 氏
大月 浩靖 氏
三重県 いなべ市 総務部 防災課 課長補佐
プロフィール
平成19年より防災の担当をし、これまで東日本大震災、熊本地震、九州北部豪雨、西日本豪雨など様々な被災地支援に従事。平時から積極的に地域に入り地域防災に取り組み、市民の防災意識の向上に努める。プライベートでは内閣府のチーム防災ジャパンのお世話係としても関わり、災害の被害軽減をするために、国民運動の展開を行うとともに、国民の防災意識の向上を行っている。
進化しない避難所に変化を生むための提案。
今回のテーマは“避難所づくり”です。そもそも避難所にはどのような役割があるかというと、生活・サービス提供・情報・対応活動という4つの拠点を担っています。単なる居住空間ではない、ということを念頭に置いていただければと思います。
-1_P02.jpg)
過去の災害における多様な避難は“分散避難”ともいわれます。要因は、指定避難所の収容率の低下や、自然災害の激甚化、感染症の発生など様々です。この分散避難は、自宅や親戚宅、知人宅などへの縁故避難、家の軒先における敷地内避難、車中泊避難、民間宿泊施設避難と、大まかに4つの避難に分かれます。
-1_P03.jpg)
これに加え、能登半島地震では“ビニールハウス避難”が出てきました。それぞれにメリット・デメリットがありますが、いずれにしても自治体は避難所外避難者への情報・物資の提供を行うことが大切です。
避難所自体に目を向けると、「避難所の姿が100年間変わっていない」と言われています。関東大震災から102年経っていますが、発災直後は施設で雑魚寝という形式が現在も続いている状況です。
コロナの時には、感染症対策という意味でパーテーションを活用し、距離を確保する対応がとられました。今後はマットや毛布の準備と同時に、プライバシーの確保が重要です。福祉避難スペースを設置することも忘れてはいけません。
-1_P06.jpg)
そして避難所運営が長期になると、生活環境をどう構築するかがポイントになるので、レイアウトを変更しつつ冷蔵庫や洗濯機などを整え、屋根付きのスペースでプライバシー確保を高めるといったことも必要だと考えます。こうした設備を平時から整えることが重要です。
続いて、初動時の避難所環境について説明します。熊本地震の例でいうと、避難者はまず、屋内の部屋や廊下などで環境が良い場所から使い始めます。その後は雨風がしのげる場所となり、屋内のロビーなどが使われる。そうした場所も人でいっぱいになると、屋根やひさしがあって雨がしのげる場所に移動します。そして最後は、雨はしのげるが近くにトイレがあるなど、環境が悪いところに入っていくのです。
つまり、移動に時間がかかる要配慮者が外で生活する流れになってしまう。それを避けるためにも、避難所に福祉スペースなどを準備しておくことが大切です。
支援は“場所”から“人”へ。避難環境の改善を進めよう。
次は、被災者のアセスメントと支援機関との情報共有です。避難所には日本赤十字社やDMAT、DPATなど様々な団体が入ってきます。そして、熊本地震では、1人に対してそれぞれの機関がアセスメントをとる状態になっていました。能登半島地震でも同じことが繰り返されました。被災地の状況にもよりますが、大規模災害になれば福祉保健医療調整本部などが立ち上がったときに、全体で共有することが大切だと思います。
-1_P10.jpg)
また、これらの団体に加えNPO、NGOも被災地に入ります。防災基本計画や災害対策基本法の中でも、NPOやNGOなどとは“協働しましょう”と書かれています。特に被災者支援では連携が必須。NPOやNGOは長期にわたる被災者支援をしていただけるので、協力することは重要です。そうした連携とともに被災者一人ひとりのケースマネジメントが求められています。
避難所はいずれ閉所します。その中でも、退所しない・できないという人が出てくる。理由はその人の環境によって異なります。こうした人々への対応は福祉の領域になる。ここがケースマネジメントという流れになるのです。
例えば事前に閉所を決めて早めに告知するなど、一人ひとりに寄り添った支援・対策の検討をする。避難生活から通常生活への移行は、被災者の思いも含めて道筋を作ってあげることが大切です。
国は従来、支援は“場所から”ということで、避難所支援や生活の居住場所の支援をしてきたのですが、これからは人の支援をしようという方向性に変わっています。これは、福祉の役割が拡大するということです。こうした点も念頭に置きつつ、今後の避難者対応をしていくことが大事です。
-1_P15.jpg)
最後に、最近注目されているイタリアの避難所について紹介します。
下記はイタリアにおける避難所の事例ですが、日本の避難所事情とはかなり異なります。イタリアは国主導で避難所の運営や物資を総合的に担っているのですが、日本では市町村が避難所を運営しています。大規模災害では市町村の職員が避難所以外の災害対応をしなければならないにも関わらず、都道府県から事務委任されているのが現状です。
今後は、このイタリア式も含めながら、円滑に避難所を開設・運営する方法を考えていく必要があると思います。
災害対応の業務は大変ですが、被災者のために自治体がよい環境を作ることも大切。災害関連死という言葉が日本から無くなることを目指すのも大事です。そこに向けて、避難所での生活を高め、環境を改善し、避難者を守ることができればと思っています。
避難所の災害に強い環境整備(電気・ガス・水のライフライン防災)
災害発生後、被災者の命をつなぐライフライン。中でもガスを活用した発電や空調については、そのレジリエンス性の高さが近年注目されている。第2部はガスを活用した避難所の環境構築を手がける事業者が登壇。避難所の質を高めるアイデアを伝える。
【講師】 平本 瑞季 氏
平本 瑞季 氏
I・T・O株式会社 営業本部
ライフラインの分断に強い“GHP”を避難所に活かす。
本パートでは、ライフライン防災と題し、災害に強い避難所の環境整備について、特に空調の導入やライフライン確保の部分を中心に説明します。
当社は、ガスの供給機器を開発・製造・販売しているメーカーですが、近年自然災害が頻発する現状を受け、防災・減災事業の取り組みを始めています。下図が、当社が提案しているライフライン防災ソリューションの全体像です。
-2_P03.jpg)
避難所では、数日間から数週間に及ぶ避難生活を続けるための設備が必要になります。そのために重要なことの1つが、電気・ガス・水といったライフラインの確保です。当社のライフライン防災はこの考えにもとづいています。
そうした防災・減災事業の一環として、能登半島地震においても支援活動をしました。被災地では断水が続いていたため、当社のサービスに加え、様々な企業と連携して、ガスによる給湯・シャワー、洗濯、乾燥などを支援しています。
この活動を通して印象に残ったのが、空調がないことの大変さです。空調のない体育館で、被災者はヒーターを使って暖を取っていたのですが、冬の寒さは深刻で、体調管理や心身のストレスに大きく影響するということを実感しました。
-2_P04.jpg)
ちなみに、災害や紛争時の避難所については、国際赤十字の「スフィア基準」にも空調の最低基準があり、“最適な快適温度を提供すること”と定められています。これには熱中症対策のための冷房はもちろん、冬の寒さ対策も含まれています。
そこで、避難所の空調導入にあたって私たちがオススメしているのが、ガスの空調です。ガスヒートポンプエアコン(GHP)と呼ばれるもので、ガスのエンジンを使って冷暖房を行います。電気の空調(EHP)は、電気のモーターを使ってコンプレッサーを動かすのに対し、GHPはガスエンジンなので、電力の消費量が約10分の1。停電時のバックアップとして必要な電力が小さいため、小型の発電機とガス供給があれば動かせるということです。
さらにGHPには停電対応型、あるいは電源自立型と呼ばれているバッテリーと発電機を内蔵した機種もあります。このタイプであれば、もし停電していてもガスの供給があれば稼動できますし、余った電力は照明やコンセントなどに使用できます。
-2_P07.jpg)
上記は、電気とガスの空調を比較したものです。避難所への空調設置を検討する際の参考にしていただければと思います。
エネルギーの弱点を補い、洗濯や入浴に不自由しない環境を構築。
ここまでガス空調について紹介しましたが、ガス空調の中にもLPガスを使うものと都市ガスを利用するものがあり、それぞれに特徴があります。主なものは以下の通りです。
-2_P08.jpg)
この違いを踏まえて、LPガスと都市ガスのどちらを利用するか、という点ですが、都市ガスの場合は導管が通っていることが前提になります。それに対してLPガスはスペースさえ確保できればどこでも設置できます。
ただし、ランニングコストは一般的に都市ガスの方が安いので、都市ガスが利用できるところは都市ガスの空調を、利用できないところはLPガスの空調を、という設置をオススメしています。同じ自治体の中でも複数のエネルギーを利用することで、リスク分散につながるというメリットもあります。
このように、ガスは災害に強いエネルギーですが、その特性をより活かすための工夫があります。
まずLPガスについて。LPガスの容器は耐久性に優れているので、地震などで倒れてしまっても、起こして配管をつなげたら使用できます。それでも復旧までに一定の時間は必要なので、地震・洪水対策を施すことで、災害に強いという特性をさらに活かすことができます。
その一例が、耐震容器スタンドです。震度7相当の地震に対応できるよう設計されており、同レベルでの加振テストも実施しています。水害による流出も防止する設計です。
-2_P10.jpg)
次に都市ガスのバックアップについて
都市ガスは水害に強い一方、導管が地下を通っているので、地震の際には安全のために供給を一時遮断する場合があります。ガス供給が再開されるまでの期間は、LPガスから都市ガスを作り出す“ガス変換器”という装置でバックアップする方法があります。一般の方でも簡単に操作できるよう設計されており、多くの自治体へ導入されております。
また、避難所空調導入の際には、以下の補助事業が利用可能です。
-2_P12.jpg)
災害時には避難所の環境整備が重要です。特にライフラインの確保は避難所運営の質を大きく左右します。当社では空調をはじめ、発電機による電気の確保、浄水装置による水の確保からトイレ、洗濯、シャワーなどを用意し、それらを組み合わせた総合的なソリューションを提案しています。地域における防災、災害対策の一助として活用いただければ幸いです。
温かいご飯が「命」を救い、「未来」を築く!
近年注目されている“イタリア式”の避難所。この方法から見習うべきところを取り入れて、日本流にアレンジしたらどうなるのか。長野県で大規模な訓練を行った民間団体の担当者が、避難所における課題の洗い出しとともに、取り組み内容をレポートする。
【講師】古越 武彦 氏
特定非営利活動法人 長野県NPOセンター 事務局次長
長野県災害時支援ネットワーク担当
プロフィール
元長野県職員。2011年以降に長野県で発生した全ての災害(9回)に従事。最終役職は「火山防災幹」。令和3年度末に早期退職し、全国災害ボランティア支援団体ネットワーク(JVOAD)事業担当として1年間従事。2023年4月より現職。
災害法制度に定められている基準は、あくまでも“最低限度”であるという認識がない。
私は長野県職員を30年勤め、令和2年度末に早期退職した後、JVOAD(全国災害ボランティア支援団体ネットワーク)に1年間従事し、その後、長野県NPOセンターで、長野県域の災害中間支援組織である「長野県災害時支援ネットワーク」の担当をしています。
県職員時代に長野県で発生した多くの災害で応急活動に従事しました。そのほかにも、阪神・淡路大震災での須磨区役所への支援や、平成24年度に神戸市にある「人と防災未来センター」に派遣されていた際には、被害日本大震災後の東北地方の自治体の検証などを経験しました。
-3_P08.jpg)
本セミナーの第1部でもありましたが、関東大震災から100年も経つというのに日本の避難所は様子が変わっていません。少しずつ良くはなってきていますが、根本的には変わっていない。右上の写真は、令和元年東日本台風災害の被災地である長野市の避難所の写真です。自宅の片付けをして避難所に戻ってきても、身体を清潔にすることができないまま弁当と汁物を受け取って、自分の寝る場所に行ってから食事をとる。これでは健康を害してしまいます。
どこの被災地に行っても、床に雑魚寝、不衛生なトイレ、避難所で提供される食事は、パンやおにぎり、カップラーメンが続き、よくなって弁当の提供。このような環境がずっと続くのです。
なぜ、このような状況が続いてしまうのか。研修などで「被災者支援はどの程度行えばいいと思いますか。最低限必要な範囲ですか?できる限り実施しますか?」と行政職員に聞くと、「最低限必要な範囲」という答えが多いです。なぜこのような答えになるかというと、被災者支援はどのくらい行えばいいのか分からないので、基準をそのまま適用すればいいのではないか、という考えになってしまうからです。災害救助法の救助の基準は、あくまでも最低のラインを示しているに過ぎません。その基準をもとに必要なものを上乗せ(特別基準の設定)して、被災者にあった支援を行うことが本来の制度運用なのです。その基準を実行すれば、きちんと被災者支援ができるという考えが、そもそも間違いになります。-3_P09.jpg)
また、「避難所で良い食事を出すと自立を阻害する」という声もしばしば耳にします。なぜこうした考えに陥るかというと、自治体の職員は災害対応に慣れておらず、独自の解釈で実施することがあるからです。初めての経験で、少ない人で対応するから誤解も生じるのです。
さらに問題なのが、被災者の生活再建には長い時間がかかるものなのに、現行制度上、“誰がそれを続けて担っていくのか”が明確になっていないという点です。災害対策基本法の考え方に「市町村長による一義的な災害応急対策(避難指示等)の実施」というのがあるのですが、これが誤って解釈され、被災者支援は全て市町村が担うべき、という認識がひとり歩きしています。これが被災者を取り巻く生活環境を向上させない原因なのではないか、と私は分析しているのです。こういった環境は変えなくてはいけません。ではどうやって変えていけばいいのでしょうか。
-3_P17.jpg)
私たちは、新たな方法があってもいいのではないかと考えています。そこで今取り組んでいるのが“直接的被災者支援方法”。第1部でも話が出たイタリア式の被災者支援の手法を参考にした手法で、この取り組みを長野県域に広げ、全国にも拡大していきたいと考えています。
イタリアの方法を手本にした“長野モデル”の被災者支援。
もちろん、イタリアと日本では環境が異なるので、イタリア式をそのまま持ってくるのは乱暴な話です。従って、これからお話しする方法は、良いと思えた部分を取り入れつつ、行政にまかせっきりにしない、ということからスタートしています。一番の目的は、イタリアでは当然のように行われている「被災者の人権を尊重した支援」の理念を取り入れることです。
まずはこの方法を試してみようということで、2日間にわたって実働訓練を行いました。主催は、長野県災害時支援ネットワーク、長野県社会福祉協議会、避難所・避難生活学会、(株)シェルターワンといった民間の支援者です。今回は行政からの支援を全く入れずに進め、全体で700万円規模の事業として実施しました。
-3_P28.jpg)
長野県諏訪市で大きな地震が発生したと想定し、市域外からパッケージ化した支援を届ける、という内容です。
長野県伊那市から諏訪市に備蓄物資を持って行き、拠点を設けて、避難者を受け入れる。そこを本部にして、避難者や近隣の在宅避難者に支援を届けるというものです。訓練会場は工場跡地を利用しました。
避難者用として空調がついた世帯用のテントを設置しました。食支援としてキッチンカーを複数台並べて、主食、主菜、副菜、汁物と分業して250食分を用意し、大型の食堂で提供しました。メニューの選択や量の調整をしたことや、避難者だけでなく支援者も一緒に食事をする。驚くべきことに「廃棄物ゼロ」という結果でした。そのほかにも、清潔なトイレやシャワー、洗濯機や乾燥機を設置しました。
この訓練は、基本的に全員参加という方針で、事前に「支援者役」と「避難者役」のどちらかに登録して参加してもらいました。
実働訓練の構成は以下の6つです。
-3_P31.jpg)
1~4はイタリア式に近い形で行い、そこに支援者のための支援拠点という位置付けを行い、福祉的な要素を取り入れたのが長野モデルです。
今の救助法などは、食品、飲料水など“モノ”を提供するという考え方です。しかし、健康的な食事ということを考えると、食事という行為がとても重要だと考えています。被災して、一番つらい時に避難所に来て、冷えた食料を配給でいただくよりは、温かい普通の食事を「命が助かってよかったね」と被災者も支援者も一緒にコミュニケーションを取りながら食べる。これが重要だと思うのです。
-3_P32.jpg)
この方法では、様々な団体や大学、地域の力を合わせるという部分を我々が災害中間支援組織として担います。ボランティアとしてかかわる人の育成もします。その上で官民が連携し、共通の目標を定めて力を合わせることで災害時に動ける仕組みを作ろうとしているところです。令和7年12月には、さらに発展した訓練を予定しています。
現行制度では被災地の市町村に大きく負担がかかるようになっています。それでは被災地が疲弊してしまいます。被災者への支援を民間が担い、行政の職員は住家の被害認定や罹災証明の発行に注力する。このような仕組みができれば、早期の被災者の生活再建につながるのではと考えています。私たちの取り組みについて、聞きたいことがあればぜひお問い合わせください。
導入自治体300以上。避難所運営だけでなく、避難所外の被災者の把握を行う防災DX最新事例
いまや重要な通信インフラの1つとなっている“LINE”。その利用率の高さを活かし、行政サービスプラットフォームを構築している事業者から、平時も有事の際もフェーズフリーで使えるツールについて、具体的な機能や自治体における活用事例を共有してもらった。
【講師】 仁志出 彰子 氏
仁志出 彰子 氏
株式会社Bot Express 執行役員 営業担当
プロフィール
23年勤めた前職の大津市役所では勤労福祉、情報システム、学校教育、保健予防、経営経理、経営戦略の業務に携わっていた。その経験を活かし、住民により便利な市役所サービスを提供するだけでなく、忙しい公務員を助けることができるBot Expressのサービスをたくさんの自治体に知ってほしいと思い営業として入社。
平時から使うことで災害時に活躍する“スマホ市役所”の特徴。
私は以前、自治体職員として23年間勤めた経験があり、住民が便利になるだけでなく、職員がより便利に、楽になるというツールを広めています。今から紹介するのは、防災に特化したサービスです。自治体の導入事例も交えてお伝えします。
当社のサービス「GovTech Express」は、「スマホ市役所」とも呼ばれています。防災に特化したものではなく、色々なサービスができるスーパーアプリみたいなものの中に防災機能が存在しています。
-4_P05.jpg)
防災アプリの場合、いざ有事になって住民が使えないというケースも多いものです。そこで、自治体が実施する検診やイベントなど、日頃使うサービスの中に防災機能を搭載することで、災害時にもスムーズに使っていただける仕組みになっています。
サービスについて、5つの特徴を紹介します。
1つ目は、説明書がいらないという点です。初めて見るアプリやWEBフォームなどと違い、LINEを使ったサービスなので、日頃家族や友だちとやりとりしているように、一問一答形式で聞かれたことに答えるだけで、申請や予約などのサービスを受けられるものとなっています。
2つ目の特徴は、双方向のコミュニケーションです。自治体からの一方的な発信だけでなく、住民から「水道が出ない」とか「この道路が陥没して避難所に行けない」といった形で、1対1でやりとりすることができます。テキストや写真だけでなく、お金のやりとりもできるので、災害見舞金をデジタル送金することも可能です。
-4_P07.jpg)
3つ目は、LINEを使っていない方や、スマホを持っていない方に対し、WEBブラウザ版を利用することができるという点です。公平なサービスを提供することができますが、災害時にはLINEを使っていただいた方が連絡もスムーズです。
4つ目は内製です。システム開発を受託するスタイルではなく、プラットフォームを提供しており、希望に応じて自由自在かつ簡単に開発することができます。いわゆるノーコードツールです。
また、サブスクでの提供なので、追加予算などの負担なく全ての手続きを実装可能。手続きのラインアップはWEB上に公開されています。中でも防災については、避難所チェックインや避難所外避難者の状況確認、防災メール連携など種類も豊富です。職員専用ツールもあり、安否確認や参集なども行えるものとなっています。
-4_P10.jpg)
そして5番目の特徴は、全国でシェアという部分です。現時点で333の自治体が導入しており、他自治体の事例を横展開して使うことが可能です。例えば岩手県などで実装している“被災者把握システム”も全国展開しており、その岩手モデルをコピーすれば簡単に導入ができます。
全国でアイデアが広がる・つながる~スマホ市役所の活用事例紹介。
ここで、実際に自治体でどのように使われているか紹介します。
群馬県で運用されているのは、日頃から住民の防災意識を高めるために、スマホで避難訓練を行うことができるというものです。住民からは「自宅や地域の危険性が確認できた」とか、「防災意識が高まった」などと高評価をいただいています。いつでもどこでも、手がすいている時に防災意識を高めていただくような取り組みです。
常滑市では、避難所受付で活用しています。受付時に二次元コードをかざすだけでチェックインが終了するというもので、1人あたりの受付時間は20秒まで短縮。従来の3分の1以下となり、避難者数のリアルタイム集計なども可能。住民・職員双方の負担を軽減し、避難所運営をスムーズにします。
-4_P12.jpg)
高畠町の事例は、スマートロック連携の公共施設予約です。オンラインでの施設予約時に、スマートロックのパスコードを送ることで、鍵の受け渡し・回収業務を削減しています。この仕組みは災害時に避難所においても遠隔で解錠することができるということで、自治体からの注目を集めています。
-4_P15.jpg)
そして庄内町で行ったのは、デジタル送金機能を活かして子育て支援金を届ける事業です。この仕組みも、災害発生時には災害見舞金で活用できるものとなっています。
このように様々なサービスがあり、アイデア次第で色々なことが実現できるのです。青森県むつ市のアイデアでは、AIのオプション機能を使って、災害の被害報告を受けた時に、AIが危険度を判定して優先順位をつけるといったものが完成しています。人による集約作業がなくなるため、よりコアな部分に時間を使うことができるようになります。
-4_P32.jpg)
このサービスは当然ながらセキュリティにも配慮し、管理画面はISMAP登録されたクラウドサービスを使用。個人情報も取り扱っているので、住民と自治体とのやりとりはサーバー上に残さないという、LINEヤフー社との追加規約の同意が存在しており、安心・安全に使っていただけます。
WEB上には防災機能の様々な動画も公開しているので、ぜひ「動画集 BotExpress」で検索してご覧ください。
“個人情報をあえて取得しない”避難所管理システム
セミナーの最後は、災害時の避難所管理システムを手がける事業者が登壇。導入・運用でハードルとなる“個人情報”を取得しないという独自の手法で開発されたシステムとはどのようなものなのか。活用例も含めて紹介してくれた。
【講師】 渡邊 英毅 氏
渡邊 英毅 氏
株式会社G-Place
公共イノベーション事業グループ マネジャー
プロフィール
2013年の入社以来、地方自治体の業務受託・サービス提供の企画営業職として従事、環境関連、子育て関連、防災関連など、幅広い分野で自治体職員の業務負担軽減や住民サービス向上に貢献する役務の提供・ICTサービスを企画している。
自治体からの声が独自の避難所システム開発につながった。
当社では、個人情報をあえて取得しない避難所管理システム「マイ避難所DXライト(以下、DXライト)」というものを開発しています。個人情報、マイナンバーカードとひも付けて連携させているシステムが多い中、あえてそうではないシステムを用意しました。この経緯なども含めて説明します。
当初はマイナンバーカードと連携したシステムを開発し、自治体に提案していましたが、その中でいくつかの課題を耳にしました。まず、マイナンバーカードを含む個人情報のセキュリティと端末維持問題です。
-5_P06.jpg)
個人情報を扱うとなると、セキュリティレベルを上げないといけないので、コストが高くなる。あるいは専用の回線や専用端末を用意しないといけない。そのため導入の手間がかかってしまう。また、普段使用しないシステムなので緊急時にアップデートがかかってしまって使えなかった、という話もありました。
また、研修やトレーニングが必要だという時点で、実際の緊急時にはとっさに対応できないことがあって、現場の混乱を考えると運用するのは難しいという声もありました。
一番大きな問題は、導入・維持コストです。セキュリティコスト以外にも、端末維持コスト、人的コストを考えると費用が見合わない。災害が発生しないと使わないシステムに高額な費用をかけることが財政的にできない、という話が多くありました。
-5_P08.jpg)
そこで当社は、DXライトを新たに開発しました。住民は空き避難所を見つけてスムーズに避難でき、受付も簡単。職員の手間も簡略化され、本部と現場の迅速な情報共有・把握ができ、より適切なスピードで初動対応をとることができます。位置付けとしては、二次避難所につながる一時避難所のデジタル管理システムです。
最大の特徴は、個人情報がなくても必要な情報をリアルタイムで把握できる仕組みです。実際、能登半島地震の課題としては、一時避難所周辺での避難者の状況把握がありました。大事なのは、災害直後に避難所ごとの避難者数や内訳、最低限留意すべき点を把握し、初動対応をして、二次避難につなげること。この仕組みが必要だと聞いています。
-5_P10.jpg)
次に、シンプルな画面設計です。個人情報を扱うことがないので、専用の端末と回線が一切不要。現場での混乱が最小限に抑えられるよう最低限の機能に絞り込んでいるので、訓練や研修がなくても直感的に利用できます。IDとパスワードがあればどんな端末からも利用でき、職員のパソコンやスマホで対応することも可能です。
そして、自治体に好評なのが、導入・維持コストが安価だという点です。キャンペーンも実施しており、受付管理機能も安価で導入できます。
住民と職員の双方を便利にするシステムの特徴。
このDXライトを導入するメリットについて3点ピックアップします。
1つ目、避難所情報を迅速かつ正確に把握し、適切な初動対応が可能になります。避難所の開設状況や受け入れ状況、避難者の属性や留意事項までを可視化。クラウドサービスなので、どの拠点から見てもリアルタイム情報が確認でき、齟齬や重複がありません。
2つ目は、引き継ぎ業務のデジタル化で、現場の負担を軽減するという点。住民は二次元コードを読むだけで簡単に受付を完了させることができます。職員が代理で入力することもでき、災害時の主業務に人員を割くことができます。
-5_P13.jpg)
3つ目は、住民からの問い合わせ軽減と、他サイトとの連携です。URLを連携するだけで、すでに運用中の防災サイトや防災アプリなどとも連携。スマホ1台で情報を確認することができます。
続いて、DXライトの主な機能について簡単に紹介します。
まず、職員向けの管理画面の機能です。避難所マップの一覧というものがあり、避難所の情報をマップや一覧形式で作成・管理できます。受付をした避難者の情報は自動で更新されます。クラウドなのでリアルタイムで状況確認が可能です。
避難所の受付機能もあり、データを抽出して避難所で別途管理、あるいは手動で退所管理することもできます。他にも、以下のような機能が搭載済みです。
-5_P16.jpg)
次に、住民向けの画面について。
こちらは管理画面と表裏一体になっており、避難所マップでは一番近い避難所を検索することが可能。自治体の防災サイトや防災ガイドマップなどを表示できる機能もあり、既存コンテンツとの連携も容易です。
また、避難者カードは事前登録もできますが、簡単な仕組みなので、その場で入力すればすぐに登録できる仕様です。あとは避難所ごとに発行された二次元コードを読み込むだけで自動的に受付登録が完了します。その他、以下のような機能があります。
-5_P17.jpg)
価格など、詳細については個別に案内します。デモ環境も用意しているので、気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ
ジチタイワークス セミナー運営事務局
TEL:092-716-1480
E-mail:seminar@jichitai.works

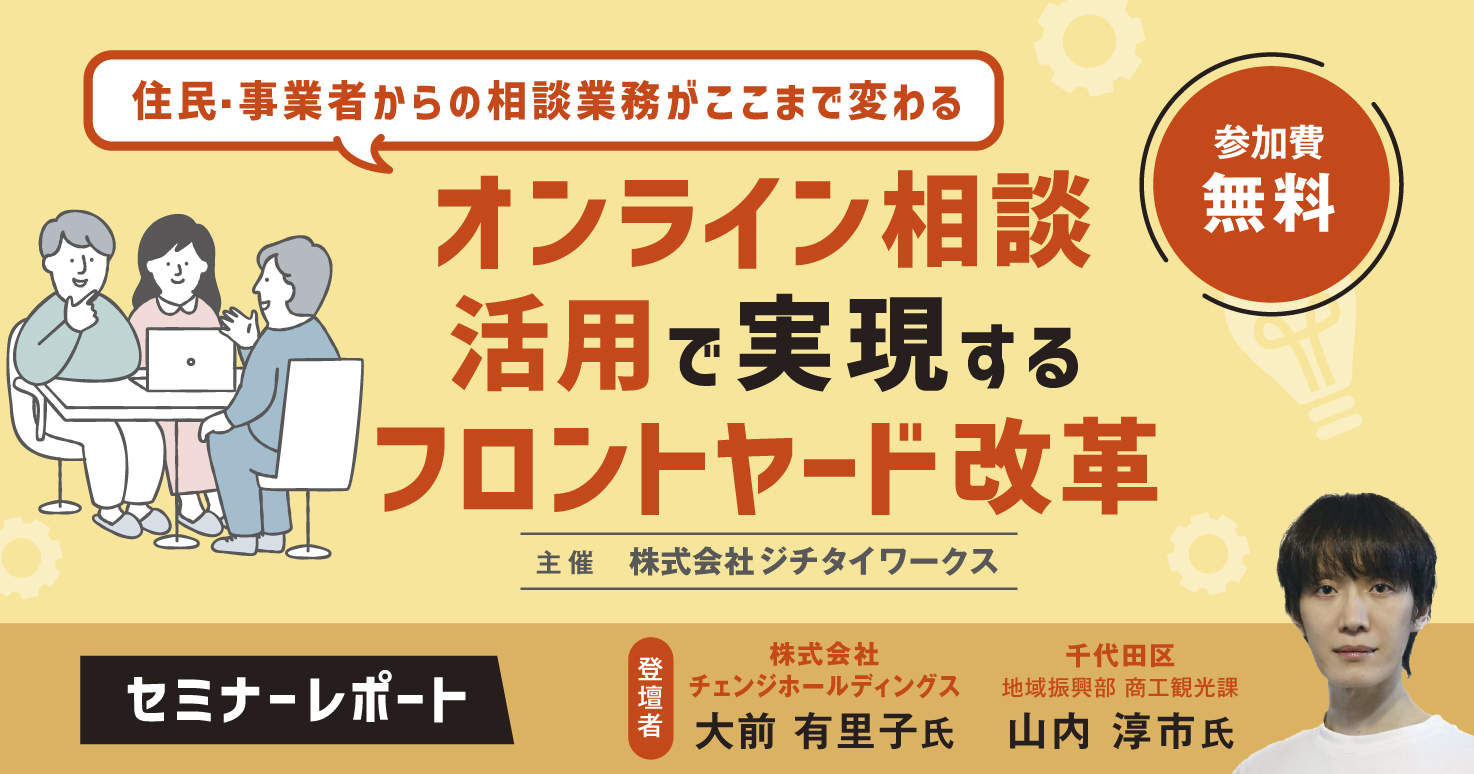




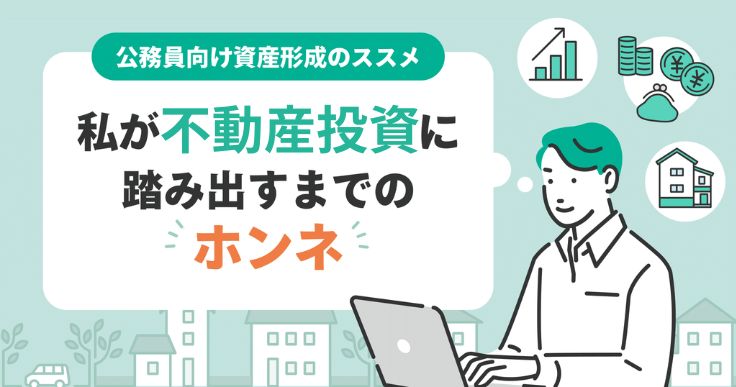
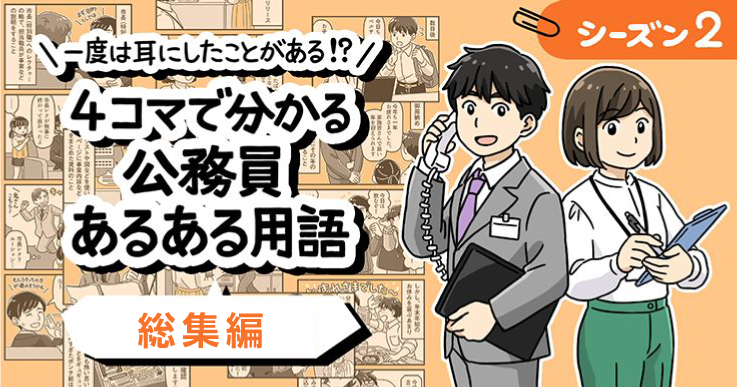







】バナー広告_株式会社ICHICO_PR.jpg)