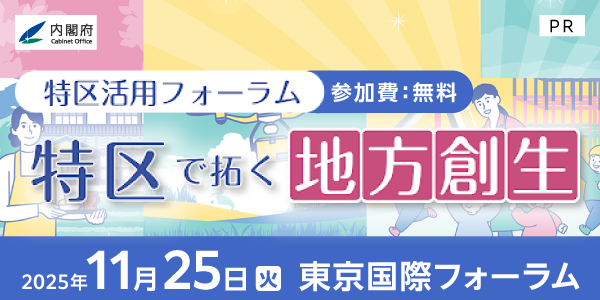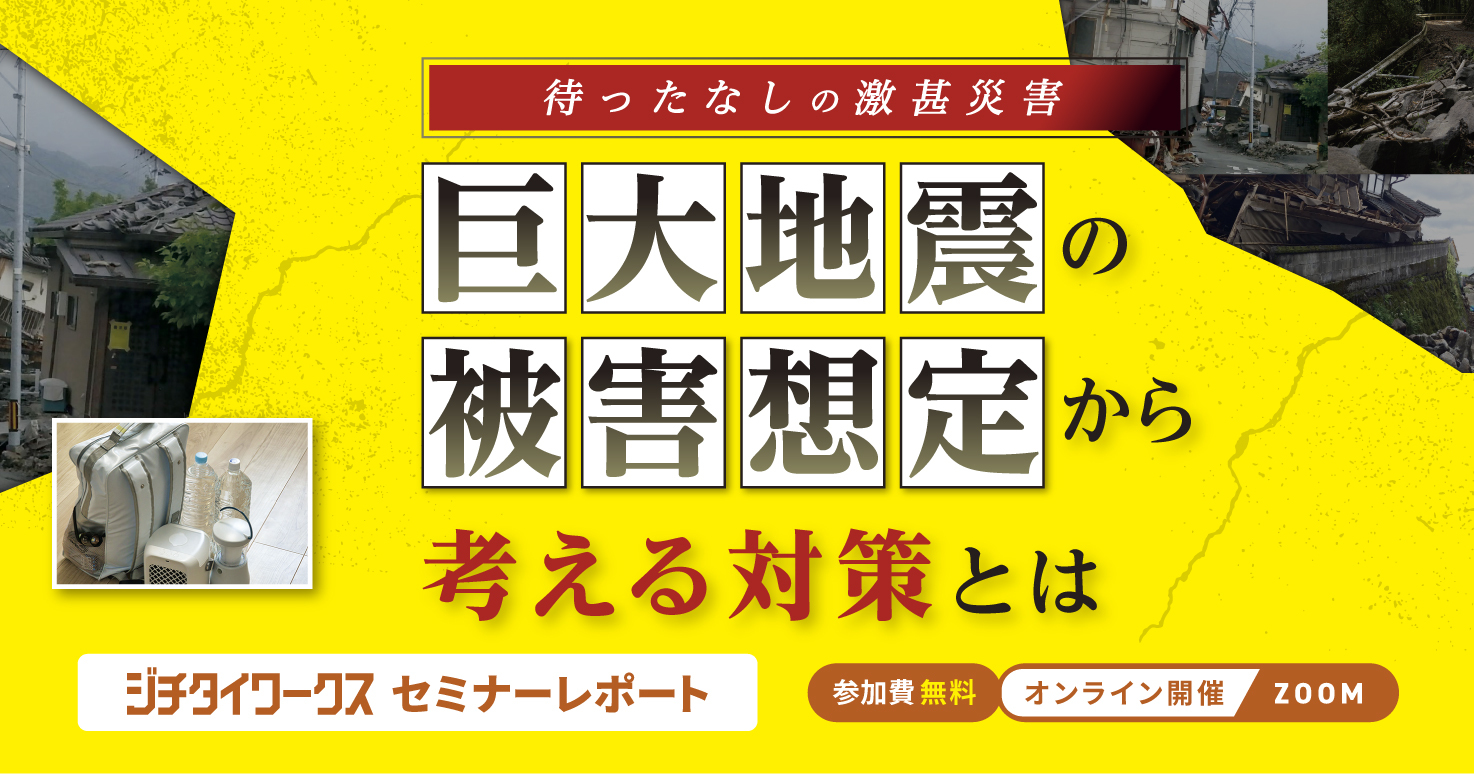
近年相次いだ大地震は、各地に被害をもたらし、傷跡を残しました。今後も、南海トラフ地震や首都直下地震などが想定されており、自治体には国や地域とも連携した対策が求められています。
本セミナーでは、こうした大規模災害への備えを中心に、災害対策の専門家や自治体の災害担当者、防災ソリューションを手がける事業者が登壇。2日間にわたり、それぞれの知見を共有しました。
概要
■タイトル:待ったなしの激甚災害 巨大地震の被害想定から考える対策とは【DAY1】
■実施日:2025年5月22日(木)
■参加対象:自治体職員
■開催形式:オンライン(Zoom)
■申込者数:175人
■プログラム:
第1部:温故知新で南海トラフ地震対策と防災庁設置を考える
第2部:宮城県など被災地の事例から見た、避難所運営の課題と防災DX事例
第3部:災害対応力の強化
第4部:防災×脱炭素で実現!避難所の住生活環境向上について
温故知新で南海トラフ地震対策と防災庁設置を考える
本セミナーのトップバッターは、防災庁の立ち上げ事業にも携わる名古屋大学の福和氏。長年にわたり災害研究を続けてきた同氏からは、「南海トラフ地震に備えるなら今しかない」という切実なメッセージが伝えられた。
【講師】 福和 伸夫 氏
福和 伸夫 氏
名古屋大学名誉教授・南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ 構成員
プロフィール
1981年名古屋大学大学院修了後、民間建設会社にて10年勤務。1991年に名古屋大学に異動。工学部助教授、先端技術共同研究センター教授、環境学研究科教授、減災連携研究センター教授を経て、2022年に定年退職。国の南海トラフ地震対策や防災庁設置に関わる議論に参画。
なかなか進まない南海トラフ地震対策と、増える避難者想定。
令和7年3月末日、当ワーキンググループにおいて新たな南海トラフ地震対策の報告書がまとまりました。あわせて、防災庁設置の検討も進んでいます。この2つの点について報告します。
-1_P01A.jpg)
報告書における被害想定は、12年ぶりに見直されました。この中で、死者数、全壊焼失棟数はほとんど減っていません。しかし資産などの被害は170兆円が225兆、避難者数も950万から1230万と増加しました。
10年前に、“今後10年間で死者を8割減、全壊焼失棟数は半減”という目標が掲げられたのですが、これが現状です。公共施設の強靭化はできたのですが、国民や経済界への取り組み促進を十分に後押しできなかったことが反省点として挙げられます。
-1_P01B.jpg)
南海トラフ地震が起きた場合は国民の約半数が被災します。そして想定のような被害が出たらリソースが全く足りないので、国家として成り立たない状況になります。南海トラフ地震対策は、地震前に勝負が決まるのです。そして勝負の要点は、国民と産業界が本気になって被害を減らす努力をするかどうかということ。被害が減れば被災者が減り、支援者が増えることになります。
また、現状の建物の耐震設計は一度の地震に対して命を守るものなので、継続使用はできません。これに対し、社会機能を維持できる社会に変えないといけない。それができないと関連死が増えることになります。
そして、国民と産業が防災行動を実践し、産業を残し、その力で行政をカバーして、官民連携で災害対応を行うしかありません。産業が回復しない場合は国際競争力を失います。全産業で産業界のどこに弱みがあるのかを見つけ、共有し、即時に対策をする体勢をとらないといけないのです。
-1_P01C.jpg)
そして医療。医療現場は外部依存が大きく、南海トラフ地震の発生後に医療継続できる病院はほとんどない。こうした社会の急所を見つけ、改善する仕組みを作らないといけません。あわせて、弱みを強みに変えるような防災ビジネスを育て、それによって被害を減らしていくことが大切です。
こうした国難を乗り越えるために、全く新しい戦略を構想し、本気で実践するための司令塔として防災庁の設置が進められているのです。
過去の教訓をもとに、いざという時への備えを。
南海トラフ地震は定期的にやってきます。短い時は90年スパンで、すでに前回の東南海地震から81年が経っています。そろそろ来てもおかしくない。そして、南海トラフ地震が発生するたびに日本の歴史は変わっています。江戸幕府の崩壊、軍国主義への傾倒といったものが代表的な例で、地震被害が体制に及ぼす影響や国力の低下が引き金の1つになっているのです。しかし、国民の多くはこういったことを“自分事”とは考えていません。
-1_P02.jpg)
1995年、阪神淡路大震災が発生し、建物が倒壊して多くの人が命を落としました。これを受けて耐震改修促進法が制定されましたが、その後の耐震化は進んでいません。国民や産業界が本気にならなかったということです。
ここで大事なことがあります。兵庫県南部地震と鳥取県西部地震、熊本地震はいずれもM7.3ですが、住宅の被害はそれぞれ10万戸、435戸、8600戸です。兵庫県の人口は鳥取県の10倍なのに、壊れた建物は200倍以上。理由は単純です。都会は人が集まるので、安全な土地が不足し、不安定な地盤にも都市が広がる。背が高い建物が密集する。そこは揺れやすい。しかし日本の建物は同じ揺れを基本に設計している。相対的に都会の建物は地震に耐える力が低下し、被害が大きくなるのです。
-1_P03.jpg)
また、能登半島地震の被害から見えてくる事実もあります。
同地震での直接死は約230人。その大半である200人ほどが輪島市と珠洲市で、古い木造建築がつぶれた圧死でした。一方、災害関連死は現時点で364人。うち、輪島市と珠洲市は170人で半分以下です。つまり、避難所の環境では後期高齢者を中心とした体の弱い方々が亡くなるということです。
南海トラフ地震で想定されている被災者人口は、能登半島地震の300倍。ということは、死者のうち直接死が約7万になる。奥能登で起きたことが、日本の半分で起きるということを意味している。能登半島地震では、国の総力を注いでも救援が進まなかったことを忘れてはなりません。
-1_P04.jpg)
まずは弱い建物を強くする。ハザードの大きなところを避ける。必要以上に人が集まらない。この3つを進めて行く必要があります。
全壊家屋に対し、行政はおおむね数千万円を支援します。一方、耐震補強は100万~200万です。本気になって耐震補強をする必要があります。地震の後では手遅れなので、発生前に耐震化する。結果としてそれがお金のかからない方法だ、ということを記憶しておいていただければと思います。
宮城県など被災地の事例から見た、避難所運営の課題と防災DX事例
第2部では、防災ツールを手がける事業者が登壇。被災自治体の課題を開発に活かした“スーパーアプリ”とは。開発の経緯から、そのツールの機能、導入メリットなどを語ってくれた。
【講師】.png) 梅本 滉嗣 氏
梅本 滉嗣 氏
ポケットサイン株式会社 代表取締役
プロフィール
日本学術振興会特別研究員DC1(京都大学 基礎物理学研究所) ダルマ・キャピタル株式会社取締役/Head of Researchを経て、2022年8月ポケットサイン株式会社を共同創業。2023年4月代表取締役に就任。理学博士(京都大学)/東京大学法学部卒。
東日本大震災の経験から生まれた避難所運営のサポートツール。
当社は、過去に大きな被災経験のある自治体と、防災サービスの構築に取り組んできました。そうした背景を踏まえ、防災DXについてお伝えします。
今後、南海トラフ地震や首都直下型地震、富士山の噴火など大規模な災害が予想されています。その備えとして防災庁の設立が進んでいますが、やはり実際に災害が起きた場合、対応の現場になるのは基礎自治体です。
-2_P08.jpg)
自治体における災害関連業務は多岐にわたります。それに加え、南海トラフ地震では1200万人の被災者が見込まれている。ここに備えるという観点から、大きな災害を経験した自治体の課題と、「もしこういうツールがあったら」といった声に耳を傾け、当社ではサービスを開発しています。
まず、宮城県と協働した取り組みです。課題は、発災後の情報共有でした。初動では、避難所と市区町村、市区町村と県など関係者の連携が必要になりますが、ここでの情報共有がうまくいかないと支援が進まない。避難所は混雑し、どの避難所に何人いるのかも分からない。避難者の属性把握もできない、という課題です。
その結果、全国から届いた支援物資を、どこにどれくらい配ればいいのか、といったことも分からない状況になる。それに対し、避難者について“誰がどこにいる”ということを中心に状況を把握するためのツールを作ろう、という結論に達しました。
このツールは防災アプリとして実用化され、すでに多くの機能を搭載しているのですが、初期に大きくフォーカスしたものが以下の3点です。
-2_P16.jpg)
これらの中で、“避難所での受付”に関して、当社のアプリにあらかじめ登録している住民については、受付で掲示されている二次元コードをスマホで読み込むだけで誰がどこにいるのか把握できる仕組みを構築。実証実験も行い、紙と比較して14倍の速さで受付が完了できるようになりました。
こうした機能を盛り込んだ後、次の課題として浮上したのが認知と普及の問題です。いくら良いものを作っても、住民が使ってくれないと意味がありません。これをクリアするために、当社では単なる防災アプリではなく、「防災スーパーアプリ」というコンセプトで製品化しました。
-2_P20.jpg)
スマホ上で、アプリ画面の下側にはアイコンが並んでいます。これはアプリ内の「ミニアプリ」として、様々な用途のものを落とし込める構造になっています。例えば地域通貨、子育て世帯への給付、市政だよりの配信などで、平時に使えるものを好みに合わせて搭載できる、という機能です。
宮城県の取り組みの一例としては、県の地域ポイントがあるのでそのアプリを入れ込み、アプリに登録をしてくれたら3000ポイントを付与するというキャンペーンを実施。現在では県民の30%を超える68万人が登録を完了しました。
熊本地震での課題も反映し、システムをブラッシュアップ。
次に、熊本市との取り組みについて紹介します。
熊本地震では、被災者の車中泊が多かったのが特徴でした。このように避難所外避難をしている方は、自治体で把握しづらくなる。しかし支援物資は避難所へ取りに来られるので、避難所ごとの物資の配分が難しくなる、ということが課題感としてありました。
同時に、災害発生後は多数のボランティアを受け入れましたが、ボランティアには災害関係の保険に入ってもらわなくてはならず、それに加えてトラブルを避けるために身元の確認ができる人を受け入れたい、という希望も。こうしたニーズに応えるため、宮城県で開発したアプリをベースに追加開発しました。
-2_P25.jpg)
まず、車中泊に対応できるよう安否確認機能を搭載しています。被災者がどこにいて、安全な状態なのかが把握でき、SOSをキャッチできる機能も追加。また、ボランティアのニーズにも対応。保険加入もできる仕組みにしました。平時においては、地域の活動参加にも使えます。
さらに、「既存の防災基幹システムと連携してほしい」という要望があったので、このシステム連携にも対応しました。災害時の情報が二重管理にならないようデータを連動させています。
この熊本市版アプリは、バス運行サービスなど地域独自の機能を組み込んで、普段使いできる防災アプリとしてすでに活用されています。
当社のアプリは、マイナンバーカードを活用して行政の方と住民の方を有事も平時も繋ぐというコンセプトのもとサービスを展開しております。現在デジタル庁より公開されている「モデル仕様書」にも対応しており、今後さらに機能を拡充していく予定です。
ちなみに、このスーパーアプリに搭載できるミニアプリは、当社のラインアップだけでも10数個あります。そのまま提供もできますし、自治体専用のものとしてOEM提供も可能です。
-2_P38.jpg)
渋谷区の事例では、すでに導入済みの防災アプリがあり、その中に当社の避難所受付機能を追加するという形になっており、こうしたニーズにも対応できます。
最後になりますが、防災アプリは本日ご紹介した避難所の受付のほかプッシュ通知、アレルギーや家族の登録、物資アンケートといった機能があり、職員が個人情報を見る際の権限設定も可能です。
このほか、避難訓練の実施支援にも対応しておりますので、お気軽にお声掛けください。
当社では「普及する防災アプリ」をコンセプトに防災スーパーアプリを展開しています。実証実験やデモ紹介なども可能なので、関心のある方はぜひお声かけください。
災害対応力の強化
自治体において、大規模地震を経験した職員は決して多くはない。その時、現場では何が起き、職員にはどういった対応が求められるのか。被災地支援などの経験が豊富な防災担当者が、防災業務の初心者編として、必要な心構えなどを共有する。
【講師]】 大月 浩靖 氏
大月 浩靖 氏
三重県 いなべ市 総務部 防災課 課長補佐
プロフィール
平成19年より防災の担当をし、これまで東日本大震災、熊本地震、九州北部豪雨、西日本豪雨など様々な被災地支援に従事。平時から積極的に地域に入り地域防災に取り組み、市民の防災意識の向上に努める。プライベートでは内閣府のチーム防災ジャパンのお世話係としても関わり、災害の被害軽減をするために、国民運動の展開を行うとともに、国民の防災意識の向上を行っている。
事前の予測がつかないからこそ、平時からの地震対策を。
今回は“災害対応力の強化”がテーマ。本セミナー参加者には初めて防災担当になった方も多いようなので、初心的なところから話していきたいと思います。
まず、風水害と地震での災害対応の違いについて。風水害では、気象庁から雨が強くなるとか、台風がいつ接近するという知らせがあるので、職員参集の連絡をするなど、時間軸を見ての事前対応ができます。通信手段が確保できれば安否確認もある程度可能で、タイムラインを活用しながらの災害対応になります。
-3_P02.jpg)
しかし地震の場合は、こうした事前対応が不可能です。しかも被害が見えにくい。地震災害で倒壊家屋がなかったから死者もないという速報が出ることがありますが、実は家具が倒れてきて圧死されている可能性もあるのです。
あとは職員安否確認も難しく、全てのインフラが使えなくなることもあります。風水害に比べて、地震対応は不慣れな自治体が多いというのが実情です。
こうした災害対応においては、それぞれの役割があります。よくあるのが、防災担当者が外部からの電話対応をするというシーンですが、これは災害の規模が大きくなるほど好ましくありません。防災担当はオペレーションをしなくてはならないので、電話対応は別の職員が担うようにする。場合によってはコールセンターを準備することも必要になるでしょう。
-3_P03.jpg)
さらに、災害の前半部分は防災や土木担当者が奔走する場面が多いのですが、後半になると福祉が担当する部分が多くなります。もちろん他の部署にも関わってくるので、全庁体制という前提で、普段から地域防災計画の内容を把握しておくことが大切です。
そうした活動のキーワードが“大風呂敷から小風呂敷へ”。災害発生時、混乱の中で被害の全体を見積もるのは困難です。そこで「多分大丈夫だろう」と考えたり、支援の要請が遅れたりすると、さらに大混乱を起こします。情報も集まってくるし、自治体からの発信も求められるからです。
-3_P07.jpg)
やはり事態を過小評価するのではなく、過大評価をしておいてから実際の規模に合わせて縮小していくことが大切。マンパワーも初動の時に多く集めておいて、被害がなければ縮小していくようにしましょう。
“平時にできないことは災害時にもできない”と心にとどめておこう。
次のポイントは、スムーズな情報手段の構築です。発災後は情報がとめどなく入ってきます。それを、とりあえず付箋に書いて関係者に渡したり、ボードに貼ったりしていくと、最終的に対応済みなのか未対応なのか分からなくなり、管理が行き詰まります。
まずは書式の統一が必要。「災害情報受付票」を作り、平時から職員に周知しておきましょう。その上で役割を明確化し、作業工程をレイアウトしていくことが大事です。
-3_P08.jpg)
また、地域を巻き込むことも忘れずに。地域には様々な知見を持つ人がいて、モノや施設があります。そうした資源をうまく活用して、訓練などを進めていきましょう。
ここで重要なのは、初めから完璧な活動を目指さないこと。例えば、勢いのある自治会長などが一気に進めてしまうと、次の人がやりにくくなるといったことも起こりがちです。この点は留意しておいてください。若い世代を地域の中で活動させる工夫などもあった方がいいかもしれません。
-3_P10.jpg)
さらに、地域という視点でいうと、“平時の困り事は災害時も困り事”です。例えば、平時にごみ出しができない高齢者がいたら、その人は災害時にも家の中を片付けられない。これに対し、要支援者の困り事を平時から支える仕組みがあれば、災害時は乗り越えられるはずです。いざという時に、人と人をつなぎながら、ボランティアの力も借りつつ対応をしていく。こうした仕組み作りは平時から進めておきましょう。
BCPでの代替え施設の事前把握も必要です。ちなみに、自然災害以外でも代替え施設が必要になる場合があります。例えば白岡市の事例では、火災で庁舎の1階部分が使えなくなり、代替え施設が活用されました。
このように、普段から考えておくことが大切で、実際に代替え施設を使うことになった場合は、「どの業務ならできます」という積極的な情報発信も求められます。白岡市では、こういう地域・住民に対して何の業務は取り扱いできる、ということを発信されていました。
-3_P17.jpg)
今回の話をまとめると、上記のようになります。
そして、忘れてはいけない大事なこととして、“自分自身が被災しない”。そのためにも、普段から家具の固定や、耐震化、備蓄ということを進めておいてください。家族を守ることも大切です。こうしたことを踏まえて、いざという時、すみやかに登庁できる準備が大切だということを念頭に災害対応を。そして、平時から人とのネットワークを構築して、防災に関しても普段からつながっていくと心強いかと思います。
防災×脱炭素で実現!避難所の住生活環境向上について
DAY1のラストは、GX事業を手がける事業者が登場。災害時のレジリエンスをテーマに、自立エネルギー型避難所を構築する意味や、それに係るコストを抑える方法など、これまでの取り組みをもとにした様々な情報を提供してくれた。
【講師】 度曾 洋徳 氏
度曾 洋徳 氏
株式会社アイネック 代表取締役CEO
プロフィール
1996年より電気、通信業界に従事、2022年代表取締役CEOに就任。「電気に関連した環境ソリューション事業を通じて、持続可能な社会の実現に貢献すること」を使命とし、地方自治体に寄り添い、電気を通じた環境ソリューションでまちの価値を高めるために奔走中。
国の方針もあり、全国で進んでいる体育館の空調導入。
当社は、自治体向け省エネ・再エネソリューションを中心として、GX全般の事業に関わる業務をしている会社です。電気に関連した環境ソリューションを使って、公共施設などの省エネ・再エネに取り組んでおり、現時点では、2万2000施設を超える施設を担当しています。
この領域に関しては、国が令和6年11月に、避難所となる体育館の空調整備についてペース倍増を目指して計画的に進めるということを閣議決定しました。これを受け、当社も体育館への空調導入について色々と支援しているところです。そして、ここで提示したいのが「導入手法は大丈夫ですか」という点です。
-4_P06.jpg)
体育館の空調には、主に3つの導入方法があります。電気、都市ガス、LPガスです。それぞれに強みがあり、レジリエンスという視点でも異なる特徴を持つので、一長一短なのです。
こうしたことを鑑みながら、災害時にどんな方法が適しているかを検討しつつ機器を選択することが大切です。そして同時に、空調だけで避難所は機能するのか、ということも考えなくてはなりません。
-4_P08.jpg)
例えば、空調が使えたとしても照明はつくのか、携帯電話の充電は不要なのか、食事を温めるのはどうか、といった問題があります。空調だけでなくインフラを備えなければ避難所として機能しない、と我々は考えているのです。
LPガスを活用し、災害時に自立できる避難所をつくる。
ここまで語ってきた防災とは違う文脈になりますが、脱炭素に関する様々な施策についても国は方向性を定め、自治体もそれに向けて取り組んでいると思います。太陽光、EV、LEDなど様々な事業が進められていますが、当社ではそれを全てつなぐ提案を進めています。つまり脱炭素事業と防災のレジリエンス強化を同時に実現するということです。具体的には、以下のような導入フローで進めていきます。
-4_P09.jpg)
こうしたことを自治体と一緒に進めていくと、事業は点から面へと変わっていきます。これがとても大切なのです。この面で行う事業から何が生まれるかというと、自立エネルギー型の避難所ができあがります。
平時には、太陽光で発電した電気を学校で使う。そして災害が発生して停電になったらすぐに切り替わって、太陽光もしくは蓄電池の電気が避難設備として選定されたものだけに供給される。この仕組みで使う容量をキープできます。
-4_P10.jpg)
空調はLPガスを使ったものなので停電しても自立で動く。照明やスマホ充電などにも電気を供給できます。公用車のEV化が進んでいれば、EV車から電気を抽出して避難所に送ることが可能です。
こうした仕組みを導入する際、一番の課題となるのはイニシャルコストだと思います。もちろん補助金や交付金なども活用しますが、太陽光設備の場合は平時の発電によって従来の電気代を抑え、その差額分をイニシャルコストに充当することが可能。この手法であれば、予算取りをせずに導入する可能性が開け、導入期間も短縮できます。
-4_P13.jpg)
当社は、こうした事業を通じて地域経済の活性化に寄与する、ということを目標に掲げています。すでに多くの自治体と取り組みを進めていますが、その中で被災者が置かれる環境の格差をなくすという目標もあります。
例えば災害で停電になり、あるまちの避難所は夏でも涼しく冬は暖かい。温かい食事も提供されていて電気も明るいという状況なのに対し、隣のまちでは夏は暑く冬は寒い。食事も冷えている……といった、避難者の環境に格差があってはならないと思うのです。
様々なアドバイスを用意しているので、まずはお問い合わせください。
自立エネルギー型避難所に関するQ&A
Q:リースで太陽光発電設備などを導入した場合、機器のメンテナンスはどのように運用されますか。
A:通常、自治体が工事発注で入れる場合は、1~2年の保証しか受けられない状態で設備を導入されており、メンテナンスはついていません。リースの場合はリース期間、例えば17年とか20年といった契約期間中の発電量モニタリングや、設備の維持も契約に盛り込んでいます。空調などについても同様で、期間中の消耗品交換も契約に盛り込むことができます。
Q:学校体育館以外の施設での事例はありますか。
A:当社における他自治体の例では、災害対策本部があります。災害時には重要な機能を果たす場所ですが、全自治体の災対本部が災害時に電気や空調が使える状態かというとそうではありません。そうした場所での導入事例はあるので対応も可能です。
Q:補助金を活用する場合、自治体が申請書類の作成などを行うのですか。
A:補助金申請では様々な資料作成があり、リース契約に盛り込んだ形で対応します。提供いただくデータなどの取りまとめ作業はありますが、補助金申請に慣れていない方でも、リース会社含めて対応します。
お問い合わせ
ジチタイワークス セミナー運営事務局
TEL:092-716-1480
E-mail:seminar@jichitai.works

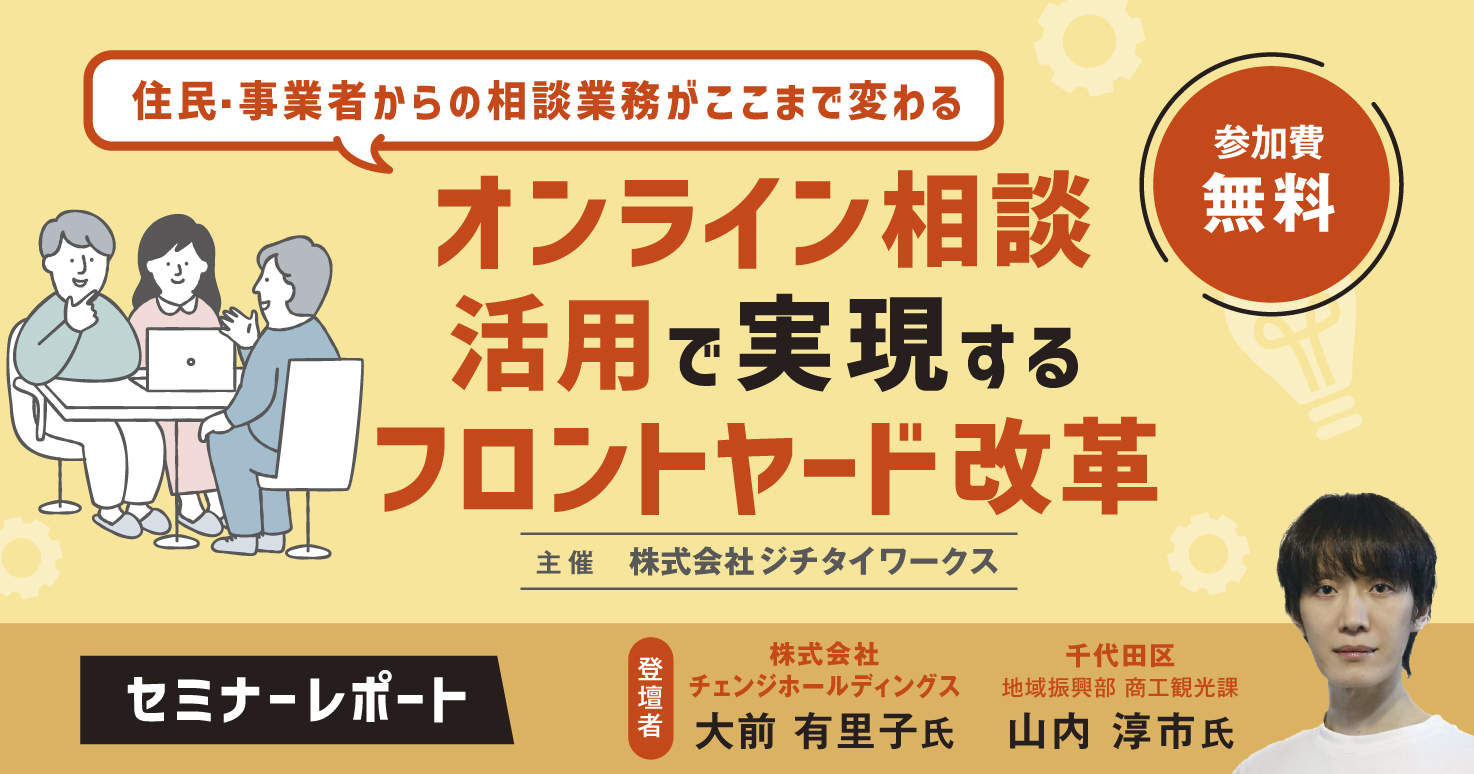




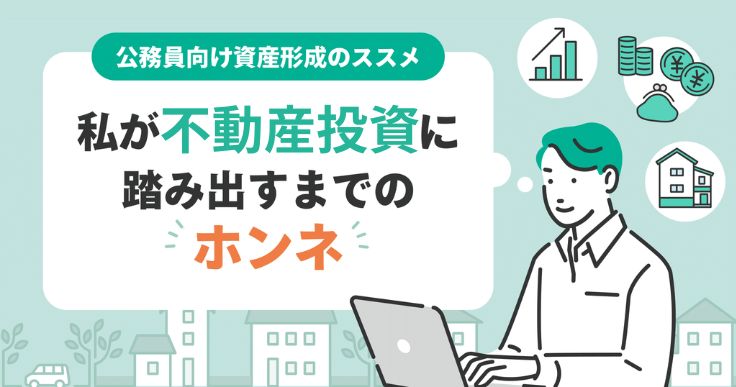
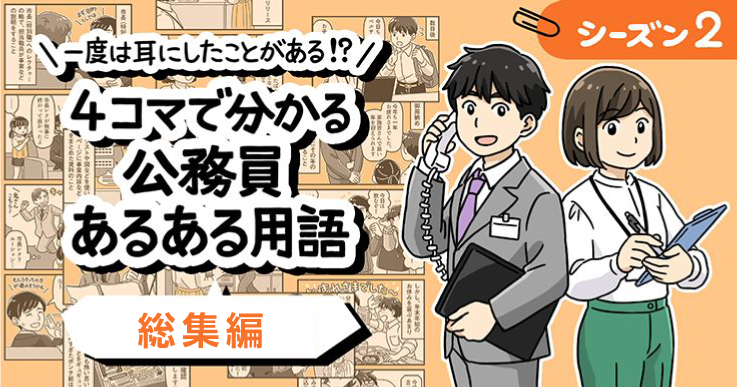







】バナー広告_株式会社ICHICO_PR.jpg)