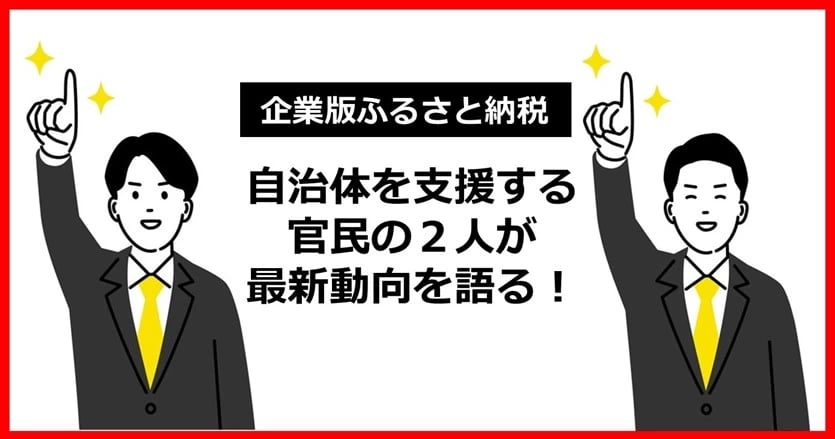公開日:
オンブズマンが必要とされる理由を解説!制度の成り立ちと役割も理解しておこう。

オンブズマンとは、行政活動における不正や不当な行為を、中立的な立場から監視・調査し、必要に応じて告発する役割を担う第三者のことだ。
19世紀初頭に「オンブズマン制度」としてスウェーデンが初めて設置。行政に対する住民の苦情を受け付け、迅速かつ公正に問題解決を図る仕組みとして発展してきた。日本では、昭和36年に総務省が「行政相談委員制度」として国のオンブズマン制度を開始。
平成2年に初めて東京都中野区および神奈川県川崎市に設置されて以降、地方自治体において本格的に導入が開始された。本記事では、公正な自治体運営を支えるオンブズマン制度の意義とその役割について、分かりやすく解説する。
【目次】
• オンブズマン制度とは?
• オンブズマン制度の歴史
• オンブズマン制度を取り入れるメリット
• オンブズマン制度の事例
• 中立的な立場で住民の苦情を調査!オンブズマン制度で行政の信頼性を高めよう
※掲載情報は公開日時点のものです。
オンブズマン制度とは?
オンブズマンとはスウェーデン語で「代理人」のことである。住民の代わりに行政の問題点を調査し、改善につなげる制度がオンブズマン制度だ。制度が必要とされる背景と、「公的オンブズマン」「市民オンブズマン」との違いを解説する。
オンブズマン制度が必要とされる背景
オンブズマンは、行政を監視し、住民の行政に対する苦情を調査し解決する。
オンブズマン制度が存在することで、透明性のある行政が行え、住民から信頼される自治体づくりができるのだ。
公的オンブズマンと市民オンブズマンの違い
日本におけるオンブズマン制度は、諸外国において「公的オンブズマン」が市民の代理人として行政への苦情を受け付け、是正を促す役割を果たしているのに対し、日本にはそのような制度がなかったことから始まっている。
そこで、「市民自らがオンブズマンとなり、行政の不正や腐敗を追及していこう」という考えが生まれ、この理念の広がりとともに、全国各地で「市民オンブズマン」を名乗る団体が設立。行政への監視活動が市民レベルで展開されるようになった。
その後、自治体が住民からの苦情を中立・公正な立場で処理するため、「公的オンブズマン」を条例にもとづいて設置する動きが徐々に進んだ。ここでは、公的オンブズマンと市民オンブズマンの違いを確認しよう。
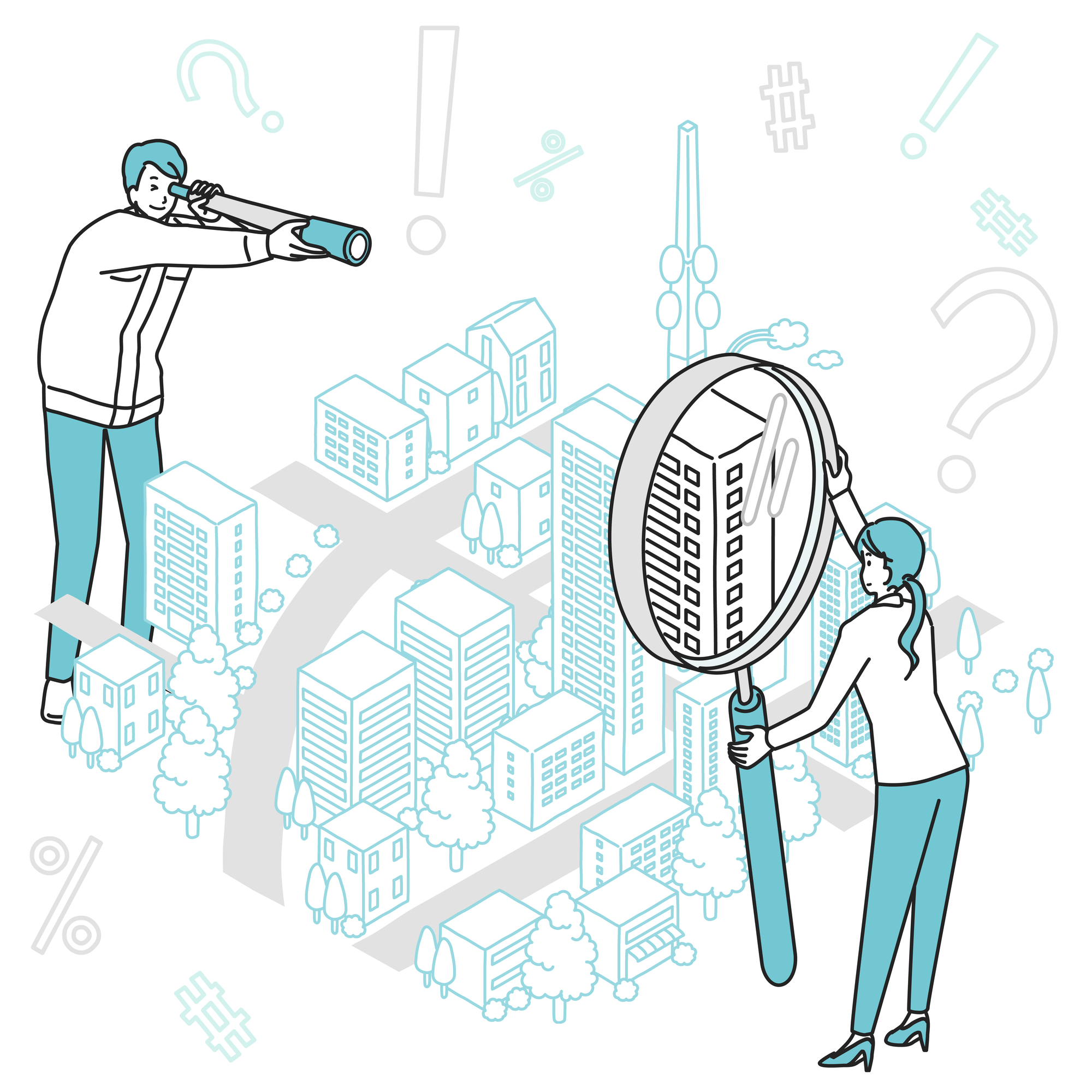
公的オンブズマンとは
公的オンブズマンは各自治体の条例にもとづき設置されており、運営費用は税金で賄われる。オンブズマンとして活動するのは、自治体の長や議会が任命した有識者(弁護士・元裁判官・大学教授など)である。
活動内容は、住民の苦情申し立てを受け付け、その内容を中立な立場で調査し処理することである。なお、活動に応じて相当額の報酬も受け取る。
市民オンブズマンとは
市民オンブズマンは任意団体であり、法令や条例にもとづき設置されたものではない。運営費用はカンパや会費で賄われ、報酬なども特に発生しない。
団体に加入すれば誰でも市民オンブズマンとして活動ができる。市民オンブズマンは行政を監視し、不明点があれば情報開示を求め、内容によっては住民監査請求や住民訴訟を行い、行政の改善を促す。
参考:全国市民オンブズマン連絡会議「よくある質問」
オンブズマン制度の歴史
オンブズマン制度の始まり、そして、どのようにして日本にも広がってきたかを確認しよう。
スウェーデンで生まれ西欧諸国に普及
オンブズマンは、スウェーデンで国外にいる国王が自分の代わりに裁判官や役人を監視する人物を置いたところから始まったものである。その後、同国で19世紀初頭に行政監視機関を置く統治法が制定されたことが、現在のオンブズマン制度の由来とされている。
その後、オンブズマン制度は行政に対する苦情救済を目的として、デンマーク、イギリス、フランスなどのヨーロッパ各国やニュージーランドに普及した。

昭和36年「行政相談制度」として導入
昭和36年に総務省が開始した「行政相談制度」が日本で初めてのオンブズマン制度とされている。その後、平成2年に川崎市が「一般オンブズマン」、東京都中野区が「福祉オンブズマン」を初めて導入し、全国の自治体に広がっていった。
現在では、政府内や多くの自治体にオンブズマン制度が存在し、行政とは別の立場で、市民の苦情を受け付け、調査処理を行っている。
政府内
政府のオンブズマンにあたるのは、総務省内にある「行政評価局」「行政相談委員」「行政改善推進会議」である。それぞれどのようなものか押さえておこう。
行政評価局:
行政上の課題を解決するため、各府省の業務状況を実地で調査し、改善が必要な場合は勧告を行う。その他、各府省が行う政策評価の点検、行政に関する苦情の受け付けも行う。
行政相談委員:
総務大臣が委嘱した民間有識者約5,000人。全国に配置されており、無報酬で国の行政活動に対しての苦情や相談を受け付け、改善申し入れなどを行う。
行政改善推進会議:
行政運営や制度の効果的な改善を目的として、民間の有識者が意見を交わすために行われる会議。
自治体
自治体が設置した「公的オンブズマン」、市民が自発的に活動する「市民オンブズマン」以外に次のようなものがある。
福祉オンブズマン:
福祉分野のみが対象。福祉サービスに対しての苦情を公正に調査し処理する。東京都中野区が初めて導入した。
オンブズパーソン制度:
公権力の監視を行い、住民の意見を行政に的確に反映するための制度。議会や自治体の長から任命された民間人が就任する。
上記以外にも、人権に関する苦情などを受け付ける「人権オンブズマン」、議会の問題点を受け付ける「議会オンブズマン」など、特定の分野に特化したオンブズマンを設置する自治体もある。
オンブズマン制度を取り入れるメリット
自治体がオンブズマン制度を取り入れるメリットを確認しておこう。
住民の不満や課題、ニーズを把握しやすくなる
オンブズマン制度が存在することで、住民の不満やニーズ、そして行政の課題が把握しやすくなる。また、課題改善も迅速に進められる。
行政の透明性を高め、住民との信頼関係を築くことができる
オンブズマンは中立な立場で、課題を調査・解決するため、行政の透明性を高める効果がある。透明性が高くなると、住民との信頼関係も築きやすくなるだろう。
行政サービスの向上につながる
オンブズマンには、住民が感じている行政の課題点が寄せられる。住民が何に対して不満を抱いているかが分かるため、行政サービスの向上につなげることができる。
オンブズマン制度の事例
オンブズマン制度を導入している自治体の中から、神奈川県川崎市、東京都多摩市、北海道札幌市の事例を紹介する。どのように運用されているか見ていこう。
神奈川県川崎市:日本で初めてオンブズマン制度を導入
 前述の通り、川崎市は日本で初めてオンブズマン制度を導入した自治体だ。市の組織内に「川崎市市民オンブズマン事務局」を設置し、市政に関する苦情などを受け付け、調査・改善に取り組んでいる。
前述の通り、川崎市は日本で初めてオンブズマン制度を導入した自治体だ。市の組織内に「川崎市市民オンブズマン事務局」を設置し、市政に関する苦情などを受け付け、調査・改善に取り組んでいる。
また、市内の小・中学校、児童養護施設で「人権オンブズパーソン子ども教室」を実施し、若年層に相談窓口の存在を知らせる活動も行っている。
なお、改善に取り組んだ課題だが、「公園および付近の広場での喫煙等について」「子どものいじめや虐待について」といった市民の日常生活に直接関連するものから、「市職員のふるまいについて」といった行政の問題までと非常に幅広いのも特徴だ。
 関連記事はコチラ
関連記事はコチラ
▶【神奈川県川崎市事例】
日本の自治体初のオンブズマン制度で市民に開かれた市政を目指す。
東京都多摩市:福祉オンブズマンから総合オンブズマン制度に移行
 東京都多摩市では、平成12年度に福祉オンブズマン制度を設置した。全国でも例が少ない民間福祉事業者への苦情受け付けも行うなど、一定の効果を出した後、平成22年度に全分野対象の総合オンブズマン制度へと移行した。
東京都多摩市では、平成12年度に福祉オンブズマン制度を設置した。全国でも例が少ない民間福祉事業者への苦情受け付けも行うなど、一定の効果を出した後、平成22年度に全分野対象の総合オンブズマン制度へと移行した。
多摩市の総合オンブズマン制度の場合、苦情申し立ては個人・団体・住所・年齢・国籍の制限なく誰でも可能だ。面談・ファックス・メールで苦情の概要を確認し、その内容にもとづき、調査が行われる。調査結果は文書で返答され、改善すべき事象があった場合は是正勧告が行われる。
北海道札幌市:活動状況を報告し公表、冊子でも見ることができる
北海道札幌市のオンブズマン制度は平成12年に条例が制定され、翌年の3月に設置された。オンブズマンとして任命されているのは大学教授や弁護士で、市の業務に関する苦情の受け付けはもちろん、自ら市政の監視および発見した課題の調査も行っている。
札幌市のオンブズマンの活動状況は、札幌市役所ホームページ内で公開されるだけでなく、毎年「札幌市オンブズマン活動状況報告書」という冊子にまとめられ、市役所などで配布もされている。
中立的な立場で住民の苦情を調査!
オンブズマン制度で行政の信頼性を高めよう
オンブズマン制度は、住民の苦情を受け付け、中立的な調査を行う制度だ。公平に調査を行い、問題点を是正することで、行政の透明性を維持できる。
また、住民が行政のどの部分を問題と感じているかが明確になり、住民サービスの充実にもつながる。住民からの信頼度を高めるためにも、オンブズマン制度を十分に活用する方法を考えていくべきといえるだろう。