公開日:

様々な行政課題の解決を目指し、民間の技術やノウハウを活用する官民連携の取り組みが各地で行われている。実際に官民連携を進める行政職員は民間事業者とどのようにつながって連携してきたのか……。ジチタイワークスVol.30では、「官民連携推進特集」として様々な連携事業に取り組み、実践経験を積んだ“つなぐ”達人3人にインタビュー。
そのうちの一人、神奈川県川崎市 上仲 俊輔さんには、連携の意義や地域・庁内外とのつながり方など、官民連携に取り組む上での基本となる心構えを伺ったが、本記事では、ジチタイワークス本誌に掲載できなかった貴重なこぼれ話をお届けする。
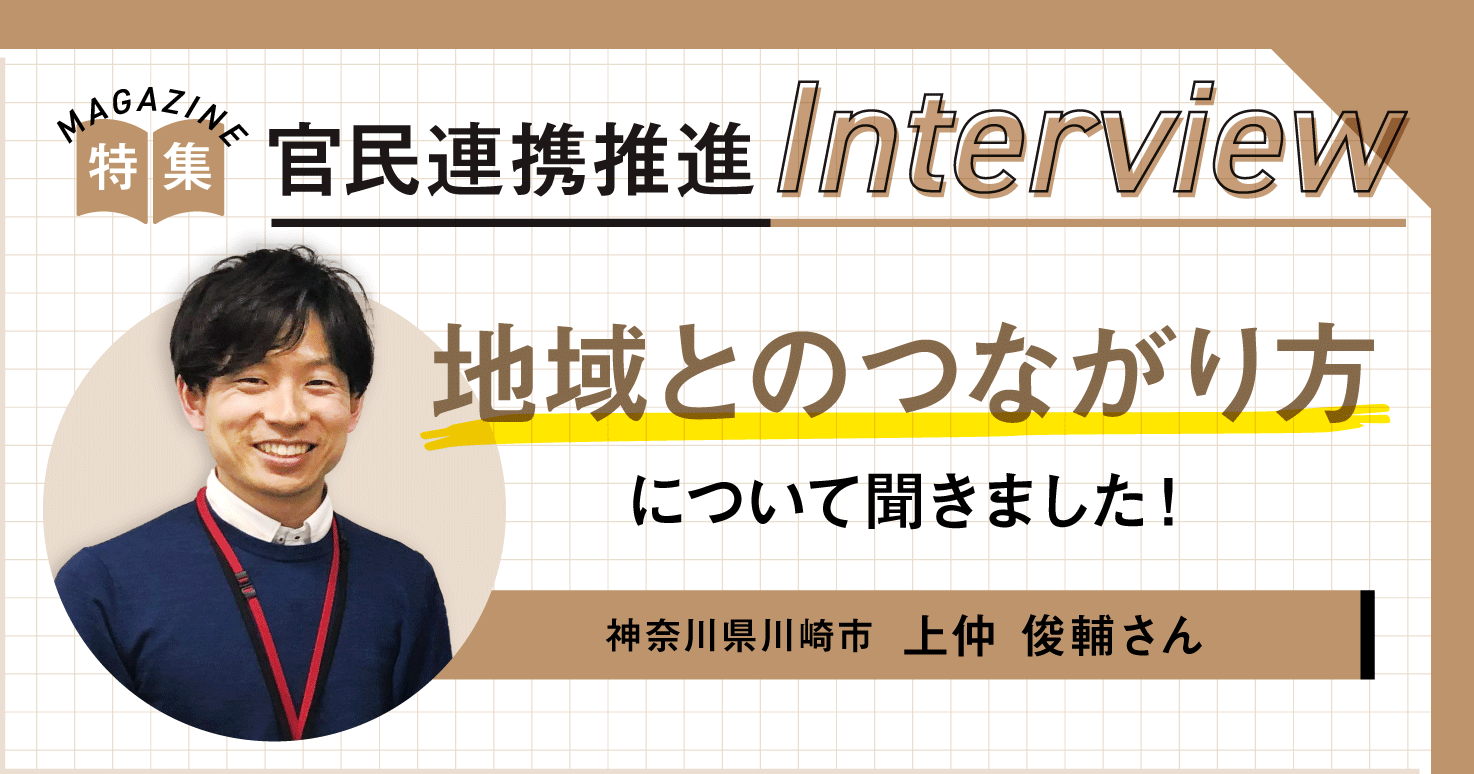 ジチタイワークスVol.30「官民連携推進特集」本編はコチラ
ジチタイワークスVol.30「官民連携推進特集」本編はコチラ
【上仲 俊輔さん】“つなぐ”達人たちに聞く!官民連携に踏み出すヒント。
 お答えいただく方
お答えいただく方
神奈川県川崎市(かわさきし)経済労働局 観光・地域活力推進部
上仲 俊輔(かみなか しゅんすけ)さん
▼プロフィール
2007年に川崎市へ入庁。農商工連携をはじめ、様々な分野にて官民連携事業に従事。プライベートでは都市経営プロフェッショナルスクールに通い、連携の方法を基礎から学ぶ。
商店街支援や商業者の支援、農商工連携、ベンチャー企業の支援など、さまざまな官民連携を経験し、現在は観光部門でインバウンド事業などを担当しています。
勉強を始めた大きなきっかけは、商店街や農家の方と接していた経験にあります。商売や仕事に一生懸命取り組んだ上で、さらにまちを良くしようと考えている方と出会ったときに、公務員である自分はどうだろうと考えました。地域にとって何が課題で、どうすれば本当に解決できるかという議論の場で、既存の施策メニューを紹介することぐらいしかできずにショックを受けたこともありました。「もっと勉強して、本気の人たちと対等に会話できるプロにならないと良い施策は考えられない」と一念発起して、都市経営プロフェッショナルスクールに通いました。
スクールでは、まちを経営する感覚を養うことを最初に教わりました。自治体を会社と見立てて、どう経営をして行けば良いかという考えることで、より広い視野で地域の課題を見極めるノウハウを学ぶのです。通学中は課題のレポートやスクールでの学びをnoteにまとめていましたが、勉強になるのはもちろん、読んでくれた方との新しいつながりもできました。自ら情報発信する重要性も学びましたね。
より広い視野で、物事を考えられるようになったと思います。
連携では、単にニーズのある者同士を引き合わせることがゴールではないと思うんです。例えば、地元の農産物で加工食品をつくりたいという事業者がいる場合、農産物の品質が変わらなければ、規格外で安く仕入れた方がコストを抑えられます。一方、農家としては大切に育てた農産物なので、規格外よりも正規品を適正な価格で販売することが望ましい。そのためマッチングの際には、こうした業種間のギャップを調整する必要があります。さらに「地域のどんな課題にアプローチできるか」という視点も意識してもらうことで、ビジネス上の利益だけでなく、さまざまな地域課題の解決にもつながる、異業種のコラボレーションになり得るんです。
例として、「Made in Local(地元産)」をコンセプトとする川崎市のベーカリー「Len」と地元農家とが連携した商品開発を、約3年前にお手伝いしたのですが、現在はさらに取組が進化しています。「FARM TO GIFT(農園からの贈り物)」という地元農産物を主役にした商品(パンやスイーツ)が誕生し、そこには農家さんの想いが製法やパッケージに込められています。

その洗練されたデザインが農家のブランディングにつながっていて、農家さん自身も近所や知り合いに紹介するなど、商業と農業がお互いに価値を高めあう効果が生まれています。こうした取組が継続すると、地元のお店や農家を応援してくれる方が増え、地域経済が循環していくので、結果として産業が強くなり、まちの魅力も高まるのだと思います。
庁内外のつなげ方について聞きました!
3人目の達人に続く
このシリーズの記事
▶ 1人目の達人:兵庫県神戸市 長井 伸晃さん/官民連携の意義について聞きました!
▶ 長井さんSideStory/課題発見は役所の外で!身に付いたスキルは「取材力&妄想力」
▶ 2人目の達人:神奈川県川崎市 上仲 俊輔さん/地域とのつながり方について聞きました!

![【連載】地方創生の新たな展開-岸田内閣審議官に聞く[下]新たな政策の「5本柱」とは。](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fstatic.jichitai.works%2Fuploads%2Farticles%2F2025-12-10-17-54-13_2510-shingikan-03-737x387.webp&w=256&q=85)









