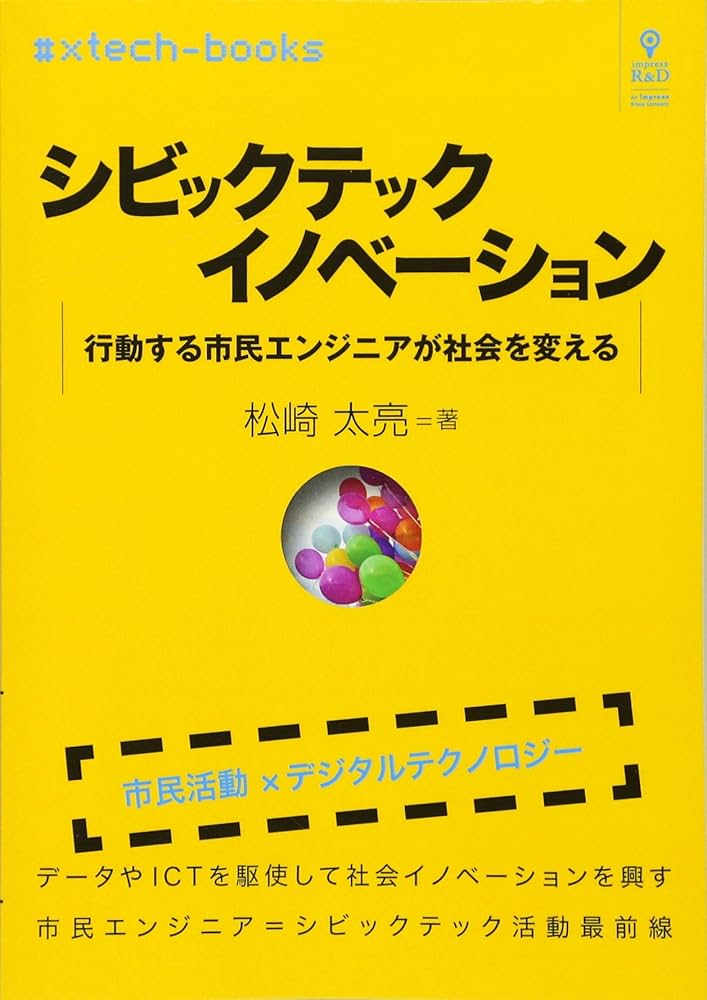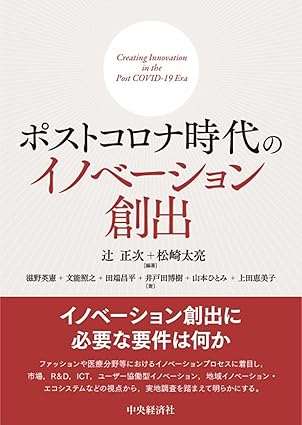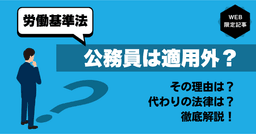監修
監修
松崎 太亮(まつざき たいすけ)さん
神戸国際大学 副学長 経済学部教授 (PhD.応用情報科学)
デジタル庁オープンデータ伝道師
総務省地域情報化アドバイザー近畿地区代表幹事
元神戸市企画調整局 ICT 連携担当部長
1984年 神戸市採用
1997年 大阪大学大学院国際公共政策研究科前期博士課程終了
2004年 文部科学省「学習素材のデジタル化連携促進事業」連携支援委員
2006年 国立教育政策研究所 教育情報ナショナルセンター運営会議委員
2007年 文部科学省委託事業「ICT 活用授業の効果等調査」企画評価委員
2009年 JICA「トルコ国防災教育普及支援プロジェクト」専門調査員
2012年 総務省・国会図書館東日本大震災アーカイブ利活用WG推進座長
2012~14年 武庫川女子大学文学部非常勤講師(図書館経営論)
2016年~総務省地域情報化アドバイザー(近畿地区代表幹事)
2019年~ デジタル庁「オープンデータ伝道師」
2021年~神戸国際大学経済学部教授
2024年 神戸国際大学 副学長
シビックテックとは
シビックテックはシビック(市民)とテクノロジー(技術)を組み合わせた造語で、市民がデジタル技術を活用して、自分たちの生活に関わる社会的な課題の解決を目指す取り組みのことだ。
デジタル技術が日本国内においても急速に発展し、国や自治体による公共データの開放(オープンデータ)とデータ利活用を進めていることから、市民が自らの手で必要なサービスを行政と共に創るシビックテックを行政側も後押ししていくことが求められている。
シビックテックの歴史
シビックテックは2000年代のアメリカで始まり、オバマ大統領が平成21(2009)年に「透明性とオープンガバメントに関する覚書」を公表したことで大きな転換期を迎えた。
オバマ政権は「開かれた政府(オープンガバメント)」の構築を表明し、政府の透明性、市民の参画、官民の連携という3つの原則にもとづき、政府や自治体が保有する情報を整理・公開した。
行政は、インターネットを通じて市民がその情報を活用できるオープンデータサイトの構築を推進した。このムーブメントをきっかけにアメリカでは、自治体や公的機関が保有する情報を市民が利用できるよう公開する流れができ、市民参加型の行政・政府へと変わっていった。
アメリカではシビックテックの活動を推進するコミュニティが登場している。代表的なシビックテック・コミュニティ「Code for America(コード・フォー・アメリカ)」は、平成21(2009)年に設立された非営利組織だ。自治体や地域のニーズに応じて、全米中から応募してきたITエンジニアを一定期間派遣し、課題を解決するフェローシッププログラムを実施している。
コード・フォー・アメリカのミッションは、人間中心の視点から行政サービスをシンプルで効果的、かつ誰でも簡単に使えるものにすることにある。IT技術と市民の力を活用して、行政と協力しながらアメリカ全体をよくしていこうという取り組みだ。
日本でのシビックテックのはじまり
.jpg)
シビックテックのムーブメントはアメリカから世界中に広がり、日本においても2010年代にシビックテックの取り組みが始まった。
平成23年3月「シンサイ・インフォ(sinsai.info)」
日本のシビックテックの先駆的な取り組みとしては、平成23年3月の東日本大震災時に開発されたサイトである「シンサイ・インフォ(sinsai.info)」が代表的だ。被災された地域の人々のために、ボランティアの有志の手によって震災の4時間後に公開された。
シンサイ・インフォは被災状況や避難所の場所、安否情報などが登録されており、地図上でその情報の位置を見ながら閲覧できる復興支援プラットフォームであり、その後の自然災害からの復旧・復興支援のモデルとなった。
平成25年「Code for Japan」設立
平成25年には非営利団体「Code for Japan(コード・フォー・ジャパン)」が設立された。デジタル技術を活用して地域課題の解決に取り組むシビックテック・コミュニティで、「ともに考え、ともにつくる社会」を目指して、市民主体で課題解決を行うコミュニティづくりの支援や自治体への民間人材の派遣などを行っている。
令和2年3月「新型コロナウイルス感染症対策サイト」
令和2年3月にはコード・フォー・ジャパンが東京都から受託して「新型コロナウイルス感染症対策サイト」を開設した。受託から公開まではわずか1日半というスピードで開発され、ソースコードを無償公開したことにより約80の自治体に展開・活用された。
このサイトは、市民からの改良提案やバグの修正を受け入れて、リリース後に5,000を超える意見が一般のエンジニアから寄せられ順次改良されていった。
シビックテックが必要な背景
シビックテックが現代の日本で必要とされる背景には、いくつかの要因が考えられる。以下で詳しく見ていこう。
Society5.0の提唱

Society5.0(ソサエティー5.0)とは、内閣府の第5期科学技術基本計画において日本が目指すべき未来社会の姿として提唱された概念だ(※1)。
仮想空間と現実空間を高度に融合させたシステムを駆使して、経済発展と社会的課題の解決を目指している。平成23年6月に閣議決定された包括的データ戦略では、Society5.0を実現させるビジョンの1つとして、「新たな価値の創出のためみんなで協力する」という方針を示した。行政と市民が協力してデータを活用し、新たなサービスを創出する仕組みをつくることが、未来の日本が目指すSociety5.0という社会モデルにもつながっている。
※1出典:内閣府「Society 5.0とは」
「小さな政府」
「小さな政府」は行政の介入を最小限に抑えて、市場原理にもとづく自由競争を促すことで経済成長を目指す考え方だ。
日本では少子高齢化による人口減少が進んでおり、将来的に財政難となる自治体も増加することが見込まれている。そのため、行政側は意図せずとも財政規模が小さく影響力の少ない「小さな政府」へダウンサイジングせざるを得ず、行政サービスだけでは地域課題に対処できない状況になることも予想されている。
行政だけの力では解決の難しい課題を解決するために、市民の力を借りて共創する手段としてシビックテックが注目されている。
デジタル庁の設立
平成23年9月に発足したデジタル庁の方針もシビックテックを後押ししている。デジタル庁は「誰一人取り残されない、人に優しいデジタル化を。」というスローガンを掲げ、職員約600人のうち約200人が民間人材で構成されている組織だ。
デジタル庁にはシビックテックを推進する担当者として、コード・フォー・ジャパン代表理事が参画するなどデジタル人材の登用も進められ、行政と市民の連携促進や民間でシビックテックを推進するリーダーの育成、市民のスキル開発機会の提供、NPOなどの非営利セクターと連携をするための仕組みづくりなどに取り組んでいる。
シビックテックに必要なこと
シビックテックが継続的に活動するためには、活動の土壌となる環境整備も必要だ。
.jpg)
オープンデータの整備とオープンソースの推進
行政が保有するデータのうち、インターネットを通じて誰でも利用できるよう公開されたデータを「オープンデータ」という。データを公開するだけではなく、フォーマットの統一など、使いやすい形で提供することが大切だ。
自治体もEBPM(※2)のためには、データを活用する環境整備が求められる。また、シビックテック活動を促進するためにも、自治体はオープンデータの整備・公開を進めておきたい。
※2:エビデンス(根拠)にもとづく政策立案
ソフトウェアを構成するプログラム「ソースコード」を、無償で一般公開することを「オープンソース」と呼ぶ。ソフトウェアやWEBサイトをオープンソースで公開することで、誰でもソフトウェアを改良・再配布することができ、市民エンジニアとのさらなる共創にもつながる。オープンソースの推進は、シビックテックが継続的に活動するためにも必要である。
官民の垣根を越えたコミュニティの形成
官民の垣根を越えたコミュニティを形成することも重要だ。行政と市民の距離を近づけるために共同でイベントを開催するなど、お互いの存在を身近なものとして意識づける工夫をしたい。
シビックテックの実際の事例を紹介
ここからは、シビックテックの実際の事例を見ていこう。
【石川県金沢市】ゴミ収集日を通知してくれるアプリ「5374.jp」
.jpg)
石川県金沢市のシビックテック・コミュニティ「Code for Kanazawa(コードフォー・カナザワ)」は、「5374(ゴミナシ).jp」というアプリを開発。いつ、どのゴミが回収されるかが直感的に分かるゴミ出し支援アプリで、居住地を登録すると最も近い収集日を上から順番に表示する。各自治体のオープンデータを活用し、オープンソースで開発されているため、地域に合わせてカスタマイズすることも可能だ。現在では全国100以上の都市に広がり、活用されている。
【北海道札幌市】さっぽろ保育園マップ
.jpg)
北海道札幌市のシビックテック・コミュニティ「Code for Sapporo(コード・フォー・サッポロ)」のパパママまっぷチームは、「さっぽろ保育園マップ」を作成。
札幌市内の保育所や幼稚園の認可状況を一目で確認でき、マップ上の保育園アイコンをタップすると開園時間などの詳細情報も表示する。札幌市の保育施設の情報や、国土地理院の地理空間情報などのオープンデータを活用して開発されている。マップのソースコードも公開されているため、各地域の有志によって様々な自治体の保育園マップが作成され、子育て世帯を支援している。
行政と市民が協力して活動することがよりよい社会につながる
コード・フォー・ジャパン以外にも、IT技術を活用した地域課題の解決に取り組むご当地シビックテック・コミュニティが全国各地に存在している。
「Code for X(地域名)」として各地で活動するシビックテック・コミュニティはブリゲード(消防団)と呼ばれ、現在では約80のブリゲードがコード・フォー・ジャパンとパートナーシップを結ぶ。行政と市民が地域課題の解決に行動を起こすことで、「ともに考え、ともにつくる社会」の実現を目指したい。
.jpg&w=3840&q=85)


.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)