フェーズフリーとは?
フェーズフリーの「フェーズ(phase)」とは、日常時・非常時の「区切り」、「フリー(free)」とは、「区切りがない」という意味をあらわしている。
防災用品といえば、普段は保管しておき災害が起きたときに出して使う、というのが従来の考え方だった。しかし、フェーズフリーでは、普段使いしているものをそのまま非常時・災害時でも使えるようデザインするという考え方をする。
“備えない防災”とも呼ばれる
防災用品は、災害時や非常時のために設計されており、災害が発生したときにのみ利用するのが一般的だ。しかしフェーズフリーでは、日常で使っている品や食品を災害時でもそのまま利用する。そのため「備えない防災」とも呼ばれている。なお、フェーズフリーの具体例には次のようなものがある。
● 食品のローリングストック
● テント、バックパックなどアウトドアグッズ
● モバイルバッテリー

フェーズフリー誕生の背景
フェーズフリーは、防災専門家・佐藤 唯行さんが平成26年に提唱した概念という。当時は東日本大震災からそれほど年月が経過しておらず、国民の防災意識が非常に高まっている時期だったが、意識の定着までには至っていないという状態だった。
この状態を見た佐藤氏は「災害に備えての特別な準備は難しいのでは」と考え、日常時と非常時を分けて考えるのをやめる「フェーズフリー」を提案した。その後、平成30年には一般社団法人フェーズフリー協会が発足し、日常・災害時、どちらでも使える商品やサービスにフェーズフリー認証を行う制度も設けられた。
出典:一般社団法人フェーズフリー協会「フェーズフリーとは」「沿革」
フェーズフリーと相性がいいジャンルは?
フェーズフリーと相性がいいとされるジャンルに、「食品」「アウトドアグッズ」がある。これらのジャンルは自治体のフェーズフリー災害対策の一環としても取り入れやすいはずだ。詳しく確認しておこう。
缶詰やレトルト食品などの「食品」
缶詰やレトルト食品、フリーズドライ食品、長期保存ミネラルウォーターなどの食品は、賞味期限が長く、常温保存ができるところからフェーズフリーに最適といえる。最近では、おいしく食べやすいパスタ・丼もの・菓子類でも長期保存可能な商品が出ており、これらの食品は、少し多めに購入して普段の食事で利用し、足りなくなったら買い足していく「ローリングストック」にも向いている
なお、ローリングストックについては「ローリングストックとは?不測の事態に備えた防災備蓄について解説!」にも詳しく記載してあるので、ぜひ参考にしてほしい。
ランタンや寝袋などの「アウトドアグッズ」
ランタン・寝袋・テント・バックパックなどのアウトドアグッズも、フェーズフリーに最適ともいわれている。アウトドアを楽しむときだけでなく、災害時、家が損壊し寝る場所がないときや、電気ガスが止まったときにも便利に利用できる。
また、普段から利用しているアウトドアグッズであれば、急に必要になっても使用方法を迷わないというメリットもある。キャンプやハイキングに使うアウトドアグッズ以外には、カセットコンロやカセットボンベも準備しておくとよいだろう。

自治体のフェーズフリー活用事例
自治体にもフェーズフリーという考え方が広がってきている。活用事例を確認してみよう。
徳島県鳴門市の道の駅「くるくるなると」
徳島県鳴門市の「くるくるなると」は、令和4年に開業した道の駅だ。地域の特産品が販売されているところは通常の道の駅と変わらないが、非常時には、扱っている商品全てが避難者のための食料として提供されるよう定められている。また、販売する商品が備蓄品を兼ねるという特性上、魚などの生鮮食品以外は在庫を多めに抱えるというローリングストックも行われている。
さらに、くるくるなるとの屋上は遊べる広場として24時間開放されており、南海トラフ地震による津波が発生した際は避難スペースとして利用できるつくりとなっている。

北海道小清水町の防災拠点型新庁舎「ワタシノ」
北海道小清水町の「ワタシノ」は、令和5年に町役場の庁舎としてオープンした。町役場機能だけでなく、健康スポーツジムやコミュニティスペース、コインランドリーなどが併設されており、住民や観光客が気軽に利用できる場所としてにぎわっている。
住民の憩いの場となっているワタシノだが、暴風雪や地震などの災害が発生した場合は、約800人が収容できる防災拠点として利用される。スポーツジム内のスタジオに床暖房を設置し、カフェに炊き出し機能を付けるなど、施設内のどの場所にも非常時のための機能がある点も見逃せない。
香川県高松市 かまどにもなるベンチ
香川県高松市では、災害時の避難場所に指定されている仏生山公園に、防災かまどベンチ2基を設置した。このベンチは高松市の高校の生徒たちが作成し、市に寄贈したものである。
防災かまどベンチは、南海トラフ地震をはじめとした災害時の炊き出しを想定してつくられており、普段はベンチとして利用できるが、座面を取り外すとかまどになる。災害により交通が寸断され、食べられるものを運ぶのが困難な場合でも、材料があれば避難場所で炊き出しが行えるという利点がある。
民間企業のフェーズフリー活用事例
民間企業でもフェーズフリーの考え方にもとづいた商品・サービスが開発されている。活用事例を見ていこう。
被災地へ派遣できるホテル
アールナインホテルズグループでは、コンテナを客室にしたホテル「HOTEL R9 The Yard」を全国で展開している。コンテナ1台を独立した客室として使えるようデザインしているため、プライバシーが守られリラックスできるということで人気を集めるホテルだ。
さらに、このホテルは、それぞれのコンテナがタイヤのついたトレーラーとなっており、ナンバープレートもついている。災害時には現場に移動させ、仮設住宅としての利用もできる。水道や電気が通っている場所に移動させれば、最短3日で使用可能となる。
フェーズフリーを意識した商品開発
フェーズフリーを意識した商品やサービスも続々登場している。文房具・オフィス家具メーカーのコクヨが開発したのは、普段はオフィス内の仕切りとして、災害が発生した際は情報を記入するホワイトボードとして利用できるパネルだ。
また、三和製作所が販売している「バケツにもなる撥水(はっすい)バッグ」は、折り畳んで持ち運びできる撥水・速乾機能があるバッグだが、災害時は水を入れて持ち運べるバケツとしても利用できる。
フェーズフリーはサービスの面でも広がっている。令和元年より東京・池袋で運行してい「IKEBUS(イケバス)」は、最高速度19kmで走る乗車定員22名の小型電気バスだ。通常は池袋周辺を周遊しているが、災害が発生した際は移動式電源としてバッテリーに蓄電された電気をスマートフォンや非常用照明の充電に活用できる。

日常と災害時を分けず、普段から意識しない防災を心がけよう
災害時に備えての備蓄の重要性は認識されているが、保管場所や管理方法の面で問題を抱えている自治体も少なくないだろう。しかし、フェーズフリーという考え方で災害対策を行えば、わざわざ災害時のための物資を準備することなく、普段使っているものをそのまま利用できる。特に、賞味期限に気を使う食品は、フェーズフリー食品をローリングストックすれば管理がラクになる
また、保管場所が取られる照明器具や寝具などはアウトドア用品で代用可能だ。防災用品の購入も減らせるため、フェーズフリーは予算の面からもぜひ導入を検討したいとこと。災害対策を行う際は、フェーズフリーを意識し“今使っているものを災害時にも使えないか”を考えるところから始めてはいかがだろうか。
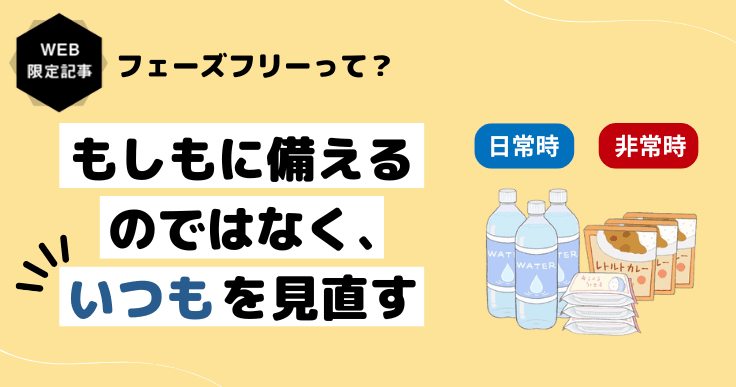





![【徳島県鳴門市事例] フェーズフリー×学校教育で、平常時の防災意識を底上げする。](/uploads/articles/2025-04-09-19-45-35_2022-04-13-10-14-53_鳴門市.jpg)
![【東京都豊島区事例] フェーズフリーの防災公園が、“にぎわいと安心”の両方を生む。](/uploads/articles/2025-04-09-19-46-21_2022-04-20-09-26-36_東京都豊島区20220418.jpg)
![【岐阜県大垣市事例] 学校で防災備品を備蓄しながら、防災教材としても活用する。](/uploads/articles/2025-04-09-19-45-56_2024-07-19-11-14-25_26_taiheiyokogyo.jpg)


















