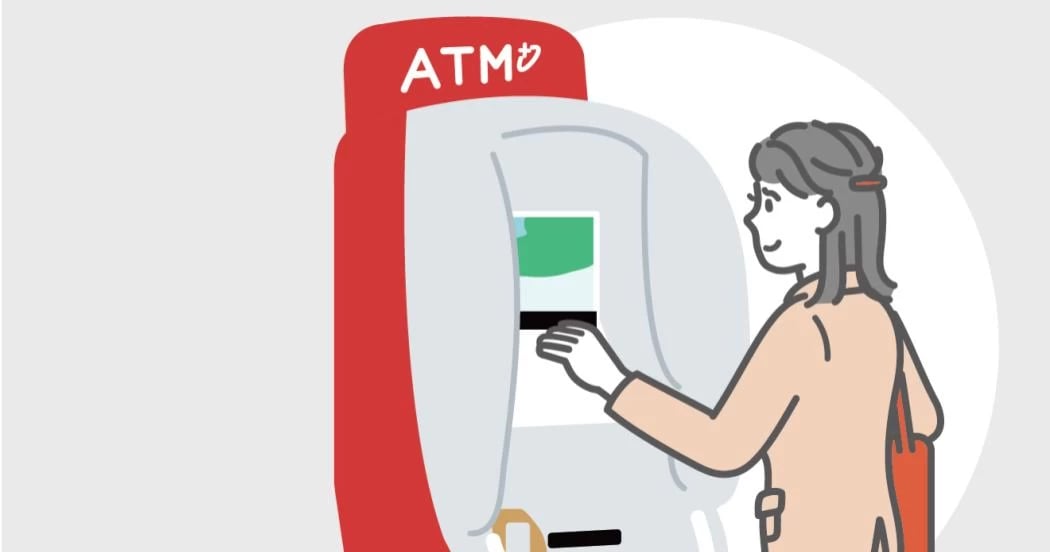公開日:
フロントヤード改革とは?デジタル化やマイナンバーカード活用で変わる自治体の窓口業務
.png&w=1920&q=85)
「フロントヤード改革」とは、行政と住民のコミュニケーションやサービス提供の仕組みを根本的に変革する取り組みのことをいう。この改革はデジタル技術を活用し、書かないワンストップ窓口の導入やオンライン申請の推進など、住民と行政の接点を多様化・充実化することを目指している。
少子高齢化や人口減少が進む中、自治体における行政サービスのあり方が大きな転換期を迎えている。この記事ではフロントヤード改革の取り組み内容や先進的な自治体の事例を紹介する。行政資源の制約が進む中で、持続可能な行政サービスの提供体制を確保するためのヒントとしてほしい。
【目次】
• フロントヤード改革とは
• フロントヤード改革、なぜ必要?
• フロントヤード改革に対する政府の支援策
• フロントヤード改革、どのように実現する?
• 自治体でのフロントヤード改革の事例
• 住民と職員の双方にメリットがあるフロントヤード改革を進めよう
※掲載情報は公開日時点のものです。
フロントヤード改革とは
フロントヤード改革とは、住民と職員の接点のあり方を見直し、よりよい行政サービスを実現するための取り組みである。従来の対面・書面中心のサービスにデジタル技術を組み合わせることで、住民と行政との利便性向上を目指す。
この改革は令和2年に総務省が策定した「自治体DX推進計画(※1)」における重要施策の一つとして位置づけられており、自治体DX推進の主要なテーマとなっている。総務省は2026年度までに総合的なフロントヤード改革に取り組む自治体数を300団体まで増やすことを目標として掲げている。
※1出典:総務省「自治体DXの推進」
フロントヤード改革では、オンライン申請の導入や窓口のデジタル化といった個別の施策だけでなく、業務プロセスの見直しや庁舎空間の活用方法まで含めた総合的な改革を行うことで、住民サービス全体の向上を目指している。
そもそも「フロントヤード」って?
.jpg)
フロントヤードとは、住民と自治体・行政の接点を指す。窓口での受付業務や相談業務、住民が利用する庁舎内のスペースなど、住民と行政が直接関わるあらゆる場面が対象となる。
一方、バックヤードとは、住民からは見えない行政機関内での業務プロセス全般を指す。バックヤードの改革は自治体内の業務効率化を目指すものであり、行政機関内での仕事の仕方やプロセスを見直すことが主な目的となる。
マイナンバーカードの活用
.jpg)
総務省はマイナンバーカードを活用した住民サービスの向上を推進している。従来は庁舎窓口でしか行えなかった手続きが、マイナンバーカードを使えば様々な場所から可能となる。
自宅からのオンライン申請をはじめ、郵便局やコンビニエンスストアでの各種証明書の取得、庁舎窓口での本人確認の簡素化など、マイナンバーカードの利用範囲は広がりつつある。住民は時間や場所の制約を受けることなく、自分に合った方法で行政手続きを行うことができ、利便性が大きく向上する。
自治体にとっても、対面での本人確認作業の効率化や申請データの正確な把握が可能となり、業務効率の向上にもつながっている。
庁舎は住民が集う協働の場・行きたい場所へ
オンライン申請の普及や業務の効率化によって生まれた時間と空間を、新たな住民サービスへと転換する動きが始まっている。
例えば職員の業務効率化と人的配置の最適化により、住民との対話や相談業務に時間を充てることができる。また、これまで手続きの場としてのみ利用されてきた庁舎空間を、市民協業スペースやコワーキングスペース、ラウンジ、カフェなど、住民が集い交流できる場として活用することも考えられる。
「書かせない」「待たせない」「迷わせない」「行かせない」行政サービスの実現
.png)
自治体フロントヤード改革は、「書かせない」「待たせない」「迷わせない」「行かせない」の4つの実現を目指している。
●「書かせない」
「書かない窓口」の実現を目指し、職員による聞き取りと代筆、アプリやWEBサイトを活用した事前情報入力などにより、住民の書類記入の負担を軽減する。
 こちらの記事もオススメ!
こちらの記事もオススメ!
▶ 【福島県南相馬市】“書かない窓口”への改革で手続き時間を短縮する。
●「待たせない」
オンライン予約システムの導入、リアルタイムの混雑状況共有、キャッシュレス決済の導入、窓口受付時間の拡張などを通じて待ち時間の短縮を実現する。
●「迷わせない」
タブレットやチャットボット、職員による案内など多様な案内方法の整備、ワンストップ窓口の設置、さらに障害者や外国人向けのバリアフリー対応を進めることで、効率的なサービス利用と対応時間の短縮を実現する。
●「行かせない」
リモート相談窓口の設置、移動窓口サービスの提供、オンライン申請システムの導入など、窓口に行く必要のない行政サービスの実現を目指す。遠隔地に住む住民も含め、誰もが手軽に行政サービスを利用できる環境を整備する。
以上の4つの取り組みを各自治体の実情に応じて工夫し、新しいフロントヤードを目指すことが求められている。
フロントヤード改革、なぜ必要?
フロントヤード改革が求められる背景には、自治体が直面する課題と、変化する住民ニーズへの対応という2つの要因がある。
少子高齢化や人口減少による行政の人手不足
人口減少と少子高齢化が進む中、業務改革や効率化によって人手不足による行政サービスの低下を防ぐことが急務となっている。
フロントヤード改革により、限られた人員でも質の高い行政サービスを維持することが可能となる。定型的な業務をデジタル化することで、職員はより専門性の高い業務や住民との対話に注力できるようになる。
申請や手続きに対する住民のニーズの多様化
世の中の様々なサービスでデジタル化が進む中、行政手続きにおいてもオンライン申請や24時間対応など利便性の高いサービスが求められている。特にスマートフォンやパソコンでの手続きに慣れた世代からは、従来の窓口での対面・書面中心の行政サービスに対して改善を求める声が高まっている。
このような住民ニーズの変化に対応し、時間や場所にとらわれない行政サービスを実現するためにも、フロントヤード改革は不可欠なものとなっている。
.png)
フロントヤード改革に対する政府の支援策
フロントヤード改革を進めるにあたり、多くの自治体ではノウハウや資金の不足などが課題となっている。そのため国は自治体を支援するために、人的支援・財政的支援・環境整備の3つの分野でサポートを提供している。それぞれの支援策は以下の通りだ。
人的な支援
●窓口 BPR アドバイザー派遣事業(デジタル庁)
自治体の窓口業務の業務改革(BPR: Business Process Re-engineering)を推進するため、専門のアドバイザーを派遣する制度(※2)。
●窓口 BPR アドバイザー育成事業(デジタル庁)
自治体職員自らが窓口改革を推進できるよう、業務改革の専門知識を学ぶための育成プログラムを提供。育成された人材がほかの自治体の窓口BPRを支援することで、自治体間の共創の輪を拡大する目的がある。
●地方公共団体の経営・財務マネジメント強化事業【地方公共団体のDX関係】(総務省)
総務省と地方公共団体金融機構が共同で実施。専門的な知識を持つアドバイザーを自治体に派遣し、経営・財務マネジメントの強化を図る(※3)。
※3出典:総務省「地方公共団体の経営・財務マネジメント強化事業」
●地域情報化アドバイザー派遣制度(総務省)
ICT(情報通信技術)を活用した行政サービスの改善を支援するため、専門家を自治体に派遣する制度(※4)。
※4出典:総務省「地域情報化アドバイザー派遣制度(ICT人材派遣制度)」
財政的な支援
●デジタル田園都市国家構想交付金(内閣府)
デジタル技術を活用した地域活性化を支援するための交付金。自治体のDX推進にも活用できる。
●自治体フロントヤード改革モデルプロジェクト(総務省)
先進的なフロントヤード改革のモデルケースとなる自治体に対し、国が支援を行うプロジェクト。ほかの自治体が参考にできる成功事例を生み出すことを目的としている。
環境の支援
●自治体窓口DXSaaS(デジタル庁)
自治体の窓口業務を効率化するためのクラウド型サービス(SaaS)でオンライン申請やデジタル窓口の導入を支援する。
このように国はフロントヤード改革を推進する自治体に対し、人的・財政的・環境的な支援を多角的に提供している。自治体はこれらの制度を活用して、フロントヤード改革を進めていくことが求められている。
フロントヤード改革、どのように実現する?
.png)
フロントヤード改革は、デジタルツールの導入が目的ではなく、住民の利便性向上と職員の業務効率化を両立させることが重要となる。そのために「書かせない」「待たせない」「迷わせない」「行かせない」の4つをどのように実現していくのか。具体的に解説する。
「書かせない」の実現方法
書かない窓口では主に2つの側面から書く手間の削減を目指す。
●住民自身が記入する場合
事前にWEBサイトやアプリ経由で情報を入力する
マイナンバーカードの情報を利用して入力する
●職員が記入する場合
住民から情報の聞き取りをして代筆する
自治体が保有しているデータを使用する
「待たせない」の実現方法

待ち時間の短縮には事前予約システムの導入が効果的だ。また、リアルタイムでの混雑状況や待ち時間の可視化、キャッシュレス決済の導入なども有効な手段となる。
さらにオンラインで手続きできる範囲を広げることで、窓口での待ち時間自体を解消することも可能となる。
「迷わせない」の実現方法
住民が迷わず手続きを行えるよう、チャットボットやタブレットを活用した案内の導入が望ましい。
また、複数の手続きを一カ所で完結できる窓口のワンストップ化や、障害者・外国人向けの対応を充実させることで、誰もが利用しやすい環境を整備する。
「行かせない」の実現方法
高齢者や庁舎から遠い場所に住む人、平日の来庁が難しい人など、様々な事情で庁舎に行けない住民に対応する。
リモート窓口の設置や、自治体の車両で地域を訪問する移動窓口、電話やWEBでの受付など、多様な手段を用意することで来庁の必要性を減らす。
▶ “紙と対面”からの脱却を支援。窓口業務のDXサービス特集
「ジチタイワークス民間サービス比較」では、サービス資料の確認とダウンロードが可能です。
自治体でのフロントヤード改革の事例
.png)
【北海道北見市】書かないワンストップ窓口
北見市で平成28年に導入された「書かないワンストップ窓口」は、フロントヤード改革の先進的な取り組みとして注目を集めている。この取り組みは平成24年に新人職員による窓口利用実験を契機に始まり、できることから改善していった結果、事業化に至った。
窓口では転居や婚姻などのライフイベントに関連する複数の手続きを一つの窓口で完結できる。住民がやることは申請書などへの署名のみで、大部分の帳票類はシステムから印刷される仕組みだ。さらに関連した手続きをシステムが自動でリストアップし、職員の業務をサポートする。
この改革により、市内転居の手続き時間が従来の45分から10分に短縮されるなど、大きな効果が表れている。住民からも「とても便利で驚いた」と好評だ。職員の業務効率化にもつながっている。
【静岡県裾野市】予約のオンライン化
裾野市では令和5年10月より市民課窓口の予約システムを本格導入した。このシステムにより住民はWEBサイトから窓口受付の事前予約が可能となり、待ち時間なく手続きを行うことができる。
実証実験では大きな成果が表れ、窓口での待ち時間が60分から15分に、手続き完了までの時間が85分から40分に短縮された。 さらに裾野市では様々な行政手続きのオンライン対応も進めており、「待たない・書かない・行かない」手続きを目指して段階的にフロントヤード改革に取り組んでいる。
【福島県いわき市】移動窓口による行政サービスの提供
いわき市では中山間地域などにおける行政サービスの利便性向上を目的として、令和2年度から出張行政サービス「お出かけ市役所」を実施している。
この取り組みは行政MaaSの一環として、住民票の発行などの行政手続きができるマルチタスク車両が中山間地域などを巡回し、地区の集会所や公民館などで行政サービスを提供する。
これにより、高齢者をはじめ庁舎への移動が困難だった住民に対しても、車両の中で行政手続きやコミュニケーションが可能となった。提供されるサービスは行政手続きだけでなく、税務相談や労働相談、福祉相談、母子健康相談など多岐にわたる。
この「お出かけ市役所」は、中山間地域における行政サービスの先進的な取り組みとして全国から注目を集めている。
住民と職員の双方にメリットがあるフロントヤード改革を進めよう
人口減少や住民ニーズの多様化が進む中、フロントヤード改革は今後の行政サービスのあり方を大きく変える重要な取り組みとなる。改革を進めることで、住民は時間や場所に縛られずに行政サービスを利用でき、職員も業務の効率化を図ることができる。
今回紹介した自治体では「書かせない」「待たせない」「迷わせない」「行かせない」という目標のもと施策を導入し、住民の満足度向上や職員の業務改善につなげている。国による人的・財政的支援も充実しており、各自治体は自らの実情に応じた最適な改革を進めることが可能だ。
今後さらなるデジタル技術の発展に伴い、行政窓口のあり方も進化していくと考えられる。各自治体が住民にとって利便性の高い行政サービスを提供できるよう、それぞれの状況に合わせたフロントヤード改革が進められていくことが期待される。