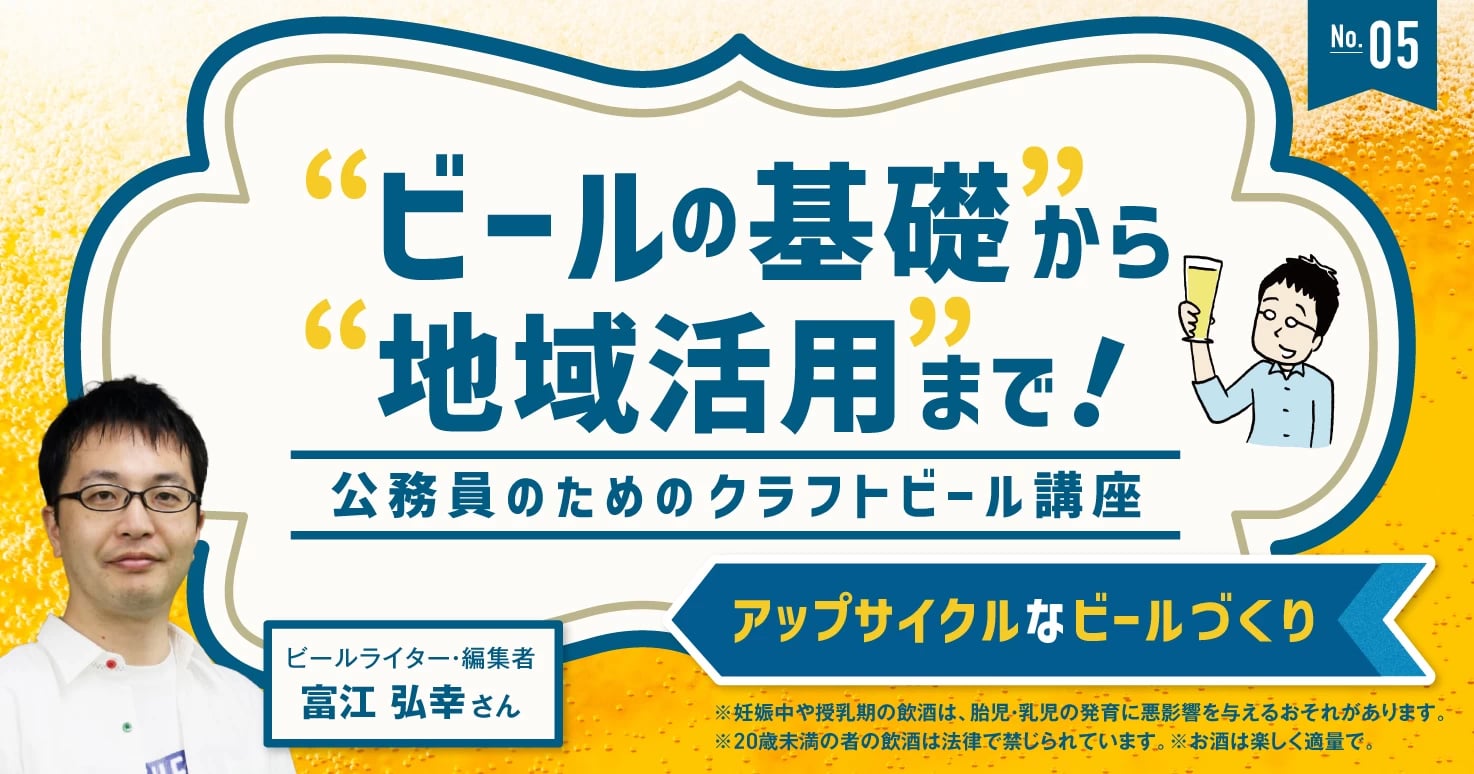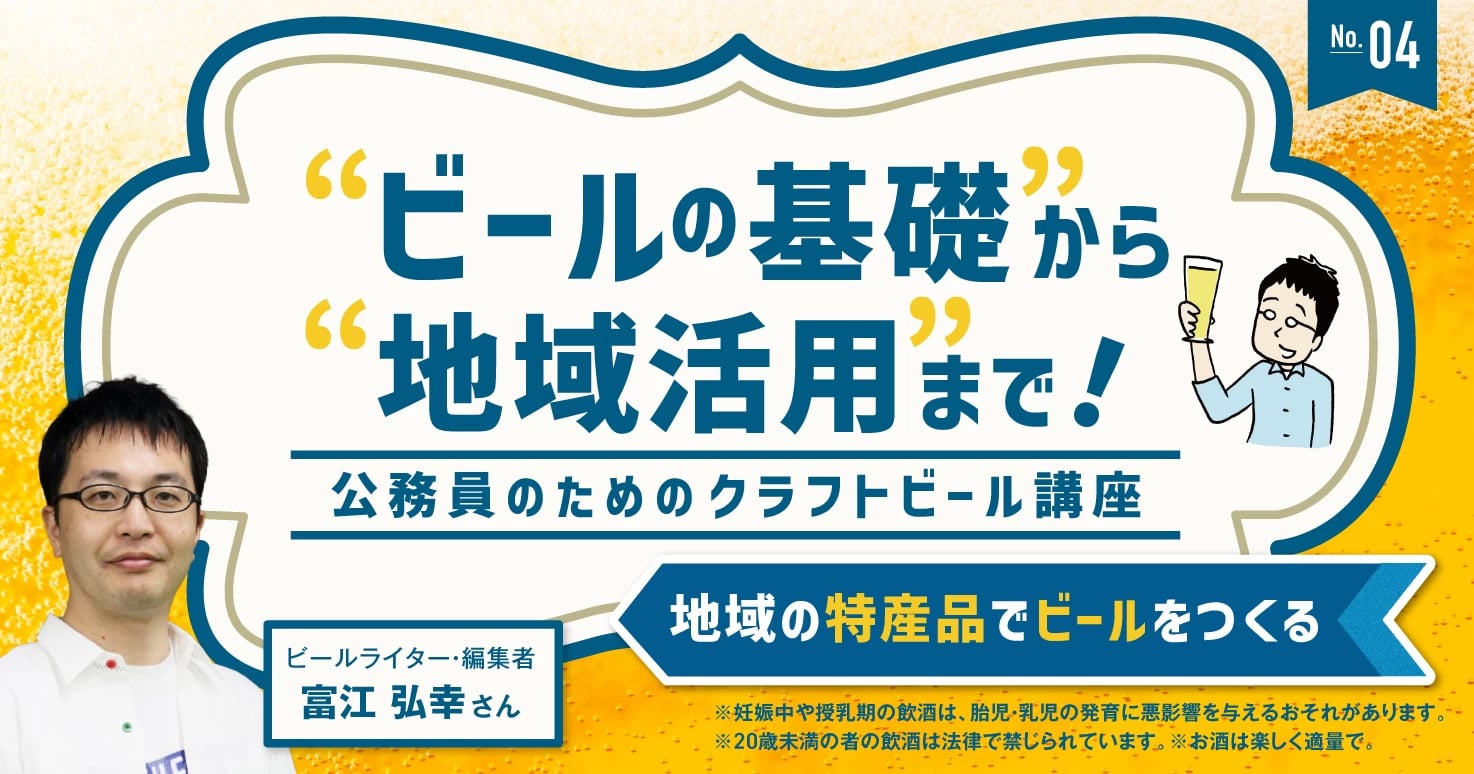公開日:
スマート農業のメリットとデメリットは?課題と自治体ができる対策を徹底解説!

スマート農業はロボット、AI、IoTなどの先端技術を活用する農業のことだ。先端技術を農業に採り入れ、省力化や労働負担の軽減を進めることで、生産効率や品質の向上が期待される。
一方で、スマート農業の導入にはいくつかの課題があり、全国でもまだ普及が始まったばかりというのが現状だ。スマート農業の推進に向けて、自治体側も事前にリスクや問題点などを整理して把握しておきたい。本記事では、スマート農業のメリット・デメリットや、課題解決のために自治体ができる対策について詳しく解説する。
【目次】
• スマート農業とは?
• スマート農業に取り組むメリットや効果
• スマート農業のデメリットと課題とは
• スマート農業の課題、どうすれば自治体が解決できる?
• スマート農業の課題を解消し、日本の未来の食を守っていこう
※掲載情報は公開日時点のものです。
スマート農業とは?
.jpg)
スマート農業は農林水産省が推進している取り組みで、ロボット、AI、IoTなどの先端技術を活用する農業のことだ。先端技術やデジタルデータを駆使することで、農業に従事する人たちの高齢化や人材不足に対応しながら、農産物の効率的な生産や品質の向上を目指す。令和4年12月に閣議決定した「デジタル田園都市国家構想総合戦略」においても、柱の一つ「地方に仕事をつくる」の中にスマート農業の取り組みが位置付けられている。(※1)
※1出典 デジタル田園都市国家構想「デジタルの力を活用した地方の社会課題解決」
スマート農業に取り組む目的とは
スマート農業に取り組む目的として、主に次の三つが挙げられる。
農作業の省力化・労力軽減
作業量の多さと重労働が当然とされてきた農作業を、先端技術の活用により省力化して、労力を軽減する。
スキルやノウハウの継承を、システム的に完成させる
農業のスキルやノウハウは、これまで人から人へと継承されてきた。また、勘や経験に頼った要素も大きい。そうした農業のスキルやノウハウをシステムとして完成させることも、スマート農業に取り組む目的の一つだ。
食料自給率の向上を目指す
日本の食糧自給率は諸外国と比べ低い水準にあり、令和4年度はカロリーベースで38%だった。スマート農業の導入によって生産性を上げることで、日本の食料自給率の向上を図ろうと、農林水産省は2030年度までにカロリーベースの食糧自給率45%の数値目標を掲げている。(※2)
※2出典 農林水産省「日本の食料自給率」
スマート農業に取り組むメリットや効果
スマート農業に取り組むメリットや、期待される効果として次のことが挙げられる。
農作業を省力化する
農業に必要な工程の一部に機械やAIなどを導入することで、農作業の省力化につながることがメリットとして挙げられる。令和3年に農林水産技術会議が行った実証試験では、農薬散布ドローンを導入した結果、最大95%の労働時間削減を実現させた。(※3)
※3出典 農林水産技術会議「労働力不足の解消に向けたスマート農業実証の結果について 」
労働の負担を軽減する
農作業の中には収穫物の積み下ろしなど、重労働が多いことも課題の一つだ。こうした作業にアシストスーツを導入するなど、先端技術を活用することで労働負担の軽減が可能になる。
農業をデータ化・活用することで新規参入が容易に
.jpg)
熟練者の農業技術をICT技術でデータ化し、ノウハウを活用することで、経験の浅い農業者でも安定した成果を出すことが可能になる。農業のデータ化により技術継承をスムーズにすることで、若手や新規就農者の新規参入がしやすくなることも大きなメリットだ。
熟練農業者が行う農作業のポイントを学習コンテンツにして、タブレットやPCで学んでもらうといった、新規就農者を応援するための農業技術学習支援システムも登場している。
関連記事|スマート農業の指導力を伸ばし、日本の農業の発展を支える。
環境に優しい農業の実現
スマート農業の導入により、化学肥料や農薬の使用量を抑えた環境に優しい農業が実現できることも利点の一つだ。農林水産省が「みどりの食料システム戦略」で2050年までに化学農薬使用量(リスク換算)を 50%低減する(※4)ことを目標とするなど、農業に使用する化学物質への対策が求められている。
※4出典 農林水産省「みどりの食料システム戦略」2030年目標の設定について
AI分析を用いて農薬を必要な箇所にだけ使うスポット散布や、ロボット除草機の導入など先端技術を活用した農薬削減の取り組みも、スマート農業の利点として注目されている。
スマート農業のデメリットと課題とは

利点の多いスマート農業だが、普及が進んでいない現状もある。ここからは、スマート農業のデメリットや課題を見ていこう。
機械やサービスの導入コストがかかる
スマート農業に必要な機械やサービスを導入するためには、まとまったコストがかかることがデメリットだ。初期投資にかかる費用が高額なため、中小規模の農家にとっては大きな負担となる。
また、導入後に必要なメンテナンスにも費用がかかるため、金銭的コストの問題は一つの壁といえるだろう。
就業者のITリテラシーが求められる
スマート農業を実施するためには就業者に一定のITリテラシーが求められることも課題として挙げられる。高齢化が進む農家では先端的な技術に慣れるのが難しく、スマート農業を導入しても使いこなせないのではないかという不安も普及を阻む要因になっている。
通信環境が整備されていない
通信環境が整備されていない場所では、通信技術を使った機械やシステムの導入が難しい。離島や山岳地帯など、一部の地域では情報通信基盤が十分に整っていないため、そうした場所ではどのようにスマート農業を導入するかが課題の一つになっている。
機械のメーカーなどによる規格の違い
スマート農業は比較的新しい技術のため、異なるメーカー間での互換性が乏しいこともデメリットとして挙げられる。機能を充実させるために新しい機器を導入しても、既存の機器との連携ができないなど、システムや機械の一元管理が難しいことにも注意が必要だ。
標準化・一律展開が難しい
農業の現場は地域の気候や土壌などの条件が一定ではないため、スマート農業の一律展開が難しいことも課題となっている。スマート農業に適した農地であるか、あるいはどのような設備が適しているかはケース・バイ・ケースであり、標準化しにくいのが現状だ。
スマート農業の課題、どうすれば自治体が解決できる?
ここからは、スマート農業の課題に対して、自治体ができる支援の内容を見ていこう。
スマート農業の導入費用を抑える
導入の際の大きな壁となり得るスマート農業の導入費用を抑えるために、次のような対策が挙げられる。
補助金・助成金制度を利用する
 スマート農業の導入費用に充てるための資金として、補助金・助成金制度はぜひ活用したい。
スマート農業の導入費用に充てるための資金として、補助金・助成金制度はぜひ活用したい。
スマート農業の普及を目的として、農林水産省でも「スマート農業総合推進対策事業費補助金」、「スマート農業総合推進対策事業費地方公共団体補助金」の二つの補助金事業を行っている。
また、地方自治体の中では機械の購入に補助金を出しているところもある。
福島県白河市では「農業の未来をつくるスマート農業推進事業補助金」として、ICT機器・ロボット技術の導入にかかる費用の一部を自治体が補助しており、機械購入費用の1/2、最大150万円の補助金を支給している。(※5)
※5出典 福島県白河市「農業の未来をつくるスマート農業推進事業補助金に係る要望調査について」
リースやシェアリングの活用
導入費用を抑えるための対策として、レンタル・リースを行う事業者から借りたり、農業者間で共有したりなど、高価な機器を自己保有せずに活用する方法もある。
農林水産省でもスマート農業導入費用を抑える策として、スマート農機を地域で広域シェアリングする実証事業も行われている。岡山県を対象にした実証では、南北約100km、標高差約500mという地域の特性を活かし、直進アシスト田植え機と食味・収量コンバイン(収穫と同時に収穫量やたんぱく値などを測定できる高性能コンバイン)の広域シェアリングを実施した。近隣地区での農機シェアリングは作業時期が競合するため、場所や標高が異なる県内広域を対象にしていることが特長だ。
スマート農業の推進に貢献できる人材を育成する
.jpg)
農業者だけではなく異分野の組織や人材を活用して、スマート農業の普及を推進しようという動きもある。
農業現場における作業代行や、スマート農業技術の有効活用による生産性向上支援など、農業者に対してサービスを提供する新しいビジネスモデルである「農業サービス支援事業者」の育成も、農林水産省によって進められている。(※6)
※6出典 農林水産省「農業支援サービスの例」
令和4年度からは農業高校・水産高校を対象に、スマート農林水産業に関する内容を盛り込んだ新高等学校指導要領もスタートしている。安定的な食料生産の必要性や、グローバル化への対応など、農業を取り巻く社会的環境が変化していることを踏まえて、先端技術を活用できる次世代の育成を目指す。
メーカー間のデータ連携を推進する
農業者がメーカーの垣根を越えてデータを活用できるよう、スマート農機メーカーの間でも規格統一のためのガイドラインが整備されつつある。令和3年には農林水産省が「農業分野におけるオープンAPIの整備に関するガイドラインver1.0」(※7)を策定。データを取り扱う農業機器を対象に、データ連携を行う上での指針を示した。
※7出典 農林水産省「農業分野におけるオープンAPIの整備に関するガイドラインver1.0」
また、国際的にシェアの大きいアプリケーションを活用する動きも国内メーカーで始まっている。ドイツのBASF社が提供する栽培管理システム「xarvio®(ザルビオ)フィールドマネージャー」のマップデータを読み込み、営農支援システムと連携する取り組みに、国内のスマート農機メーカーが次々と参画した。
民間企業同士が垣根を越えてデータの相互連携を図ることで、スマート農機のユーザーである農業者の利便性が向上する画期的な取り組みだ。こうした動きが広がることで、スマート農業の普及促進が期待されている。
スマート農業の課題を解消し、日本の未来の食を守っていこう
スマート農業はまだ始まったばかりの取り組みで、解決すべき課題も存在する。その一方で、技術の進歩も目覚ましく、新しいテクノロジーが次々と生まれていることも事実だ。どのような技術が日本の農業を変えていくのか、今後の展開に注目したい。
スマート農業をさらに普及させるため、地方自治体として地域特性に合ったスマート農業のあり方や、推進する方法について考えてみよう。

.png) 関連記事
関連記事