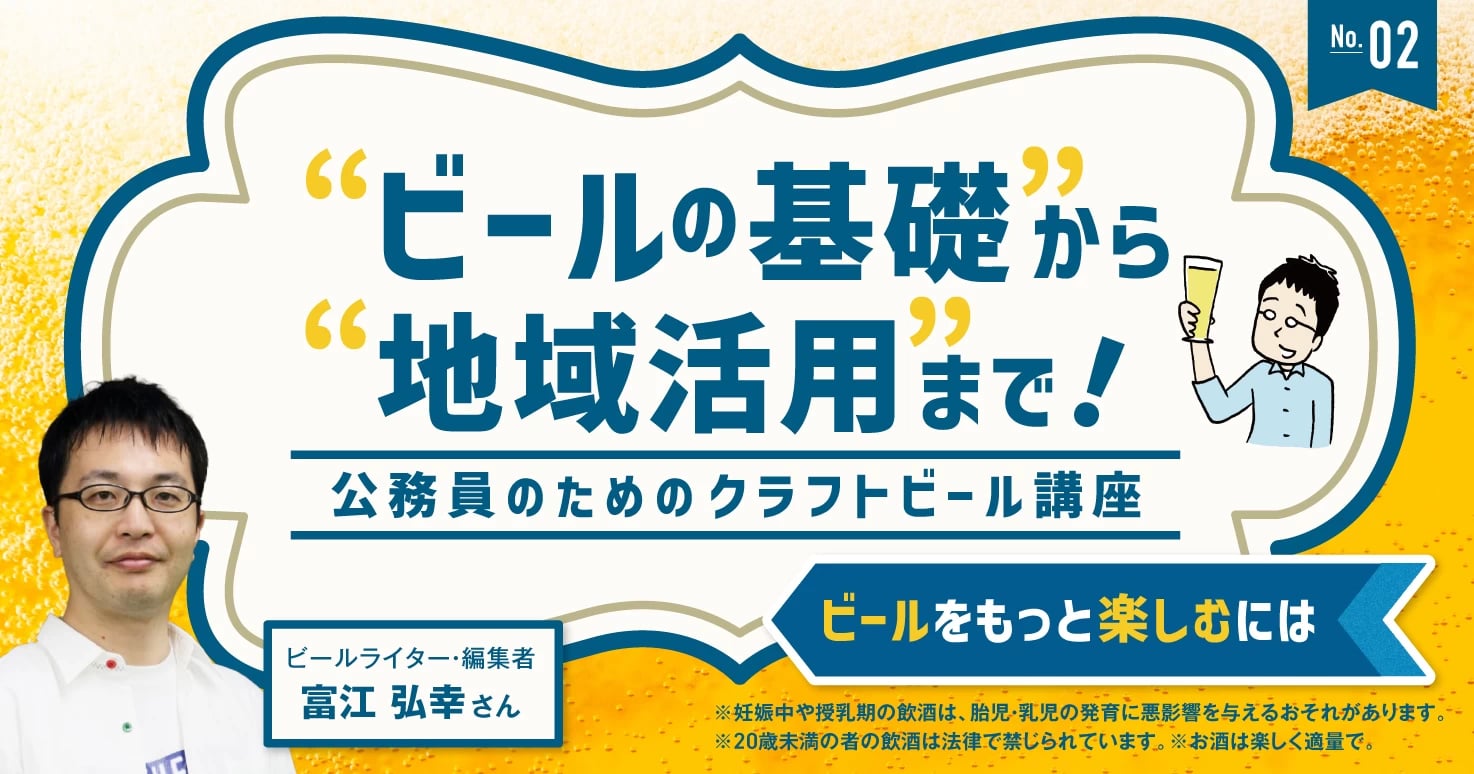公開日:
【連載】ビールの基礎から地域活用まで!―公務員のためのクラフトビール講座<1>ビールってどんなお酒?

お風呂上がりに仕事の後に、お酒好きにとっては欠かせないビール。近年のクラフトビールブームを経て、特産品を活かしたビールづくりも各地に定着し、地域活性化の主役にもなりつつあります。この連載では、ビールの基礎知識から地域での活用事例まで、ビールライターの富江 弘幸さんが分かりやすく解説します。その第1回は「そもそもビールとは?」。
※掲載情報は公開日時点のものです。
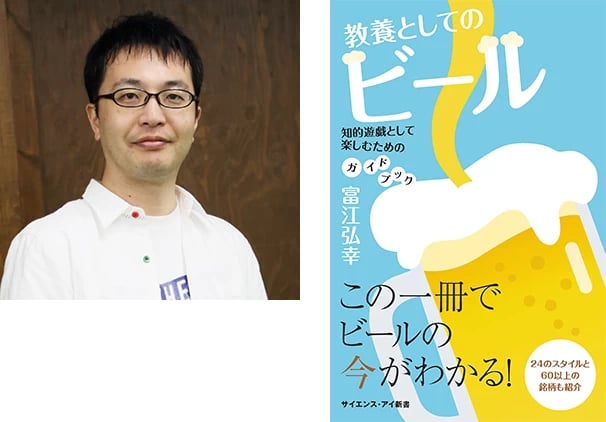
解説するのはこの方
富江 弘幸(とみえ ひろゆき)さん
ビールライター・ビアジャーナリストアカデミー講師
編集者。昭和50年東京生まれ。法政大学社会学部社会学科卒業。卒業後は出版社・編集プロダクションでライター・編集者として雑誌・書籍の制作に携わる。中国留学を経て、英字新聞社やDXコンサル会社などに勤務。ビール・飲食関連記事の執筆や、ビアジャーナリストアカデミー講師など、幅広く活動している。著書に『教養としてのビール』(サイエンス・アイ新書)など。
ビールは世界中で親しまれているお酒ですが、どうやってつくるのか、どんな種類があるのかを意外と知らない人も多いと思います。大手ビールしか飲んだことがないという人もいるでしょう。
しかし、ビールは非常に多様性があり、地域経済や地域の特産品などとも関連しやすいお酒でもあります。ビールについて少し知識を深めるだけで、地域とビールとの連携についてのヒントを得られるかもしれません。
この企画では全5回にわたって、ビールに関する基礎知識や、地域とビールの関わりについて紹介していきます。第1回は、ビールの原料やつくり方、クラフトビールと地ビールの違いについて解説します。
ビールとはどんなお酒?
ビールは、麦芽・ホップ・水を主原料とし、酵母で発酵させた醸造酒です。
お酒は醸造酒と蒸留酒に大きく分けられ、酵母によって糖分をアルコールに変えたお酒が醸造酒です。ブドウを発酵させたワインや、米を原料とする日本酒も、ビールと同じ醸造酒になります。
その醸造酒を加熱・蒸留して気化させ、気体となったアルコールを液体に戻したお酒を蒸留酒といい、ウイスキーや焼酎などが代表的です。
一般的にはビールといえば上記のような説明になるのですが、日本では酒税法で「ビール」と称するための条件が法律で定められています。アルコール度数が20%未満で、麦芽、ホップ、水を原料として発酵させたものであれば、ビールと表示できることになっています。

さらに、政令で定める物品(副原料)についても、麦芽重量の5%以内であれば使用することが可能です。ただし、5%を超えたり、政令で定める物品以外を使用すると、ビールと表示できず、発泡酒と表示しなければなりません。
発泡酒と聞くと、「ビールと似た味わいの安いお酒」という印象を持っている人もいるかもしれませんが、実は全ての発泡酒がそうだとは限らないのです。酒税を下げるために発泡酒とするものもあれば、クリエイティブなお酒づくりをするために地域の特産品を副原料に使った結果、発泡酒と表示せざるをえないお酒もあります。
しかし、日本の酒税法では発泡酒であっても、世界には同様のつくり方で「ビール」とされているお酒も多数あります。そういったこともふまえて、この企画では酒税法で発泡酒と表記すべきお酒も「ビール」として紹介しますので、ご了承ください。
ビールに使われる原料
ビールに使われる原料は、前述のとおり麦芽・ホップ・水と酵母です。ここでは、水以外の主原料と、副原料について見ていきたいと思います。
麦芽:麦を発芽させ、焙燥・焙煎したもの

麦芽とは、麦を発芽させてから焙燥・焙煎したものです。ビールは麦のお酒ですが、実は麦のままではビールをつくることができません。お酒をつくるには糖分が必要ですが、麦にはデンプンはあっても糖分はないのです。
しかし、麦を発芽させることで、麦の中にあるアミラーゼという酵素が活性化します。アミラーゼは麦のでんぷんを糖に変えることができ、その糖を酵母がアルコールに変えていきます。
ちなみに、人の唾液にもアミラーゼが含まれています。お米をよく噛むと甘く感じるのは、その酵素が米のでんぷんを糖に変えているからなのです。
ホップ:ビールに香りと苦味をつける植物

ホップという名称は聞いたことはあっても、何かは全くわからない人が大多数ではないでしょうか。
ホップはつる性の多年草植物で、日本では北海道や東北などの寒冷地が主な栽培地です。最近では、北海道・東北以外でも自治体と連携してホップ栽培による地域活性化を進めている地域も出てきました。
世界では、アメリカやドイツ、チェコといったところが有名な栽培地として知られています。
ホップはつる性の多年草植物で、何かに絡まっていないと上に伸びていけないのですが、ホップ栽培では上にロープを渡しそこにつるをひっかけて伸ばしていきます。夏が収穫時期で、その時期になると高さ8メートルほどにもなります。
収穫するものは、雌株にできる「毬花(まりはな)」という部分。これがビールの原料になります。

この毬花を割ると、「ルプリン」という小さな黄色い粒があり、ここにビールの香りと苦味のもとになる成分が詰まっています。
また、ホップは品種によって香りの種類や苦味の量が異なります。柑橘系の香りがするホップや、ブドウ、メロン、マンゴーなどのフレーバーをつくり出せるホップもあり、ビール醸造では複数品種を組み合わせて、独自の香りをつくり上げていくのが一般的です。
酵母:糖をアルコールとCO₂に分解

酵母は、糖をアルコールとCO₂(二酸化炭素)に分解する微生物です。名前が酵素と似ているので間違えられやすいのですが、全く別物です。酵素はタンパク質で構成されたもので生物ではありません。一方、酵母は単細胞生物で真菌類の一種です。
酵母の役割は、糖をアルコールとCO₂に分解すること。アルコール発酵には糖分が必要になりますが、その理由は酵母が糖分を分解してアルコールをつくるからなのです。
そして、酵母にもたくさんの種類があります。ビール醸造に使われる酵母は、ラガー酵母とエール酵母に大きく分けられます。
ビールの名前に「ラガー」や「エール」と書かれているのを見たことがある人もいるでしょう。これは、ラガー酵母またはエール酵母でつくられたビールということです。一般的に、ラガーはすっきりした味わい、エールはフルーティーな香りのついた味わいになりやすいとされています。
ほかにも、空気中に浮遊している野生酵母を使ったビールなどもあり、こういったビールは酸味のある味わいが特徴です。酵母の種類によっても、ビールの味わいが大きく変わってくるといえるでしょう。

酵母は、糖をアルコールとCO₂(二酸化炭素)に分解する微生物です。名前が酵素と似ているので間違えられやすいのですが、全く別物です。酵素はタンパク質で構成されたもので生物ではありません。一方、酵母は単細胞生物で真菌類の一種です。
酵母の役割は、糖をアルコールとCO₂に分解すること。アルコール発酵には糖分が必要になりますが、その理由は酵母が糖分を分解してアルコールをつくるからなのです。
そして、酵母にもたくさんの種類があります。ビール醸造に使われる酵母は、ラガー酵母とエール酵母に大きく分けられます。
ビールの名前に「ラガー」や「エール」と書かれているのを見たことがある人もいるでしょう。これは、ラガー酵母またはエール酵母でつくられたビールということです。一般的に、ラガーはすっきりした味わい、エールはフルーティーな香りのついた味わいになりやすいとされています。
ほかにも、空気中に浮遊している野生酵母を使ったビールなどもあり、こういったビールは酸味のある味わいが特徴です。酵母の種類によっても、ビールの味わいが大きく変わってくるといえるでしょう。
副原料:糖分やフレーバーを付加する原料
副原料とは、麦芽・ホップ・酵母以外にビール醸造として使われる原料のことです。必ずしも副原料を使わなければいけないわけではなく、副原料を入れないビールは「麦芽100%ビール」と言われることもあります。
前述のとおり、麦芽重量の5%以内であれば副原料を使用してもビールと表記することが可能です。政令で定められた副原料は下記のとおりで、かなりの種類がリストアップされています。

コーン(とうもろこし)やスターチは、大手ビールでも副原料として使われているので、原材料表示の欄で見たことがある人もいるかもしれません。コーンやスターチはでんぷんとして使われ、比較的すっきりした味わいになりやすいとされています。
また、オレンジピールやコリアンダー、シナモン、クローブなどはベルギービールでよく使われます。牡蠣(かき)やかつお節など、一見ビールとは合わなそうな原料もありますが、実際にこれらを使ったビールもあります。
日本酒やワインなどと違って副原料を使うことができるのも、ビールの特徴といえるでしょう。地域の特産品である原料をビール醸造にうまく使うことで、地域活性化やブランディングにつなげることもできます。
ビール醸造の流れ

ビールに使う原料を理解したら、ビール醸造の流れについても知っておきましょう。ビール醸造は、上記の図のような流れで行われます。
糖化:麦芽のでんぷんを糖に変える
まず、麦芽を粉砕してお湯と混ぜます。この段階で、麦芽に含まれるアミラーゼによって麦芽のでんぷんが糖に変わります。マイシェと呼ばれるどろどろの甘いおかゆのような状態になったら、これを濾過していきます。
濾過・スパージング:麦汁をつくる
マイシェを濾過すると、クリアで甘い液体が取り出せます。これを麦汁といい、最初に取り出した麦汁を「一番搾り麦汁」といいます。「キリン一番搾り生ビール」は、この一番搾り麦汁だけを使っており、それを商品名にしているのです。
一般的には、マイシェにさらに温水をかけてエキスを出し、それら全てを混ぜたものをビール醸造に使っています。
煮沸:殺菌とホップの香り・苦味成分を抽出する
続いて、麦汁を煮沸します。煮沸は、殺菌して雑菌の繁殖を防ぐ目的があるのですが、この段階でホップを入れて香りや苦味成分を抽出します。この煮沸の前半にホップを入れると苦味付け、後半に入れると香り付けになります。香りは熱で飛びやすいので、香り付け用のホップはできるだけ後半に入れて熱があまりかからないようにするのです。
発酵・熟成:酵母を入れてアルコールを生成する
煮沸後は、かすなどを取り除いて冷却し、そこに酵母を加えて発酵させます。発酵が終わったらすぐビールとして完成するわけではなく、酵母を取り出した後に熟成という工程が必要です。熟成させると味わいがまるくなったり、不快な香りを飛ばしたりすることができます。
容器詰め:樽や缶、ボトルにビールを詰める
熟成期間が終われば、容器詰め後に出荷されていきます。なお、ビール醸造は早ければ1カ月くらいでできてしまいます。また、麦芽やホップ、酵母などの原料も長期保存できるので、季節を問わず比較的早いスピードでつくれるというのが、ビールの特徴の1つといえるでしょう。
クラフトビールと地ビールの違い
最近はクラフトビールという言葉をよく聞くようになりましたが、昔は地ビールという言葉もよく使われていました。今でも地ビールという言葉がなくなったわけではないのですが、だいぶ聞く機会は少なくなりました。この2つの言葉がどう違うのか、わかっていない人も多いと思いますので、クラフトビールと地ビールの違いについて解説したいと思います。
クラフトビール:1980年頃から始まったアメリカ発のムーブメント
クラフトビールとは、1980年(昭和55年)頃から始まったアメリカ発のムーブメントのことです。
その当時のアメリカは、大手ビール会社によるライトビールというジャンルが人気でした。すっきりした味わいでゴクゴク飲むにはいいのですが、ライトビールばかりでは伝統的なビールの多様性が失われるという考え方もありました。そういった画一的なライトビールへのアンチテーゼとして生まれたのが、伝統的で自由なビールづくりを目指すクラフトビールというムーブメントです。
さらに、この当時のアメリカで、カスケードという新しい品種のホップが出てきました。柑橘系フレーバーをつくり出せるホップで、今でも人気のホップです。そのカスケードを使ったビールの代表格が、1980年からつくられているシエラネバダというブルワリーのペールエールです。

また、ホームブリューイング(自家醸造)がアメリカで解禁されたことも、大きな影響を与えています。日本では、ビールに限らず1%以上のアルコールを醸造するのは違法ですが、アメリカでは認められています。ホームブリューイングで試行錯誤し、おいしいビールがつくれたら事業としてブルワリーを立ち上げるという人も出てきたのです。
現在、アメリカでは9,000軒以上のブルワリーがあり、世界のビールシーンを引っ張っているといっても過言ではありません。その発端となったのがクラフトビールというムーブメントなのです。
地ビール:平成6年の酒税法改正が生んだ小規模醸造
地ビールとは、平成6年の酒税法改正によって生まれた小規模醸造のビールのことです。平成6年に酒税法が改正されるまでは、ビールをつくるには年間2,000キロリットルのビールをつくれないと醸造免許を取得できませんでした。2,000キロリットルというのは、350ミリリットルの缶ビールで571万本です。1日当たりでは約1万5,000本となり、これだけの規模で醸造・販売するのは難しく、ビール醸造ができるのは実質的に大手に限られていました。
しかし、酒税法改正によって、最低製造量が2,000キロリットルから60キロリットルに緩和されました。60キロリットルは、350ミリリットルの缶ビールで約17万本。1日当たり約470本です。これにより、小規模事業者でも参入が可能になりました。
この酒税法改正をきっかけに全国各地に小規模のブルワリーが生まれ、その小規模醸造ビールのことを地ビールと呼んでいたのです。その小規模ブルワリーの第一号がエチゴビールで、現在でも人気のブルワリーなのでぜひ飲んでみてください。

この後、 2000年(平成12年)くらいまでは、地ビールブームといわれて小規模ブルワリーがどんどん増えていきました。しかし、それ以降ブームは廃れて地ビールという言葉だけが残ったのです。
そして、2000年代前半にアメリカから「クラフトビール」という言葉が日本に入ってきました。地ビールとクラフトビールは言葉の由来は違うものの、大手とは違う小規模なビールという共通項があったからか、「クラフトビール=地ビール」という印象になっているというのが現状です。
どのようなビールなのかを知るとビールの楽しさが広がる
現在、クラフトビールと地ビールはほぼ同義の言葉であり、かつ大手ビールとは違うビールという認識が一般的です。とはいえ、大手メーカーも「クラフトビール」を冠した商品を出しているため、境界が曖昧になっているともいえるでしょう。
しかし、大手ビールかクラフトビールかではなく、「どんな味か」「どんな思いでつくられたか」「地域とどのような関わりがあるのか」といった情報が伝わると、消費者もそのビールに思い入れを持てるようになります。その「どんな味か」の基準となるのがビアスタイルなのですが、それは次回で紹介したいと思います。
◆